|
1 国内貨物総輸送需要の動向50年度以降の国内貨物総輸送需要の動向をみると,50年度,50.3億トン,3,608億トンキロが55年度は59.9億トン,4,391億トンキロとなっている。この5年間で輸送トン数,輸送トンキロとも1.2倍,平均年率4%増程度の伸びにとどまった。これは,高度経済成長期の40年度から48年度の同10%台成長に比べ,伸び率の著しい低下と言えよう。次に,国内貨物総輸送需要の趨勢をみると,輸送トン数では47年度,輸送トンキロでは48年度をピークとして急落したが,各々51年度,50年度を底として急速な回復をみせた。53,54年度においては,輸送トン数では対前年度比でそれぞれ8.6%,7.5%増,輸送トンキロでは同5.8%,8.0%増となり,輸送トン数では53年度,輸送トンキロでは54年度に各々ピーク時を上まわる水準に回復した。しかしながら,55年度においては輸送トン数で同0.5%増と横ばいとなり,輸送トンキロでは同0.7%減と再びマイナスに転じた 〔2−2−27図〕, 〔2−2−28図〕。
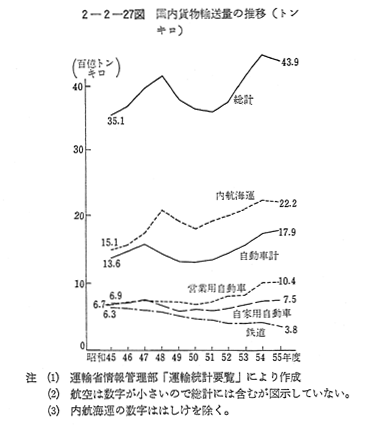
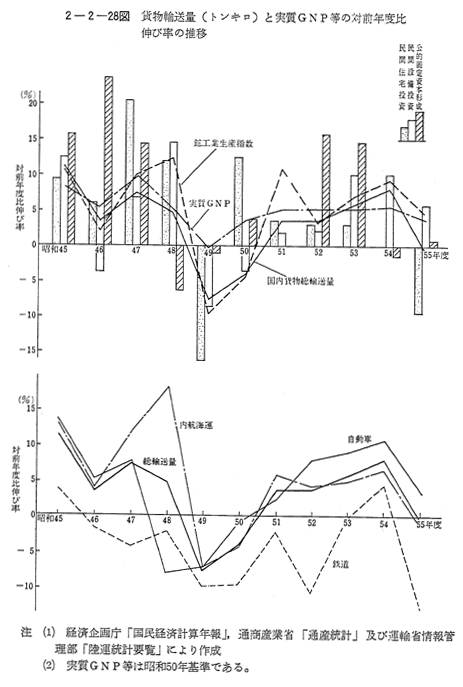
このように,安定経済成長下における国内貨物総輸送量の伸びの鈍化,特に55年度における不振をもたらした背景としては,次のようなことが考えられる。
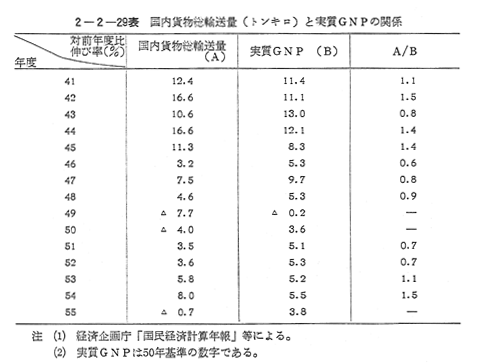
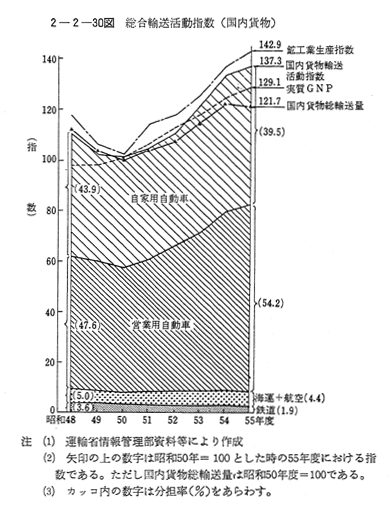
こうした現象をもたらす要因としては産業構造の変化が大きく寄与している。 〔2−2−31図〕のとおり,名目価格ベースで,45年度においては第二次産業のウェイトは42.2%,第三次産業は51.1%であったが,54年度はそれぞれ37.7%,57.4%と,産出額1単位当たりの発生輸送需要の比較的小さい第三次産業化(サービス経済化),高付加価値化が,基調としてはなお進行している。更に,第二次産業も大量の輸送需要をもたらす素材型産業(窯業・土石製品,鉄鋼等)の伸びが鈍化するとともに,一方輸送単位が小さく,比較的産出額1単位当たりの輸送量も小さく,しかも高度の輸送サービスの質を要求する加工型産業(電気機械,精密機械等)の伸びが高まっている 〔2−2−32図〕, 〔2−2−33図〕。このように産業構造自体は,輸送量を誘発しにくい構造への傾向を強めている。
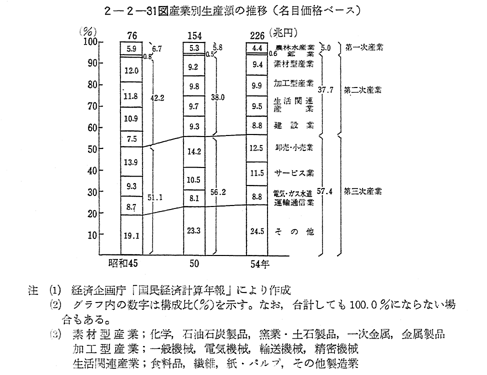
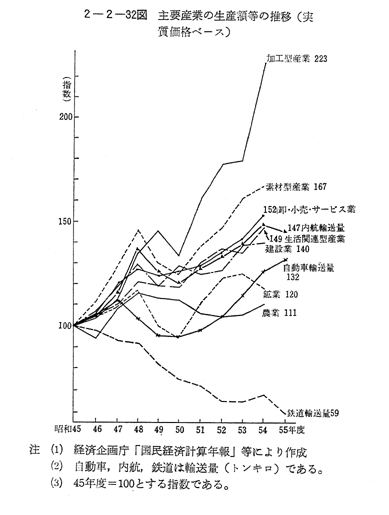
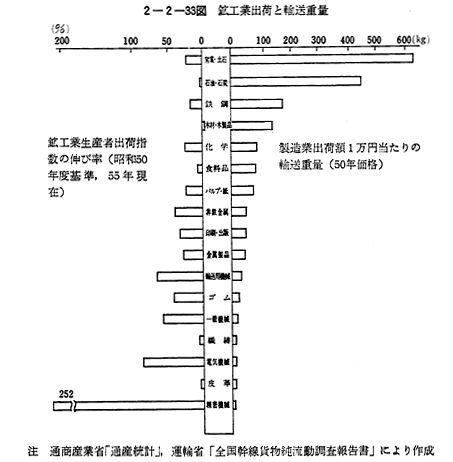
第2に,公共投資,民間設備投資の伸びの鈍化と質的変化があげられる。国民総支出における最終需要項目別にみた誘発国内貨物総輸送量の推移をみると, 〔2−2−34図〕のとおり,民間固定資本形成(民間設備投資,住宅投資)及び民間最終消費支出からの誘発が大きい。これを寄与度でみると,50年度以降の総輸送量の回復には,これらの項目とともに公的固定資本形成(公共投資)の寄与(52,53年度)が目立つ。ところが,55年度においては,これらの項目全ての寄与度が小さく,これが特に55年度の総輸送量の不振につながったと言える。
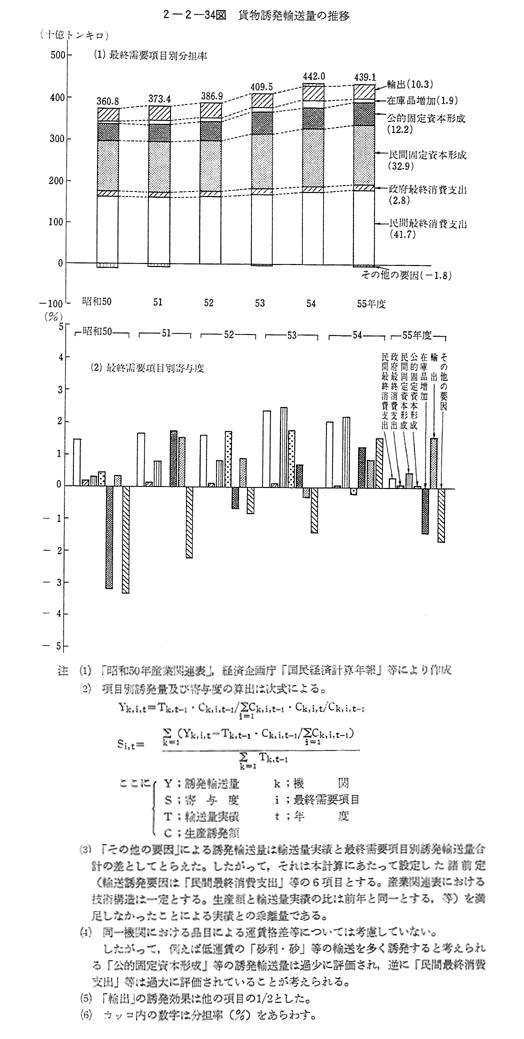
すなわち,もともと,公共投資及び民間設備投資の動向は,輸送量に大きな影響を与える。公共投資は高度経済成長期の40年度から48年度では平均年率11.1%増,民間設備投資も同15.7%増であったが,50年度から55年度でみると各々5.6%,4.2%増と伸び率は低下している。
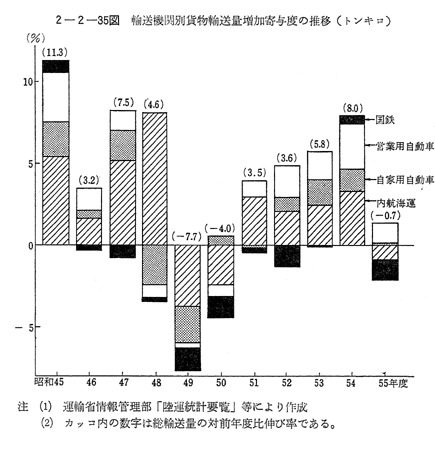
品目別に見ると 〔2−2−36図〕のとおり,石油製品,工業用非金属鉱物(石灰石,原油等),セメント等輸送量に占めるウェイトの高い貨物の落ち込みが,特に55年度においては目立っている。 〔2−2−37図〕のとおり財別の鉱工業生産者出荷(金額ベース)でみても,建設財,生産財等を中心に出荷の減少ないし停滞が生じている。また,産業別では,55年度においては,機械が対前年度比14.2%増と加工型産業の伸びは目立っているが,鉄鋼,非鉄金属,金属,窯業・土石製品,化学,石油・石炭製品,パルプ・紙・紙加工品など素材型産業を中心にほとんど全ての産業において前年度水準を下まわっている。これは,これら産業にかかる貨物の荷動きが小さかったためである。更に第2次石油危機後においては,鉄鋼を始めとするエネルギー多消費産業に広く省エネ化が進み,セメント産業や電力における石油から石炭への転換等のエネルギー転換も進行している。こうした背景もあって,55年度においては原油輸入量が減少し,このため原油の二次輸送が減少した。
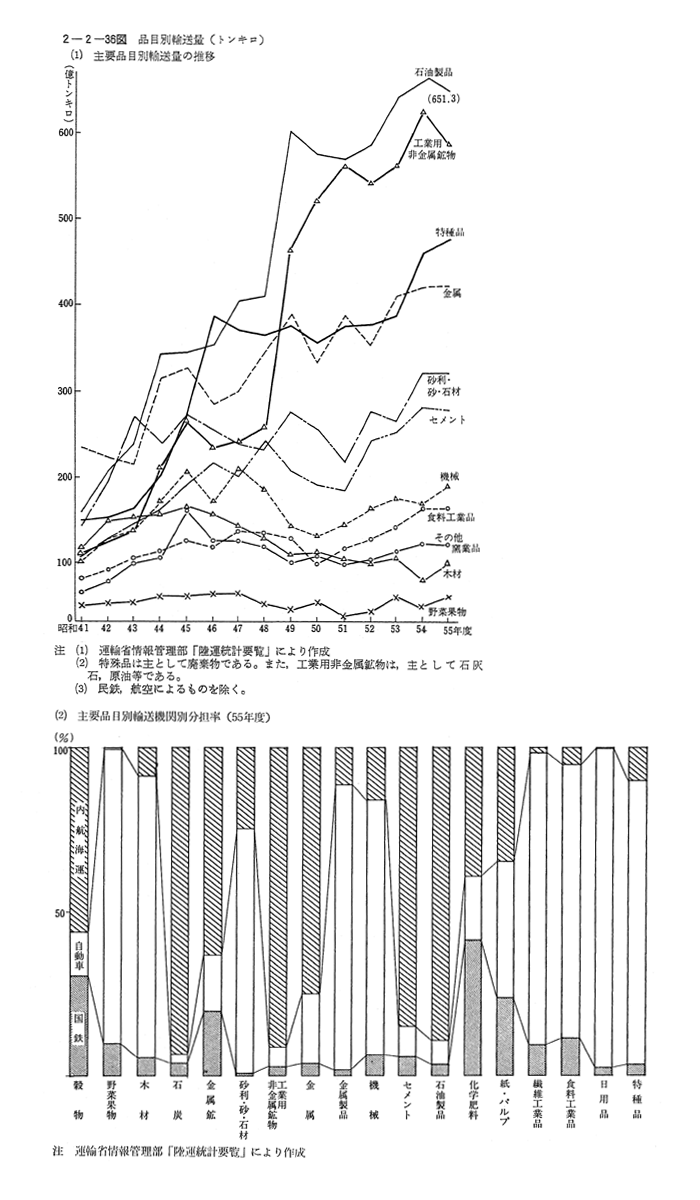
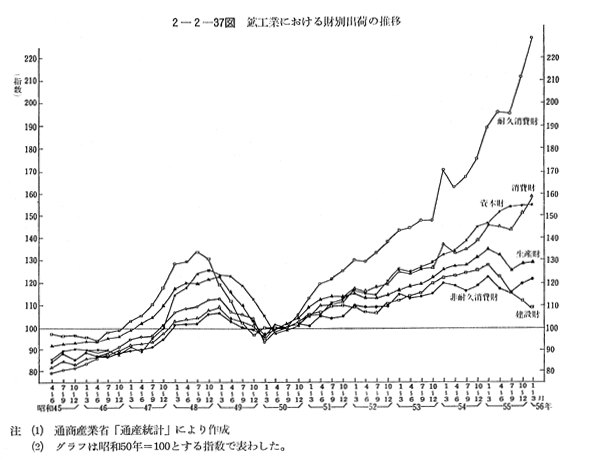
|