|
2 石油危機と貨物輸送
48年秋の第1次石油危機(前回)後と,53年末からの第2次石油危機(今回)後の輸送動向をみてみよう。前回は原油価格が約4倍の大幅かつ極めて短期間の急速な上昇であり,狂乱物価,物不足といった心理的影響を含めて産業活動等に一種のパニック状況をもたらした。今回は,原油価格の値上げの絶対額は大きいものの,約2.5倍とその幅は小さく,しかも長期にわたる小きざみな上昇である。また,我が国経済をとりまく諸情勢も前回に比べて良好であり,かつ,石油危機に対して我が国の経済体質が強くなっていることもあり,前回ほど大きな影響は受けなかった。 〔2−2−38図〕のとおり,前回は実質GNPが石油危機直後からマイナスとなり,マイナス成長はほぼ4四半期続いた。鉱工業生産も同様に大きく落ち込んだ。このため,自動車は,折りからの軽油供給不足もあって走行キロ自体が減少し,石油危機直後からその輸送量も大きく減少した。総輸送量も49,50年度とマイナス成長となり,ようやく51年度に至ってプラスに転じており,石油危機の影響は極めて大きくかつ長期にわたった。しかしながら今回は,実質GNP,鉱工業生産がやや弱含みながらも横ばいの推移を見せており,狂乱物価や物不足といったパニック状況もおこらず,産業活動等への影響は前回に比べると比較的軽微であった。次に,輸送面をみてみる。まず総輸送量においては,54年7〜9月期をピークとして期を追うごとに伸びは鈍化し,55年7〜9月期にはマイナス成長となったあとやや回復しつつあるが,なお年度を通してマイナスとなっている。そのなかで産業の基礎資材等の物資を輸送する内航海運は,鉄鋼,セメント,石油製品等素材型産業の不振のため,総輸送量の動きと同じ推移となっているが,自動車は加工型産業の好調もあり,伸びが鈍化しつつあるもののマイナス成長とはならなかった。また,軽油価格は上昇したが,前回のような軽油不足は起こらなかった。このため,走行キロ自体の落ち込みもなかった。なお,鉄道は石油危機の影響のみならず,運賃改定等による競争力低下や産業構造の変化など種々の要因により,54年4〜6月期をピークとして,その輸送量はいわば構造的とも言える長期的低落傾向を示している。
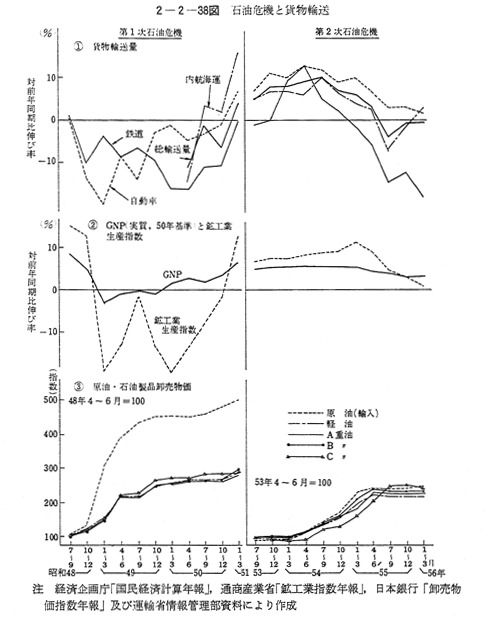
今回の石油危機の与えた影響は,エネルギーコストの増嵩のため,経営面では前回同様大きなものであったが,輸送面では前回に比べて比較的軽微であったと評価できよう。
|