|
3 輸送機関別輸送の動向
安定経済成長下にあっても,そのテンポは緩やかなものになりつつあるものの,なお高度経済成長期以来の産業構造,立地構造の変化や,都市化とモータリゼーションの進展等は依然として続いている。これを背景として輸送機関のそれぞれの特性に応じた輸送分担も進行している。鉄道輸送の衰退,自動車輸送の伸長,内航海運輸送の安定がその特徴と言えよう。なお,航空輸送も成長を続けている 〔2−2−27図〕, 〔2−2−28図〕, 〔2−2−39図〕。しかしながら,55年度においては,5年ぶりに総輸送量(トンキロ)が減少した。そのなかで鉄道の輸送量は大きく前年度水準を下まわり,また,自動車の輸送量は営業用を中心に伸びが鈍化したものの増加しており,更に,内航海運もその輸送量の減少が目立つ。
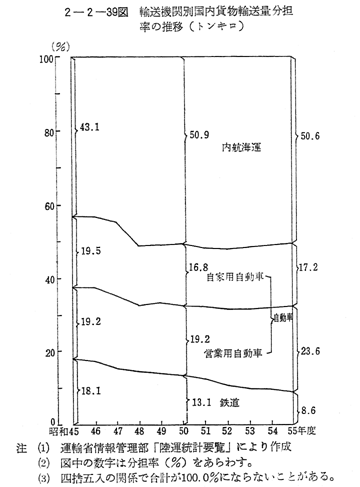
まず,鉄道輸送をみると,特に国鉄は,55年度,輸送トン数で1.2億トン,輸送・トンキロで370億トンキロとなり,国内貨物総輸送量に占めるシェアもそれぞれ2.0%,8.4%となっている。輸送トンキロでは45年度をピークとして,54年度を除き一貫して対前年度比マイナスが続き,特に55年度は対前年度比10%以上の大幅な落ち込みとなっており,このためこの10年間で約40%の減となっている。輸送量としては昭和20年代半ばとほぼ同じ水準となっている。このように,安定経済成長下にあっても,国鉄輸送のいわば構造的とも言える長期的低落傾向は依然として続いている。主な輸送品目別に見ると 〔2−2−40図〕のとおり,石炭など一部の品目を除きほとんどの品目で減少しており,なかでも石灰石,セメント,鉄鋼等の減少が目立っている。特に55年度は,比較的好調であった石油製品も落ち込んだ。なお,国鉄輸送は 〔2−2−41図〕のとおり1次産品,2次産品のすべてにわたり,多品種の輸送が特色である。
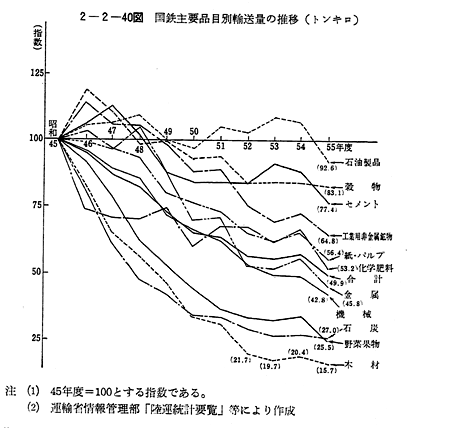
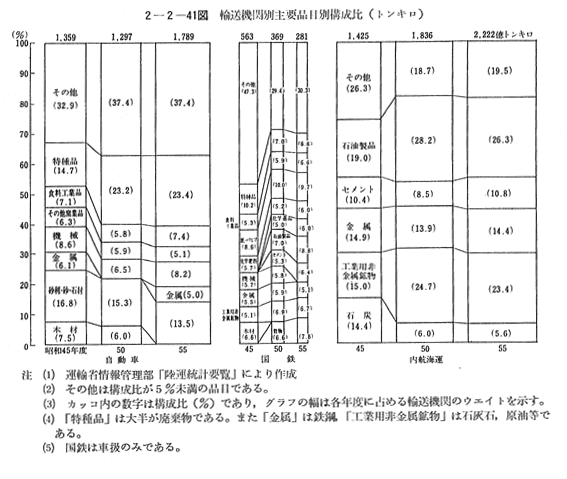
国鉄輸送が不振を続けている背景としては次のようなことが指摘できる。第1に,産業構造の変化,臨海型又は道路志向型立地の増大といった立地構造の変化,石炭から石油へのエネルギー革命,一次産品の海外依存度の増大といった経済構造の変化のため,石炭,木材等の大宗貨物の輸送需要が減少し,鉄道輸送の特性を発揮できる分野が相対的に縮小したこと。第2に,国鉄は輸送サービスを供給する企業として,市場指向認識が必ずしも十分でなく,これに伴う事業の合理化への努力や,輸送サービスの高度化,多様化を求める荷主のニーズに十分対応できなかったこと。また,繰返し行われたストライキにより,輸送の信頼性を低下させたこと。第3に,自動車等の他の輸送機関の発達に伴って国鉄の競争力が低下したことが指摘できよう。 〔2−2−42表〕のとおり,例えば「東京-大阪」等の主要区間についてみても,トラック運賃はトン当りでみると,国鉄運賃に比べてやや高いものの,その差は小さくなりつつある。また,所要時間については,国鉄はトラックの倍近い時間がかかっている。更に,トラックは積み替えがないこと(ドア・トゥ・ドア),荷いたみが少ないこと,きめ細かく柔軟な輸送サービスであること等の利点が大きい。このような,価格,非価格両面における競争力の低下は,国鉄輸送不振の要因の一つである。
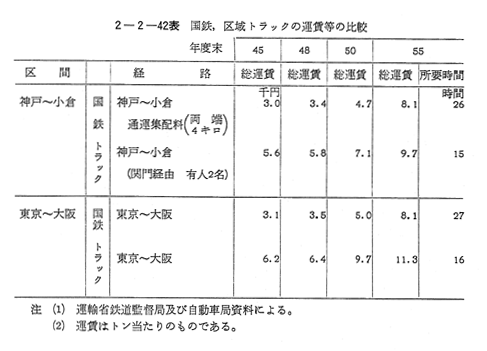
こうした競争力の低下は,従来国鉄が比較的優位にあった中・長距離を含めた距離帯において, 〔2−2−43図〕のとおり,シェアの低下を招いている。なかでも,高速道路等の道路整備の進展につれ,近距離はもちろん,中・長距離輸送への自動車の進出や長距離を中心とした内航海運の発展が著しい。
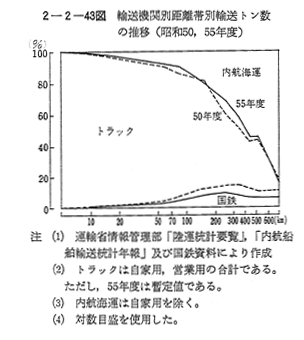
このように,かつて陸上輸送において独占的な地位にあった国鉄は,今や他の輸送機関との厳しい競争関係に置かれた限界的な輸送サービス供給主体となっている。
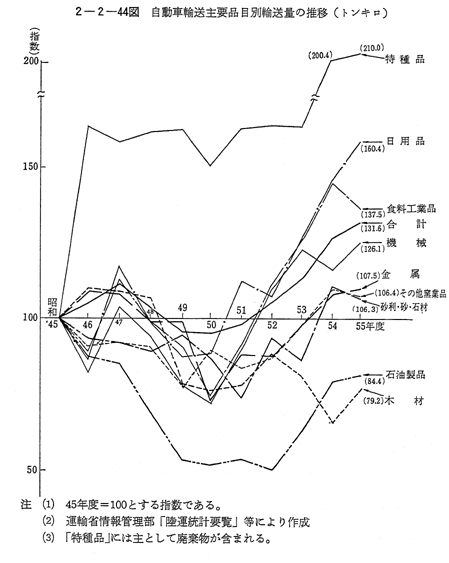
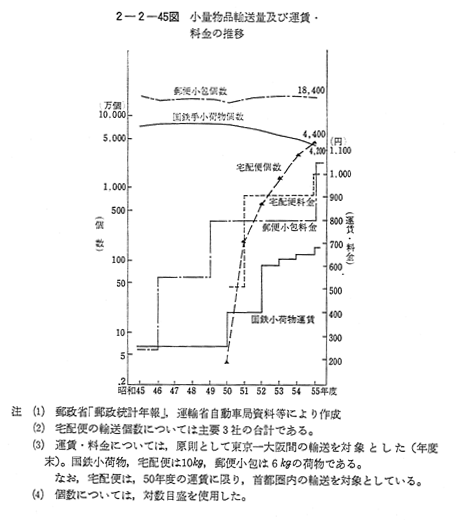
次に,内航海運輸送をみると,55年度は輸送トン数で5.0億トン,輸送トンキロ2,222億トンキロとなり,国内貨物総輸送量に占めるシェアは各々8.4%,50.6%となった。50年度に比べ,輸送トンキロで1.2倍(平均年率3.9%増)となっている。これは,高度経済成長期の40年度から48年度の平均年率12.6%増に比べ,大幅な伸びの鈍化である。特に55年度においては,50年度以来5年ぶりに輸送トン数で2.8%減,輸送トンキロで1.6%減と対前年度比マイナスに転じたことが特記される。輸送品目別にみると,石油製品,鉄鋼,セメント,工業用非金属鉱物(石灰石,原油等)など長距離・大量輸送を要する産業の基礎資材物資に特化しており,いわば少品種,大量輸送が特色である 〔2−2−36図〕, 〔2−2−41図〕, 〔2−2−46図〕。55年度においては,第2次石油危機後の「景気のかげり」が素材型産業を中心に現われ,鉄鋼,石油等においては出荷が対前年度比マイナスとなっており,このため,輸送においても石油製品等の減少を招いた。加えて,省エネの浸透やエネルギー転換等による原油輸入の減少は,これの二次輸送を行う内航海運の輸送量の減少をもたらした。
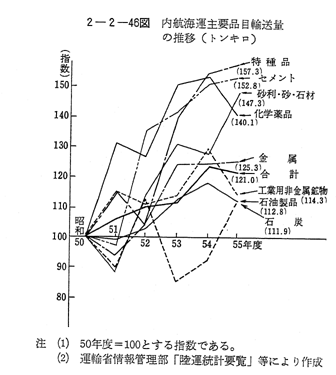
次に,国内航空輸送は 〔2−2−47表〕のとおり,55年度は,輸送トン数32.8万トン,輸送トンキロで2.9億トンキロとなった。50年度からの5年間で平均年率10%台の高い成長となっている。しかしながら,55年度においては,第2次石油危機後の国内経済の停滞や55年3月の運賃改定の影響もあり,対前年度比で輸送トンキロは6.0%増と,54年度の同22.1%増に比べ,その伸びが大幅に落ち込んでいる。国内航空は,生鮮混載貨物や一般混載貨物,動植物,通信・報道原稿,衣料・装飾品,書類など比較的小型・軽量・コンパクトな商品等が主な輸送品目となっている。特に最近では,例えば地方空港のジェット化を契機に,“臨空工業団地“とか“シリコンアイランド"とか呼ばれるように,九州や東北地方等の一部の空港を中心とした周辺地域に,IC,LSI等のエレクトロニクス製品を生産する工場の進出が相次いでおり,これによる機械器具,部品の輸送が目立っている。しかも,地方空港のジェット化,生産拠点の分散化に伴い幹線よりもローカル線の輸送が伸びている。このように,運賃負担力に富む貨物を中心に国内航空は発展している。これは,高級青果物や電子部品等に見られるように,たとえ高運賃を払っても,迅速かつ荷いたみなく,流通市場に出荷され,又は,生産拠点に輸送されればかえって高い付加価値を生むこと,また,航空輸送は所要時間やサービス水準の高さ等を考慮すると,必ずしも他の輸送機関に比べ高運賃ではないこと,更に,機材の大型化に伴い,輸送力が増大したこと,地方空港のジェット化が進んだこと等がこの発展の要因であろう。
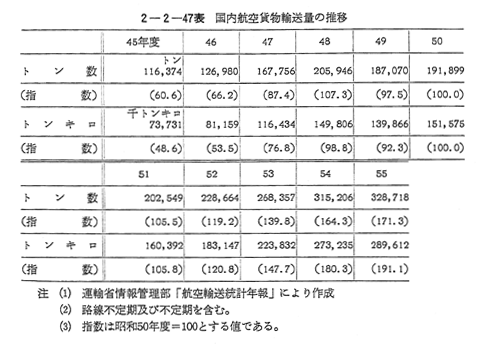
|