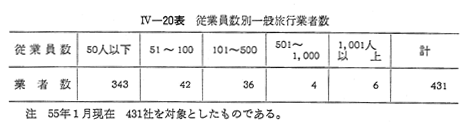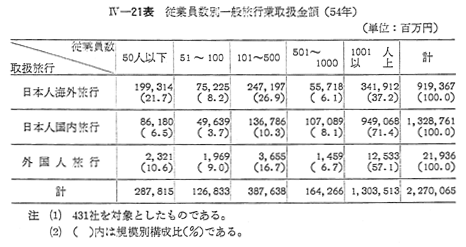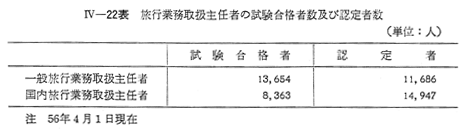|
2 旅行業
(1) 現状
(ア) 一般旅行業
56年4月1日現在の一般旅行業者数は456業者である。55年度中に新規登録を受けたもの32業者,廃業したもの23業者で,差引き9業者の増加をみた。このような激しい業者数の変動は,参入容易,継続困難といわれている旅行業の性格を如実に物語っている。
一般旅行業者の従業員数別の分布をみると 〔IV−20表〕のとおりである。従業員数50人以下の中小企業が全体の80%近くを占めている。
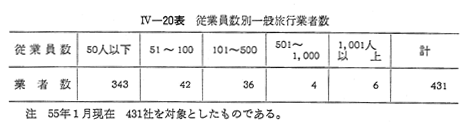
一般旅行業者の54年の取扱金額を見ると 〔IV−21表〕のとおり,総額で2兆2,000億円を超え,1業者当たりでは53億円に達している。日本人海外旅行と日本人国内旅行との取扱金額を企業の規模別に比較すると,海外旅行では中小企業の取扱金額もかなり大きく従業員1,001人以上の企業の取扱金額は全体の約37%を占めるのみであるが,国内旅行では大企業の取扱金額が圧倒的に大きく,従業員数1,001人以上の企業が全体の約70%を取り扱うに至っている。
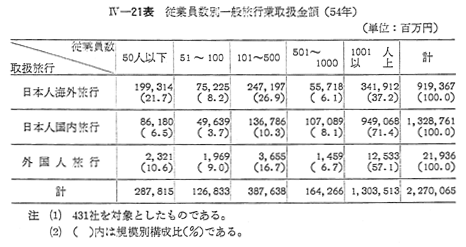
(イ) 国内旅行業
56年4月1日現在,国内旅行業者数は4,691業者である。55年度中に新規登録を受けたもの295業者,廃業したもの251業者で差し引き44業者が増加した。国内旅行業者は,その数においては一般旅行業者の約10倍あるが,1業者当たりの従業員数は6.4人(54年12月31日現在)と小規模のものが多く,企業形態も40%近くが法人形態をとらない個人経営である。また,54年の取扱金額は,総額で6,000億円を超え,1業者当たり約1億4,000万円程度と推定される。
(ウ) 旅行業代理店業
56年4月1日現在,一般旅行業代理店業者数は1,379業者で,55年度中に差し引き126業者が増加した。一般旅行業代理店業者は年々増加しているが,その背景には次のような事情がある。第1に,ホールセーラー(卸売業者)とリテーラー(小売業者)への旅行業者の機能の分化が進み,大手業者が企画したパッケージ旅行商品をその代理店を通じて広く販売するようになってきたこと,第2に,海外旅行分野に進出しようとする国内旅行業者が増えており,それらが一般旅行業代理店業の登録を受けることが多いこと,第3に,大きな資金がなくとも開業できるので参入が容易であること等である。今後ともこの増加傾向は続くものと思われる。
これに対し,国内旅行業代理店業者は56年4月1日現在34業者で,55年度中に差し引き12業者の減少をみた。
(エ) 旅行業務取扱主任者
旅行業法は,旅行業者に対し,営業所ごとに資格を有する旅行業務取扱主任者を選任して,取引の公正を確保するために必要な管理・監督を行わせるよう義務付けている。旅行業務取扱主任者となる資格を有する者は,運輸大臣が社団法人日本旅行業協会及び社団法人全国旅行業協会を通じて実施している旅行業務取扱主任者試験に合格した者又は運輸大臣若しくは都道府県知事による認定を受けた者である。56年4月1日現在,試験合格者数及び認定者数は 〔IV−22表〕のとおりである。
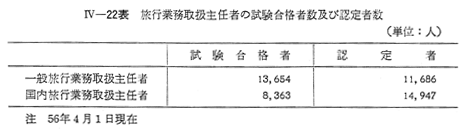
(2) 旅行者の保護
観光旅行の普及に伴って様々なトラブルが発生するようになり,旅行者保護及び旅行業界の秩序確立の必要性はますます高まってきている。
このため,従来より旅行業法に基づいて各種の措置を講じているが,55年度においても次のような措置を講じ,旅行者保護の一層の強化を図った。
(ア) 旅行業モニター制度を引き続き実施して,旅行取引に関し国民から広く意見を徴し,これを旅行業法の施行に当たっての諸施策に反映させた。
(イ) 55年11月の栃木県川治温泉での旅館火災事故にかんがみ,再びこのような惨事に旅行者が巻き込まれるのを防ぐため,56年1月関係省庁間で「旅館,ホテル防火安全対策連絡協議会」における了解事項をとりまとめ,これに基づいて旅行業者に対し,旅館,ホテルの選択に当たっては防火,避難施設等の状況について事前に調査すること,老人,身体不自由者等の団体旅行者については旅館,ホテルへその旨の連絡をすること,非常時における避難方法等の旅館側による旅行者への周知について添乗員が確認すること等指導を行った。
(ウ) 46年の旅行業法の改正以来の旅行業をとりまく情勢の変化に対応するため,54年7月運輸省に学識経験者,関係業界団体の代表等の委員からなる旅行業制度検討委員会を設け,添乗員の資質の向上など旅行者の保護を一層強化するための方策及び旅行業界の秩序を確立するための方策について検討してきたが,55年10月よりは同委員会の下に約款小委員会を設け,旅行業約款等に関する問題について審議を進めている。
|