|
1 世界経済の概況1981年の世界経済は,第2次石油危機の後遺症と高金利問題に悩まされた。欧米先進国の多くは,労働生産性の伸び悩み,市場機能の硬直化等の構造的問題を抱える中で,石油価格上昇によるデフレ効果,物価鎮静化を意図してとられた金融引締め政策と高金利の出現により,景気後退あるいは景気回復の遅延を余儀なくされ,失業者数も大幅に増大した。発展途上国でも全般に景気の鈍化傾向が強まった。このような世界経済の停滞と失業の増加を背景に,各国で保護貿易主義的圧力が高まっている。こうした中で,物価面では上昇率がなお高いものの,石油需給の緩和や景気後退の影響等から騰勢が鈍化し始めている。国際収支面では,非産油発展途上国の経常収支の赤字幅は更に拡大したが,先進工業国グループでは石油消費節約の進捗もあって収支改善へ向けての進展がみられた。 主要先進国の経済動向をみると,80年夏以後回復に転じたアメリカ経済は,81年の初頭にはかなりの拡大を示したものの,春以降は高金利の長期化に伴う個人消費(特に耐久財)の伸び悩み,住宅投資及び輸出の減少から早くも息切れし,再び景気後退局面に転じている。西欧では,フランスにおいて81年5月に誕生したミッテラン社会党政権が雇用拡大のために景気刺激策を採用したことから,年央以降個人消費の堅調を背景に景気がやや持ち直したが,西ドイツ,イギリス等では個人消費の減退,住宅・設備投資の不振等から,年後半に至っても浮揚力に乏しい景況が続いた。 このように世界経済は総じて停滞気味に推移しており,第1次石油危機後の景気回復が比較的速やかであったのとは対照的な姿となっている 〔1−1−1図〕。その背景の第1は,石油消費国の対OPEC向け輸出の増加を通ずる需要の回復が前回ほど進展していないこと,第2は,第1次石油危機後には多くの国で金融・財政政策を早めに緩和したのとは対照的に,今回は金融政策を中心に各国ともインフレ抑制を重視した慎重な政策運営を行ったこと,第3は,アメリカの厳しい金融政策運営が各国に異常な高金利をもたらすこととなり,このため各国とも,設備投資,住宅投資等の国内最終需要が停滞していること,である。 82年に入って,世界経済は石油需給の緩和を背景とする石油価格の低下,緊縮政策の奏功によるインフレの鎮静化といった明るさもみられるものの,依然として,景気の低迷と失業の増大に悩まされている。
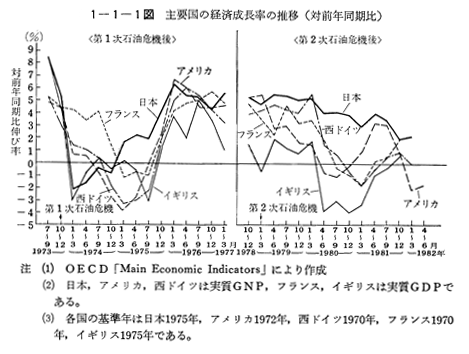
|