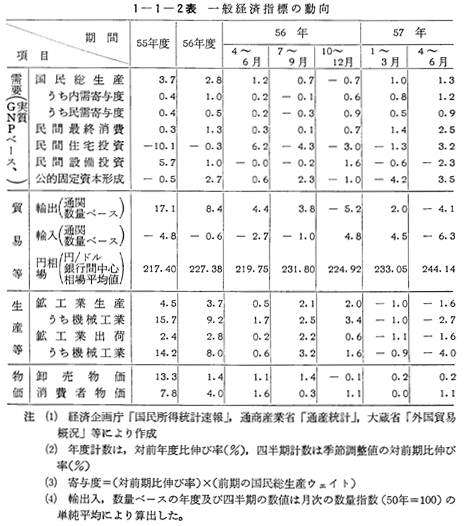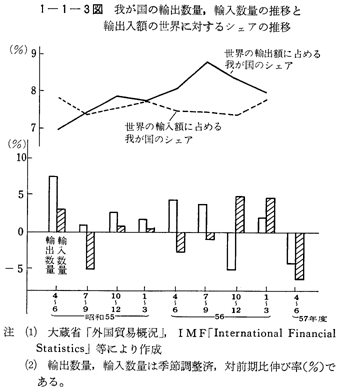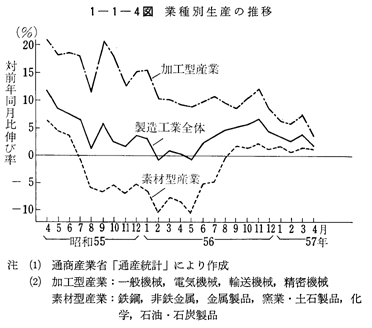|
2 日本経済の概況
昭和56年度の我が国経済は,物価や国際収支の面では,他の先進諸国と比べて良好なパフォーマンスを示した。しかしながら,その実態をみると,内需の伸びには力強さを欠き,年度後半以降には輸出の増勢が鈍化するなど,景気回復の足踏み状態がみられた。この結果,実質経済成長率は2.8%と49年度(マイナス0.2%)以来の低い伸びに止まった 〔1−1−2表〕。また,石油危機以降の業種別,規模別,地域別の景気動向の跛行性がみられている。
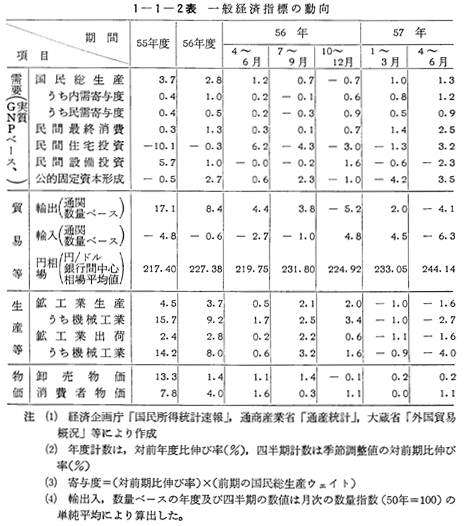
内需をみると,実質GNPの過半を占める民間最終消費(GNPベース,実質)は,年度前半の伸び悩みが影響し,対前年度比1.3%増に止まった。これは,消費者物価が安定的に推移したものの,実収入が低い伸びに止まっている中で,税金,社会保険料等の非消費支出が高い伸びを続けたために,実質可処分所得の伸びが低かったためである。
民間住宅投資(GNPベース,実質)は,55年度に対前年度比10.1%減と大幅な落ち込みを示した後,56年度も同0.3%減と引き続き低水準で推移した。これを新設住宅着工戸数でみると,同5.9%減の114万戸と,42年度の104万戸以来,14年ぶりの低水準となった。これには、所得の伸び悩み,建築費・地価等の住宅取得費が依然高水準にあること,人口移動や婚姻件数の減少等の要因が作用しているとみられる。
民間設備投資(GNPベース,実質)は,前年度比で,54年度9.8%増,55年度5.7%増のあと,56年度は1.0%増と増勢は著しく鈍化した。これは,55年後半以降規模別,産業別の跛行性が顕在化し,特に大企業は製造業,非製造業ともに堅調さを持続しているのに対し,中小企業の停滞が目立つようになったためである。この背景には第1に,消費支出,住宅投資等中小企業と結びつきの深い需要が伸び悩んだこと,第2に,中小企業の業況が悪化し,それだけ投資マインドも慎重化したこと等が考えられる。
公共投資は,年度全体としてはほぼ景気中立的なものとなった。即ち,上期には公共事業契約前倒しの効果もあってある程度景気の下支え的役割を果たしたが,下期にはその反動から減少した。
次に輸出入をみると,輸出は,世界貿易が停滞している中で,機械機器のウェイトが高まるなど輸出構造の高度化によって,55年度17.1%増(通関,数量ベース)に続き,56年度も年度全体では8.4%増とかなり増加したが,56年度下期に入って伸びが大きく鈍化した。これは,世界景気の低迷,我が国輸出商品の現地在庫の累増等が原因である。一方,55年度に4.8%減となった輸入(通関,数量ベース)は,内需全体の伸びが緩やかな中で,年度後半は増加の動きがみられたものの,56年度も0・6%減となり2年連続して減少した 〔1−1−3図〕。
次に,56年度の鉱工業生産は,対前年度比3.7%増に止まったが,これを業種別にみると,加工型産業が堅調な伸びを示した一方,鉄鋼,金属製品,化学等の素材型産業は停滞し,その跛行性は依然として残った 〔1−1−4図〕。これには,国内需要の低迷の影響を素材型産業の方がより強く受けていること,56年度中の円安が円ベースでのエネルギーコスト上昇に伴う素材型産業の国内需要の低下をもたらしたこと,及び加工型産業における国際競争力の強化等が考えられる。しかしながら,56年度第4四半期には,機械工業の生産・出荷とも対前期比減少に転じるなど,それまで堅調に推移してきた加工型産業にもかげりがみられる。
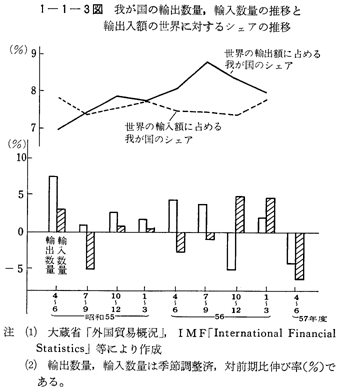
なお,57年度に入ってからの我が国経済をみると,大企業の設備投資は底固さを維持しているが,中小企業では停滞が続いている。また,個人消費は基調的には回復の方向を示している。一方,輸出は減少気味に推移しており,国内経済活動へもマイナスの影響を波及させている。
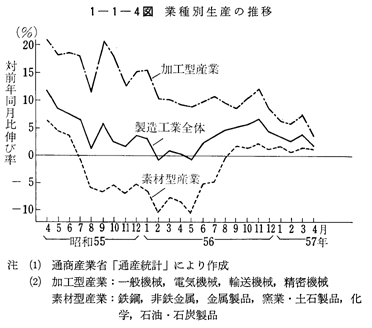
|