|
1 旅客輸送
昭和56年度の国内旅客輸送は,総輸送人員で517億9,600万人,対前年度比0.1%増と横ばい,総輸送人キロは7,905億人キロ,同1.1%増であった 〔1−1−14表〕。
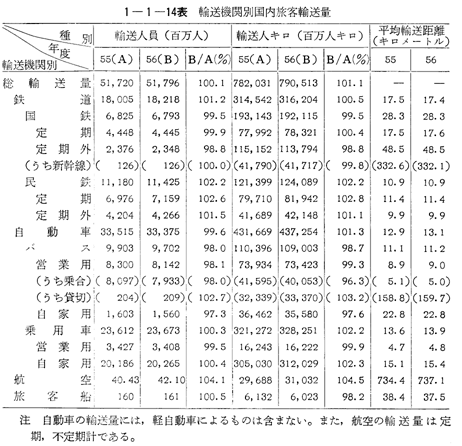
56年度の消費動向は,実収入が低い伸びであったこと等により実質民間最終消費支出は対前年度比1.3%増に止まり,また,全国世帯(家計調査)の実質消費支出も対前年同期比伸び率で7〜9月期,10〜12月期がマイナスとなり,年度全体では0.2%増に止まった 〔1−1−15図〕。56年度の旅行動向をみると, 〔1−1−16表〕, 〔1−1−17表〕のとおり,宿泊旅行回数,宿泊数,延人数,消費額等は実質民間最終消費支出及び家計消費支出の伸びをはるかに上回る伸びを示しており,旅行動向と消費支出の増減等,家計面との相関があまりみられなくなっている。
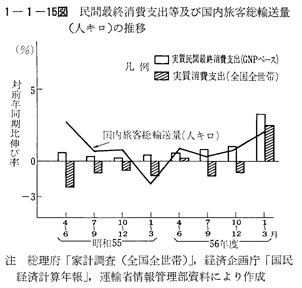
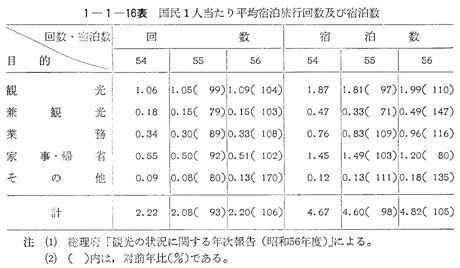
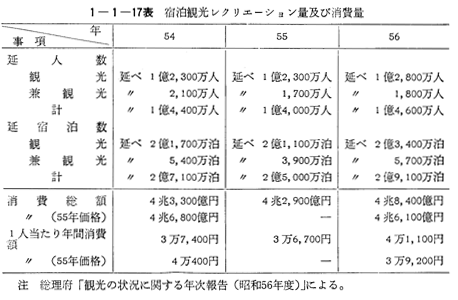
四半期別に輸送動向をみると, 〔1−1−18表〕のとおり,総輸送量(人キロ)は,前半は不振であったものの,10〜12月期以降は自家用乗用車の伸びにより徐々に回復傾向を示している。
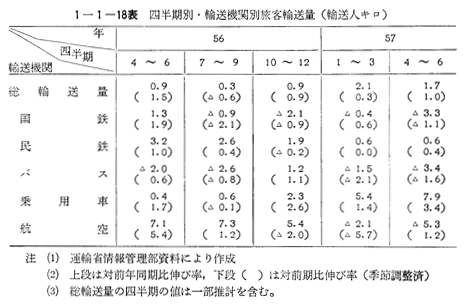
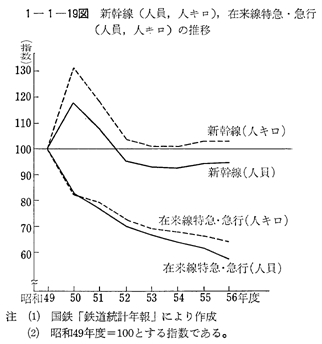
民鉄は, 〔1−1−20図〕のとおり,大都市を中心とする地下鉄の伸びの影響等により比較的堅調に推移し,輸送人員,輸送人キロとも対前年度比2.2%増であった。このうち,地下鉄の輸送人員は対前年度比4.9%増,輸送人キロ同4.8%増であり,東京と大阪における地下鉄の輸送人員は対前年度比東京4.0%増,大阪同7.5%増,輸送人キロは東京同4.3%増,大阪同7.1%増であった。なお,大手私鉄(14社)の輸送人員は対前年度比0.7%増,輸送人キロは同1.6%増とそれぞれ51年度以来の低い伸びとなっている。

自動車(軽自動車は含まない)は,第1次石油危機以降増勢が鈍化傾向にあるが,56年度は輸送人員が対前年度比0.4%減となり,輸送人キロは同1.3%増に止まった。バスは,輸送人員,輸送人キロとも前年度水準を下回り,このうち,乗合バスは,輸送人員で対前年度比2.0%減,輸送人キロで同3.7%減とかなりの減少となっている。なお,貸切バスは,56年度は過去最高を記録し,ここ数年着実に増加してきている。一方,乗用車は,輸送人員が対前年度比0.3%増,輸送人キロが同2.2%増であった。このうち,自家用乗用車は,その伸びが大幅に鈍化した55年度に引き続き,輸送人員が対前年度比0.4%増,輸送人キロが同2.3%増に止まり,ハイヤー・タクシーは,輸送人員が対前年度比0.5%減,輸送人キロが同0.1%減となっている。次に高速道路の交通量(台数)をみると,第1次石油危機後の50年度(対前年度比3.2%減)に減少した後は毎年増加を続け,56年度は対前年度比8.2%増となった。
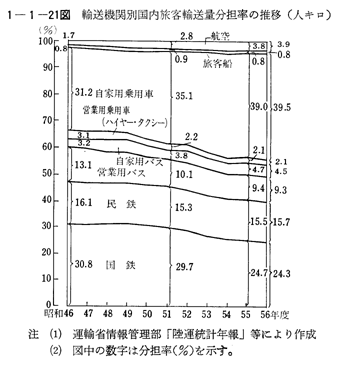
57年度に入って個人消費は回復の方向にあるものの,4〜6月期の輸送動向は,全般的に不振である。対前年同期比でみると,国鉄は,輸送人員2.7%減,輸送人キロ3.3%減となっている。民鉄は,輸送人員0.3%増,輸送人キロ0.6%増と伸びが鈍化している。また,自動車は輸送人員1.2%増,輸送人キロ4.8%増となっており,このうち,自家用乗用車は輸送人員4.0%増,輸送人キロ8.6%増であった。一方.航空は57年2月以降8か月連続して減少が続いており,57年4〜6月期は輸送人員5.4%減,輸送人キロ5.3%減であった。
51年度以降の国内旅客総輸送需要(人キロ)の動向をみると, 〔1−1−22図〕のとおり,51年度7,095億人キロが56年度7,905億人キロと1.11倍になっており(平均年率2.2%増),41年度から46年度1.53倍(同8.9%増),46年度から51年度1.15倍(同2.8%増)に比べ次第に伸びが鈍化している。対前年度比伸び率も 〔1−1−23図〕のとおり,46年度以降次第に低下し,51年度においては,戦後,統計が整備されて以来初めてマイナス(対前年度比0.2%減)を記録したが,53,54年度と対前年度比5.1%増,4.0%増と順調に回復したものの,55年度は対前年度比0.6%増と伸びが鈍化し,56年度は同1.1%増となった。
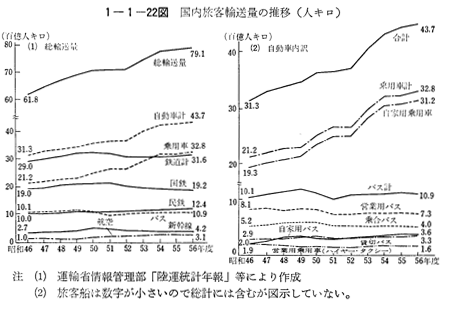
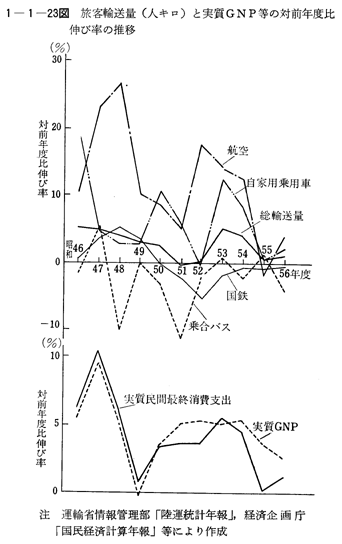
こうした国内旅客総輸送需要の鈍化傾向の背景としては次のようなことが考えられる。
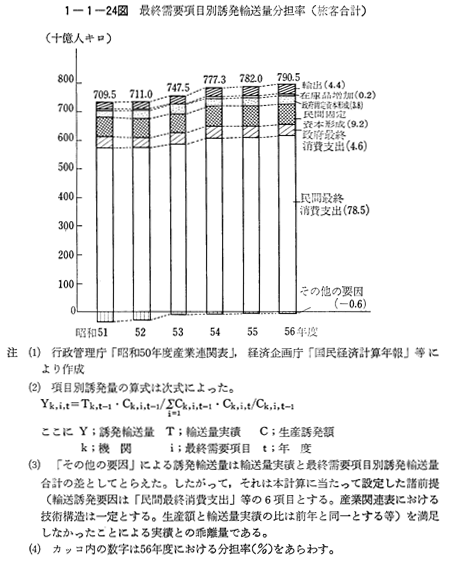
第2に,実質民間最終消費支出の伸びほどには国内旅客輸送量が伸びなくなってきていることがあげられる。54,55年度と国内旅客輸送量の実質民間最終消費支出に対する弾性値は0.9,2.0であったのに対し,56年度は0.8となっている。家計消費支出(実質)の動向をみても, 〔1−1−25図〕のとおり,51年から56年の消費支出(総合)は4.3%増となっているが,その内訳をみると,近年のレジャー指向を反映してスポーツ,外食費等のレジャー費は高い伸びを示し,また,自動車購入費,ガソリン代などの自動車等関係費は大きく伸びているものの,交通費は航空運賃を除き電車・汽車賃,バス代などの落ち込みがみられ,全体で3.5%減となっており,消費の伸びがあったとしてもそれが交通費に振り向けられなくなってきている。
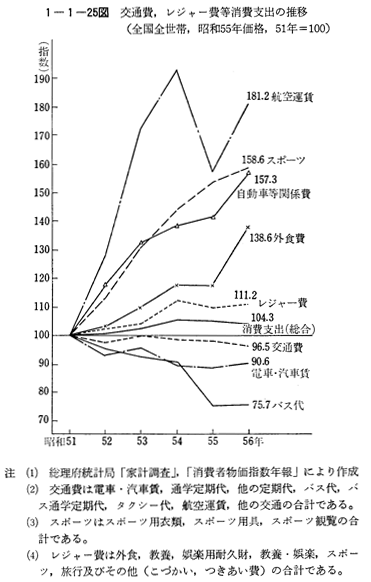
第3に,人口の伸びが低下していることや人口移動率の低下などの社会的移動要因が減少してきていることがあげられる。生産年齢人口(15歳〜64歳)の推移をみると, 〔1−1−26表〕のとおり,40年から45年平均年率1.3%増,45年から50年回1.0%増に対して,50年から55年は同0.8%増となっており,また,全人口に占める比率も次第に低くなってきている。次に,人口移動率を「住民基本台帳人口移動報告年報」(総理府統計局)によってみると,市区町村間の人口移動率(日本人人口に対する移動数の比率)は,30年代前半は5%台で推移し,35年には6%台に,38年には7%台に,45年には8.02%に達した。
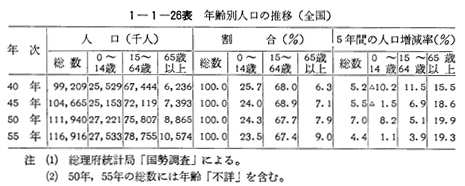
しかし,その後移動率は低下を続け,55年には6.09%と35年当時の水準に,56年には5.89%と30年代前年と同程度にまで低下してきている。3大都市圏の人口の増加は,50年から55年平均年率1.0%増となっており,40年から45年回2.7%増,45年から50年回2.1%増に比べ低下しており,3大都市圏への人口の集中化傾向が鈍化していることがわかる 〔1−1−27表〕。
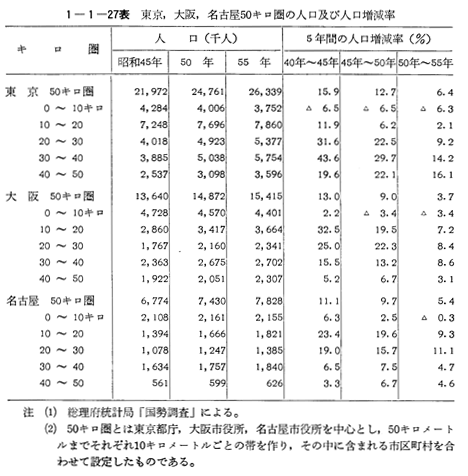
今後の国内旅客総輸送需要の動向については,経済の安定成長期の下で基調としては,高度経済成長期のような高い伸びはみられないものと考えられるが,以上のような要因のほかに,週休2日制の進行等による自由時間の増加 〔1−1−28図〕,消費の多様化等の国民生活の変化や団体旅行型から小グループ型へといった旅行動向の質的変化など種々の要因もあり,旅客輸送需要の具体的な増減を推定することは極めて困難な状況にある。
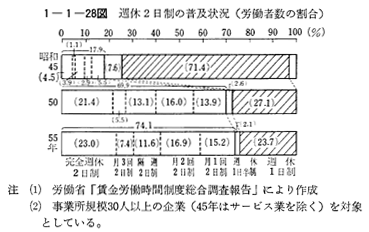
|