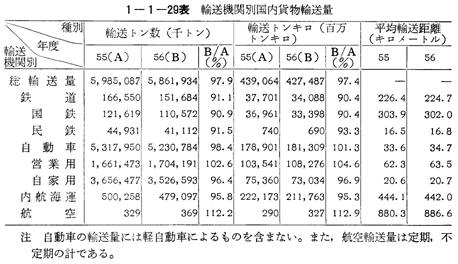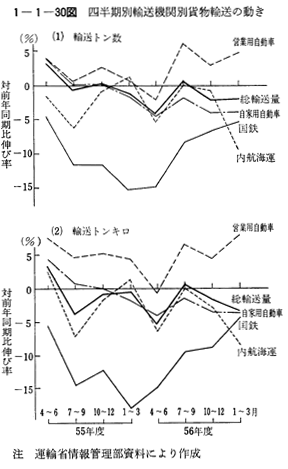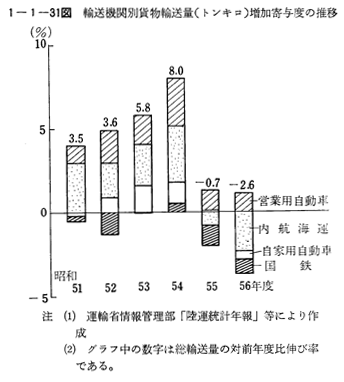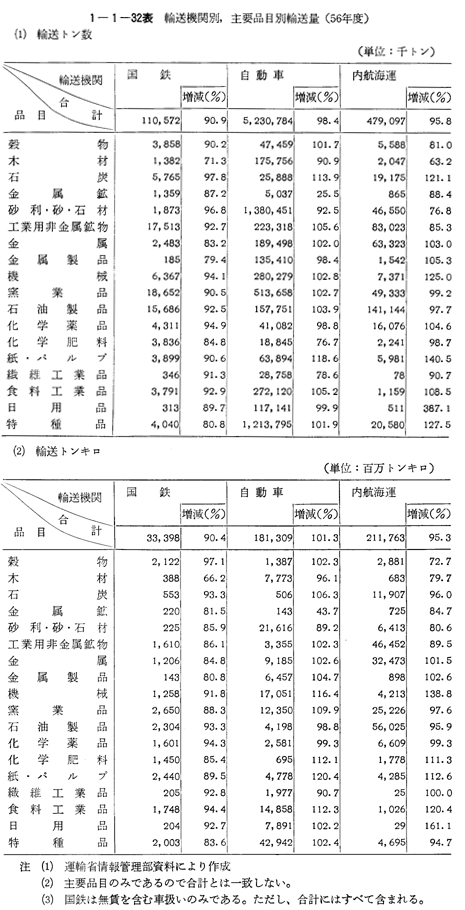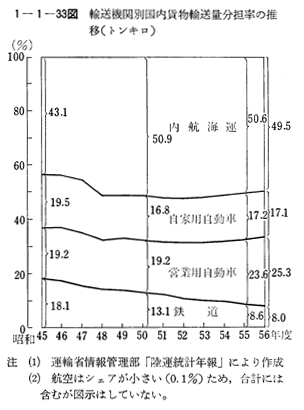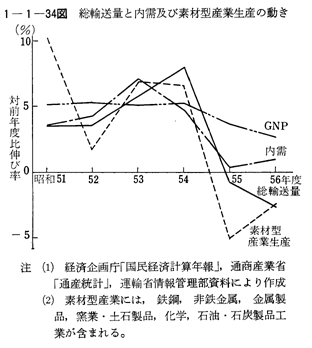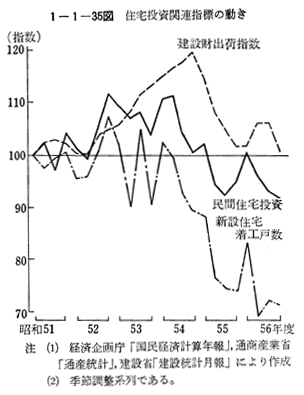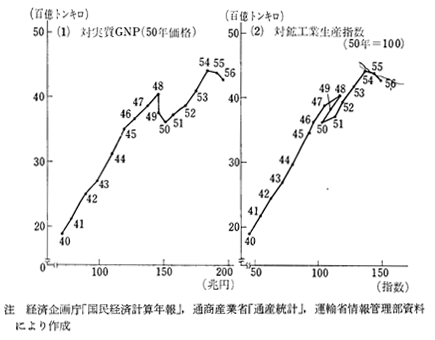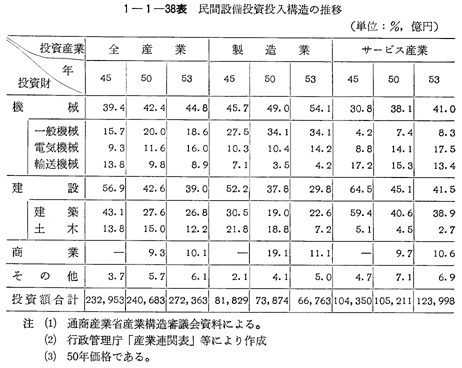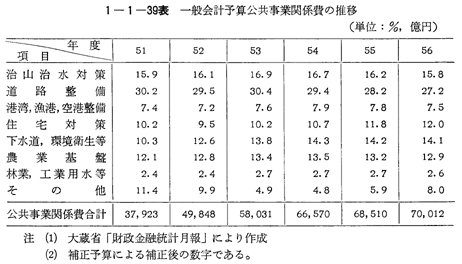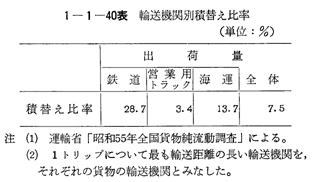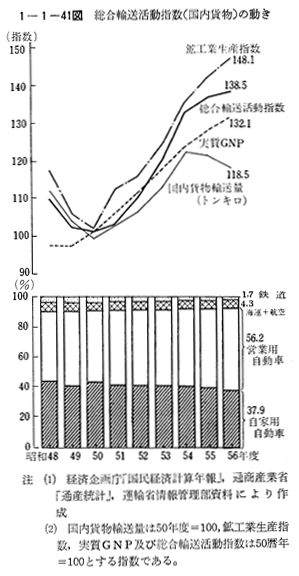|
2 貨物輸送
(1) 56年度の概況
56年度の国内貨物輸送の動向をみると,総輸送トン数は,58億6,193万トン,対前年度比2.1%減と51年度以来5年ぶりの減少となり,総輸送トンキロも4,275億トンキロ,同2.6%減と前年度(0.7%減)に引き続く減少となった 〔1−1−29表〕。
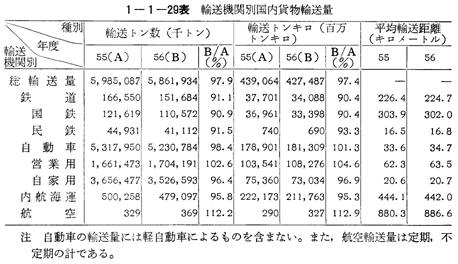
56年度の特徴としては,第1に,航空を除く各輸送機関で前年度並みかそれ以上の落ち込みとなっていること,第2に,国鉄の長期的低落傾向が依然として続いており,56年度も10%程度の大幅な減少となっていること等があげられる。
このような貨物輸送の落ち込みをもたらした要因としては,景気の停滞が考えられる。つまり,56年度の我が国経済は,内需の伸びに力強さを欠くとともに,その間,景気の下支えをしてきた輸出にかげりがみられるようになり,実質GNPは対前年度比2.8%増と49年以来の低い伸びに止まった。また,生産面においても,素材型産業の停滞に加え,加工型産業にも増勢鈍化がみられるようになった。更に,構造的には我が国の経済構造は高度成長期に比べて,より輸送を誘発しにくい構造へと変化しつつあると考えられる。
輸送機関別にみると,国鉄は, 〔1−1−30図〕のとおり,55年7〜9月期から56年4〜6月期まで4四半期にわたって対前年同期比10%以上の大幅な落ち込みを続け,56年7〜9月期以降は1桁台の減少に止まっているものの,依然として大幅な減少を続けている。その結果,56年度は輸送トン数が対前年度比9.1%減,輸送トンキロが同9.6%減となり, 〔1−1−31図〕のとおり総輸送量の落ち込みに大きく寄与している。この輸送量は,輸送トン数では22年度,輸送トンキロでは25年度とほぼ同水準である。これを品目別にみると, 〔1−1−32表〕のとおり,紙・パルプ,窯業品,工業用非金属鉱物等の比較的輸送ウェイトの高い貨物を中心にほとんどすべての品目で減少している。なお,コンテナによる輸送量をみると,56年度は対前年度比5.0%減の78億トンキロとなっている。このような国鉄貨物輸送の落ち込みは,輸送構造の変化による国鉄の地位の低落のほかに,最近の経済活動の停滞という短期的要因もあり,その落ち込みをより大きくしていると考えられる。
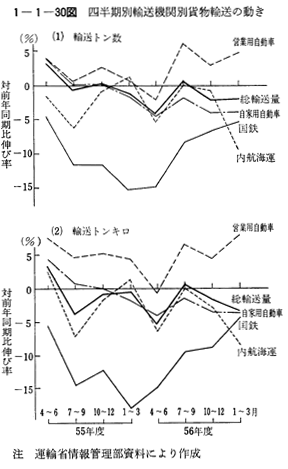
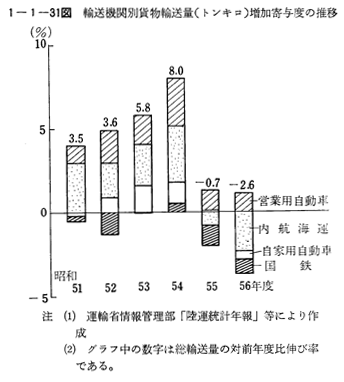
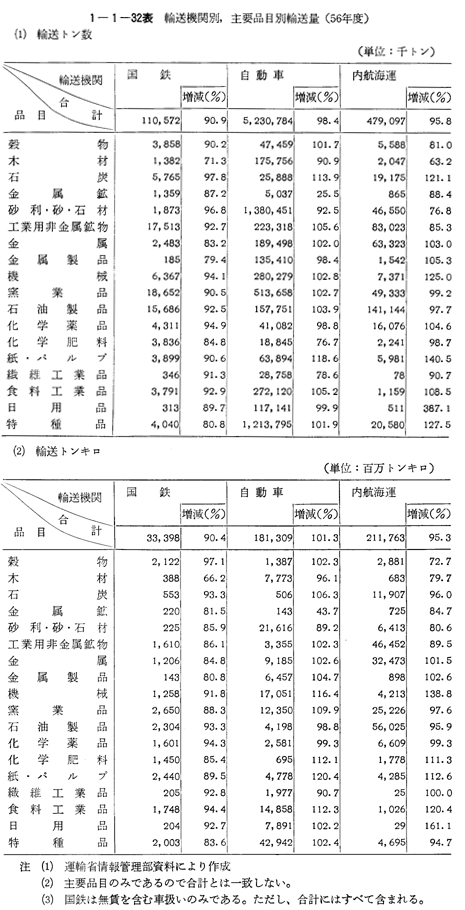
次に,自動車(カーフェリーを利用したものを含み,軽自動車によるものを含まない)をみると,輸送トン数は対前年度比1.6%減と51年度以来のマイナスとなり,輸送トンキロも同1.3%増と前年度水準を上回ったものの,その伸びは大きく鈍化している。これを営業用,自家用別にみると,営業用自動車は,4〜6月期こそ対前年同期比でマイナスとなったものの,7〜9月期以降は比較的堅調に推移し,年度全体では輸送トン数で対前年度比2.6%増,輸送トンキロで同4.6%増となった。これに対して自家用自動車は,56年1〜3月期から落ち込みを続けており,56年度は輸送トン数で3.6%減,輸送トンキロで3.1%減となった。これは,自家用自動車の大宗貨物である木材,砂利・砂・石材,セメント等が大幅減少となったためである。なお,保有台数をみると,営業用自動車は,対前年度末比で55年度末3.8%増,56年度末2.8%増と増加を続けているが,自家用自動車は,55年度末が0.2%の微増となった後,56年度末は初めて0.6%の減少となっている。
内航海運は,前年度に引き続いて前年度水準を下回り,輸送トン数で4.2%減,輸送トンキロで4.7%減となった。これを四半期別にみると,56年4〜6月期,57年1〜3月期の落ち込みが大きく,特に1〜3月期は輸送トン数,輸送トンキロとも対前年同期比で10%近い大幅な落ち込みをみせている。これは,民間住宅投資等の内需の不振,素材型産業の生産の停滞,石油需要の低迷等により,荷動きが鈍かったからである。品目別の動向をみると,砂利・砂・石材,工業用非金属鉱物(石灰石,原油)等での落ち込みが目立っている。内航海運の減少は,総輸送量(トンキロ)の落ち込みに大きな影響を与えており,56年度においてはマイナス2.1%の寄与度となっている。
航空は,輸送トン数で対前年度比12.2%増,輸送トンキロで同12・9%増と,55年度に鈍化した伸び(輸送トン数4.3%増,輸送トンキロ6.0%増)が回復し,年度を通して好調に推移した。これを路線別(不定期を除く)にみると,幹線は輸送トン数10.1%増,輸送トンキロが10.6%増,ローカル線は,同じく17.2%増,20.6%増と,ローカル線の高い伸びが目立っている。
次に,営業倉庫の取扱量をみると,普通倉庫の入庫量は,前年度に比べ0.2%の微増に止まり,1億5,147万トンであった。一方,前年度急増した平均月末在庫量は,窯業品等を除く各品目で減少し,全体で対前年度比5.7%の減少となった。また,前年度増加した冷蔵倉庫の入庫量は,ほとんどの品目で増加し,全体では対前年度比9.4%増の950万トンであったが,貨物の回転が速くなったことにより,平均月末在庫量は前年度並みに止まった。
以上のような輸送動向により,56年度の輸送機関別国内貨物輸送トンキロ分担率は, 〔1−1−33図〕のとおり,前年度に比べて鉄道,内航海運,自家用自動車が低下したのに対して,営業用自動車の増加が目立っている。
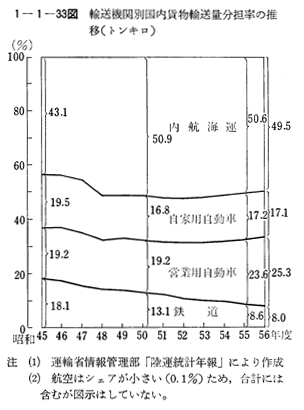
(2) 近年の国内貨物総輸送需要の動向について
国内貨物総輸送需要(トンキロ)の動向をみると,高度成長期に10%台の成長を続けた後,第1次石油危機の影響により48年度をピークとして急落したが50年度を底に急速な回復をみせた。しかし,55年度に5年ぶりにマイナスとなった後,56年度は減少幅を拡大し対前年度比2.6%の減少となっている。
このような国内貨物総輸送需要の伸び悩みの背景としては次のようなことが考えられる。
まず第1に,国内需要の低迷があげられる。第2次石油危機の影響により景気の調整過程に入った我が国経済は,55年度から56年度の半ばにかけて外需に支えられた経済成長を遂げた。しかし,その過程では内需の基調は弱く, 〔1−1−34図〕のとおり,55年度は対前年度比0.4%増,56年度同1.0%増とわずかな伸びに止まった。内需のうち誘発輸送量の大きな民間住宅投資をみると,55年度10.1%減,56年度0.3%減と連続してマイナスになっており,民間住宅投資に関係の深い指標をみても55年度に入ると急速な落ち込みをみせ,56年度末に至っても依然として回復の兆しをみせていない 〔1−1−35図〕。なお,外需による誘発輸送量は内需のそれに比べて小さいと考えられるため,外需依存の経済成長下ではGNPの伸びほどには貨物輸送量は伸びず,GNPよりは内需の動きに近くなっている。
第2に,生産面では,素材型産業が不振であったことがあげられる。 〔1−1−34図〕をみると,素材型産業の生産がマイナスの伸びとなった55,56年度は,総輸送量も落ち込んでいる。また 〔1−1−36図〕により主要品目別の輸送動向をみると,窯業品,石油製品等の素材型産業関連貨物の伸びは,55,56年度と低くなっている。
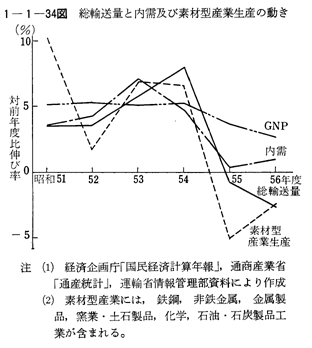
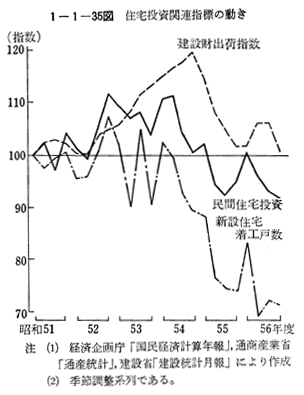

第3は,輸送需要をめぐる環境が変化しつつあることであり,産業構造,経済構造等の環境が,徐々に輸送需要を発生しにくいものへと変化しつつあることが考えられる。 〔1−1−37図〕により,貨物輸送量と経済指標(実質GNP,鉱工業生産指数)の関係をみると,第1次石油危機以前は両者に強い相関があり,経済の拡大に伴って輸送量も順調に鉱大したが,第1次石油危機以降は,経済の拡大ほどには輸送量は伸びなくなっている。
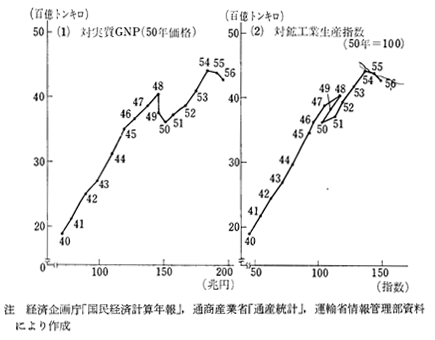
そのような環境変化として第1にあげられるのは産業構造の変化である。我が国の産業に占める第2次産業の比重は徐々に低下しており,代わって単位産出額当たりの発生輸送需要の小さな第3次産業の比重が高まっている。国民経済計算により産業別生産額の推移をみると,第3次産業の比率は,名目価格ベースで45年51.1%,50年56.2%,55年58.0%と上昇している。更に,比重を下げつつある第2次産業においても,大量の輸送需要を発生させる素材型産業の伸びが鈍化するとともに,単位産出額当たりの発生輸送需要が小さく,しかも高度の輸送サービスの質を要求する加工型産業の伸びが高まっている。
その第2は,民間設備投資の質的変化である。民間設備投資は,第1次石油危機後の安定経済成長下においても投資額としてはかなりの水準を維持しているものの,その内容についてみると質的変化が生じており,同額の投資に対する輸送需要の発生はより小さなものになりつつある。 〔1−1−38表〕により,民間設備投資に占める建設向け投資の比率をみると,45年56.9%,50年42・6%,53年39.0%と大きく低下しており,逆に,電気機械を中心とする機械向け投資比率は,45年39.4%,50年42.4%,53年44.8%と増加を示している。これは,第1次石油危機後の期待成長率のシフトダウン,エネルギー価格の上昇等の企業環境の悪化に加え,近年の急速なエレクトロニクス化の進展に対応するため,かつてのような工場の新増設といった拡張投資から省エネ投資,合理化・省力化投資へと投資重点が移っているためと考えられる。
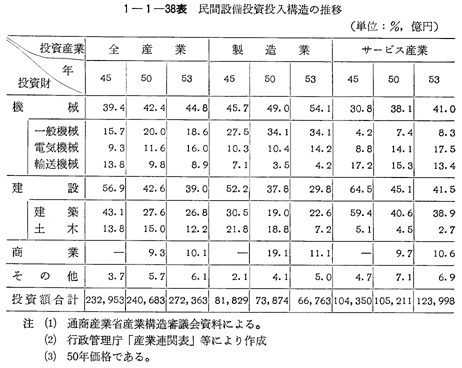
その第3は,住宅投資の変化である。住宅投資は,55年度以降低調に推移しているが,これには,景気停滞に伴う所得の伸び悩みや建築費・地価等の住宅価格の高値安定による住宅取得能力の低下のほかに,人口の移動や増勢の鈍化,住宅戸数水準の高まり等の要因も考えられる。したがって,単に景気が回復しただけではかってのような住宅投資の盛り上がりは期待し難い状況にある。
その第4は,公共投資の伸びの低下及び質的変化である。近年の公共投資は高度成長期に比べてその伸びが低下しており,50年度から56年度までの平均伸び率は4.5%となっている。この伸びの低下が貨物輸送の低下をもたらしている。また, 〔1−1−39表〕により,公共事業関係費の推移をみると,治山治水対策,道路整備等の項目でシェアの伸び悩みや減少がみられるのに対して,住宅対策,下水道,環境衛生等の項目はシェアを拡大させており,公共投資が生活環境の充実により多く向けられつつある状況となっている。
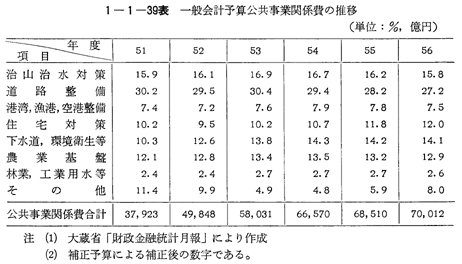
今後の貨物輸送需要の動向については,景気の回復とともにある程度の回復は見込まれるが,経済の安定成長期の下では,基調としては高度成長期のような高い伸びは期待できないと考えられるが,以上の要因のほかに直行輸送比率の上昇,物流の合理化,工場立地の変化等にも注目する必要がある。
まず,直行輸送比率の上昇が総輸送量(トン数ベース)に与える影響についてみると, 〔1−1−40表〕のとおり,他の輸送機関に比べて直行輸送比率の高い自動車輸送のシェアが上昇すれば,積替え減少による総流動輸送量の減少により,総輸送量の伸びを鈍化させることになる。純流動に対する総流動の比率をみても,49年の1.85,54年の1.73と徐々に小さくなっており,直行輸送の比率が高まりつつある。なお,自動車のシェアの高まりの結果,付加価値ベースによる輸送活動指数は,依然として増加傾向を続けている 〔1−1−41図〕。
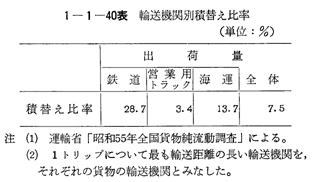
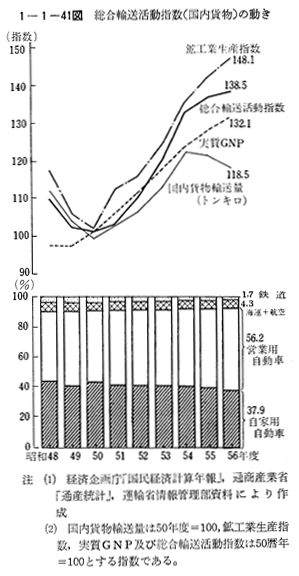
次に,物流の合理化が貨物輸送に及ぼす影響に着目する必要がある。高度成長期には,少数の大規模工場より生産された商品が全国的に展開し,各々独自の販売網が形成された。そのため,交錯輸送が増大したが,近年は販売網の確立に伴って工場が全国に分散立地されるようになり,更に商品交換までもなされるようになっている。石油を例にとると,従来は各企業が独自の販売網を持ち,全国的にはかなりの交錯輸送が行われていたと考えられる。しかし,石油危機後は,企業のブランドイメージやタイミング等の問題もあり,必ずしも急速な進展をみせているとはいえないが,精製委託や製品交換といった形の物流の節約が行われるようになっている。精製委託量をみると,全原油処理量に対する比率が51年度の8.8%から55年度には11.2%にまで上昇しており,このような形の交錯輸送の減少が品目によってかなり進んでいると考えられる。このような物流の合理化も省輸送につながっていくものと考えられる。
更に,工場立地の変化がある。かつては素材型産業を中心とする臨海型の大規模工業立地が多く,大量に発生する貨物の輸送は海運により担われていたが,近年は内陸部に加工型産業による小規模な立地がみられるようになっている。これは,全国的な道路網の整備や加工型産業の発展とともに,荷主による販売網の形成等の理由によるものであり,各地の小規模工場に関連する貨物の輸送は自動車が担うものと考えられる。
このような中で,輸送機関別にここ数年の貨物輸送の動向を考えると,内航海運は現在のような経済情勢の下では大宗貨物である基礎資材の伸び悩みが予想されることから高い伸びは期待できない。鉄道は,大宗を占めている比較的ロットの大きな貨物の需要が停滞するとともに,小ロットの貨物も自動車に移転しつつあり,今後も減少傾向を続けると考えられる。これに対して自動車は,高速道路網の整備等により環境条件が整ったことに加え,その輸送サービスが荷主のニーズにマッチしたこと等によりシェアを拡大してきているが,今後とも他の輸送機関に比べて相対的に高い伸びを示すものと考えられる。
今後は,総体としての伸びよりも,個々の輸送機関,輸送品目の動きに注目することが重要になるとともに,輸送機関サイドにおいては,物流の合理化,効率化の要請に対応していくことが必要になると考えられる。
|