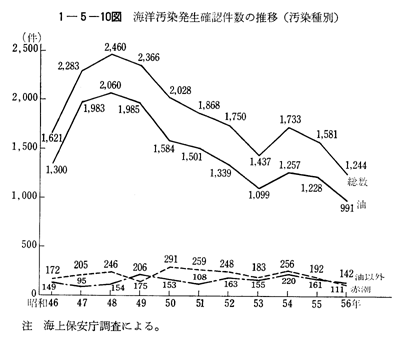|
2 海洋汚染の現況と対策
(1) 海洋汚染の現況
海上保安庁が確認した海洋汚染の発生確認件数によると,我が国周辺海域においては,48年の2,460件をピークに54年はやや増加したものの全体として減少傾向を示しているが,依然として56年は1,244件もの汚染が発生している 〔1-5-10図〕。汚染種別では油汚染が全体の80%を占め,その排出原因は取扱い不注意及び故意排出によるものが大半を占めている。海域別には東京湾,伊勢湾及び瀬戸内海(大阪湾を含む)で,全体の48%を占めている。
また,56年に海上保安庁及び気象庁が実施した海洋汚染の調査によると,日本周辺海域及び西部北太平洋における油分,重金属等による海洋汚染は低レベルにあり,汚染の進行は認められないが,廃油ボールは黒潮流域に常時漂流しているものと推定され,特に南西諸島においては他の海域に比べ,漂着が依然として多い状況であることが認められている。
(2) 海洋汚染防止対策
海洋汚染を防止するため,各種の規制法が制定されているが,海洋汚染の主な原因となっている油及び廃棄物による汚染を防止するため「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」が制定されている。この法律に基づき①船舶,海洋施設及び航空機から海洋に油及び廃棄物を排出すること並びに船舶及び海洋施設において油及び廃棄物を焼却することを規制し,②これらの規制を担保するため,ビルジ排出防止装置の設置,廃棄物排出船の登録,焼却設備の検査等を義務付け,③大量の油の流出に対処するため,タンカー所有者等に対し,オイルフェンス,油処理剤等の備付けを義務付ける等の措置を積極的に講じている。
これらの排出規制を合理的に実現するため,船舶から発生する廃油を処理する廃油処理施設が,57年4月現在,民間,港湾管理者等により83港141か所に設置されており,56年度は事業費8,000万円をもって川崎港等2港の既存施設の改良を実施した。
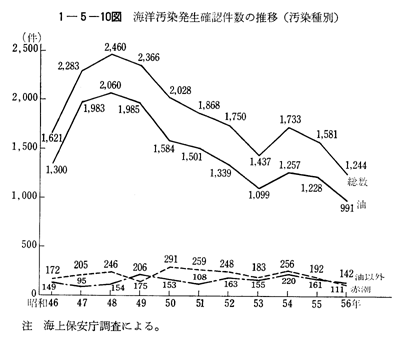
また,海洋汚染の防除事業として,56年度は,港湾区域内では有害物質等を含む堆積汚泥の俊傑,覆土等の公害防止対策事業を事業費78.8億円をもって水俣港等12港において実施し,更に,浮遊ごみ等の清掃を行うための清掃船の建造を事業費1.1億円をもって名古屋港等2港において実施した。また,一般海域については,海洋環境の保全を図るため,浮遊油及び浮遊ごみの回収事業を事業費17.1億円をもって東京湾,伊勢湾及び瀬戸内海において実施するとともに,事業費3.1億円をもって油回収船1隻を建造した。
このほか,内湾,内海における水質,底質の汚染を防除するため,東京湾,伊勢湾,大阪湾,広島湾及び周防灘において56年度は事業費6.7億円をもって底質浄化に係る実施設計調査を直轄事業として実施した。
ところで,海洋汚染の大半は船舶からの油によるもので,その排出原因としては,油取扱い作業時の不注意がその半数を占めている現状にかんがみ,海上保安庁は,海事関係者等に対し油排出事故防止のための基本的事項を内容とするパンフレットを配布するとともに,財団法人日本海難防止協会等の海洋汚染防止講習会を通じて海洋汚染防止思想の普及及び関係法令の周知徹底を図っている。更に毎年期間を定めて「船舶漏油事故防止推進期間」を設けて各船ごとに漏油事故の防止指導を行っている。一方海洋汚染事犯は,その発見が容易でなく,しかも証拠となる油が比較的短時間に拡散消滅することなどから,違反船舶の特定が困難となるため,監視機能に優れた航空機と証拠資料採取,立入検査等を行う巡視船艇を連携させて監視取締りを行っている。
特に,我が国周辺海域において確認した外国船舶からの海洋汚染は,ほとんど油によるものであり,その原因としては,初歩的ミスのほかに,海洋汚染防止に対する認識の欠如に起因すると思われる作業時の注意不足,我が国の関係法令に対する理解不足もみられるため,我が国の関係法令の要旨,汚染防止のため具体的な対策等を内容とする数か国語のパンフレットを配布し漏油事故防止指導を行っている。
また,外国船舶からの油による海洋汚染のうち,領海内で発生したものについては,我が国の法令を適用してその刑事責任を追及しているが,領海外で発生したものについては,日本国内法を適用できないため,「1954年の油による海水の汚濁の防止のための国際条約」(62年及び69年に改正,以下「1954年条約」という)に基づき当該船舶の旗国に対し違反事実の通報を行い適切な措置を求める旗国通報を行っている。しかし,こうした制度は旗国の裁量に任されているという点で限界があり,このため海洋法条約草案で規定されている200海里排他的経済水域における沿岸国の海洋汚染取締権限の早期確立が望まれる。
更に,海洋汚染は地球的規模の環境問題であるので,その防止については,国際協力を積極的に推進する必要があることが早くから認識されていた。我が国としては現在までに1954年条約,「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」等を締結し,それぞれ昭和42年,55年に国内法化し,国際的動向に対応しつつ,規制の強化を図ってきている。ところが,国際的には更に規制強化の方針が打ち出され,軽質油,有害液体物質,汚水等規制対象物質の大幅な拡大と排出規制の強化に加え,油排出監視制御装置,分離バラストタンク等による未然防止効果の高い船舶の構造・設備規制とこれらに対する検査制度の義務付け等を内容とする「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書」が53年に採択されている。本議定書は商船船腹量の合計が総トン数で世界の商船船腹量の50%以上になるような15か国以上の国が締結した日の後1年で発効することになっているが,57年10月1日にイタリアが批准したことにより,商船船腹量53.7%,締約国数15か国となり,発効要件を満足することとなったため,本議定書は58年10月2日に発効することとなった。我が国としても,このような国際的動向に対応して海洋汚染防止の一層の推進を図るためこれを早期に締結し,国内法化するための所要の準備を進めているところである。
海洋は今後ますます海上交通,漁業,海底資源開発,海洋レクリエーション等各種の分野において海洋の利用・開発が進むものと予想されるが,その利用・開発の影響が広範囲に及ぶという海洋の特殊性を考慮し,広域的,長期的視点に立脚して海洋の利用・開発と海洋環境の保全との調和を図る必要がある。
|