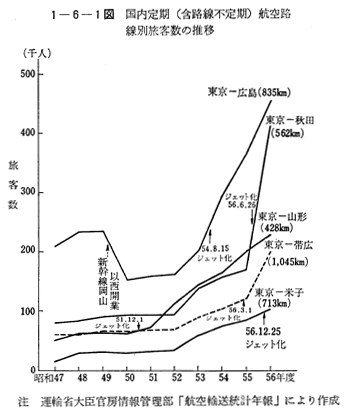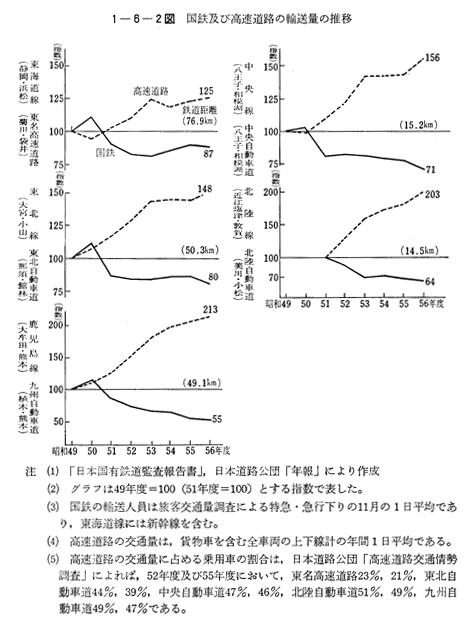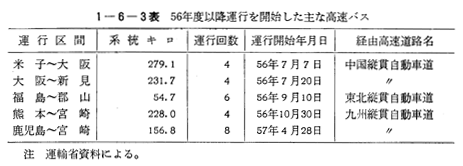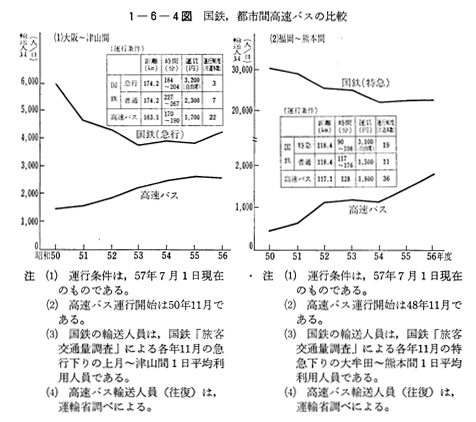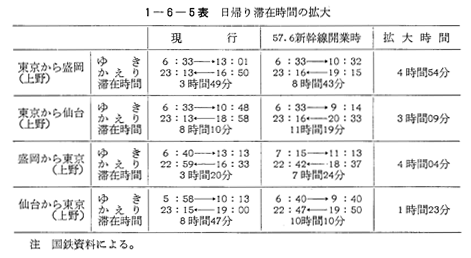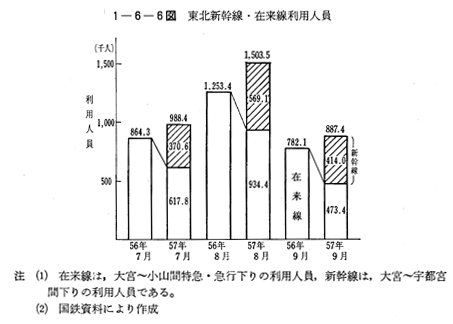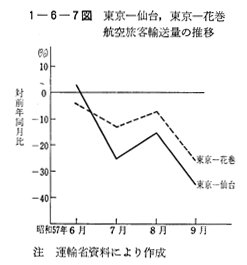|
2 高速交通網の進展
国民の高速化指向の高まりの中で,高速交通手段の整備が順次進められている。
航空については,地方空港と首都圏等とを結ぶ路線,離島本土間の路線のジェット化,増便が進められている。
最近ジェット化された路線の輸送人員の推移をみると 〔1−6−1図〕のとおりであり,いずれもジェット化により大きく伸びている。東京-帯広(56年3月ジェット化),東京-秋田(56年6月ジェット化),東京-米子(56年12月ジェット化)では,各々対前年度比76.0%増,140.3%増,23.1%増となっている。
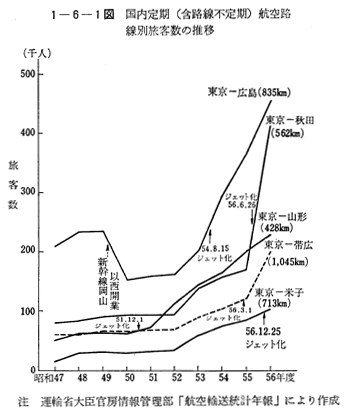
離島路線については,56年度以降,宮古-石垣(56年8月),東京-八丈島(57年4月)がジェット化され,長崎-福江(56年8月),福岡-対馬(56年11月),鹿児島-屋久島(57年7月)等で増便されている。なお,対馬空港,宮古空港において,現在,ジェット化のための滑走路延長工事が進められている。
高速自動車国道の56年度末供用延長は,3,010.4キロメートルに及んでおり,高速道路を利用した自動車輸送の進展が著しく, 〔1−6−2図〕のとおり,並行する国鉄の輸送需要の減少に対して,自動車の伸びが目立っている。また,高速道路を利用した都市間高速バス(運行系統キロの概ね半分以上が高速道路利用のもの)は,57年8月現在,134系統(40社),1日当たりの運行回数は,1,777便,高速道路内の運行距離は,1日当たり延べ13万キロに及んでいる。56年度においても,中国縦貫自動車道,九州縦貫自動車道等を利用した都市間高速バスが運行を開始している 〔1−6−3表〕。
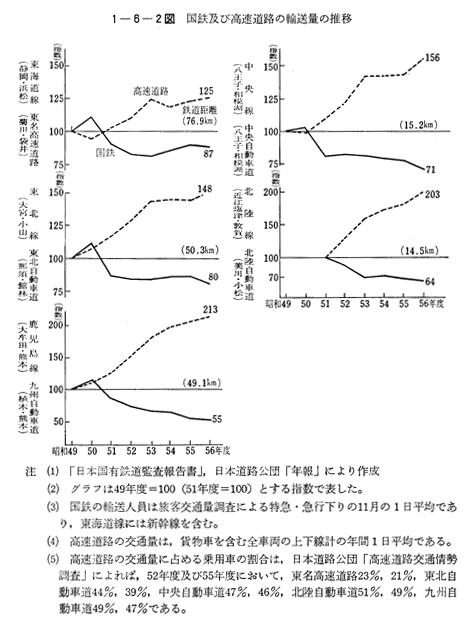
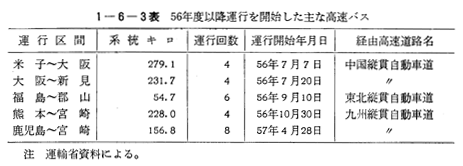
都市間高速バスと国鉄とを比較すると,所要時間,運行頻度や運賃面で高速バスが優れ,市街地へのアクセスが便利な場合もあり,国鉄の利用人員の減少傾向に対して高速バスは年々輸送量を伸ばしている 〔1−6−4図〕。鉄道によるほど輸送需要がなく,鉄道ではフリークエントなサービスが困難な地域,殊に,地方都市と大都市圏を結ぶ路線,地方都市相互間の輸送において,高速バスは,利用者ニーズに適合したフリークエントなサービスを提供するなど効果を発揮している。
57年6月23日,東北新幹線大宮〜盛岡間が開業し,新幹線沿線都市と上野間の時間距離は,盛岡が2時間20分程度,仙台が1時間30分程度各々短縮し,この結果,日帰り滞在時間も拡大するなど利便向上が著しい 〔1−6−5表〕。開業後3か月の利用人員は, 〔1−6−6図〕のとおりである。また,東北新幹線と競合する航空路線では,輸送人員の落ち込みが目立っている 〔1−6−7図〕。
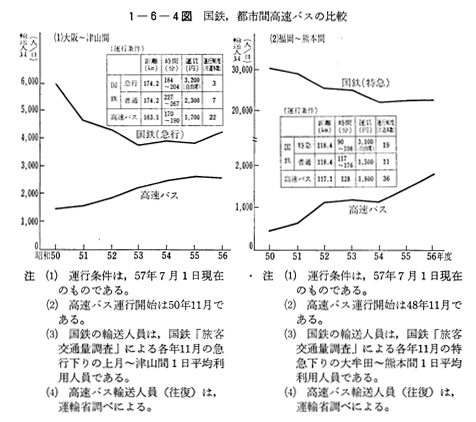
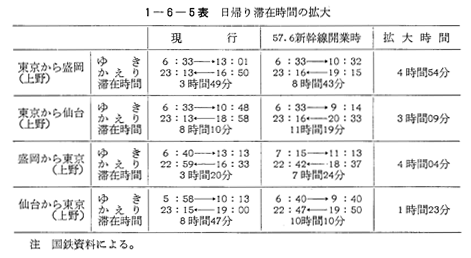
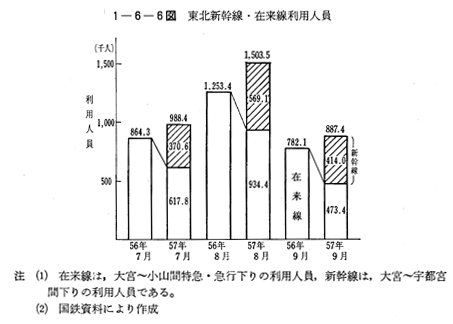
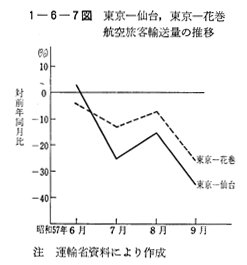
なお,57年11月15日,上越新幹線大宮〜新潟間が開業し,これにより,上野〜新潟間は,1時間40分程度短縮し,2時間40分程度で結ばれることとなった。
|