|
3 地域旅客輸送の充実
55年に実施した「大都市交通センサス」によると,首都圏では,人口が50年から55年にかけて6.7%増加した。このうち鉄道定期券利用者は7.8%増となったが,バス・路面電車定期券利用者は15.4%減となっている。また,近畿圏,中京圏も同様の傾向を示しており,大都市圏においては,大都市高速鉄道網の進展等により,鉄道定期券利用者が増加しているのに対し,バス定期券利用者が減少している 〔1−6−8図〕。
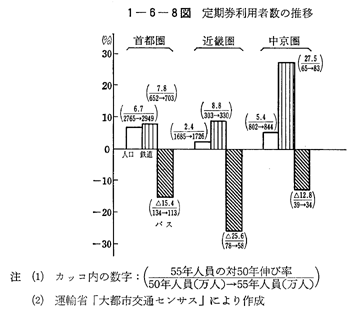
また,鉄道定期券利用者の端末交通手段の推移をみると,いずれの圏域でも二輪車利用の増加が目立っている 〔1−6−9図〕。

居住地から通勤,通学地への移動の際に利用する交通機関(鉄道・バス等)の平均利用回数(鉄道定期券利用者)は,首都圏の都県間移動では2.4回,近畿圏の府県間移動では2.2回,中京圏の県間移動では2.1回となっており,大都市圏において交通機関の乗継ぎが多いことがわかる。

なお,総理府統計局による55年国勢調査に基づく従業地,通学地集計結果でも,全国の15歳以上の通勤,通学者総数は,対50年度比で10.4%増であるのに対し,自市区町村内への移動は6.4%増,県内他市区町村への移動は16.1%増,他県への移動は15.1%増となっており,全国的にも通勤,通学の遠距離化が進んでいることがわかる 〔1−6−11図〕。

「大都市交通センサス」にもあるとおり,大都市圏においては,交通機関の乗継ぎが多くなっているが,利用者ニーズの多様化,高度化に対応した効率的で質の高い都市交通ネットワークの整備を図っていくためには,乗継ぎに伴う物理的,心理的抵抗感をなくすなど,出発地から目的地までの移動の連続性を確保するハード面,ソフト面の施策が必要となっている。
ア 相互乗り入れ,乗換えを容易にするための施設整備の進展
相互乗り入れについて54年度以降の進展をみると,54年7月には名古屋市交鶴舞線と名鉄豊田・三河線,55年3月には都営新宿線と京王線が各々乗り入れを開始し,56年4月には東急新玉川線・田園都市線と営団半蔵門線の相互乗り入れ区間が延長されるなど逐次相互乗り入れが進展している。54年度以降,相互乗り入れ区間は延べ約60キロ増加し,この結果,56年度末現在の相互乗り入れ区間は,三大都市圏で延べ580キロに上っている。 相互乗り入れば,乗換えのための待ち時間や階段の上り下りといった物理的障害だけでなく,心理的抵抗をなくし,利用者サイドの利便向上に著しいものがある。例えば東急線,営団線を利用した通勤経路をみると, 〔1−6−12図〕のとおり,相互乗り入れ区間を利用した経路と比べ,運賃額において他の経路より高いものの,乗換えが1回で済む,所要時間が短いといった利便性の点で優れていることから,利用率が最も高くなっている。
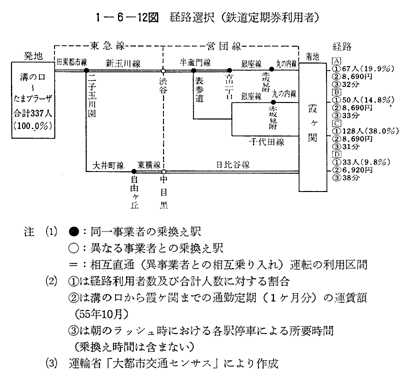
鉄道相互の移動の連続性については,相互乗り入れのほか,同一ホームにおける対面乗換えを含め,今後ともその向上を図っていく必要がある。
イ バスロケーションシステムの整備
このような状態の中で,バスの運行状態を正確,迅速に把握し,主要バス停留所に次のバスの行き先,到着予告を表示するなど,必要な情報を伝えることにより,バス待ちのイライラ感を解消し,バスの利便性を高めることを目的として,バスロケーションシステムの開発,導入が進められている。 56年度においても,札幌市,秋田市,市川市,京都市において導入されており,この結果,56年度末現在,バスロケーションシステムの導入された都市は13に上っている。バスロケーションシステムの導入効果については,いずれの都市においても,バス待ちのイライラ感が減った,バスが利用しやすくなったとする利用者が多くなっている 〔1−6−13図〕。
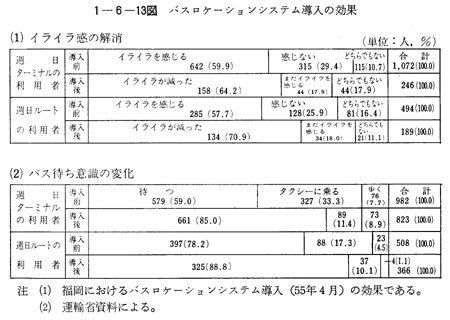
ウ 運賃制度の改善
57年1月8日の営団地下鉄運賃改定時に,東京都営地下鉄との併算割引額を普通運賃については30円から40円に引き上げられ,また,57年4月20日の国鉄運賃改定時に,営団地下鉄との相互直通区間について,初乗り普通運賃の併算額から20円割引く乗継運賃が新設されるなど,乗継運賃の導入,拡大が進んでいる。 乗継運賃の導入については,制度上,実務上の問題があり,現在,これら問題を含め,乗継運賃システム導入のための調査研究が行われている。 なお,営団地下鉄運賃改定に当たっては,普通運賃について,将来,ゾーン運賃制移行を前提として,その移行が円滑に実施できるよう,同一運賃となるキロ程を拡大し,運賃区界数を10区から6区に減らし,運賃制度の簡素化,簡明化を図っている。 また,大都市域の乗合バスは同一路線を複数の企業が運行していることが多いが,事業者別の定期券,回数券となっている場合には,共通に利用することができない。こうしたことから,複数企業の乗合バスを共通に利用できるよう,東京都,横浜市,大阪市,神戸市等において,共通定期券,共通回数券が導入されている。
エ 自転車利用の円滑化と秩序化
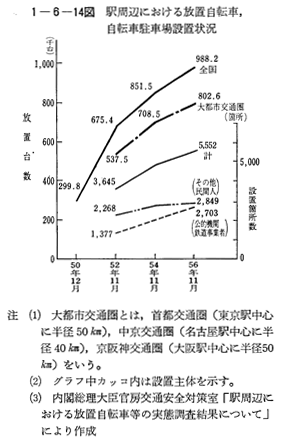
このため,自転車利用の円滑化を図るための自転車道,自転車駐車場の整備,駅前広場等の機能確保のための規制,取締り等が逐次進められてきており,駅周辺放置自転車数は,増勢を鈍化させつつある。また,56年5月にはこれらの対策を総合的に推進するため,自転車の安全利用の促進及び自転車駐車の整備に関する法律が施行されたが,運輸省においても,鉄道事業者に対し,地方公共団体又は道路管理者から公共自転車駐車場の整備に関し,鉄道用地の提供について申入れがあったときは,その事業との調整に努め積極的に協力するよう指導している 〔1−6−15表〕。
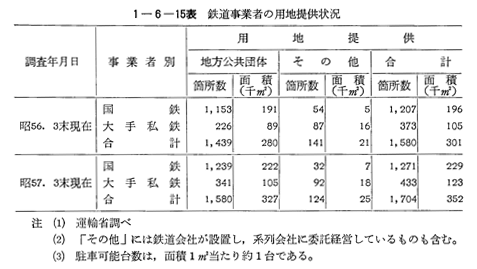
公共交通機関を,速く,便利に,快適に利用できる魅力ある乗り物とするため,駅,停留所,車両,走行環境等の改善が進められている。

車両については,冷房化率の推移(50年〜56年)をみると, 〔1−6−17図〕のとおり,国鉄では,東京地区は23%から60%に,大阪地区は34%から64%に,大手私鉄14社計では34%から65%に各々向上しており,乗合バス(全国計)でも50年8%から55年28%と大きく向上している。また,鉄道の乗り心地の改善につながる空気バネ取付車両や省エネ効果とともに加速衝撃緩和効果のあるチョッパ車両の導入が進められており,更にレールのロングレール化が進められている 〔1−6−13図〕。
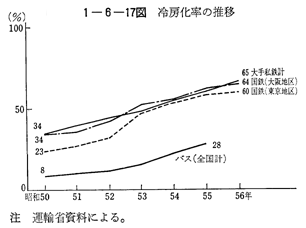
また,大手私鉄14社の最混雑区間における混雑率は,輸送力増強投資の結果,50年204%から56年189%と改善を示してきている。なお東京,大阪の地下鉄の最混雑区間における混雑率は50年199%から56年198%に,また,国鉄山手線外回り(上野一御徒町)では223%から233%に,大阪環状線内回り(鶴橋一玉造)では245%から229%になっている。このように,概ね混雑率は,改善の傾向がみられるものの,依然として高水準にあり,地域によっては悪化しているところもある。

走行環境については, 〔1−6−19図〕のとおり,バス専用レーン,優先信号等の整備が進められている。なお,56年度では,名古屋市において,都市基幹バスが整備され,57年3月末運行を開始した。都市基幹バス構想は,大都市における都市交通体系の骨格を形成する路線についてバス専用レーンを設置するとともに,基幹バスと一般バスを区別し,基幹バスについては,停留所間隔を広げ,一般バス追い抜き用バスベイを設け,表定速度の向上と定時性の確保を図り,車両を低床,低ドア化,冷房化,大型化し,停留所にシェルター付き上屋を設けるなど輸送サービスの向上を図ったものである。名古屋市都市基幹バスについて運行開始後の調査では,次第に速度も向上し,乗車人員も増加するなど効果をあげている。

また,大都市周辺の鉄道駅から団地等への深夜の足の確保を図るため,乗合バスの運行時間帯の延長や深夜バス,乗合タクシーの運行が進められている。
地域旅客交通の整備を着実に進めていくためには,地域における旅客交通のあり方について長期的な展望を踏まえた計画を策定し,行政上その達成に努めるとともに,事業者,利用者に対する行動の指針としていくことが必要であるとの考えに基づき,55年度から地域交通計画の策定を行っている。地域交通計画は,陸運局長が,地方陸上交通審議会(学識経験者,地方公共団体及び関係行政機関の代表者,利用者代表,労働者代表等で構成)に諮ったうえで,原則として府県単位にその策定を行っているが,既に,道南(北海道),山形県,福島県,山梨県,三重県,滋賀県,香川県,鹿児島県の8地域において,計画が策定された。運輸省では,今後とも,順次,地域交通計画の策定を進めるとともに,計画に基づき地域社会づくりの基盤となる地域旅客交通の充実を図ることとしている。
東京,大阪等の大都市圏における高速鉄道を中心とする交通網の整備については,都市交通審議会の答申に基づいてその推進を図ってきている。東京圏については,47年3月の都市交通審議会答申第15号による60年を目標とする基本計画に基づいて鉄道網の整備を行ってきているところであるが,最近における東京圏の人口の分布及び就業地の状況は,都市圏の広域化,副都心の整備等により答申時の想定とかなり異なったものとなっており,今後もこのような事態が更に進展し,これに伴い交通需要の変化をもたらすものと予想される。
|