|
4 過疎地域等における足の確保
過疎地域等人口密度の低い地域においては,公共交通機関に対する輸送需要の減少が著しく,このため,乗合バスについては企業としての運営が困難になり,路線の廃止,縮小も進んでいる 〔1−6−20図〕。しかし,自家用車を利用できない人々の足の確保,シビルミニマム維持の観点から通勤,通学等の輸送については,バス輸送の確保を図る必要がある。生活路線維持の観点から,都道府県知事が指定した生活路線に関し,経営状況が極めて悪化しているバス事業者に対して 〔1−6−21図〕のとおり地方バス路線の運行維持費,バス車両購入費等について地方バス路線維持費国庫補助が地方公共団体と共同して行われている。また,地域の実情に応じ路線維持の困難な路線バスの市町村代替バスへの転換が行われている 〔1−6−22図〕。なお,56年度末現在,市町村代替バスが運営されている市町村数201のうち54については,バス運行の民間委託により効率化が図られており,また,最近,一部の地区において中,小型のバスを導入することにより,低い乗車密度の下で一定の運行効率を上げている例もあり,廃止か存続かという二者択一の方式ではなく,地域の実情に応じた方策を求める必要があろう。
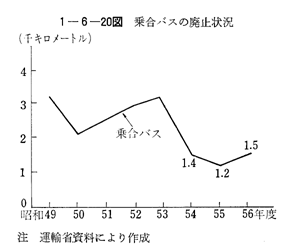
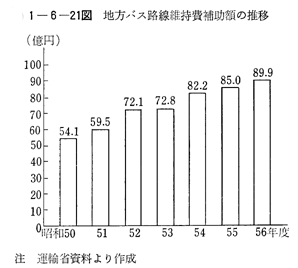
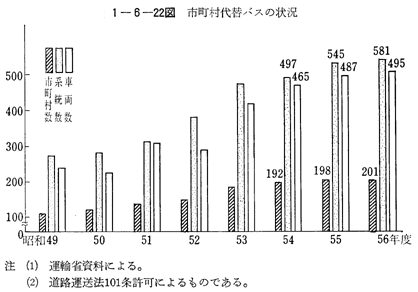
過疎地域等における足の確保の問題は,交通におけるシビルミニマムの確保という問題とともに,雇用,教育,文化,医療等の地域経済社会の現在及び将来の姿と深いかかわりを有するので,これらの人間居住の基礎的条件の総合的整備の視点から検討を進めていく必要がある。
私的交通機関(自家用車,自転車,オートバイ等),公共交通機関(鉄道,電車,乗合バス,タクシー等)及び徒歩の利用交通手段別シェアの45年度から55年度の推移をみると,全体として,公共交通機関及び徒歩のシェアが低下しているのに対し,私的交通機関のシェアが大きく拡大していることがわかる 〔1−6−23図〕。
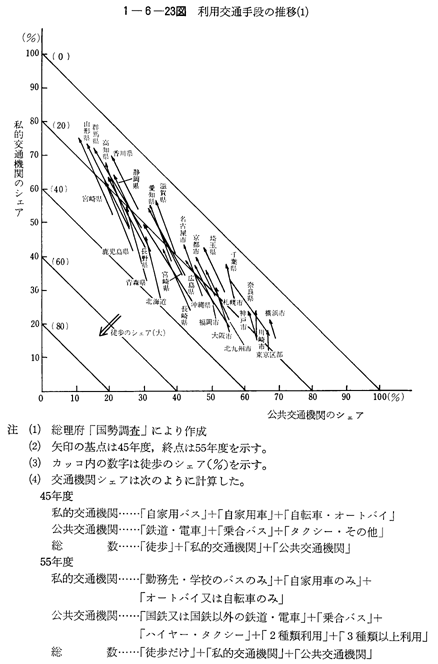
地域別の動きをみると,東京都特別区及び10大都市では,北九州市を除き,公共交通機関のシェアは,横ばいないし5〜6%減少,徒歩のシェアも4〜7%の減少に止まり,私的交通機関は,12〜13%の増加となっており,また,埼玉県,千葉県等の大都市近郊県も,ほぼ同様の傾向を示している。これに対し,これら以外の県では,公共交通機関及び徒歩のシェアは大きく減少し,私的交通機関のシェアは,16〜25%の増加を示しており,地方ほど公共交通機関のシェアの低下,私的交通機関のシェアの増加が著しいことがわかる。
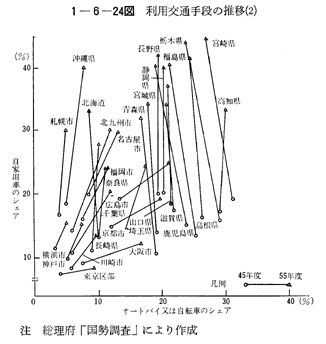
また,私的交通機関のうち,自家用車のシェアとオートバイ・自転車のシェアの推移をみると,東京都特別区,大阪市等の大都市圏においては,自家用車のシェアの増加はさほど大きくなく,むしろ,オートバイ・自転車のシェアの増加が目立っているのに対し,地方ほど自家用車のシェアの増加が著しくなっている 〔1−6−24図〕。
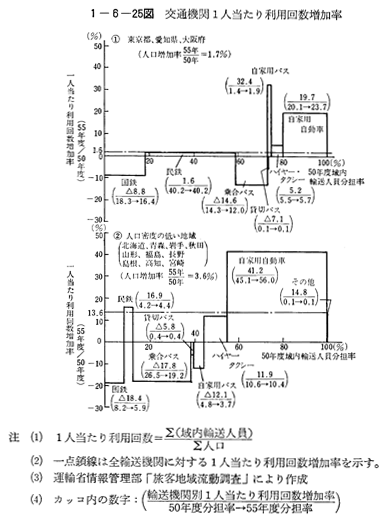
このように自家用車は,過疎地域等において特にそのシェアを増大しており,今後も国民生活の高度化,多様化に伴い,その機動性,随意性という特性がますます人々に選好されることになると予想される。このような自家用車の普及は過疎地域等における国民のモビリティの向上に資するものであるが,他方,自家用車利用の増大により公共交通機関の需要が減退するとその経営が困難になり,自家用車を利用できない人々の足をどのように確保するかという問題等を生ずることにも配慮していく必要がある。
|