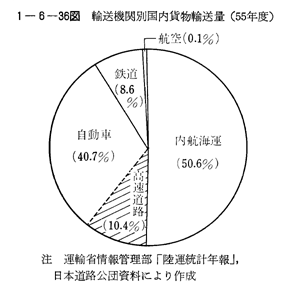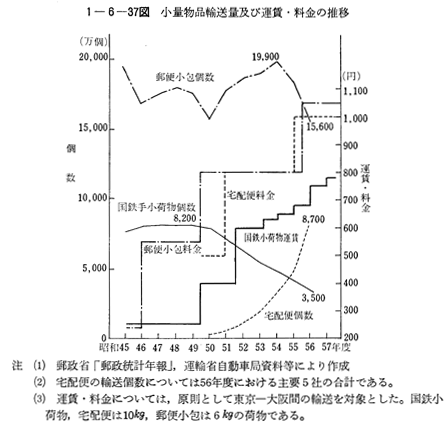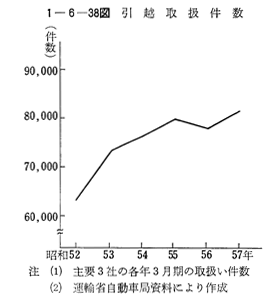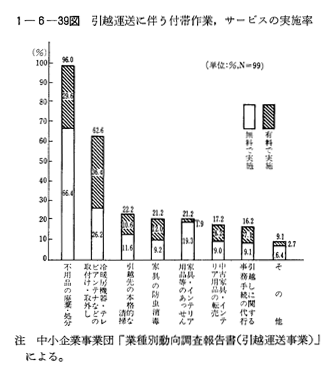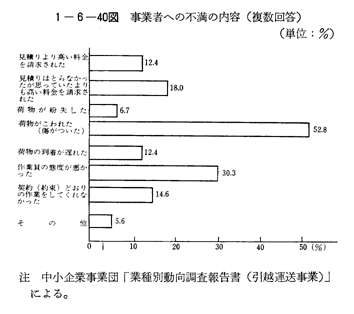|
3 宅配便,引越サービスの急成長
(1) 宅配便の急成長
トラック輸送は,いずれの産業分野においても進出が著しいが,特に,最近では,大量貨物の輸送から,主として一般家庭,消費者を荷主としたものや高い付加価値を生む小量物品輸送において,大きくその分野を広げつつある。
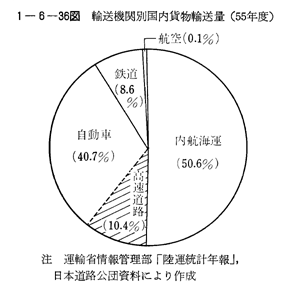
トラック宅配便は, 〔1-6-37図〕のとおり,50年以降進展が著しく,56年度には8,700万個(主要5社の取扱個数)にまで急成長している。一方,国鉄手小荷物は,49年度(ピーク時)の8,200万個が年々減少し,56年度には3,500万個となり,トラック宅配便を大きく下回る状況となっており,また郵便小包も,54年度をピークに減少を続けており,56年度にはピーク時の約8割となっている。これは,トラック宅配便が自動車輸送の特性を発揮し,戸口から戸口への配達,近距離帯では即日配達,長距離帯でも翌日配達とする,また,単なる輸送サービスに止まらず,包装,商品管理などの広範な物流サービスを提供するなど,所要時間,サービスの面で優れていること等から荷主ニーズによく合致したためと考えられる。
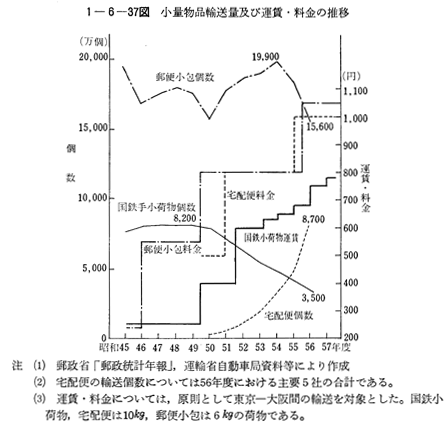
こうした状況から,国鉄手小荷物輸送のあり方が問題となるなど,現在は,小量物品輸送体制の再構築の時期にあると考えられ,過疎地域における集配体制の問題を含め,そのあり方について検討する必要がある。
トラック宅配便は,50年以降急速に市場を拡大し,また,新規参入も著しく,競争が活発化している。こうした宅配便輸送量の急増に伴い,貨物の破損,延着等の事故が増大する一方,事故の処理体制も必ずしも十分整備されていない現状にある。このため,一般消費者を対象とする宅配便輸送の特殊性を考慮しつつ,利用者保護の観点から,事故の防止や事故処理体制の充実を図る必要があり,現在,検討が進められている。また,運賃制度についても,現在は,路線トラック運賃制度の範囲内で各社が設定しているが,一般路線トラックの貨物と異なり,宅配便の貨物は小口貨物が主体であること等から,宅配便に適合した運賃制度についての検討が進められている。
(2) 引越サービスの充実
宅配便同様,近年,一般消費者向け輸送サービスとしてトラックによる引越サービスの成長が著しい 〔1-6-38図〕。
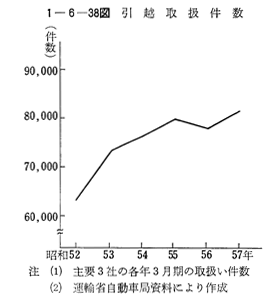
生活水準の高度化に伴って,家具,家財の大型化,高級化により,引越における運搬にもかなりの労力と技術が必要となったこと等から,引越を専門の運送事業者に依頼することも増加している。一方,運送事業者サイドでも,企業内の引越運送部門の拡充,独立化を図る企業や引越運送を専業とする企業も現われている。
引越運送需要の前提となる人口移動を総理府統計局「住民基本台帳人口移動報告年報」によってみると,人口移動(市区町村間の転出,転入者の計)は,55年年間で700万人,日本の人口の約6%に当たっている。また,55年1年間の政令指定11都市へ転入した者は,121万人,転出した者は132万人となっており,人口移動は,大都市圏を核として形成されていることがわかる。
中小企業事業団が引越運送を行っているトラック運送事業者を対象として行った調査(56年)によると,全体(215社)の5割の企業が引越運送専門の受付窓口を設置しており,33%の企業において引越運送専門の営業,開拓要員が配置され,需要開発が進められている。同調査により,引越運送に伴う付帯作業,サービスの実施状況をみると,全体の46%の企業が何らかの付帯作業,サービスを実施している。その具体的内容は, 〔1-6-39図〕のとおり,不用品の廃棄・処分,冷暖房機器・テレビアンテナ等の取付け・取外し,引越先の本格的な清掃家具の防虫消毒,家具・インテリア用品の斡旋等多様なサービスに及んでおり,引越サービスが単なる運送行為に止まらず,消費者の引越に求めるニーズに応じて多様化し,充実していることがわかる。一方,引越サービスに対する利用者の不満内容は, 〔1-6-40図〕のとおり,荷物の破損,紛失,到着の遅れが7割,作業員の態度,作業内容の不備が5割,高い料金の請求が3割となっている。引越サービスが多様な要求をもつ個人を相手とするものであることから,消費者ニーズの的確な把握と消費者に対する引越サービスの内容,料金等の条件に関する明確な情報の提供と苦情処理体制の整備が必要となろう。
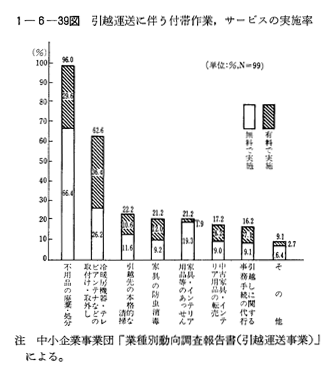
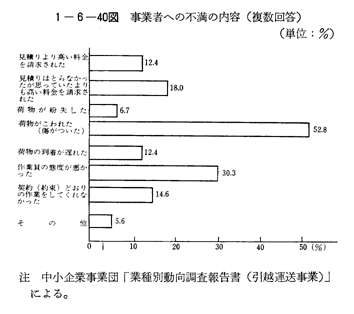
|