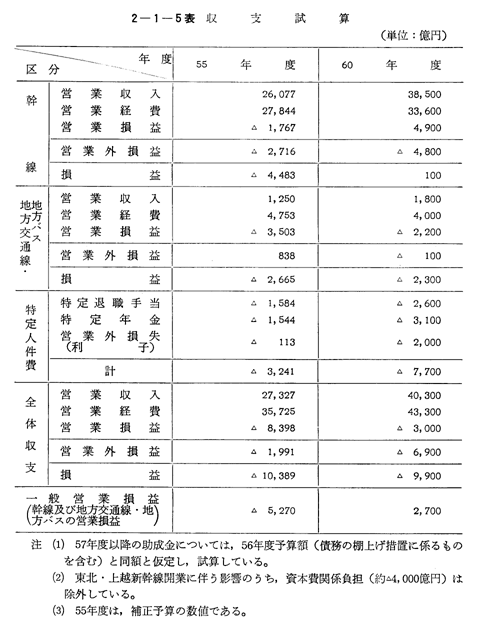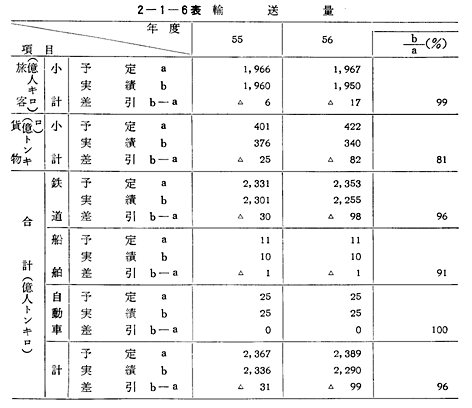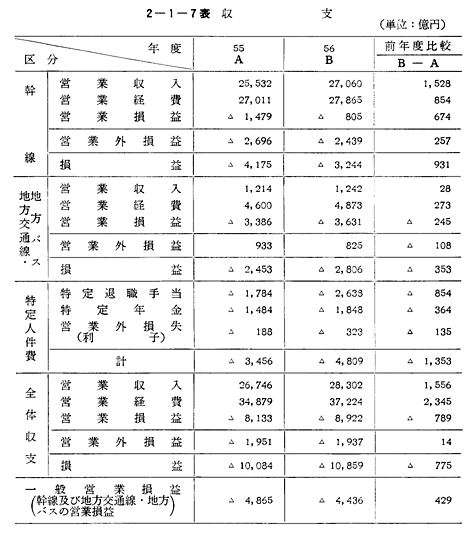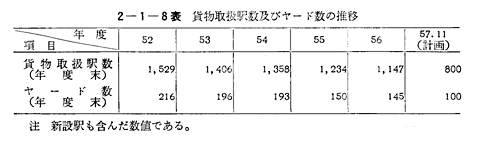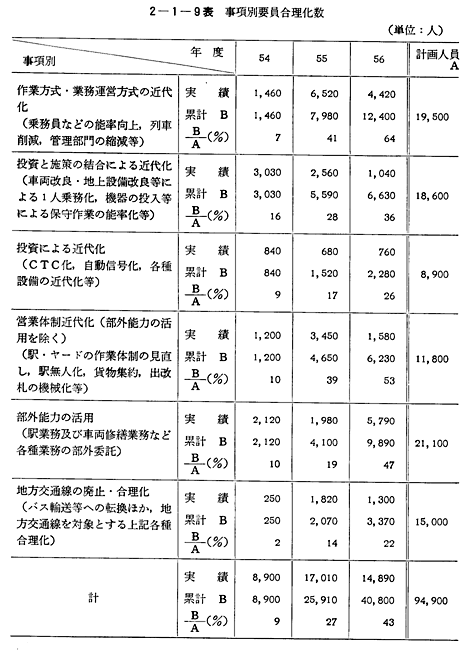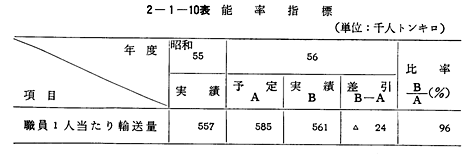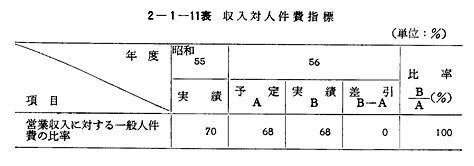|
2 現行再建対策
(1) 現行再建対策の経緯
国鉄の経営状況の悪化に対処するため,国及び国鉄は,44年度以降,日本国有鉄道財政再建促進特別措置法に基づく第1次再建対策(44~47年度)及び第2次再建対策(48~50年度)並びに日本国有鉄道再建対策要綱(50年12月閣議了解)に基づく第3次再建対策(52年度において一部改正)と3次にわたり再建対策を講じてきた。しかし,これらの対策は,いずれも所期の目的を達することができず,国鉄の経営状況は好転しなかった。
現行再建対策は,国鉄経営の危機的状況に対処すべく,52年12月29日に行われた旧本国有鉄道の再建の基本方針」の閣議了解によりその基本的方向づけがなされた。政府は,この閣議了解の趣旨に基づき,国鉄が自らのとるべき施策の考え方を示した「国鉄再建の基本構想案」(54年7月2日)を踏まえて,54年12月29日「日本国有鉄道の再建について」の閣議了解を行い,政府及び国鉄が当面緊急に実施すべき対策を策定した。この閣議了解を具体的に実施するため,「日本国有鉄道経営再建促進特別措置法」(以下「再建法」という)が55年12月27日に公布,施行された。
再建法は,国鉄の経営再建の目標を,60年度までにその経営の健全性を確保するための基盤を確立し,引き続き速やかにその事業の収支の均衡を図ることに置き,そのために必要な法的措置として,①国鉄の経営改善措置の確実な実施を期するため,国鉄は,経営改善計画を作成,実施するとともに,毎事業年度,経営改善計画の実施状況について検討を加え,必要に応じこれを変更すること,②地方交通線に関しては,徹底した合理化及び特別運賃の設定を行うとともに,特定地方交通線については,路線ごとに設けられる特定地方交通線対策協議会において協議を行った上で,バス輸送等へ転換するための措置を講ずること,③政府は,国鉄に対する助成措置として,国鉄の債務のうち累積赤字の一部に相当する5兆599億円について,棚上げ措置を講ずること等を規定している。
その後,国鉄は,その経営の重点化,減量化など徹底した経営改善措置を推進するための「経営改善計画」を策定し,56年5月21日,運輸大臣の承認がなされた。
経営改善計画は,いわゆる「後のない計画」との認識の下,国鉄のあらゆる分野において徹底的な経営改善措置を講ずるため,要員縮減等の年次別計画,旅客,貨物等の部門別の計画等により具体的な目標を明示しており,その概要は次のとおりである。
ア 経営の重点化,減量化と能率の向上
都市間,大都市圏旅客輸送及び大量・定型貨物輸送といった鉄道の特性を発揮しうる分野に経営を重点化するとともに,業務運営全般にわたる能率化を進め,職員1人当たり輸送量で示した能率指標を約25%アップする等により,60年度に職員35万人体制とする。
イ 収入の確保
国鉄自身の創意工夫により増送増収努力を行うとともに,他の輸送機関との競合関係等を考慮しつつ,きめ細かな工夫を凝らし,適時適切な運賃改定を行う一方,関連事業の増収及び資産処分の推進に努めることにより,60年度までの累計でそれぞれ約5,000億円の収入を確保する。
ウ 設備投資の抑制
設備投資については極力これを圧縮することとし,計画期間中の投資規模を現状程度に抑制する。
エ 労使関係の改善等
国鉄再建のための前提条件である労使関係の改善,職場規律の確立に努める。
オ 収支改善の目標
この計画における経営改善措置を確実に実施することにより,国鉄の収支は,行財政上の措置と相まって,60年度までに一般営業損益においてできるだけ多くの益金を出し,60年度には幹線の損益において収支均衡を達成する(東北・上越新幹線開業に伴う影響を除く)など健全経営の基盤を確立するとともに,61年度以降については可及的速やかに収支均衡の実現を図ることとする 〔2-1-5表〕。
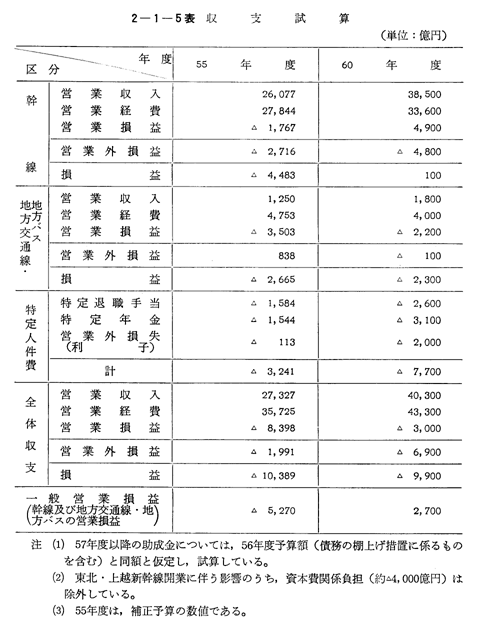
(2) 経営改善計画の実施状況
56年度における国鉄の鉄道輸送量は,旅客貨物とも前年度より減少し,特に貨物においては経営改善計画の年度予定を大幅に下回ることとなった。旅客については,列車別にみると,新幹線及び在来線特急がほぼ前年度並みの輸送量となったものの,在来線急行の輸送量は輸送力削減もあって大幅に減少し,また,普通列車の輸送量は微増に止まったため,全体の旅客輸送量では経営改善計画の予定を1%下回った。貨物については,車扱,コンテナとも輸送量が大幅に減少し,主要物資別輸送量でみても,いずれの物資についても減少したため,全体の輸送量でも昨年度に続き大幅に減少し,経営改善計画の予定の達成度は約81%に止まる事態となった 〔2-1-6表〕。
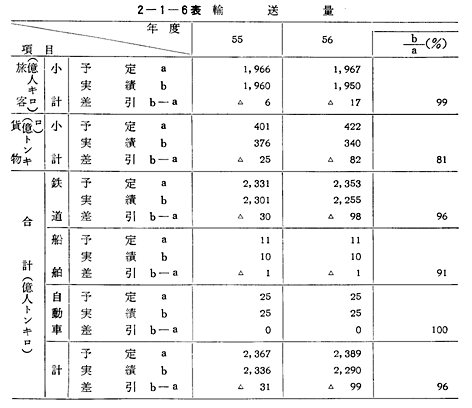
収支状況をみると,幹線の損益は3,244億円の損失となったものの,前年度に比べて931億円の改善となった。しかし,地方交通線・地方バスの損益は,逆に前年度に比べ353億円悪化して2,806億円の損失が生じ,一般営業損益では4,436億円の損失となった。また,職員の年齢構成の歪みにより急増した年金,退職金のうち一定の基準を超える人件費負担である特定人件費(特定年金,特定退職年金)は前年度に比べ1,353億円の増加となった。この結果,全体収支では,損益が前年度より775億円悪化し1兆859億円の欠損を生じたが,このうち,地方交通線・地方バスの損失及び特定人件費の合計の占める割合は前年度の65%よりも5%上昇して70%を超えることとなった 〔2-1-7表〕。
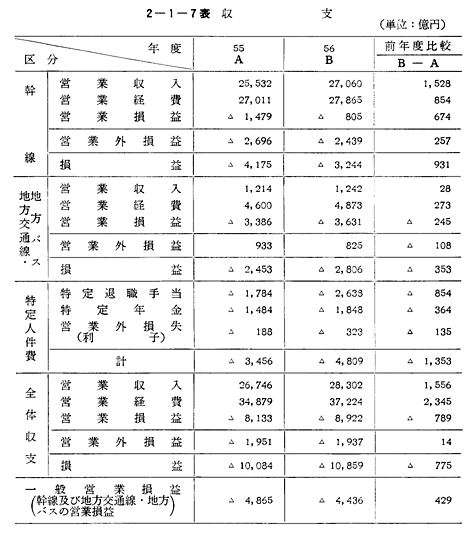
経営改善計画の主な具体的方策ごとにその実施状況をみると次のようになっている。
ア 輸送の近代化
56年度は前年度のダイヤ改正により実施された輸送体制の改善を基本としその実効をあげることに努め,全国的なダイヤ改正は行われなかったが,貨物輸送については,109貨物取扱駅の集約及び6ヤードの廃止が行われた 〔2-1-8表〕。
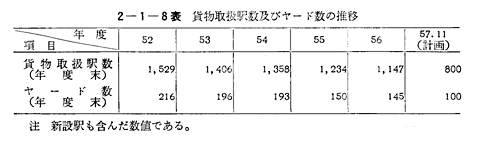
イ 業務運営の能率化
56年度は営業体制近代化に伴う駅の無人化,施設保守業務の近代化,各部門における部外能力の活用等近代化,合理化施策が実施され,合計1万4,890人の要員合理化が行われた。一方,東北・上越新幹線開業準備等に伴う要員2,890人が増員された結果,1万2,000人の要員縮減となり,経営改善計画の年度計画を達成した 〔2-1-9表〕。しかし,能率指標である職員1人当たり輸送量については計画どおりの要員縮減が行われたにもかかわらず,56年度の輸送量が貨物を中心に大きく落ち込んだため,前年度に対して1%増加したものの,年度予定を4%下回った 〔2-1-10表〕。一方,営業収入に対する一般人件費の比率は68%となり年度予定を達成した 〔2-1-11表〕。
ウ 収入の確保
旅客部門については,56年4月及び7月に合わせて平均9.7%の運賃改定を実施するとともに,新規商品の開発等積極的な販売施策が推進され,また,フロントサービスや車両の冷房化等のサービスの向上が図られた結果,前年度を1,610億円上回る2兆4,034億円の収入となった。一方,貨物部門については,56年4月に平均9.7%の運賃改定を実施するとともに,新規貨物の積極的開発,空コンテナ回送区間の増送等の増送活動が展開されたものの,輸送量の減少により,収入は前年度を182億円下回る3,114億円となった。
関連事業収入は駅ビル等新規事業の開発,店舗の改装等既存事業の充実等により前年度に対して12%増加し635億円となり,55,56年度の累計収入は1,201億円となった。
また,資産処分についても,不用地のみならず事業用地等からも処分用地を生み出すことにより従来にも増して積極的な処分が行われた結果,前年度に比べ2倍以上の571億円の実績を収め,55,56年度の累計収入は822億円となった。
エ 経営管理の適正化
職員管理の改善については,後述するとおり職場規律の総点検を実施し,その結果に基づいて職場規律の確立及び人事管理の適正化等所要の措置が講じられているところである。
また,56年度の組織の効率化・簡素化については,全国の鉄道管理局等地方機関において全体の15%に当たる250の課室の削減が行われた。
オ 設備投資
56年度は総額1兆185億円の設備投資が行われたが,安全対策,老朽設備・車両の取替え,近代化,合理化等の体質改善,大都市交通対策及び東北新幹線の建設に投資の重点化が図られ,特に,保安取替投資には全体の投資額の約37%が充てられた。一方,大都市交通対策以外の輸送力増強投資については,工事の実施について見直しを図り圧縮して実施された。
カ 地方交通線の改善
56年度の地方交通線の収支については,駅の停留所化,業務委託,貨物取扱駅の集約等各種の合理化施策が講じられたが,地方交通線特別交付金1,264億円の助成後においてもなお3,473億円の損失を計上した。また,特定地方交通線については,後述するとおり廃止等の手続きが進められている。
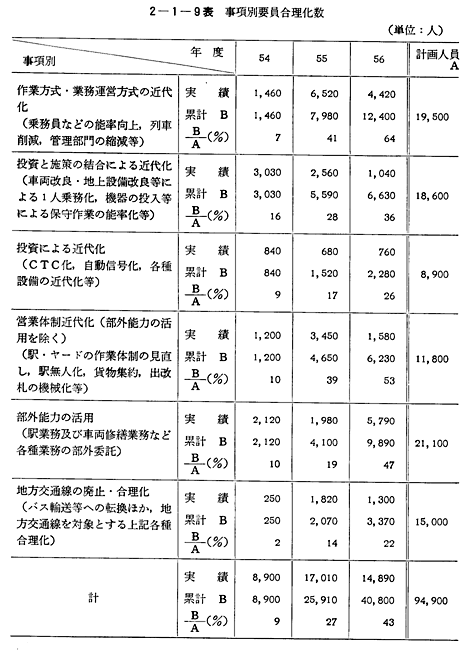
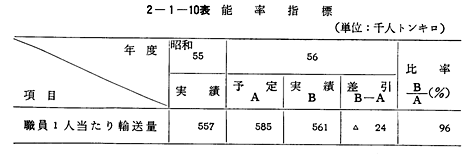
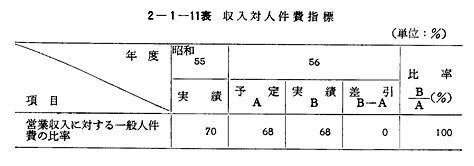
|