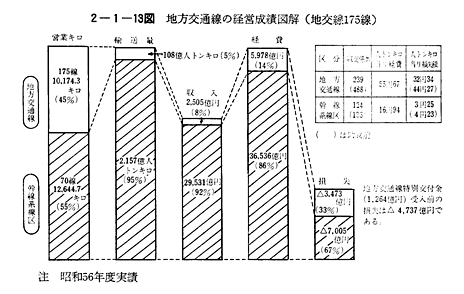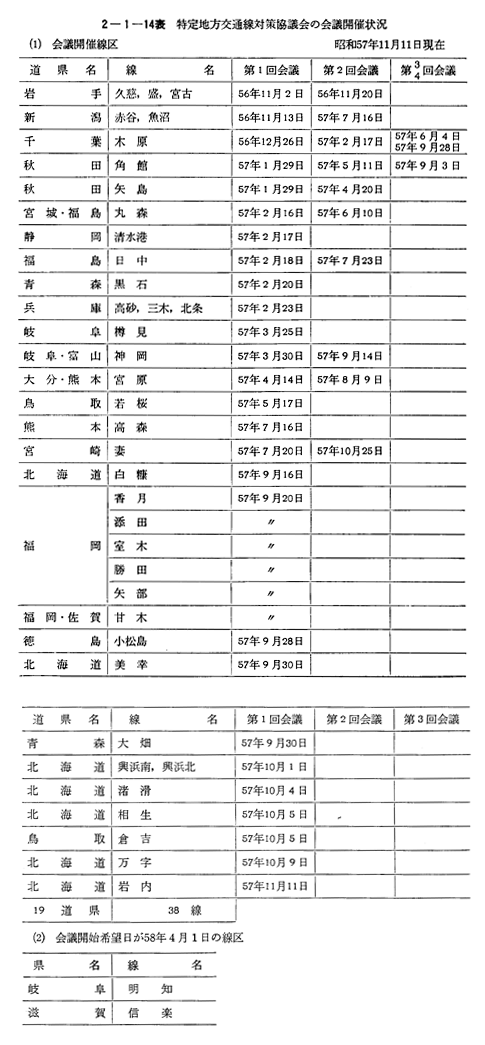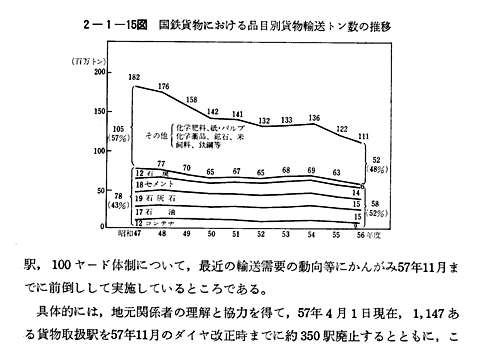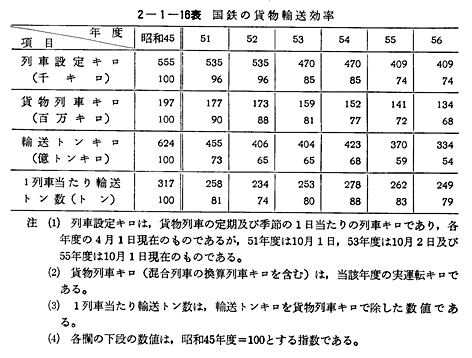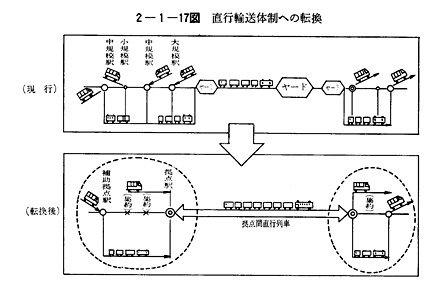|
2 経営の重点化
鉄道輸送は,総費用に占める固定費の比率が高いこと,専用軌道を有するため比較的スピードメリットが大きく,かつ,定時性,安定性が高いこと及び輸送力の設定の弾力性が小さいこと等から,大量かつ安定した輸送需要の発生する分野においてその特性を発揮することが可能である。国鉄が経営してきた分野の中では,連鎖状に分布した主要都市相互間の旅客輸送,通勤通学輸送需要の大きい大都市圏の旅客輸送及び物資別専用輸送等の大量・定型貨物輸送がこれに相当する。我が国経済の安定成長への移行に伴う輸送の効率化の要請に応えつつ,今後とも鉄道が基幹的輸送機関としての機能を果たしていくためには,これら以外の分野においては,徹底した経営の合理化,減量化が必要である。
(1) 地方交通線対策
まず,国鉄が運営の改善のために適切な措置を講じたとしてもなお収支の均衡を確保することが困難な路線である地方交通線については,輸送量で全体の5%,収入で全体の4%を占めるにすぎないにもかかわらず,経費では14%,損失では40%を占めており,国鉄経営の大きな負担となっている。このため,徹底した合理化努力を行うとともに,地方交通線の中でも輸送需要が極めて少なく,国民経済的にみても鉄道による輸送に代えてバス輸送を行うことが適切な路線であるいわゆる特定地方交通線については,バス輸送等への転換を図る必要がある 〔2−1−13図〕。
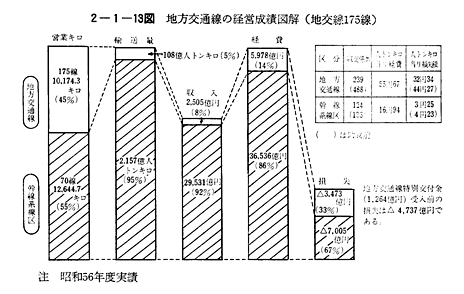
このため,56年4月には地方交通線の選定(175線,約10,160キロ)についてまた,同年9月には特定地方交通線の選定(第一次選定対象40線,約730キロ)について,それぞれ再建法に基づく運輸大臣の承認がなされた。
この40線のうち38線については,経営改善計画において廃止予定時期を58年度とし,また,特定地方交通線対策協議会の会議開始希望日を56年11月2日(大畑線と岩内線は57年4月1日)と定め,地元と話合いを始めることとしたりしかし,会議開始希望日に会議が開始されたのは第三セクターによる運営が予定されている岩手県の3線のみであり,56年度中には17線区につき会議が開催されるに止まり,残りの線区については地元の反対のため開催が遅れていた。このため,陸運局,国鉄の再三にわたる働きかけが行われた結果,関係機関の間で調整が得られ,57年11月11日にはすべての会議が開催されるに至っている。現在,特定地方交通線を廃止する際必要な代替輸送の確保に関し具体的な協議が進められているが,廃止予定時期までに代替輸送の確保に関し最善の結論を得て円滑に他の輸送機関への転換を実施していく必要がある 〔2−1−14表〕。
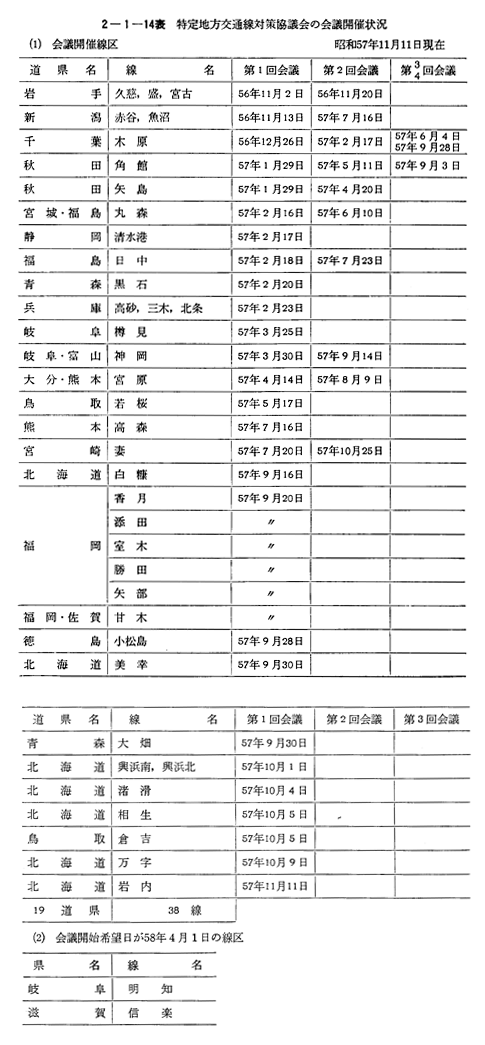
更に,国鉄の経営改善計画において60年度までの間にバス輸送等への転換を行うこととされている路線(選定除外条件に該当しない旅客輸送密度2,000人/日未満の路線)で未選定のものについても早急に選定を行い,引き続き速やかに対策協議会を開催し転換対策を推進していくことが,経営改善計画の達成のために不可欠である。
また,これら以外の特定地方交通線を含む地方交通線についても,再建法において地方鉄道を営もうとする者に貸付け又は譲渡することができるよう定められており,私鉄への譲渡,第三セクター化,民営化等を積極的に進めていくとともに,引き続き国鉄が運営する地方交通線については,駅の停留所化,業務委託,貨物取扱駅の集約,輸送力の適正化等の徹底した合理化,業務運営の効率化を推進し,収支の改善に努めることが必要である。
(2) 貨物輸送体制の転換
貨物輸送については,輸送量の減少傾向が続いており,特に石灰石,セメント等の大量・定型輸送になじむ主要物資以外の貨物の減少が著しい 〔2−1−15図〕。このため,貨物部門の収支は,旅客貨物両部門に共通する経費を除いた貨物部門に固有の経費をも償いえない状況が続いており,貨物輸送体制の転換による収支の改善は国鉄の経営改善のための重要な課題となっている。
貨物輸送は,貨物の積換えやヤードにおける解結作業等の非効率的な要素を有していることから,貨物部門の収支を改善するためには,これらの要素を回避しうるコンテナ輸送,物資別専用輸送等の大量・定型貨物輸送の分野に経営を重点化し,輸送の改善や近代化,要員の合理化を行うことが必要である。しかし,1列車当たり輸送トン数でみてもここ数年漸減しており,貨物取扱駅,ヤードの統廃合実績等を勘案すると,大量・定型輸送への移行による効率化は必ずしも十分とはいえない 〔2−1−16表〕。
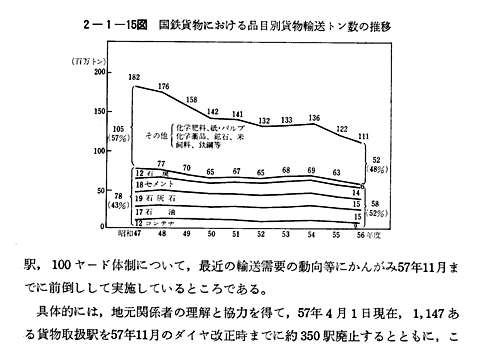
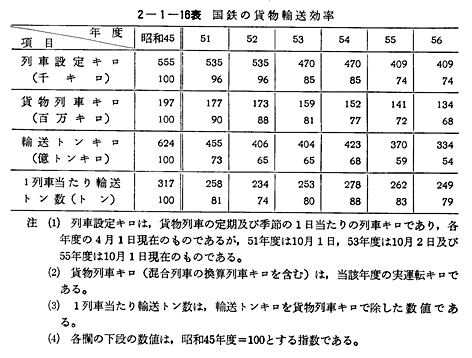
このため,現在,経営改善計画で60年度までに実施することとしている800駅,100ヤード体制について,最近の輸送需要の動向等にかんがみ57年11月までに前倒しして実施しているところである。
具体的には,地元関係者の理解と協力を得て,57年4月1日現在,1,147ある貨物取扱駅を57年11月のダイヤ改正時までに約350駅廃止するとともに,これに伴い,現在,貨物運輸営業を行っている204線区のうち,貨物取扱駅がなくなる深名線広尾線等の約40線区(一部区間の廃止を含む)の貨物運輸営業線の廃止や,約45ヤードの統廃合を進める等の対策を強力に推進している。
また,貨物部門の固有経費における収支均衡を図るよう,貨物の需要動向に対応して,コンテナ列車及び専用列車等の大量・定型貨物輸送の分野に重点的に輸送力を配置する等効率的な拠点間直行輸送を中心とする輸送体系に再編成するとともに,作業方式及び業務運営方式の近代化の促進,部外能力の活用等業務運営の見直し及び能率化の推進により,業務のあり方を抜本的に再検討し,一層の増収努力,合理化計画の促進等所要の措置を早急に実施に移しているところである 〔2−1−17図〕。更に,60年度までには,引き続き,貨物のダイヤ改正等の機会を通じて,こうした具体的な貨物輸送の近代化,合理化施策を強力に推進することとしている。
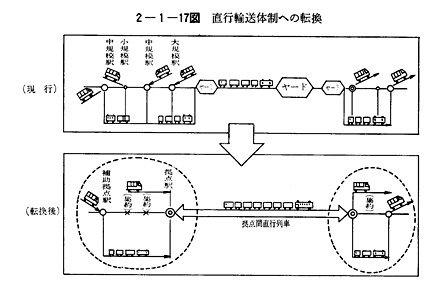
|