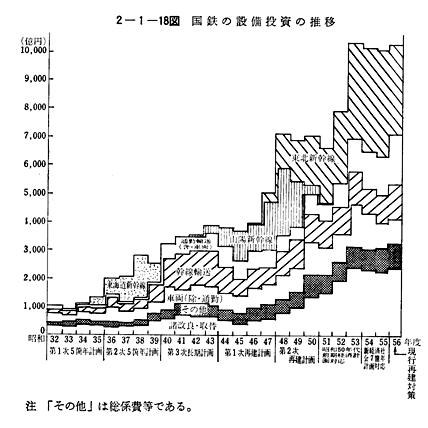|
4 設備投資の抑制
国鉄の設備投資は,30年代においては,第1次及び第2次5箇年計画に基づき,老朽資産の取替え,輸送力の増強,輸送方式の近代化等が重点的に行われ,また,40年代前半には,第3次長期計画に基づき,大都市圏の通勤輸送対策,幹線を中心とした輸送力の飛躍的増大及び保安設備の強化が積極的に進められた。
44年度から実施された第1次再建対策以降,設備投資も再建対策の一環としてその重点化が図られているが,新幹線投資の増大が続いたため,その他の投資は抑制されたものの投資総額は増加の傾向をたどり,近年は毎年1兆円を超える規模の設備投資を行ってきている 〔2−1−18図〕。
国鉄の経営が赤字基調に転じて以後の設備投資については,その財源は政府助成のほかすべてを外部資金に依存しており,借入金の累増に伴う利子負担が経営の大きな圧迫要因となっている。このため,経営改善計画においては,設備投資は鉄道特性を発揮しうる分野に一層重点化し,安全の確保に留意しつつその効率化を進めることとしており,計画期間中の投資規模を現状程度に抑制することとしている。
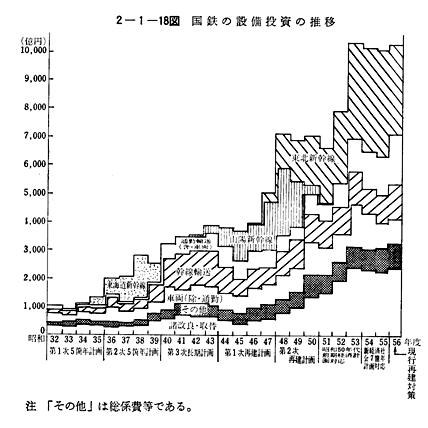
しかしながら,国鉄の経営が更に悪化していること等により,今後の設備投資については,老朽設備の取替え,踏切保安設備の整備等の安全確保のための投資を除き極力抑制し,投資規模を大幅に圧縮する必要がある。
また,個々の具体的な投資については,限られた資金を有効に使用することが重要となっており,工事施行方法の改善等による工事費の節減等に努める必要があり,更に,設備の標準及び規格についても,現在の輸送の実態,技術の進展等を踏まえた見直しを進めているところである。
|