|
1 日本経済の国際化の進展
戦後の世界経済の発展により,1955年から1980年に世界の実質生産は3倍に増加したが,なかでもとりわけ我が国経済は最も顕著な拡大を果たした。特に1970年までの高度成長期には年平均10.3%のGNPの伸びを示し,1955年には世界の2・4%に過ぎなかった我が国GNPシェアは,1980年には9.5%に達して自由主義経済圏ではアメリカに次いで第2位の経済大国に成長した。我が国経済の拡大を貿易の面からみても,世界貿易が世界生産の伸びを上回るテンポで拡大(1955年から1980年に約3.5倍)した中にあって,我が国はシェアを大きく伸ばし,アメリカ,西ドイツに次ぐ第3位となった。特に資源,エネルギー輸入の世界貿易に占めるシェアは,1980年では,石油14.1%,石炭26.3%,鉄鉱石41.1%,大豆16.0%等の極めて高い割合となっている。
このような我が国の経済発展は,勤勉な国民性,良質な労働力,高い貯蓄率といった国内的要因だけでなく,1950年代,60年代に世界経済情勢が比較的順調に推移し自由な国際貿易秩序(GATT体制)が維持されたという国際的要因に支えられたところが大きい。即ち, 〔2−2−1表〕に示されるように,我が国は資源,エネルギー,食料等の多くを海外に依存しており,それらを安定的に確保することが,国民の消費生活の維持に不可欠であるとともに,それらの輸入に要する外貨を獲得し国民生活水準の一層の向上を図るため,工業製品の輸出市場を広く海外に求めなければならず,しかもその輸出依存度は年々高まっている。したがって我が国としては,世界経済の安定的発展の下に各国との相互依存関係を進展させつつ経済の発展を確保する必要があり,自由貿易体制を基調とした世界経済の安定と発展が損なわれる場合には,我が国経済の安定と発展もありえないことを十分認識しなくてはならない。
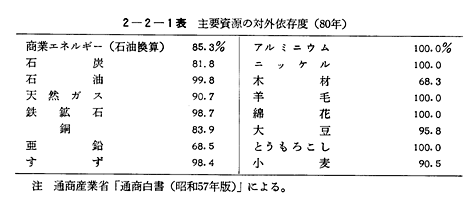
ところが,二度にわたる石油危機以降,世界の貿易構造は,貿易量が飛躍的に拡大した60年代にはみられなかった新たな要因一つまり,かつて圧倒的な経済力を有し,自由貿易主義の旗手として,その発展に強力なリーダーシップをとってきたアメリカの地位の日本,欧州諸国の経済成長による相対的な低下;韓国,シンガポール,ブラジル等の中進工業国(NICS)の経済技術水準の急速な高まりと国際市場への浸透;石油価格の大幅な上昇に伴う生産コストの上昇と生産技術の変化への対応の差違等に起因する先進工業国間の競争力の相対的変化等一により,地域別構成及び商品別構成の面で大きく変化をした。しかし先進工業国において,これに適応するための国内の産業調整が円滑に行われず,ともすれば,長期化する世界的不況のため深刻化している雇用の確保等の見地から,比較優位性を失い国際競争力の低下した産業を擁護する経済運営,即ち,保護主義の圧力が高まるようになった。
日本経済全体としての国際化の進展に伴い,運輸部門においても,国際化が進展しており,外航海運,国際航空,国際観光,造船,自動車等の部門に後述するような国際問題が増大している。また,これらの部門では輸出入及び人的交流の著しい拡大によりそのサービス,製品の貿易量が増大しただけでなく,旅行業,ホテル業,貨物取扱業等の運輸・流通業等に対する,本邦企業の海外進出及び海外企業の本邦進出という外国株式投資を中心とした企業活動の国際化も徐々に進展している。
|