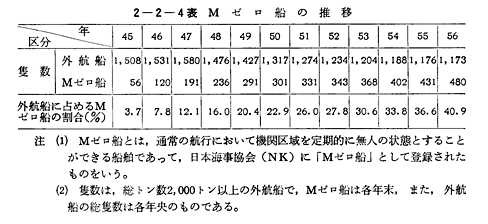|
3�@���ۊ��̕ω��ƑD�����x�̉��v
(1)�@�T��
�@�@�ߔN,�䂪���̊O�q�C�^�̒S����ł�����{�D������芪�����ۓI�Ȋ��̕ω��ɂ͒��������̂�����B
�@�@����,���a40�N��̌㔼����D����𒆐S�Ƃ����D���R�X�g�̏㏸�ɂ����{�D�̍��ۋ����͂̒ቺ�������ƂȂ����B
�@�@����ɑΉ�����,�䂪���̊C�^��Ƃ�,�����͂����邽��,�@�ւ̖��l�^�]���\��M�[���D�̓������n�߂Ƃ���,�D���̐ݔ��ʂɂ����鎩�������̋Z�p�v�V��ϋɓI�ɐ��i���Ă��� �k�Q�|�Q�|�S�\�l�B�������Ȃ���,���̂悤�ȋZ�p�v�V�̐i�W�ɂ�������炸,�C�^��Ƃ�,�X�u�БD�𒆐S�Ƃ���O���p�D�ւ̈ˑ��X��������,����ɔ����ĉ䂪���̊O�q�D�����͌����̈�r�����ǂ��Ă����B�O���p�D�ւ̈ˑ��X�������̂܂ܐi�ނƓ��{�D���̐E�悪�܂��܂��k���������łȂ�,���肵���C��A���̊m�ۂ̂���,���{���D���̒��j�Ƃ��ē��{�D�������g�ޓ��{�D�̈��D���ʂ��m�ۂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����v���ɂ��Ή��ł��Ȃ��Ȃ邨���ꂪ����,���{�D�̍��ۋ����͂̉��}���ƂȂ��Ă����B
�@�@�܂�,42�N�ɉp���C���ɂ����Ĕ����������x���A�Ѓ^���J�[�u�g���[�L���j�I�����v�̍��ʎ��̂��_�@�Ƃ���,�D���̎��i,�Z�\�ɂ��č��ۓI�ȍŒ����߂�ׂ��ł���Ƃ̗v�������܂����B������Đ��{�ԊC�����c�@��(IMCO-57�N5����IMO�ɉ���)�ɂ����Č������i�߂�ꂽ����,53�N7���Ɂu1978�N�̑D���̌P���y�ю��i�ؖ����тɓ����̊�Ɋւ��鍑�ۏ��v(STCW���)���̑������Ɏ������B
�@�@���̂悤�ȓ��O�̊��̕ω��ɑΉ�����,���{�D�������̗D�ꂽ�Z�\���\���Ɋ��p��,�ӗ~�I�ɐE���𐋍s���邱�Ƃ��ł���悤�ȐV�����E���̐����m������ƂƂ���,����ɂ��,���{�D�����^�q������{�D�����ۊC�^�E�ɂ����Ĕ�d�𑝂�,���{�D���̐E�悪�m�ۂ������������邱�Ƃ�ړI�Ƃ���,���J�g�y�ъw���o���҂̋��͂̉���,�D�����x�̋ߑ㉻�̌������i�߂��,�܂�,STCW���ɂ��Ă�,���̍������{��}�邽�߂̌������s���Ă����B
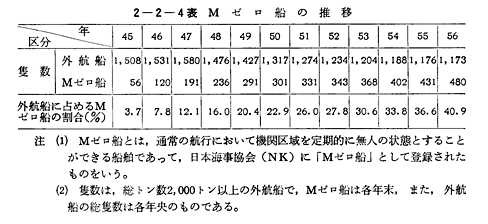
�@�@�D���@�y�ёD���E���@�̉����ɂ��Ă�,��L�̌����̐��ʂ܂����D�������J���ψ���y�ъC����S�D������R�c��̓��\����,57�N3����96���,�D�����x�̋ߑ㉻�̉~���Ȑ��i�y��STCW���̍������{�̂��߂́u�D���@�y�ёD���E���@�̈ꕔ����������@���āv����o����,4��23����������,5��1���Ɍ��z���ꂽ�B�܂�,STCW���̒����ɂ��Ă�������,57�N4��23������ɂ����ď��F����,5��27��1MO�ɉ������������,�䂪���͓�����18�Ԗڂ̒��ƂȂ����B
�@�@�����,��L�����@�̓K�Ȏ{�s��}�邽��,�W���ȗ߂̐���,�������s�̐��̐�������i�߂�ƂƂ���,�V�����D�����x�ɑΉ������D������P���̐����[���������Ă����K�v������B
�@�@�ȏ�̂ق�,���D�ɂ�����J������,�����ݔ����ɂ��Ĉ��̐��������ۓI�Ɋm�ۂ��邱�Ƃ�ڎw���u���D�ɂ�����Œ��Ɋւ�����v(ILO��147�����)��56�N11���ɔ����������Ɠ��ɂ���,�C�^���ł���䂪���Ƃ��Ă������̒����ɂ��đ��}�Ɍ�����i�߂邱�Ƃ��v������Ă���B
(2)�@�D���̋Z�p�v�V�ɑΉ������D�����x�̌�����D�����x�̋ߑ㉻
�@�@�D���̋Z�p�v�V�ɑΉ�����,�V���ȑD���̎��i�y�ёD����g�̐����m�����邱�Ƃ�,���{�D���̏��g�ޓ��{�D�̍��ۋ����͂̉y�ѓ��{�D���̐E��m�ۂ�}���ł̏��������邽�߂ɂ��K�v�s���ł���B
�@�@���������ϓ_����,52�N4���D�����x�ߑ㉻�����ψ���ݒu����,54�N4���ɂ͓������ψ����D�����x�ߑ㉻�ψ���ɔ��W�I�ɉ��g��,�V�����D���E���̐��̎��Ăɂ��Ă��̎��s�̉\���y�ёÓ������������邽�߂̎�����i�߂邱�ƂƂ����B
�@�@����,54�N�x�ɂ͍b���y�ы@�֕��Ƃ����]������̑D���̏c�̕ǂ���蕥��,���ꂼ��̕��ɑ�����D�����݂��ɑ����̋Ɩ����s���u���̘A�g�v���тɓ��ꕔ���ɂ�����E���y�ѕ����Ƃ����㉺�̕ǂ��ĕ������E���̋Ɩ����s���u�c�̘A�g�v��g�ݍ��V�����A�J�̐��̉��ł̑D���̉^�q����e�Ƃ��鑍���������J�n�����B
�@�@�X��,���ψ����,55�N5���Ɏ����������I�ɐ��i���邽�߂̖ڕW�Ƃ��āu���ݓI�D�����v�����肵���B����́u�����̖ڕW�Ƃ��Ẳ��ݓI�D�����v�Ƃ���Ɏ���ߓn�I�i�K�́u�ڍs�ߒ��Ƃ��Ẳ��ݓI�D�����v�Ƃ���Ȃ��Ă��邪,��҂ɂ����Ă�,�b�E�@�����ɂ킽��E�����s���V�����^�C�v�̑D���Ƃ���,�������x���ł̃f���A���E�p�[�p�X�E�N���[(D.P.C.),�E�����x���ł̃E�I�b�`�E�I�t�B�T�[(W/O)�����邱�ƂƂ��Ă���B�������56�N2������u�ڍs�ߒ��Ƃ��Ẳ��ݓI�D�����v�ɉ�����,�O���q�C�m�ƎO���@�֎m�����݂ɘA�g���čb�E�@�����̍q�C�����𒆐S�Ƃ���Ɩ����s�������ɒ��肵,56�N10���ɂ͂��̎������ʂ܂���,����̑D�����x�̋ߑ㉻�̐��i�Ɋւ����ꎟ���s�����B
�@�@��ꎟ��,����܂ł̎����ɂ��D.P.C.,W/O�ɂ��ėL�����������ꂽ����,����X��,�q�C�m�E�@�֎m���x���ł̋��ʋZ�\�̏K���̎�����i�߂�ׂ�����,�ߑ㉻�𐄐i�����ł̐��x�I�Ȑ���v������������K�v�����邱�Ɠ�����e�Ƃ��Ă���B
�@�@���̒����Ƃ�,�^�A�ȂƂ��Ă�,57�N�x�ȍ~��������,�D�����x�ߑ㉻�ψ���ɂ�����R�c�܂���,�u�ڍs�ߒ��Ƃ��Ẳ��ݓI�D�����v�ɉ�����,�q�C�m�E�@�֎m���x���ɂ����Ă������̐E�������݂ɘA�g���čq�C�����𒆐S�Ƃ���Ɩ����s��������i�߂�Ȃ�,�D�����x�̋ߑ㉻�𐄐i���Ă������ƂƂ��Ă���,����܂ł̎������܂�,�����̐��ʂ̒i�K�I���{��e�Ղɂ��邽�߂ɕK�v�Ȑ��x��̑[�u���u���邱�ƂƂ���,�D���@�y�ёD���E���@�̉������s�������̂ł���B
(3)�@STCW���ւ̑Ή�
�@�@STCW����,SOLAS��D���̍\��,�ݔ����̕��I���ʂɂ�������S����߂Ă���̂ɑ���,�D���̒m���E�Z�\�E��������l�I���ʂɂ����鍑�ۊ���߂邱�Ƃɂ��,�D���̍q�s�̈��S���m�ۂ��悤�Ƃ�����̂ł���B
�@�@���̎�ȓ��e�Ƃ��Ă�,�@�D��,�ꓙ�q�C�m,�@�֒�,�ꓙ�@�֎m,�����S���E�����̎��i��^���邽�߂ɕK�v�Ȓm���y�ъC��q�s�����̗v��,�A�m���E�Z�\�̃��x���ێ��̂��߂̗v��,�B�b��,�@�֕��ɂ����铖�����ێ����邽�߂̊�{����,�C�b��,�@�֕��ɂ����铖���S�������̗v��,�D�^���J�[��g���̂��߂̓��ʂ̗v��,�E�~������̗v��,�F�����{�ɂ��C�Z�Ə�̗������x,�G���`���ɂ�����ē葱������߂��Ă���B
�@�@��i�C�^���ł���䂪���Ƃ��Ă�,�����ɂ��̏��������,���ۓI�ȑD���̎����̌���Ƃ���ɂ��q�s�̈��S�̊m�ۂɎ�����K�v������Ƃ̍l���ɗ�����,����,�����̒����̎葱�����Ƃ������̂ł���B
�@�@�Ȃ�,���̏���,25�����ȏ�̍���������,���ۗ̕L�D���ʂ����E�̑D���ʂ�50%�ȏ�ƂȂ���������1�N��ɔ������邱�ƂƂȂ��Ă��邪,57�N9��������21����(���v�ۗL�D����57%)�������ς݂ł���̂�,�����v���͂���4�����̒����Ŗ��������ł���B
(4)�@�D���@�y�ёD���E���@�̈ꕔ�����̊T�v
�@�A�@�D���@�̈ꕔ����
�@(�A)�@�q�C�����̎��{�Ɋւ������
�@a�@�D����,�ȗ߂Œ�߂�Ƃ���ɂ��q�C������ɏ]���ēK�ȍq�C
�@�@�����̎��{���m�ۂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂƂ����B
�@b�@�D�����L�҂�,�q�C������S������b�����͋@�֕��̕��������g�܂���ꍇ�ɂ�,�N��,�Ɩ��̌o�����Ɋւ����̗v�������҂������ď[�ĂȂ���Ȃ�Ȃ����ƂƂ����B
�@(�C)�@�^���J�[�ɏ��g�ޑD���̗v��
�@�@�댯����A������^���J�[�ɏ��g�ޑD���y�ю�v�ȐE����,�댯���̎戵���Ɋւ���Ɩ��o����L����ƂƂ���,���I�ȌP�������҂łȂ���Ȃ�Ȃ����ƂƂ����B
�@(�E)�@�O���D�ɑ���ē[�u�̑n��
�@�@�O���D���䂪���̗̊C���͓����ɂ����ďՓ�,���g�����������N�������ꍇ��,���̑D����STCW���ɒ�߂�q�C������ɏ]���ē��������{���Ă��Ȃ������ƔF�߂�Ƃ���,���̑D���̑D���ɑ��q�C������ɏ]���ē��������{����悤�����ɂ��ʍ����邱�Ƃ��ł�,�X�Ɉ��̏ꍇ�ɂ�,���̑D���̍q�s�̒�~�𖽂�,���͂��̍q�s�������~�߂邱�Ƃ��ł��邱�ƂƂ����B
�@(�G)�@�q�C�����̐��̓���
�@�@���̐ݔ���L��,�b��,�@�֕������̍q�C�������s�����Ƃ̂ł��镔������萔�ȏ���g�ޑD���̂�������^�A��b���w�肵��,������ߑ㉻�D�ɂ��Ă�,�q�C�����̐��ɂ��Ă̓��Ⴊ�K�p����邱�ƂƂ����B
�@�@�q�C�����̐��̓���Ƃ�,�]���̂悤�ɍb���̕����͍b���̍q�C������,�@�֕��̕����͋@�֕��̍q�C�������s���Ƃ����̐��ł͂Ȃ�,�O�L�̕������b��,�@�֕������̍q�C���������{����Ƃ����̐��������B
�@�C�@�D���E���@�̈ꕔ����
�@(�A)�@�u������`�v�̗̍p
�@�@STCW���̒�߂������`�ɏ]��,�O���@�l���ɗ��݂����ꂽ���{�D�ɑ��Ă��D���E���@��K�p���邱�ƂƂ����B
�@(�C)�@�u�^�q�m�v�̐��x�̑n��
�@�@�ݔ��������̊�ɓK������,������ߑ㉻�D�ɂ�����,�q�C�����𒆐S�Ƃ����E�����s���u�^�q�m�v�Ƃ����V���ȑD���E����n�݂��邱�ƂƂ����B
�@(�E)�@���i���x�̍ĕ�
�@�@�C�Z���i��,1�`6���C�Z�m(��������1�`3��)�ɍĕ҂�,�����̎��i�ɂ��Ă̒m���v����STCW���ɑΉ������邱�ƂƂ����B
�@(�G)�@�Ə�̍X�V���̓���
�@�@�C�Z�Ə�̗L�����Ԃ�5�N�ԂƂ�,�X�V�̍�,���̏�D������L��,����,�g�̓K����L���邱�Ɠ���K�v�Ƃ��邱�ƂƂ����B
�@(�I)�@��g�݊�̐��߂ւ̈ϔC
�@�@�D�����L�҂�,���̑D���ɑD���E���Ƃ��ď��g�܂��ׂ��C�Z�]���҂ɂ��Ă̊��,�]���̖@���̕ʕ\�łȂ�,���߂ɂ����Ē�߂邱�ƂƂ����B
�@(�J)�@�O���D�ɑ���ē[�u�̑n��
�@�@���{�̍`�ɂ���O���D�ɂ���,���g��ł���D���E����STCW���ɍ��v�����Ə��L���Ă��邩�ǂ����̌������s��,�v�������Ă��Ȃ��ƔF�߂�Ƃ���,���̐�����ʍ����邱�ƂƂ�,�X�Ɉ��̏ꍇ�ɂ�,���̑D���̍q�s�̒�~�𖽂�,���͂��̍q�s�������~�߂邱�Ƃ��ł��邱�ƂƂ����B
�@�E�@�����@�̎{�s
�@�@���̉����@��,58�N4������{�s����邱�Ƃ��\�肳��Ă���B���̂���,����,�W���ȗ߂̐���,�O���D���̊ē̐��̐���,�C�Z�]���ҖƋ��o�^���������̐��̋�����,�@�{�s�̂��߂̏�����Ƃ𐄐i���Ă���Ƃ���ł���B
(5)�@�D������̐��̍���̕���
�@�@�D�����x�̋ߑ㉻�̐��i�ɓ������Ă�,�V�����D�����x���u��������D�����v���̗{���̂��߂̑D���ċ���P���̎��{�ƂƂ���,�V���x�ւ̉~���Ȉڍs��}�邽��,�]������̊K�w�敪�y�яc����E���敪�̘g�����V�����D���E���̐��ɑΉ�������s����̎��{���s���ȉۑ�Ƃ��đD�����x�ߑ㉻�ψ�����N����Ă���B
�@�@���������v���ɉ�����,�C�Z��w�Z�ɂ�����,55�N9������b�����y�ы@�֕����ɑ�,���̔��Ε���̒m���E�Z�\���C�������邱�Ƃ�ړI�Ƃ���D.P.C.��������{����ƂƂ���,56�N5�������,�q�C�m,�@�֎m�y�ёD���ʐM�m�ɑ��q�C,�@�֊W�̓����Ɩ��𒆐S�Ƃ������ʂ̒m���E�Z�\���C�������邱��,�y�ѕ����ɑ������Ɩ��ɏ]������D���E���Ƃ��ĕs���Ȓm���E�Z�\���C�������邱�Ƃ�ړI�Ƃ���W/O��������{���Ă���B�܂�,57�N5��1���Ɂu�D���@�y�ёD���E���@�̈ꕔ����������@���v�����z����,�V���ɉ^�q�m�̐��x�����n�݂��ꂽ���ƂɑΉ�����,�����̗{���̂��߂̋�����e�ɂ���,�X�Ɉ�w�̏[����}��K�v������B�܂�,�V�l����@�ւł��鏤�D��w�y�я��D�������w�Z�ɂ����Ă�,�^�q�m�̗{���ɂ��Č�������K�v������B
�@�@���,STCW���ɂ����đD���E���ƂȂ邽�߂̗v���Ƃ���Ă������,���[�_�[,�~�����Ɋւ���m���E�Z�\�ɂ��Ă�,�O�q�̂悤��,�u�K�̌`�ł��̒m���E�Z�\���m�ۂ��邱�Ɠ��̑D���E���@�̉������s���Ă���,����ɑΉ�����,�D���{���ɂ����鋳��P���J���L�������̌�����,�֘A�{��,�@�ނ̐�����,����P���̐����[�������邱�Ƃ��K�v�ƂȂ��Ă���B
�@�@���̂���,����,�C����S�D������R�c��ɂ�����,�D������P�����x�S�ʂɂ킽�鑍���I�Ȍ�����i�߂Ă���Ƃ���ł���B
(6)�@ILO��147�����̒����̑��i
�@�@�ߔN,�X�u�БD�̕��y���ɂ݂���悤�ɊC���Ƃ̊��������G�����Ă��邱�ƂɑΉ�����,�D���ɂ�����J����������ݔ��ɂ��Ĉ��̐��������ۓI�Ɋm�ۂ��邱�Ƃ��K�v�ł���Ƃ����F�������܂��Ă���,ILO�ɂ����Ă�,���̂悤�ȔF���̉���,51�N10����ILO��147����̑�����Ă���B
�@�@���̏���,���D�̏�g���Ɋւ�,�D���̈��S�,�J������,�����ݔ����ɂ��č��ۓI�Ȋ���߂�ƂƂ���,���̎��s���m�ۂ��邽��,�����̍`�ɓ��`����O���D�ɑ�,���̍���,���̍��ۓI�Ȋ�Ɋ�Â��Ĉ��̊ē��s��������|�[�g�E�X�e�[�g�E�R���g���[�����ɂ��ċK�肵�Ă�����̂ł���B������,56�N11���Ɋ��ɔ������Ă���,���ɉ��B������,������ē�Ƃ��铝��I�Ȍ����w�j�Ɋ�Â��|�[�g�E�X�e�[�g�E�R���g���[����57�N7��1��������{���Ă���B���̃|�[�g�E�X�e�[�g�E�R���g���[����,���B�����̍`�ɓ��`����O�����D�ɂ���57�N7��1������3�N�ȓ��ɓ��`�ǐ���25%��ڕW�Ƃ���,�ē�ƂȂ鏔���ɒ�߂�v���ɓK�����Ă��邩�ǂ�����������,���ׂ��������ꂽ�ꍇ�ɂ�,�D���̗}�����܂ޕK�v�ȑ[�u���Ƃ�Ƃ������̂ł���B
�@�@�䂪���Ƃ��Ă�,ILO��147������������Ă��Ȃ����Ƃɂ��䂪���O�q�D�̉~���ȉ^�q���W�����邱�Ƃ̂Ȃ��悤��,����������̖��_�̑��₩�ȉ�����}���Ă��̑���������ڎw���ׂ����̂ƍl������B�����̑��������ɂ��Ă�,�J�g�o������������v�]����Ă���,����,�W�Ȓ��ƒ����̂��߂̌�����i�߂Ă���Ƃ���ł���B
|