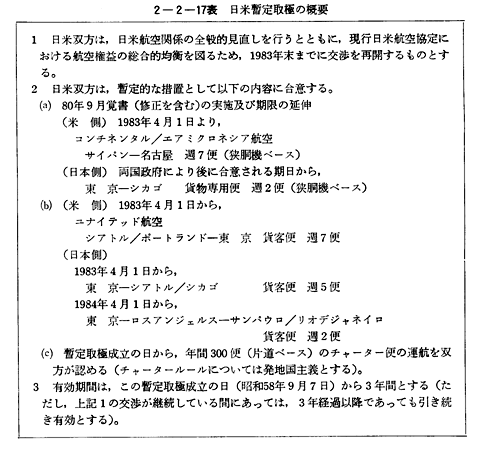|
3 航空交渉
昭和56年度において,我が国は16か国と延べ30回にわたって航空交渉を行ったが,そのうち7回は日米間の航空権益の不均衡の是正を目指すアメリカとの交渉であった。
ア 現在の国際航空輸送の枠組は,1944年に採択された国際民間航空条約(シカゴ条約)と同条約によって設立された国際民間航空機関(ICAO)にその基礎を置いている。即ち,国際定期航空運送業務は原則として関係二国間の航空協定に基づいて運営されること,不定期航空運送業務については発着地の政府の規制に従って実施されること等が同条約に定められている。
イ 航空交渉とは,こうした航空協定の締結又は改定等についての交渉をいうが,最近では,航空協定外の業務である不定期航空運送業務も交渉の議題とされるケースが増えている。
現在我が国が締結している36の航空協定は,すべて「バミューダI型協定」といわれるものである。バミューダI型協定とは,46年に英米間で締結された航空協定をモデルとしたものであるが,英米協定自体「空の自由」を主張するアメリカと「空の秩序」を主張するイギリスとの妥協の産物であるため,輸送力決定の基準,いわゆる第五の自由(以遠区間における積込み,積卸し)の輸送のあり方,当事国の指定企業数等の点で各国の間で争いが多いものとなっている。
ウ アメリカは,第二次大戦後の混乱期にも強大な航空企業を擁していたこともあり,バミューダI型協定を各国と締結して,自己に有利な戦後の国際航空体制を維持してきた(バミューダ体制と呼ばれる)。その後,西欧諸国の復興,発展途上国等の成長により,これらの国々の輸送需要の増大と航空企業の成長がみられたため,アメリカ航空企業の輸送シェアは相対的に低下してきている。しかしながら,アメリカ航空企業の力は依然大きく,アメリカの国際航空政策は,世界各国に大きな影響力を有しているといえる。
(1) アメリカの国際航空政策
アメリカは,自国の輸送シェアの相対的低下を食い止め,更にシェアの拡大を図るため,78年8月,カーター政権下で従来からの自由競争政策をより一層推進するための「新国際航空政策」を発表した。その内容は航空企業の国際航空運送業務の運営に対する政府の規制を極力排除しようとするものであり,具体的には企業の新規参入,輸送力決定の自由化,運賃決定の弾力化,チャーターの自由化等を図ることとしていた。また,80年2月には,同政策の実現を図るため国際航空輸送競争法を制定し,外国政府によるアメリカ航空企業に対する制限的又は差別的措置に対して一方的制裁措置を取りうることとした。その後,アメリカは相手国に対するアメリカ国内乗り入れ地点及び以遠権の追加と引換えにこうした自由化を内容とする新協定(リベラルアグリーメント)の締結及び既存協定の改定に努めた。81年1月カーター政権を引き継いだレーガン政権は,いまだ明確な形で独自の国際航空政策を打ち出してはいないが,基本的にはカーター政権の自由化政策を踏襲しているものと思われる。しかしながら,ブラニフ航空の倒産に象徴される最近の主要航空企業の経営状況の悪化を背景に,基本的な政策の方向に変化はみられないものの,航空交渉の場においては,アメリカの政策を一括して相手国に受け入れさせるとの方針を改め,当面の課題を中心に問題を解決する方法をとることも多くなっていると思われる。
なお,アメリカをめぐる新しい動きとして,アメリカとブラジルとの間の暫定協定,アメリカと欧州諸国との間の運賃取極があげられる。後者は,アメリカが,欧州諸国が加盟している欧州民間航空会議(ECAC)との間で北大西洋路線の運賃決定方式としてゾーン方式(基準レベルの上下何%かの範囲内にある運賃は両国政府により自動的に認可されるという方式)を実験的に導入することを取り決めたものである(同取極は,82年8月1日から6か月間有効とされているが,従来から北大西洋の運賃は事実上大幅に自由化されていたため,現時点では大きな変化はみられないといわれている)。
(2) 我が国の国際航空政策
我が国は航空輸送の秩序ある発展を航空政策の基本としており,具体的には,適正な需給バランスを確保するため実効性のある輸送力決定方式を設定すること,IATAにおける運賃決定機能を活用して多国間調整の基礎の上に立った合理的運賃水準及び運賃体系を設定すること,乗り入れ地点の交換に当たっては相手国との権益バランスを確保すること,相手国以遠の運航については両国間の運航との関係において従たる位置付けを行うこと,チャーター便については定期便優先の考え方にのっとり定期便を補完するものとしてその活用を図ること等を目的としている。
(3) 日米航空交渉
日米間の航空路は,日米の航空企業5社のほか,第三国航空企業6社が就航しており,世界でも有数の航空市場となっている。そして,我が国にとっても,日米間の航空関係は,前述のとおり,旅客数,提供輸送力とも枢要な位置を占めており,また,航空事業の経営の面からも大きな意味をもっている。
このような日米間航空路の運営のあり方をめぐって,日米両国航空当局は,長い間議論を重ねてきた。
日米航空協定は,終戦後のアメリカに圧倒的に優位な力関係を背景に締結されたものであり,相手国内乗り入れ地点,以遠権,輸送力等の面で両国間の航空権益は我が国に著しく不利なものとなっている。
こうした日米間の不均衡を是正するため,昭和47年の沖縄返還の際の日米合意により,51年10月から協定改定交渉が開始され,その後若干の中断期間をはさみ,56年4月から正式協義が再開された。再開後は,アメリカが,前述のとおり新国際航空政策を発表したこともあって,運賃決定の弾力化,チャーターの自由化等を強く求めてきたことから,従来の航空権益の交換といった面に加えて両国の国際航空政策の調整といった面を有することになったのが特徴的である。
再開された交渉は,57年3月まで7回の協議が行われたものの,同3月のサンフランシスコでの最終協議においても合意に達することはできなかった。しかしながら,その後の外交ルートを通じての折衝を経て,6月4日,日米首脳会談において3年間の暫定取極を締結することが合意されるに至り,日米航空交渉は当面の決着をみることとなった。同取極は,9月7日両国代表により外交文書の署名・交換が行われ即日発効したが,その概要は 〔2−2−17表〕のとおりである。
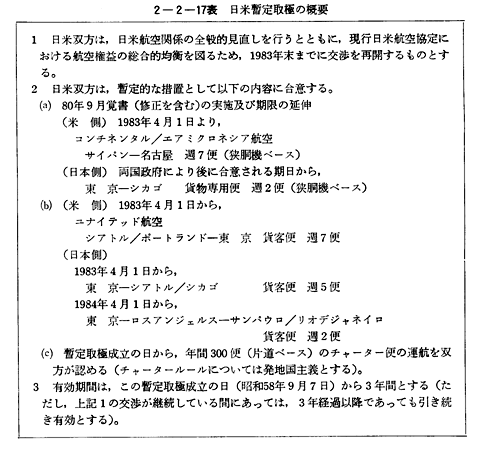
今回の暫定取極により,我が国は,便数等一定の条件付きではあるが,長年の懸案であったロスアンジェルス以遠ブラジル路線を完全な運輸権付きで獲得し,加えて,極めて重要度の高いシアトル・シカゴへの乗り入れを可能とした。暫定取極とはいえ,新規地点への乗り入れ及び以遠権の拡大が図られたことは,我が国にとって日米間航空権益の不均衡是正に向けて前進をみたものと考えられる。
同取極においては,58年末までに,日米航空関係全般を見直すとともに,現行日米航空協定における航空権益の総合的均衡を図るため本格交渉が再開されることとなっているが,我が国としては,引き続き旧米間の航空権益の不均衡是正」と「秩序ある競争の確保」という交渉目的を達成するとともに,公正な日米航空関係全体の一層の発展を図るべく鋭意努力を行っていく必要がある。
また,一連の交渉の過程においてアメリカ側が日本における空港使用条件に関する制限を問題としたことは,こうした空港使用条件に関する制限が「日本の航空政策は閉鎖的ではないか」との誤解を受けたりする原因にもなっていると考えられるため,我が国の国際航空に取り組む主体条件を整備する観点からも,国際空港の整備・拡充に尽力する必要があると考えられる。
(4) 我が国のその他の航空交渉
現在我が国に対して32か国から航空協定締結の申入れがなされており,我が国はこれらの申入れに対し,両国間の政治・経済・文化等の交流関係,両国間の航空需要の見通し,相手国のハイジャック防止対策への配慮等の諸点を考慮しつつ対処していくこととしている。
また,我が国は,既に航空協定を締結している国との間においても,航空協定の付表で定めている路線の改訂,両国の指定航空企業の運航便数,使用機材の変更等について必要に応じて交渉を行っており,この結果,56年度においては,中国,タイ,マレーシア,フィジー,ブラジルとの間で新たな合意が成立している。
主要な交渉について若干概説すると,中国との交渉では,日中間の輸送力を双方がそれぞれ約40%増加させることで合意が成立し,57年春から実施されたが,中国側の日本以遠太平洋線への乗り入れ問題,運賃問題については,引き続き協議することとなった。マレーシア,タイとの交渉では,輸送力を増加することが合意され,ブラジルとの交渉では,日本企業のロスアンジェルスでのチェンジ・オブ・ゲイジ(機材変更)によるサンパウロ乗り入れという日本側要求が認められた。イギリスとの交渉では,イギリス側の太平洋線乗り入れ,日英間新運賃の導入要求等,日英航空関係の見直しのための協議が行われたが,結局,何ら新しい合意は成立せず,輸送力につき現行取極が延長されることとなった。
このように,我が国関係航空路において新規乗り入れや増便の要請が多く寄せられている。これは我が国を中心とする国際航空市場は他地域に比較しても安定的に成長していることによるものと考えられる。しかしながら,今後の旅客需要の見通しは必ずしも明るいものではなく,これらの要請には需要の動向を踏まえたうえで,適切に対応し,旅客等の利便の向上に資することが望ましい。
|