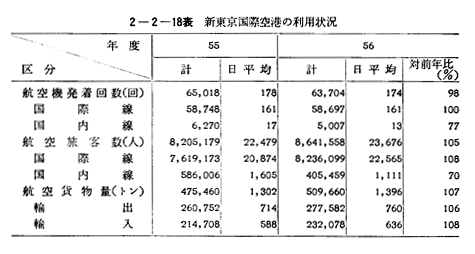|
4 国際空港整備の現状と今後の方策
我が国の国際航空輸送は,経済社会の発展,国際交流の活発化等を背景として,近年めざましい進展を遂げてきている。旅客輸送は,46年度の431万人から56年度には1,334万人と,この10年間に約3.1倍に拡大した。また,貨物輸送も,航空輸送に適合する高付加価値製品を中心として輸送量が著しく増大し,46年度の17万トンから56年度には57万トンと,この10年間に約3.4倍に拡大した。この10年間には,二度にわたる石油危機という厳しい試練があったが,内外環境の厳しい中で生きていくため我が国は国際化を一層進展させなければならず,こうした流れの中で国際航空輸送も大きな進展を遂げてきたものと考えられる。
今後の国際航空輸送については,国際的相互依存関係が一層深まる中で,単に経済社会的な活動を増進するだけでなく,政治文化的にも相互理解を深めていく必要性が強く指摘されており,こうした傾向を受けて引き続きかなりの需要増を示すものと見込まれる。
一方,このような国際航空需要の受け皿である我が国の国際空港の現状は,まだ不十分であり,国際化の進展に与える影響が懸念されるところである。我が国の国際航空輸送需要の9割は,東京,大阪という二大経済拠点に集中しており,各国からの乗り入れ要望もこれら大都市圏にある空港,即ち新東京国際空港,大阪国際空港に集中しているが,両国際空港は空港処理能力,空港施設の制約等からこうした諸外国からの要望に対応できない状況である。
今後一層国際化が進展する中で,こうした制約状況を早急に改善する必要があり,このため,運輸省としては,首都圏,近畿圏における国際空港を優先して整備していくこととしている。具体的には,首都圏について新東京国際空港の第2期工事を早急に完成させ,また,近畿圏について関西国際空港の建設を推進することである。
(1) 関西国際空港計画について
ア 関西国際空港の必要性
近畿圏の航空輸送活動の中心となっている大阪国際空港は,東南アジア,欧米等の20数都市と国際航空路線で結ばれる一方,我が国国内航空ネットワークの二大拠点の一つを形成している。
しかしながら,同空港は,市街地に囲まれているという立地条件に起因して,航空機騒音による深刻な環境問題が生じており,環境対策の一環として,運用時間を7時から21時までの14時間,1日当たりの離着陸回数も370回,うちジェット機200回に制限している。このため,国際貨客の増加に伴う外国からの新規乗り入れや増便の要求に対し十分対応できず,これらの国との間で問題となっており,前述の日米航空交渉においても,米国側は,大阪が乗り入れ地点として認められているにもかかわらず,大阪国際空港の運用制限により同国の航空協定の権利が不完全にしか実現されていないとして,同空港の使用条件の改善を強く要求し,空港問題が大きな交渉議題とされた。また,国内航空においても,増便はおろか,既にジェット機就航可能な空港からのジェット機の乗り入れもできない状況である。このような大阪国際空港の空港機能の制約がこのまま推移するとすれば,航空輸送の健全な発展を阻害することとなり,近畿圏のみならず,国全体の均衡ある発展と国際化のますます進む社会における経済・文化の交流の活発化等に支障を生ずることとなる。
したがって,大阪国際空港の騒音問題の抜本的な解決を図るためにも,また,新たな航空輸送の増大に適切に対応しつつ国際交流を深めていくためにも,国際・国内両用の24時間運用可能な関西国際空港を早期に建設する必要がある。
イ 航空審議会の答申及び調査の実施
関西国際空港は,40年代の初め頃から関西地区における航空輸送需要の増加に対処するためその必要性が認識され,運輸省において43年度から各種の調査を実施してきたが,46年10月,運輸大臣は航空審議会に対し「関西国際空港の規模及び位置」について諮問した。同審議会は2年10か月に及ぶ慎重な審議を行い,49年8月,関西国際空港の位置について,泉州沖,神戸沖,播磨灘の三候補地の客観的かつ総合的な評価の結果,泉州沖の海上が最も望ましいとする旨等の答申(第1次答申)を行った。
これを受けた運輸省は,泉州沖候補地に新空港計画を策定するための調査に着手すべく,関係府県(大阪府,兵庫県,和歌山県)と協議の上,51年9月,空港の計画は関係府県の合意を得て決定することなどを骨子とする「関西国際空港の計画に係る調査の実施方針」を定めて,今後の調査に取り組む基本的な姿勢を明らかにするとともに,翌52年2月には「関西国際空港調査の全体計画」を作成し,公表した。
このような地域社会の理解と協力を得る努力を重ねるとともに,空港候補地の海上等に固定観測施設を設置し,53年1月から気象・海象等の通年観測を開始し,翌54年5月と10月に実機飛行調査を実施するなど調査の全体計画に基いて,自然条件,社会条件,空港条件及び環境影響に関し,本格的な海上空港を建設するための広範囲にわたる調査を実施してきた。
これらの調査のまとめの段階に至った54年11月,空港計画の基本的事項について航空審議会の意見を求めた。同審議会は,第1次答申を基礎にその後の調査研究の成果を積極的に取り入れて鋭意検討を重ね,55年9月に,滑走路の計画,空域飛行経路の計画,建設工法,空港施設の計画からなる「関西国際空港設置の計画について」を答申した(第2次答申)。
一方,新空港の立地に伴う地域整備に資するため,52年度から55年度にかけ,国土庁,通商産業省,建設省(53年度から農林水産省も参加)及び運輸省が,国土総合開発事業調査調整費による調査を行った。
ウ 関係府県等との意見交換
関西国際空港の計画は関係府県の合意を得て決定することとしており,52年11月には関係府県の副知事と航空局長からなる「関西国際空港連絡会議」を設置し,調査の円滑な実施と新空港建設の合意を図るため,率直な意見交換を行ってきた。56年5月,二度にわたる航空審議会答申とこれまでの調査検討の結果をもとに,「関西国際空港の計画案」,「関西国際空港の環境影響評価案」及び「関西国際空港の立地に伴う地域整備の考え方」(いわゆる三点セット)を取りまとめ,関係府県に提示した。これ以降,三点セットについて関係者への説明を行うとともに関係府県との間の意見交換を鋭意進めてきたが,地元市町村議会の新空港反対決議もすべて撤回される等地元における情勢も変化し,57年7月には大阪府から,8月には和歌山県からそれぞれ計画の具体化を進めるべき旨の回答がなされた。
エ 今後の進め方
このような情勢を踏まえ,運輸省としては,今後は,関西国際空港建設計画について関係省庁等との協議を進め,早期に結論を得た上,その推進を図ることとしている。
(2) 新東京国際空港の整備について
新東京国際空港は,53年5月20日に開港され,目下,全体計画の約2分の1の規模である4,000メートル滑走路と,これに附帯する誘導路,エプロン,ターミナル等をもって運営されている。
現在,日本企業2社,外国企業33社が国際線の定期航空会社として乗り入れており,56年度における航空機の離着陸回数6万3,704回(1日当たり約174回),利用旅客数864万1,558人(1日当たり約2万4,000人),貨物輸送量50万9,660トン(1日当たり約1,400トン)である 〔2−2−18表〕。
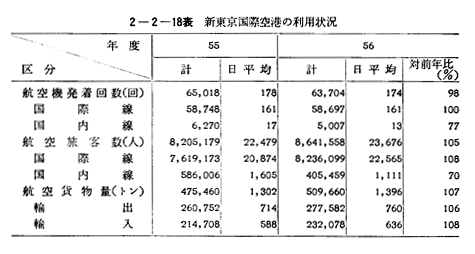
なお,航空燃料は,千葉港及び鹿島港からの鉄道及び暫定パイプラインによる暫定輸送によっているが,その期限については,55年12月の閣議決定により,58年12月末までとされており,これに代わる航空燃料パイプラインの建設は,全延長約46.9キロメートルについて導管等の敷設が完了しており,このまま順調に工事が進捗すれば,58年12月末までには完成し,供用できる見通しである。
しかしながら,新東京国際空港の現状は,日本を代表する国際空港としてはまだ十分ではなく,今後,第二期工事として横風用滑走路(3,200メートル),平行滑走路(2,500メートル)及びこれらに附帯する空港諸施設を整備することにより,将来にわたって増大する航空需要に応えてゆく必要がある。
このためには,地元の理解と協力を得ることが不可欠であり,空港と周辺地域社会とが一体となって調和のある発展を遂げていくよう環境対策,農業振興策等の種々の地元対策を推進していく必要がある。
このうち,農業振興策については,53年12月「新東京国際空港周辺地域における農業振興のための基本となる考え方について」(閣議報告)が策定され,この趣旨に沿い,更に地元の意向を反映しつつ農業生産基盤の整備,新東京国際空港公団所有農地の一部の貸付けなどの推進を図っているところである。
また,環境対策については,従来から,「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律」に基づき,民家,学校,病院等の防音工事の助成,移転補償等の施策を実施しているが,53年度末から民家の全室防音工事に着手するとともに,同法に基づく第一種区域を54年7月に80WECPNL以上に,57年3月に75WECPNL以上に拡大し,航空機騒音に係る環境基準の達成に努めているところである。更に,航空機騒音による障害の発生を未然に防止しながら,空港と調和のとれた周辺地域の土地利用を実現するため,「特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法」の積極的な活用を図っていくこととしている。
|