|
II-(I)-1 外航海運
1 海運市場の動向と我が国商船隊の輸送活動
(1) 世界の海上輸送
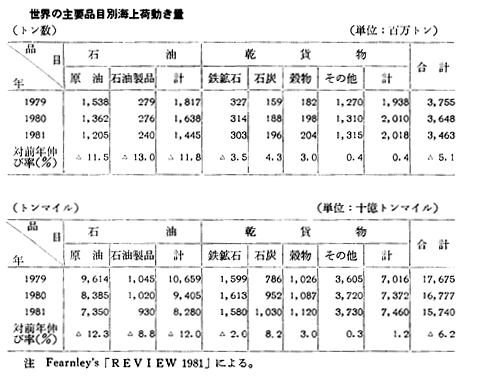
1981年の世界の海上荷動き量は,80年に比してトン数ベースで5.1%の減少,トンマイルペースでは6.2%の減少となった。昨年に引き続き原油が大幅に減少し代替エネルギーとしての石炭が増加したことが注目される。
(2) 世界の船腹量
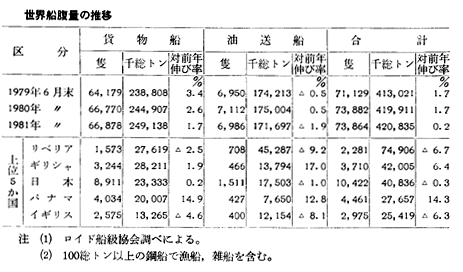
81年央の世界の船腹量は,約4億2,100万総トン,対前年比0.2%増と極めて低い伸びにとどまった。船腹量を国籍別にみると,リベリアが前集に引き続き大きく減少しており,一方パナマ,ギリシャ,サウジアラビアの伸び率は大きくなっている。とりわけイギリス,ノルウェー等先進国の多くがその船腹量を減少させたなかにあって,年々その船腹量を増加させているギリシャが,日本を追い抜いてリベリアに次ぐ世界第2位の船舶保有国になったことは注目される。
(3) 海運市況
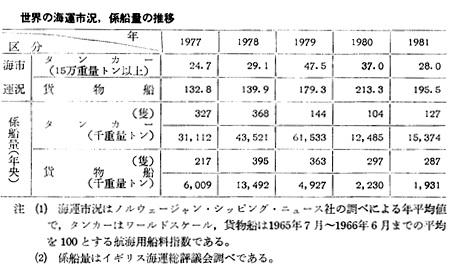
81年における海運市況は,貨物船は80年の堅調な推移から一転して低下傾向となり,またタンカーは年を通じ極端な低迷を続けた。貨物船市況の続落の原因としては,世界経済の低迷により海上荷動き魔が伸び悩んだにもかかわらず,大量のばら積貨物船が竣工したことなどが考えられる。一方タンカー市況については,船腹の大幅な過剰に加えて,世界的に代替エネルギーへの転換や石油消費の節約が進み,もって石油の海上荷動き量が減少したためであると考えられる。
(4) 我が国の海上貿易蟻
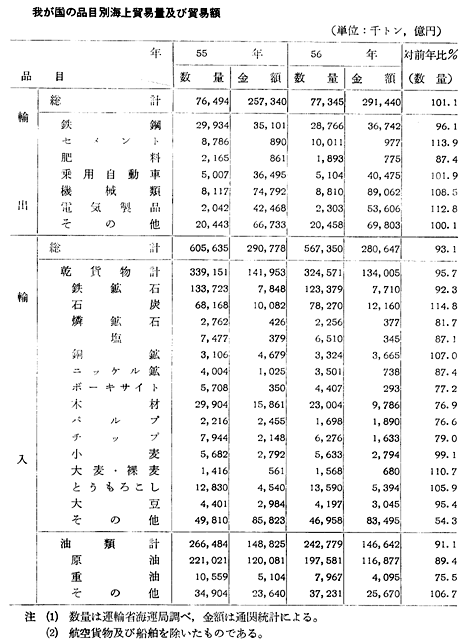
昭和56年の我が国の海上貿易量(トン数ペース)は,輸出はセメント,電気製品,機械類が増加したものの,肥料,鉄鋼の落ち込みが大きく,全体としては対前年比1.1%の微増にとどまった。一方輸入については,石油,木材,鉄鉱石等が減少したため,対前年比6.3%の減少となった。
また海上貿易額は,輸出が電気製品,機械類等の高付加価値製品の数量の増加により対前年比13.3%増,輸入が原油,木材等の主要貨物の数量の減少により対前年比3.5%となっている。
(5) 我が国商船隊の輸送量
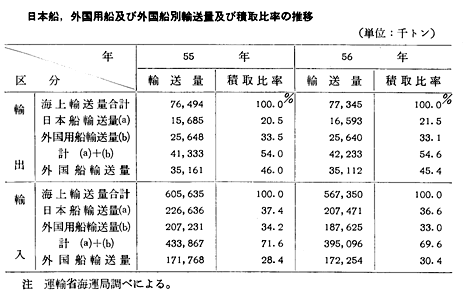
56年の我が国商船隊(外国用船を含む)の輸送量は,輸出が,我が国商船隊の積取比率の高い自動車の貿易量の伸びが鈍化したことなどから対前年比2.2%増にとどまり,また輸入及び三国間は,原油等の荷動きの減少からそれぞれ対前年比89%,11.6%の減少となった。
56年央の我が国商船隊(2,000総トン以上の外航船)の船腹量は,前年に比べて隻数で100隻,総トン数で329万総トンそれぞれ減少した。
これを日本船,外国用船別にみると,日本船は,隻数が3隻減少したものの,総トン数では23万総トン増加しており,一方外国用船は,前年に比べて97隻,351万総トンの減少となっている。なお,外国用船が大幅に減少した理由としては,世界経済の低迷に伴い海上貿易量が減少したこと,55年に米国,豪州で生じたような長期滞船が56年には生じなかったこと,などが考えられる。
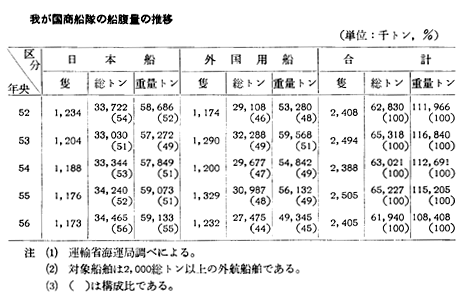
(6) 海運関係国際収支
海運関係国際収支(IMF方式)は,55年度には29.6億ドルの赤字であったが,56年度には用船料の赤字幅が多少拡大したものの,貨物運賃の大幅な黒字により全体として23.5億ドルの赤字となった。
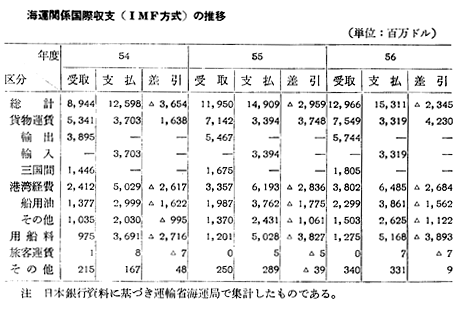
2 我が国外航海運企業の経営状況
(1) 損益状況
営業収益は,円安が大きく貢献したことと,上期において輸出が引き続き堅調であったことなどにより,一応の増収となったが,この増加率は,過去3か年で最低のものであった。これは,油送船が不振を続けていることに加えて,不定期・専用船において,貨物船市況が堅調な時期に好条件で締結した積荷契約が切れてくるのに伴って56年初来の市況下落の影響が出始めてきたことなどのためと考えられる。
一方,営業費用は,燃料油価格の騰勢が鈍化したこと,貨物の荷動きの停滞や貨物船市況の下落を反映して借船料の増加が一段落したことなどから対前年度比5.3%の低い伸びにとどまった。
これらの結果,経常利益は対前年度比30.1%の増益となったが配当会社数は,助成対象会社の半数にも及ばないという状況である。
年度を通じての損益状況は以上のとおりであるが,上期,下期の内訳を中核会社の経常利益でみると,上期の392億円に対して下期は273億円と減益になっている。下期には上期に比べて若干の円安になっていたことを考えれば,貨物船市況の下落の影響が56年度決算に現れつつあるといえる。
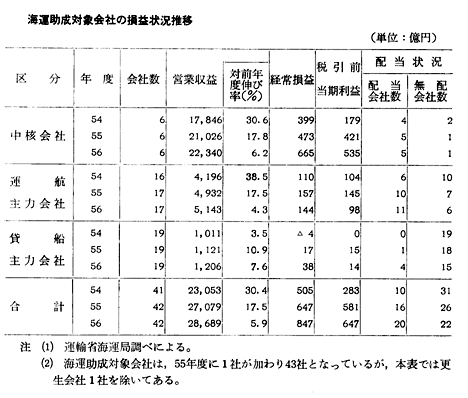
中核6社合計の営業収益の対前年度比を部門別にみると,不定期・専用船及び在来定期船は前年度に比べて円安に推移したにもかかわらず,伸び率は大幅に鈍化し,油送船は前年度に引き続き大幅な減収となった。コンテナ船は,航路の新規開設もあって,前年度を上回る伸びを示した。
今後については,定期船は,荷動きに大きな影響を与える先進諸国経済の早期回復が必ずしも期待し難いこと,貿易摩擦等我が国をとりまく貿易環境も厳しさを増しつつあること,更に,各航路での外国船社との競争が激しいことなど,業績の先行きには厳しいものがある。
不定期・専用船は,堅調を続けた不定期船市況に支えられて53年度からの3年間に収益規模が2倍に拡大して,ここ3年の企業業績回復に大きく貢献したが,市況は56年初来下落を続けており,早期の回復も期待し難い。しかも今後は,市況が堅調な時期に高い用船料で用船した船舶が,現在の市況低迷のなかで低い運賃水準による運航を余儀なくされており,今後の業績にとっての不安要因である。また,専用船についても世界各国の経済活動の低迷に伴う海上荷動き量の停滞により,契約の更新が困難になることも予想される。油送船については,依然として業績回復の目途を立て難い状態が続いている。
このように56年度の決算は黒字であったが,定期船,不定期・専用船,油送船の3部門とも厳しい見通しであり,その兆しは既に56年度下期の業績の下降にみられ,今後は業績の悪化が懸念されるところである。
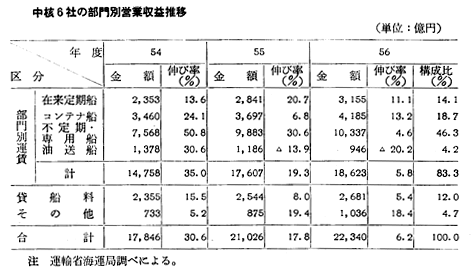
(2) 財務内容
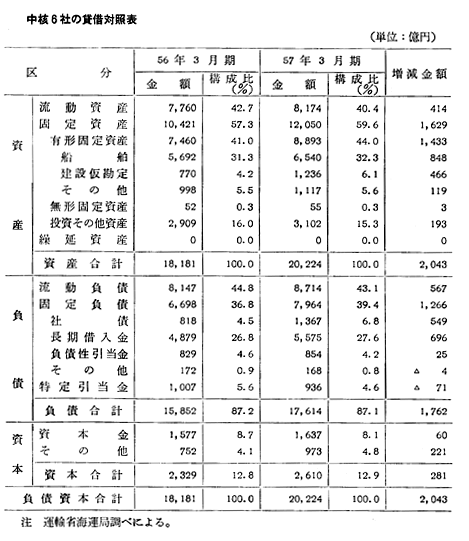
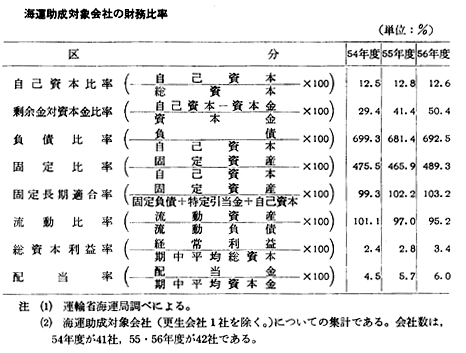
船舶勘定が前期に続いて増加しているが,これは,外航船舶緊急整備対策により日本船の建造が促進されたためといえる。しかし,これに対応して長期借入金も増加しており,黒字決算が継続したにもかかわらず借入金依存の体質は依然変わりない。これを財務比率でみると,目立った改善はみられず,企業体力が脆弱であることを示している。
今後は,外航船舶緊急整備対策の期間中に建造した船舶にかかる借入金の返済が本格化するうえに,業績の悪化も予想されるため,資金繰りが厳しくなることは避け難く,船舶建造資金の調達に支障が生じることが危惧される。
(3) 海運企業の経営構造
海運企業の経常は,国際政治・経済・社会情勢の影響を受けやすく不安定な環境下で行われているため,著しい業績悪化に陥ることが多い。業績の変動と度重なる欠損計上のため内部留保は厚みに乏しく,準備金及び剰余金に特定引当金を加えた内部留保の総資産に対する割合をみても,中核6社では9.4%(56年度末)と,製造業の15.5%(55年度末)に比し大きな格差がある。
海運企業においては,特別償却準備金の制度が,内部留保の蓄積に寄与してきたが,この制度は漸次縮小されてきている。この準備金の残高は,大幅な減少を続けており,海運企業の経営基盤を強化するうえで大きな問題となっている。
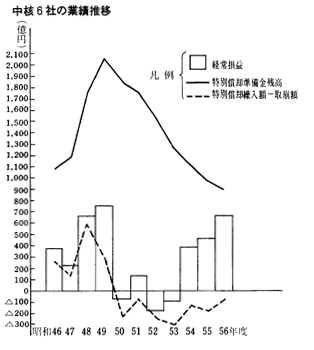
3 近海海運問題
近海船は,合理化の余地に乏しく,国際競争力が弱いうえ,近年,その主要貨物である木材の輸入量が55年春頃から大幅に減少し,慢性的な過剰船腹状況が続いているため,近海海運業者の経営は不安定な状況となっている。このため近海船の建造抑制や解撤建造方式による船舶整備公団との共有船建造等の措置が講じられてきた。他方において,最近は,資源保有国の自国海運の増強や木材輸出制限の動きが強まりつつあるため,近海海運業をめぐる環境は厳しさを増しつつある。
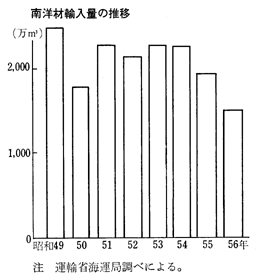
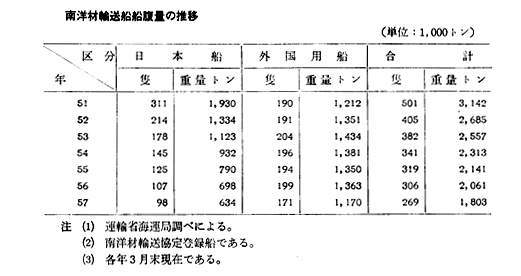
4 日本海運をとりまく国際的諸問題
(1) 国際緊張と日本海運
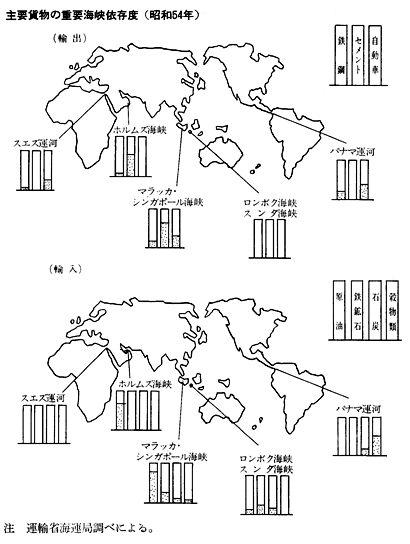
資源に乏しく,貿易立国である我が国において,海上輸送の国民経済に占める地位は極めて大きいものがある。また,原油,鉄鉱石等の重要資源,輸出品等の輸送路は,マラッカ海峡,ホルムズ海峡,パナマ運河,スエズ運河等に相当集中している。これら重要海峡等の多くは,その沿岸国あるいは周辺国において紛争が多発しており,船舶航行が不能となる事態が発生する危険性を潜めており,かかる事態が我が国経済に及ぼす影響は極めて大きい。
このような状況を踏まえて,運輸政策審議会において,我が国の総合的な安全保障政策に関する検討がなされているほか,海上保安庁は,現在整備中の海洋情報システムを活用して,国際紛争等に巻き込まれるおそれのある日本船舶に対し,航行安全情報を提供する等により,危険を回避ないし,被害を最少に止めることができるような体制を検討している。
(2) 便宜置籍船及びサブスタンダード船問題
(3) 二国間の海運問題
米国をめぐる海運問題
米国は,定期船同盟活動に対し広範な政府介入を行うなど我が国を含む先進海運諸国と異なった独自の海運政策をとってきているため,これら諸国との間で種々の摩擦を生み出している。かかる摩擦を回避するため,我が国を含む伝統的な海運国は先進海運国グループ(CSG)を結成し,米国との間で協議を行ったり,種々の申入れを行っている。
レーガン政権は,発足以来,海運政策の全面的な見直しを行ってきたが,57年2月にまず海運規制政策がとりまとめられた。その内容は,概ねCSG諸国にとって好ましい内容となっている。方,議会で審議が進められているゴートン法案,ビアツギ法案は,基本的には,行政府の見解と一致しているが,強制的インデペンデント・アクション,サービス・コントラクト等問題のある条項もある。
日中海運問題
日中間の海運業務については,日中海運協定に基づき指定された両国の民間協議団体により協議することとされており,現在まで5回にわたり,主として日中間の定期航空路開設につき協議されたが,双方の考え方に隔たりがあり未だに実現していない。他方,両国政府間においても,すでに民間協議の促進方については意見の一致をみており,特に昨年の日中閣僚会議の場で合意された両国政府間の実務者協議が57年5月に行われ,定期航路開設につき基本的合意に達するとともに,今後,必要に応じて両国政府が民間協議団体を指導していくことなどが確認された。
東欧圏問題
ソ連を中心とする東欧圏海運は,自国関係航路のみならず,三国間航路において,低い運賃を呈示して活発に集貨するなどの盟外活動を行っている。
東欧圏に関しては,他にシベリア・ランド・ブリッジ(シベリア鉄道を利用した極東/欧州・中東間の海陸一貫輸送)輸送問題がある。同輸送は輸送手段の多様化という観点から一概に否定すべきものではないが,日欧間の輸送が特定の国の内陸輸送に過度に依存することにより,安定的な輸送に問題が生ずることのないよう配慮する必要があろう。
(4) 航海の安全問題等
ア マラッカ・シンガポール海峡通航問題
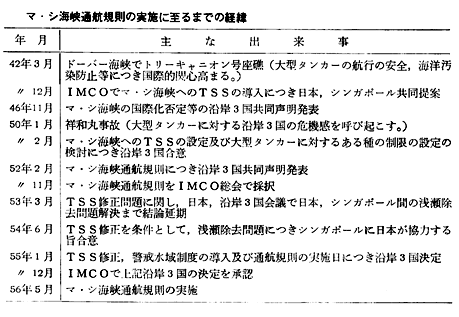
イ 海上における安全及び汚染防止問題
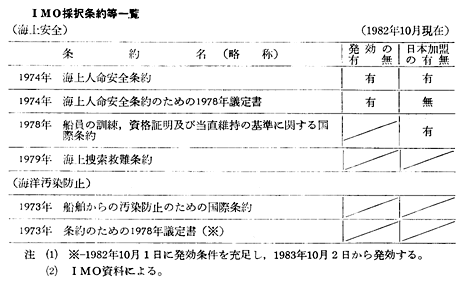
(5) 船舶事故に係る被害者救済制度
(ア) 現在の「船舶の所有者等の責任の制限に関する法律」(以下「船主責任制限法」という)に基づく船主責任制限制度については,その責任限度額の基礎を定めている1957年の「海上航行船舶の所有者の責任制限に関する国際条約」の採択後,すでに25年を経過しており,船舶所有者等の責任限度額が不十分なものとなるなどの問題が生じている。
(イ) このような事情に鑑み,我が国は,第96回通常国会において,責任限度額の大幅な引上げなどを目的として1976年に採択された「海事責任権についての責任の制限に関する条約」を締結するとともに,これに伴う船主責任制限法の一部改正を行い被害者保護の充実を図った。
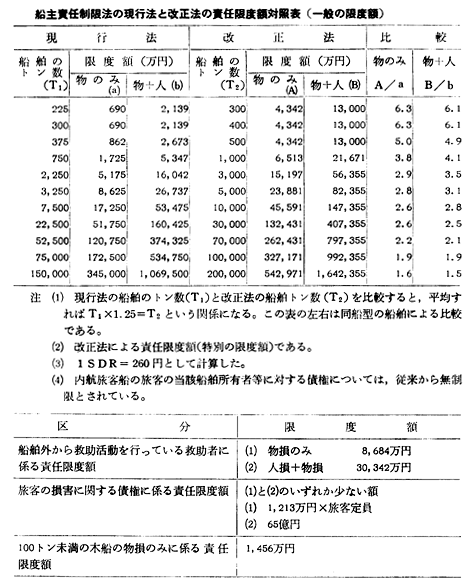
イ 油濁損害賠償保障制度等
(ア) タンカーの事故による油濁損害については,1969年の「油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約」(以下「民事責任条約」という。)及び1971年の「油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約」(以下「基金条約」という。)を国内法化した「油濁損害賠償保障法」(昭和51年9月施行)により,被害者の救済保護を図っている。
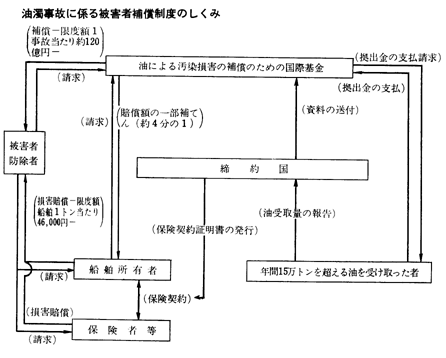
(イ) また,我が国は,「油による汚染損害の補償のための国際基金」において,重要な役割を果している。
ウ 油濁損害賠償制度の見直し等
|