|
II-(I)-2 内航海運
1 内航貨物輸送
(1) 輸送活動の動向
(2) 内航船舶と船腹需給の現状
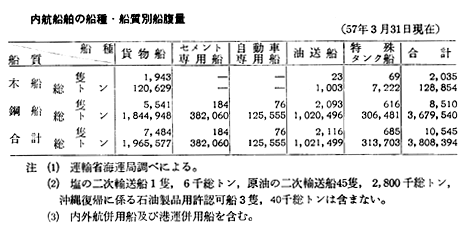
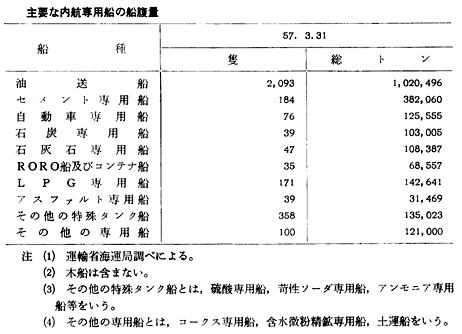
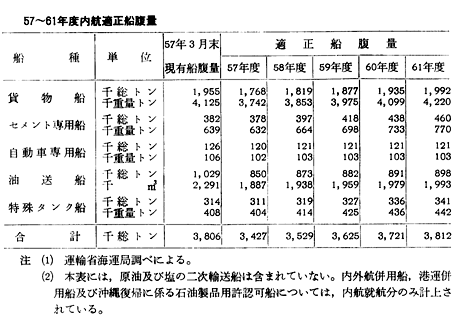
内航船腹量は,57年3月31日現在,総計1万545隻,約381万総トン(原油及び塩の二次輸送船を除く。)となっている。
また,鋼船については,専用船化が着実に進んでおり,全鋼船に占める専用船の船腹量の割合は,46年度末の48.8%から56年度末の60.8%へと高まってきている。特にRORO船及びコンテナ船は,船腹量及び隻数とも45年度以降年々増加しており,内航海運における雑貨輸送の推進と荷役効率の向上が着実に進展している。
(3) 内航海運事業者の概要
57年3月31日現在の内航海運事業者数は,合計10,677(うち実事業者数9,205)事業者であり,その事業規模についてみると,小規模な事業者が多く,許可事業者のうち,資本金1億円未満の会社及び個人事業者が約95%を占めている。
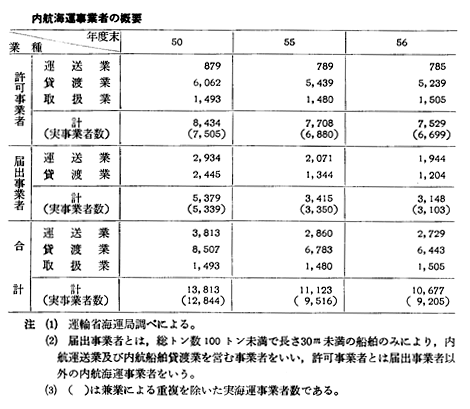
(4) 内航海運事業の経営状況
内航海運企業の経営状況をみると,55年度の経営内容は,輸送量の低滞及び燃料油価格の高騰等の影響を受け,売上高利益率は前年度に比し低下している。また,56年度については,景気回復の遅れ,石油需要の低迷等により,前年度より荷動きの減少が顕著となり,燃料油価格も高値安定に推移するなど企業経営の環境には一段と厳しいものがある。
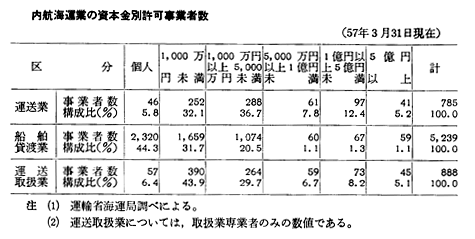
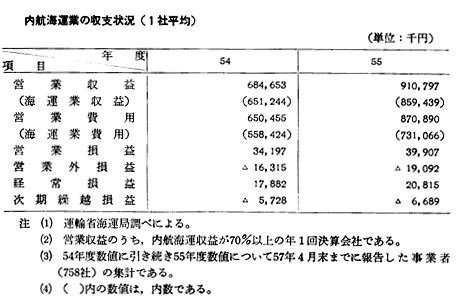
(5) 内航海運組合等の組織
(6) 船腹需給の調整及び船舶の近代化
内航船腹の需給調整については,内航海運組合総連合会が内航海運組合法に基づき,自主的にスクラップ・アンド・ビルド方式による船腹調整を行っている。
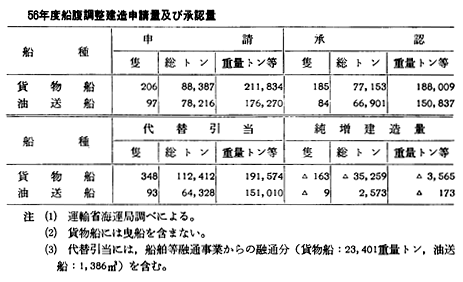
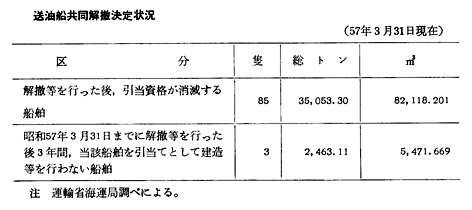
(7) 内航海運企業の経営体質の改善
内航海運業においては,内航海運業法に基づく許認可を通じ,構造改善施策を推進し,小規模事業者の経営体質の向上,事業規模の適正化等による輸送秩序の維持及び企業基盤の強化を図っている。この結果,事業者数が46年度末から56年度末の10年間において16,041から10,677へと減少し,企業の集約化が図られるなど徐々にではあるが,内航海運業界の体質改善が進みつつある。
(8) 自家用船対策
自家用船の届出を行っている船舶が,安定した自己の貨物の輸送需要が得られなくなった場合,他人の需要に応じる営業行為を行う事例が生じており,これが内航海運秩序を混乱させる一因となっている。
このような内航海運秩序の混乱を防止するため,営業船及び自家用船の船舶を峻別する手段を講じ,監視体制の強化を図るとともに,自家用船舶所有者の遵法精神の高揚を図る必要がある。また,他方では,自家用船から営業船に転用を望む者のため内航の秩序維持を踏まえた転進の道を設ける必要があり,現在対策が進められている。
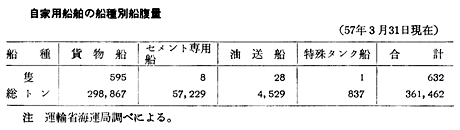
2 旅客輸送と自動車航送
(1) 輸送活動の概況
(2) 旅客航路事業
(3) 長距離フェリーの現状
長距離フェリー業界は,54年の第二次石油危機により,燃料油価格及び諸経費の高騰と国内経済の停滞による輸送需要の低迷の結果,多額の累積債務をかかえて苦しい経営を余儀なくされている。しかし,長距離フェリーは,我が国の輸送活動の重要な一翼を担う幹線的輸送機関であり,56年7月に発表された運輸政策審議会の答申でも物流体系の効率化を図るため,長距離フェリーを利用した協同一貫輸送を推進することが国民経済的にみて必要であることを強調しており,今後とも長距離フェリーに期待される役割は大きいものがある。
このため,長距離フェリー各社は,より一層,省エネルギーに努めるとともに,航路の見直し等を含めた経営合理化を進め,現在の苦境を乗り切ることが望まれる。
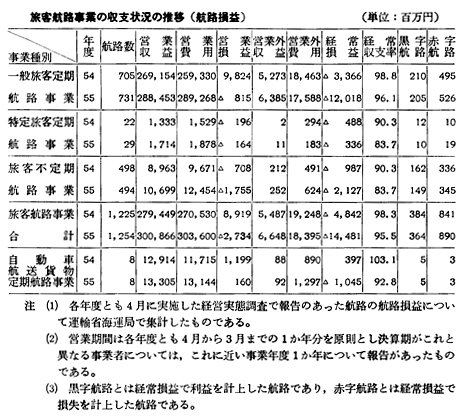
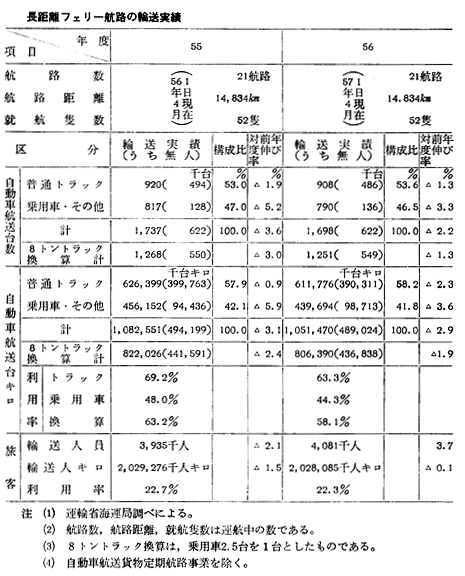
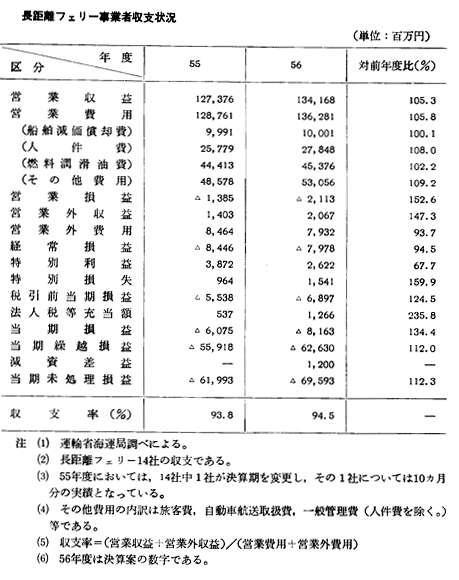
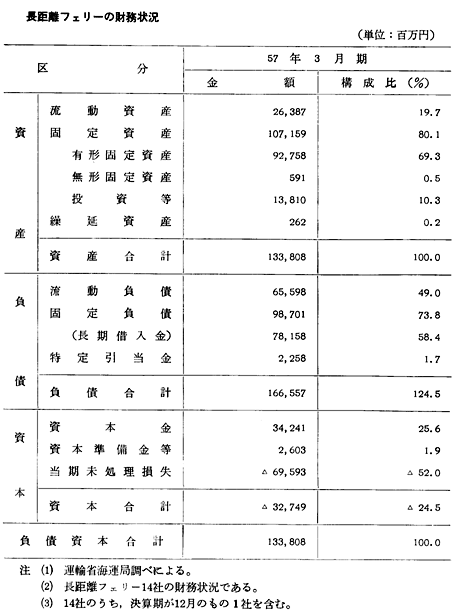
(4) 離島航路の現状と助成
離島航路は,観光資源に恵まれた一部の航路を除いては過疎化により減少した離島の住民を主たる輸送対象とするため,輸送需要は概ね低迷を続けている。一方,諸経費の上昇は避けられず,合理化の余地も極めて乏しいところから,赤字経営に悩んでいるものが多い。
このため,離島航路のうち生活航路であって,かつ,一定の要件を備えた航路について,国庫補助航路として指定し,これらの航路がその経営に当たりやむを得ず欠損を生じた場合には,その欠損額に対し国が75%相当額(集約航路にあっては80%相当額)を,また,関係地方公共団体が25%相当額(集約航路にあっては20%相当額)を,それぞれ補助金として交付することとしている。
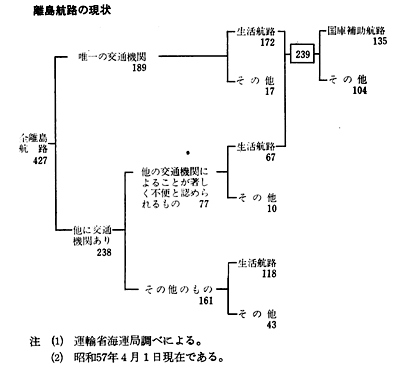
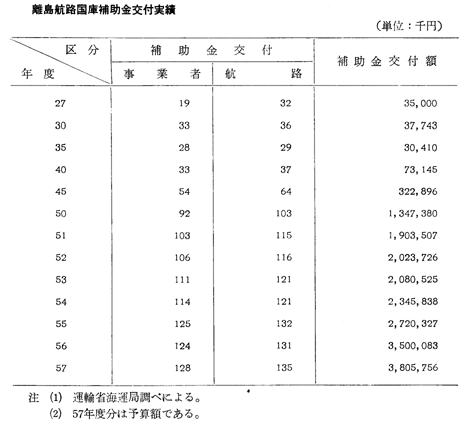
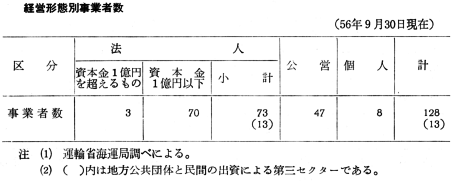
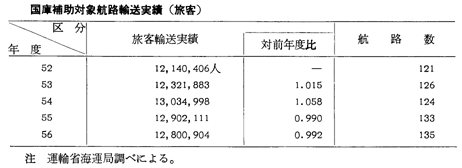
(5) 旅客船の事故発生状況
(6) 本州四国連絡橋の建設と一般旅客定期航路事業への影響
本州四国連絡橋の建設により,この地域の交通に重要な役割を果たしている一般旅客定期航路事業等は相当の影響を受けることになる。このため,関係者間では本州四国連絡橋の建設に伴う影響をできる限り軽減するための対策について協議が行われてきたが,56年6月,第94回通常国会において「本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法」が成立し,同年11月から施行された。
更に,同年12月,海運造船合理化審議会の答申を踏まえて,架橋に伴う事業の整備,再編成に伴い不要となる資産の利用及び離職者の雇用の安定を図るための措置についての基本的方針を示す「再編成基本方針」を定めた。また,これとともに,供用開始の間近い尾道・今治ルートの因島大橋に関連する航路を架橋により影響を受ける航路として指定したほか,57年6月には,神戸・鳴門ルートの大鳴門橋に関連する航路を指定し,同法に基づく諸措置の具体的な実施を図ることとしている。
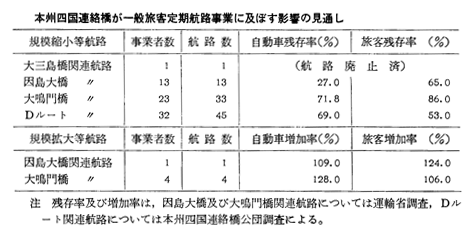
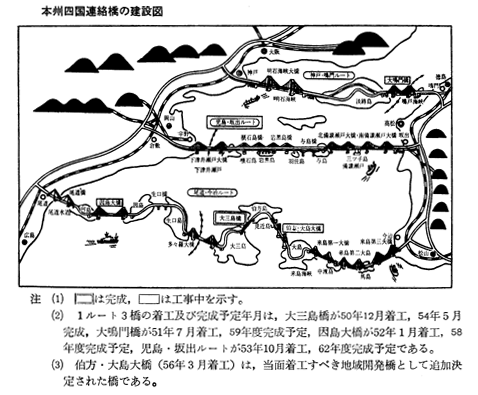
3 船舶整備公団
公団の事業実績の推移は,表に示すとおりで,34年度に公団が設立されて以来56年度末までの建造実績は,旅客船542隻,210千総トン,内航貨物船1,193隻,1,086千総トン,近海貨物船52隻,182千総トンに達している。
公団の事業規模は,事業者の近代化,合理化への意欲を背景に着棄に拡大してきており,また,建造実績に占める公団共有船の比率も,旅客船が33%,貨物船が59%に達している。このように公団は,旅客船,内航・近海貨物船の近代化に大きく寄与している。
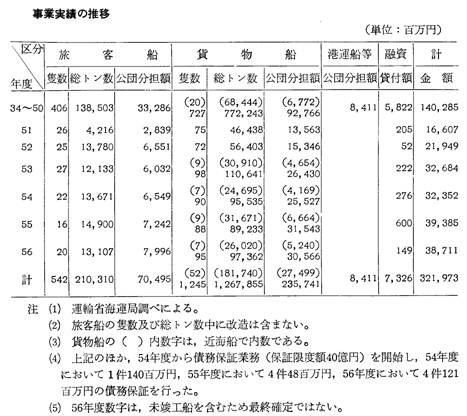
|