|
II-(V)-3 海難審判による海難原因の究明
1 海難の原因
海難審判庁は,海難の再発防止に寄与するため,海難が発生した場合にその原因を①乗組員の資格・技能,労働環境,②船舶の構造性能,③航海環境,④気象・海象の自然現象等の諸要素について幅広く科学的に調査し,審判によって明らかにしている。
昭和56年には,地方海難審判庁において,968件の裁決が行われた。
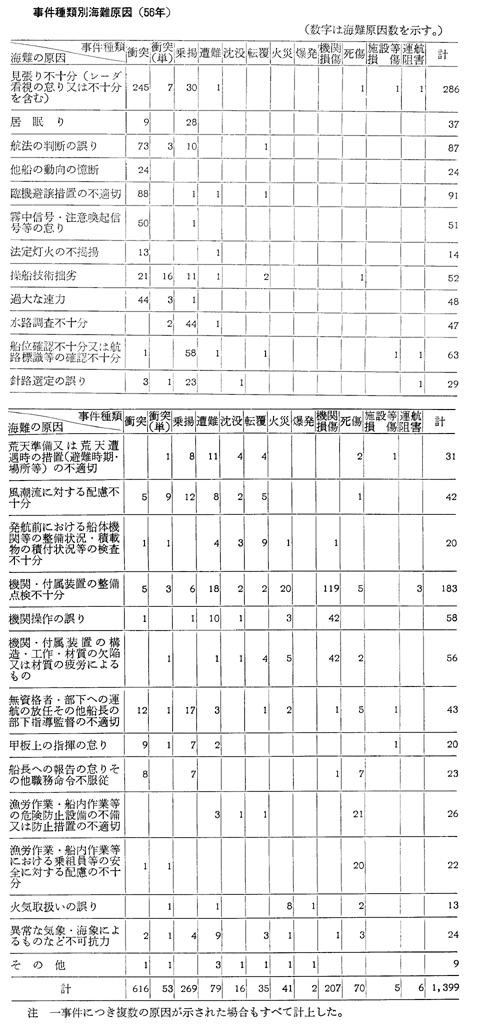
2 重大海難事件
(1) 56年に発生した重大な海難事件
ア 油送船ハーモニーベンチャー爆発事件
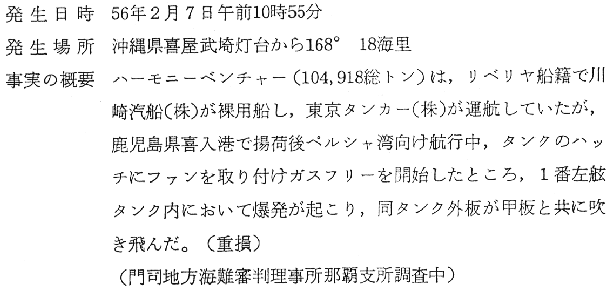
イ 貨物船中和丸・油送船第16港明丸衝突事件
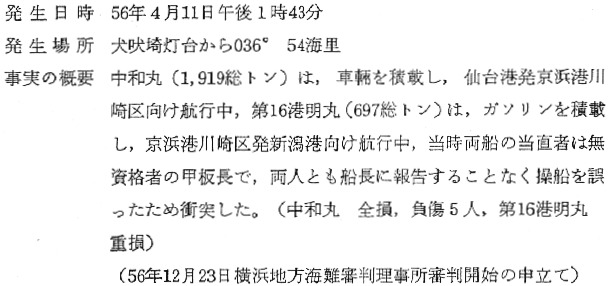
ウ 貨物船祥海丸遭難事件
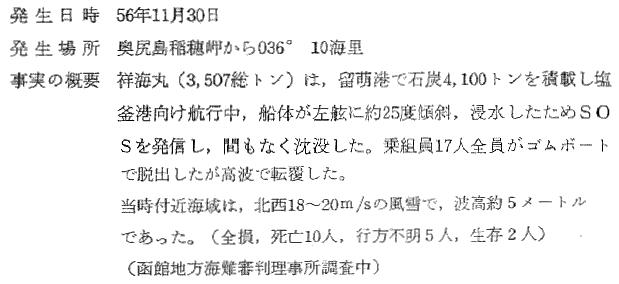
(2) 57年1月以降8月までに発生した重大な海難事件
ア 漁船第28あげぼの丸転覆事件
(1月6日午後4時57分ベーリング海で発生,船体沈没,死亡8人,行方不明24人,生存1人,57年8月31日横浜地方海難審判理事所審判開始の申立て)
イ 漁船第十正一丸遭難事件
(6月27日午前10時30分宮城県金華山沖で発生,船体沈没,仙台地方海難審判理事所調査中)
ウ 漁船第八蛸島丸遭難事件
(6月27日午後2時0分宮城県金華山沖で発生,船体沈没,死亡1人,行方不明1人,生存20人,仙台地方海難審判理事所調査中)
(3) 56年に地方海難審判庁において裁決のあった重大な海難事件
ア 旅客船フェリーこがね丸・旅客船あいぼり丸衝突事件
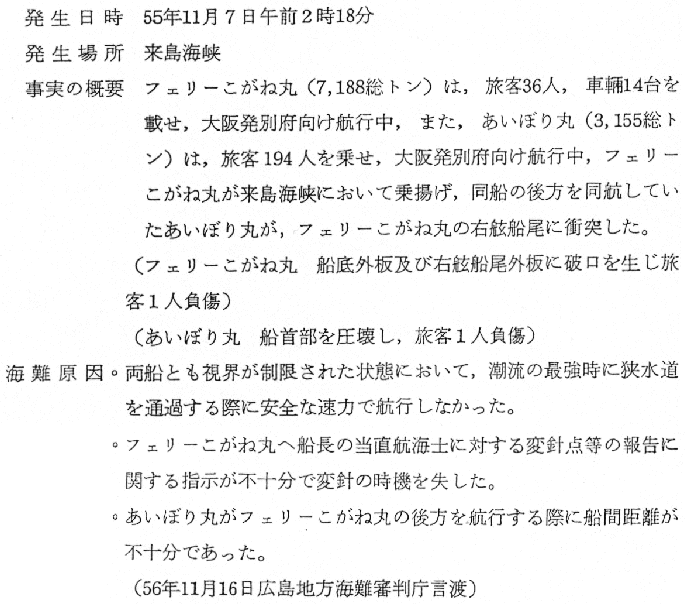
3 海難原因の系統的な究明
海難事件の裁決は一件ごとに行われ,海難の再発防止に寄与しているが,海難防止により一層寄与するためには,同種海難の態様や原因を系統的に観察することにより,その傾向と問題点を浮き彫りにすることも極めて重要であると考えられる。この趣旨に基づき,海難審判庁は,機関損傷の実態について調査分析をし,問題点の指摘を行って,57年2月に刊行物「船舶におげる機関損傷の実態」を発表した。
本調査は,51年から55年までの5か年間に裁決があった機関損傷事件679件を対象として調査・分析を行い,その結果,機関損傷の防止策への具体的な提言として次のことを指摘した。
(1) 機関の性能向上に対する教育・訓練等について
機関取扱者が機関の性能向上に的確に対応できないために発生した場合が多くあるように見受けられるので,船舶所有者,運航管理者等は平素より機関取扱者に対する教育,訓練等を徹底的に行うなどにより,機関の性能を十分に熟知させ,その整備,取扱い等に遺漏のないようにすべきである。
また,機関のメーカーは,新しい機関又は附属装置を製造販売したときは,想定される対象者の知識技能に合わせて理解しやすいように,平易な文書で図解入りの説明などを加えたハンディマニュアル類を作成し,従来の取扱説明書とともに交付することが望ましい。
(2) 潤滑油,冷却水等機関警報装置の活用について
各種警報装置を採用した場合は,同装置に頼る程度が高くなればなるほど,従来の五感による監視が疎そかになりがちとなるので,常時,その機能を十分に発揮できるよう日常の整備点検を入念に行っておくべきである。
(3) 起動直後の事故防止について
機関室内における当直員の常時配置は事故防止上望ましいことであり,機関取扱者としては,起動に際しての諸操作手順を省略せず,少なくとも運転状態が整定するまでは,機関室内における当直を怠らぬようにすべきである。
(4) 機関取扱責任者の機関状況の把握について
定期,中間検査を受検又は任意に開放検査を行ったのち,短期間のうちに事故を起こしているものが多数あるのは,検査後の取扱いの不注意にもよるが,機関長等取扱責任者が検査工事そのものを業者に放任し,検査時に開放した機関の現状や工事の内容を知らなかったのではないかとみられるものが少なくないので,機関長等取扱責任者はこれらの工事に立ち会うことが必要である。
また,機関長等取扱責任者が交替する場合には,前任者は後任者に対して機関の性能,現状,取扱上の注意事項等についても詳細に引継ぎ,当該機関の現状を正確に把握しておくようにしておかなければならないので,船舶所有者,運航会社等によるこれらの面での指導監督の一層の強化が望まれる。
4 海技従事者等の行政処分
海難審判庁は,海難が海技従事者又は水先人の職務上の故意又は過失によって発生したことが明らかになったときは,免許の取消し,業務の停止又は戒告の懲戒処分を行い,海技従事者又は水先人以外の者で海難の原因に関係のある者に対しては勧告を行うことができることになっている。
56年に海難審判の対象となった海技従事者及び水先人は1,294人である。
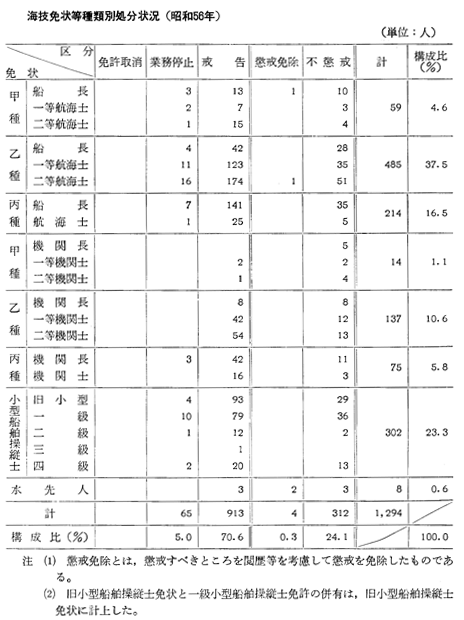
|