|
II-(V)-4 海上交通の安全対策
1 船舶の安全な運航の確保
船舶職員制度の現況
船舶には,航行の安全を図るため,船舶職員法に基づき中板部,機関部及び無線部にそれぞれ船舶の大きさ,航行区域等に応じて必要な免許を有する資格者(海技従事者)を乗り組ませなければならないこととなっており,昭和56年度末現在海技従事者の数は約220万人であり,55年度に比べて約4%,約9万人増となっている。
このうち大部分は小型船舶操縦士の資格に係る免許受有者の増加によるものであり,前年度に比べて約5%,約7万人増となっている。
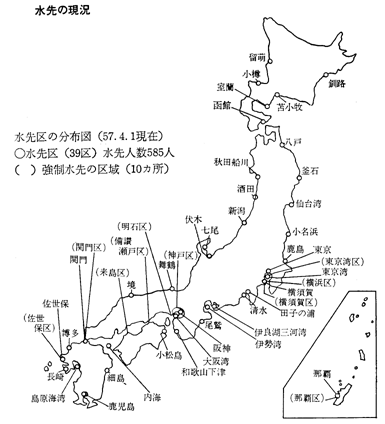
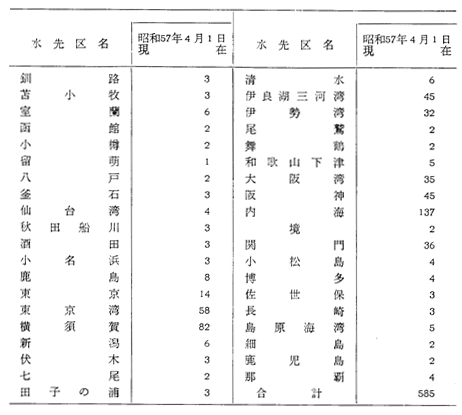
2 船舶の安全等の確保
(1) 船舶検査と安全基準
海上における人命の安全を確保するためには,船舶の構造が堪航性を保持するのに十分であること,万一非常の危難に遭遇した場合にも人命の安全が保持できるように必要な設備が備えられていることが要求される。このため,船舶安全法は,船舶の構造,設備等について技術基準を定めており,検査を行うことによりこれを励行せしめている。
船舶検査は,全国65か所の海運局等に245名(内沖縄5名)の船舶検査官を配置し,また,小型船舶を対象として,日本小型船舶検査機構の35か所の支部等に181名の小型船舶検査員を配置し,実施している。
更に,検査業務の合理化を図るため,事業場認定制度及び型式承認制度がとられており,56年度末現在で214事業場が認定され,また,1,605物件が型式承認されている。
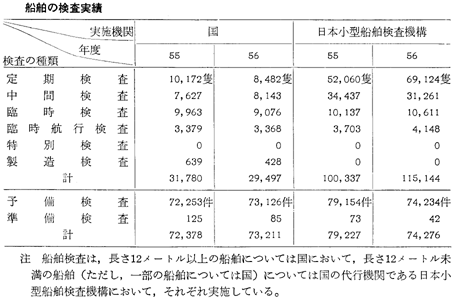
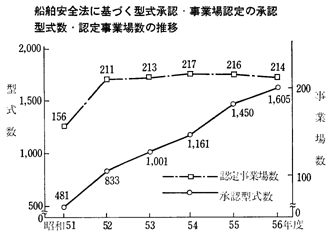
一方,船舶検査業務は,近年,技術革新による輸送形態の多様化,諸設備の高度化等に伴い,ますます複雑化してきている。また,放射性物質・化学物質等危険物の海上輸送量は,化学工業の発展により増大の一途をたどり,これに係る積付検査,安全確認業務等の新たな業務が急増している状況にある。これらに対応し,また,国際的にも条約等との整合性を保ちつつ安全基準の整備強化を行ったところである。
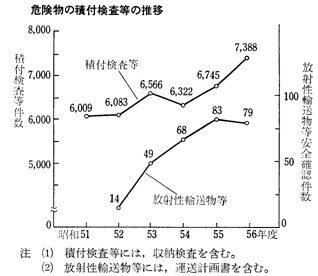
(2) 船舶のトン数測度
船舶のトン数は,船舶の大きさ,稼動能力等を表わす指標であり,多数の海事関係法令等の適用上の基準として用いられている。
船舶のトン数の測度の種類は,新造時及び改造時の測度があり,総トン数20トン以上の船舶については国が,総トン数5トン以上20トン未満の船舶については地方自治体が測度を実施している。
更に,トン数が公証され,既に運航の用に供されている船舶についても,一定期間毎に検認を行い公証トン数の確認を行うほか,違法改造防止の観点から立入臨検を行っている。
現在,これらの船舶のトン数測度及び立入臨検を実施するため,全国62か所の海運局等に64名の船舶測度官を配置している。
また,57年7月18日からの船舶のトン数の測度に関する法律の施行に伴い,関係諸規則等の制定改廃を行ったところである。
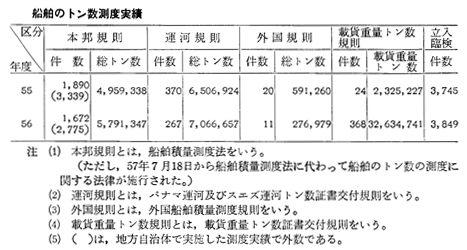
|