|
II-(V)-5 海洋汚染防止と海上防災
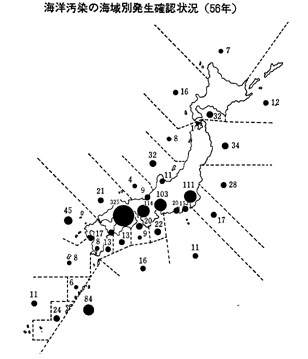
昭和56年に,我が国周辺海域において海上保安庁が確認した海洋汚染の発生件数は,1,244件となっている。
排出源別にみると,船舶からのものが大半を占めており,排出源不明のものもそのほとんどが船舶からのものであると推定される。
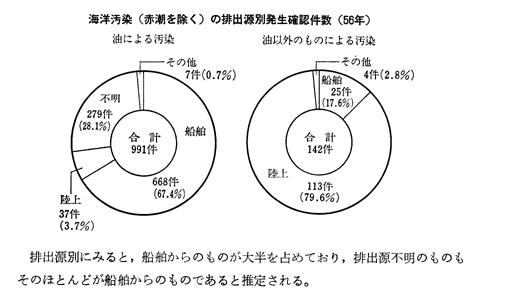
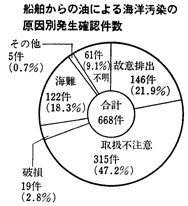
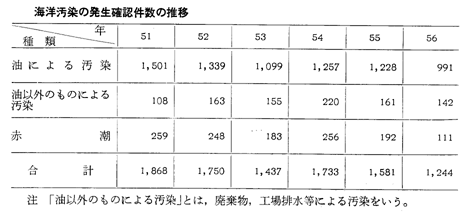
最近6年間の海洋汚染の発生確認件数の推移をみると,減少傾向を示しているものの依然として年間1,200件を超える汚染が発生している。
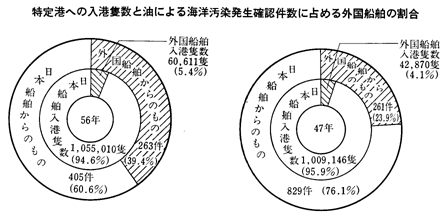
56年において,入港隻数と油による海洋汚染発生確認件数に占める外国船舶の割合をみると,外国船舶が入港隻数で占める割合は5.4%であるのに対し海洋汚染発生確認件数で占める割合は39.4%と入港隻数の割合に比べ著しく高率になっており,こうした特徴は,10年前の47年と比較し目立ってきている。
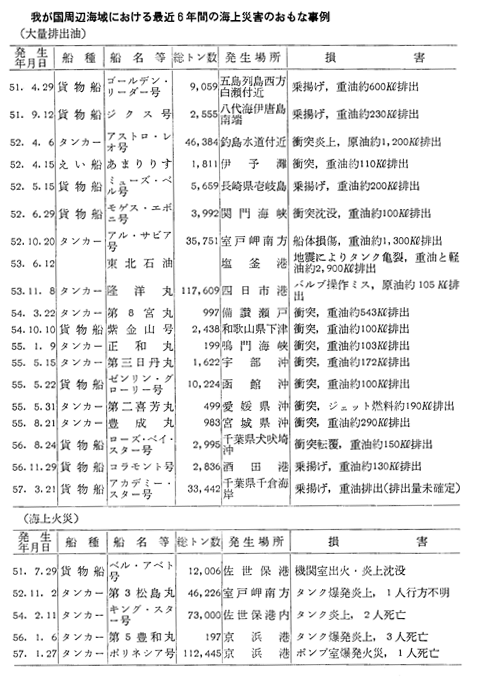
56年には,防除措置を講じた油排出事故は467件発生し,このうち1キロリットル以上の排出油を伴った事故は35件で,内訳は,貨物船15件,タンカー2件,漁船5件,その他の船舶2件,陸上からのもの5件,海洋施設からのもの1件,排出源不明のもの5件であった。一方,船舶の火災事故は,130件発生し,このうちタンカーは11件,1,000総トン以上の貨物船は16件であった。また,大規模な海上災害を引き起こす可能性のあるタンカーによる衝突,乗揚げ事故はそれぞれ9件,26件発生している。
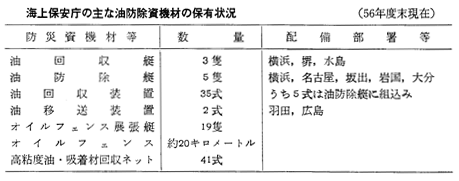
海上保安庁は,原因者責任体制の充実を図る一方,自らは油排出事故が発生した場合には巡視船艇・航空機等を出動させ,油排出状況の把握,航行船舶に対する周知,航行制限,原因者・海上災害防止センター等の防除措置実施者への指導・助言等を行うとともに,原因者側の措置が十分でない場合には,全国主要部署に配備している油防除資機材を使用して排出油の防除を行うなど被害を最小限にくいとめるための措置を講じている。
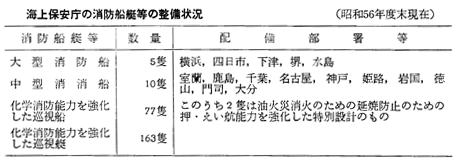
海上保安庁は,海上における消防責任を負う公的機関として,海上火災が発生した場合には,巡視船艇・航空機等を出動させ,消火・延焼防止のための措置を講ずるとともに,航行船舶への周知,航行制限等の船舶交通の危険を防止するための措置を講じている。また,消防機関との間では,船舶火災に関し業務協定を締結しており,相互の協力により消火活動を迅速・的確に案施している。
海上災害防止センター
51年10月に設立された海上災害防止センターは,全国29か所の基地に防除資機材を備え付けるとともに,東京湾,伊勢湾及び瀬戸内海の10基地に油回収船等を,さらに,東京湾には消防船2隻を配備し,事故発生時には同センターと契約した防災事業者により,防除活動を行う体制を備えている。このほか,船舶乗組員,石油関係企業従業員等を対象とした消火及び排出油防除措置に関する訓練を行っており,57年度から消火実技訓練の実施回数を大幅に増加している。
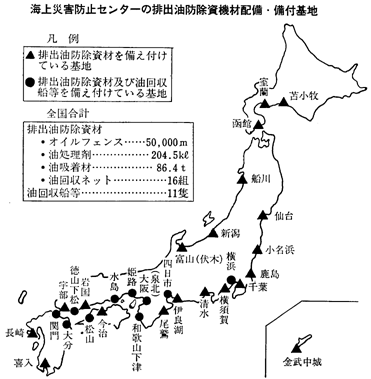
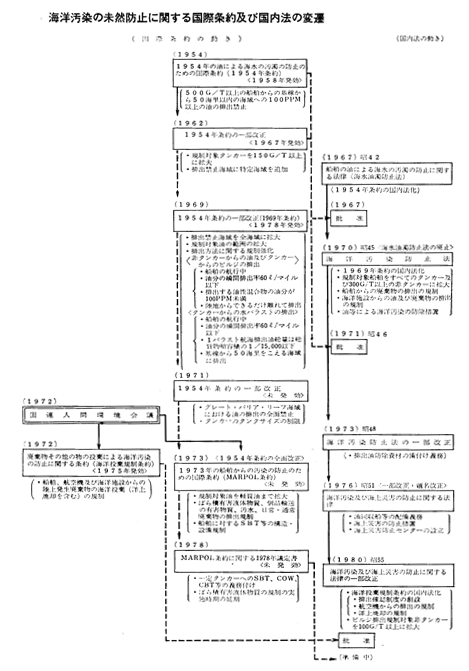
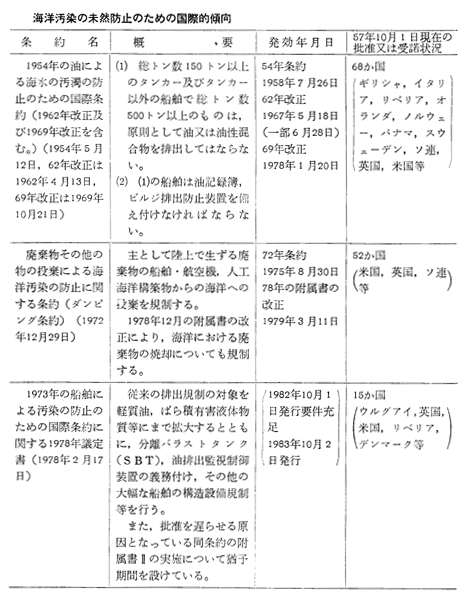
|