|
1 気象
昭和56年度は,5月下旬の東日本と北日本の低温と晩霜,梅雨期の大雨,6月から10月にかけての台風の接近や上陸,8月から10月にかけての北日本の低温,そして,早い冬の訪れ等,気象現象が国民生活に及ぼした影響は大きかった。
5月下旬に日本の上空に強い寒気が流入したため,東日本から北日本にかけての広い範囲で冷え込んだ。特に,29日から31日にかけては,北海道北部やオホーツク海沿岸部で季節はずれの雪が降り,旭川を始め,各地で観測開始以来最も遅い雪となった。この寒さのため,宗谷支庁を中心に上川・網走支庁管内で乳牛が60数頭衰弱死した。また,31日は関東地方北部を中心に,長野県や東北地方で記録的に遅い霜を観測した。この降霜のため,各県で桑,野菜,たばこ等に大きな被害が生じ,特に,群馬県と栃木県の被害は大きかった。
6月下旬から7月にかけて梅雨前線の活動が活発になり,各地方で大雨が降った。6月25日から30日にかけて,九州北部と中国地方で日雨量が連日100ミリメートル以上となり,総雨量は多い所で600ミリメートルを超えた。また,7月2日から4日にかけては北陸,中国,九州北部で,5日から7日にかけては東北北部と北海道南部及び九州北部と中国西部で,それぞれ日雨量が100ミリメートル以上の大雨が降った。これらの大雨のため,浸水,道路の損壊,鉄道の不通,山崩れ,がけ崩れによる死者等の被害が続いた。その後,7月9日から15日にかけては,日本海から東北地方にかけて前線が停滞し,また,16日から22日にかけては,日本は太平洋高気圧の影響下に入り,東北北部の17日を最後に梅雨が明けたが,北からの寒気の流入が続いた。このため,全国的に不安定な大気の状態が続いて,各地で大雨,落雷,突風,ひょう等による被害が出た。
台風は,平年より多い29個(暦年)が発生し,そのうち,第5号,第10号,第15号の3個が上陸した。第5号は,6月22日夜に長崎県北部に上陸して,“弱い熱帯低気圧”となった後,日本海を東進した低気圧と前線に影響して,東北地方と新潟県に大雨を降らせて水害をもたらした。第10号は,7月31日に宮崎県に上陸して九州南部に暴風雨による被害をもたらしたほか,関東地方以西の太平洋側にも局地的な大雨を降らせて水害をもたらした。
第15号は,8月23日早朝に千葉県南部に上陸した後,勢力が衰えずに速さを増しながら関東地方東部を北に進み,東北地方と北海道の渡島半島を縦断した。そして,同日21時に稚内の北西海上で温帯低気圧となった。21日朝から紀伊半島で降り始めた局地的な強い雨は,台風の本州南岸接近と上陸に伴って急速に北へ広がり,東日本と北日本では22日から23日にかけて大雨となった。日雨量は,22日に群馬県の榛名で418ミリメートル,青森県むつで163ミリメートル,23日に札幌で207ミリメートル等,いずれも観測開始以来第1位の記録となった。この大雨で東日本から北日本にかけての広い範囲で大河川の増水や洪水が起こり,24日未明には,利根川支流の小貝川の堤防が決壊して,多くの家が水につかり,多数の住民が避難した。最大風速は沿岸部で秒速20メートルを超え,最大瞬間風速は東北地方と北海道で秒速30メートルを超えた所が多かった。苫小牧では,23日午後に最大風速秒速27.7メートルと最大瞬間風速秒速386メートルのいずれも南東の風を観測し,それぞれ観測開始以来第1位の記録となったのを始め,ほかでも上位の記録を更新した所が多かった。この台風第15号による被害は西日本の一部を含む21都道府県に及び,秋田県八郎湖で漁船が転覆して,10人が死亡する等,死者・行方不明43人を始め,建物,耕地,公共土木施設等の被害も大きかった。
これらの上陸した台風のほかに,日本に接近した台風により沖縄,伊豆諸島,関東南部及び北海道で暴風や大雨の被害があった。
北海道と東北地方では,8月初めから10月末までの間,特に著しい低湿は出現しなかったが,長期間にわたって低温傾向が続いた。また,9月29日に北海道や東北北部の山々で初冠雪を,30日に帯広等で初霜と初氷をそれぞれ観測した。更に,10月23日には,北海道で平年より10日前後も早い初雪が降った。これらの低温傾向に台風第12号,第15号及び第18号の大雨による影響も加わって,東北地方と北海道では,前年の冷害に続いて農作物が不作となり,被害額は約2,622億円に達した。
西日本の各地では,11月上旬に初霜と初氷を観測する等,冬の訪れが早かった。12月1日から2日にかけて関東地方の平野部を除いて,北海道から九州までの広い範囲で雪が降り,西日本では初雪となった所が多かった。特に,1日には,鹿児島県枕崎で観測開始以来最も早い初雪(平年より40日早い)が降り,3センチメートルの積雪となった。その後,2月にかけて日本の上空に数回寒気が流入したが,いずれも長続きせず,1日の降雪量が1メートルを超えるような大雪は比較的少なく,特に,北陸地方の雪は,例年に比べて少ない方だった。
なお,昭和57年度に起こった顕著な気象現象をあげると,次のとおりである。
(1) 4月には,日本付近に強い寒気が雨下し,九州から東北地方南部にかけての広い範囲で数回にわたって降霜があった。特に,4月10日,11日及び19日には,九州で最低気温が平年より8℃以上も低い所もあり,九州各県で農作物の被害が大きかった。
(2) 6月26日から27日にかけて,台風第5号が日本の南海上を北上し,三陸沖を通過した。このため,27日午後に三陸沖で漁船2隻が遭難し,1人が死亡,1人が行方不明となった。
(3) 7月中旬から下旬にかけて,梅雨前線の活動が活発になり,九州を中心に断続的に大雨が降った。特に,7月23日には,長崎市で19時から22時までの3時間に315ミリメートルの豪雨があり,がけ崩れ等により多数の死者が出た。これらの大雨に伴う災害は,長崎県粒中心に九州各県と山口,広島両県にも及び,死著・行方不明345人,家屋の全壊や半壊800棟余り等,甚大な被害が出た。
気象庁は,この7月23日から25日にかけての大雨を「昭和57年7月豪雨」と命名した。
(4) 8月2日0時ごろ,大型で並の強さの台風第10号が,愛知県渥美半島西部に上陸し,同日早朝に日本海へ抜けた。続いて8月2日から3日にかげて,低気圧が日本の南岸沿いに東北東進した。この台風と低気圧及び関東の南海上にあった梅雨前線のため,7月31日から8月3日にかけて,東北南部から中国東部及び四国東部にかけての地方では,日雨量100ミリメートル以上の大雨が降り,特に,近畿地方と東海地方の総雨量は,多い所で800ミリメートルを超えた。このため,各地でがけ崩れ等が発生し,死者・行方不明89人,家屋の損壊・流失703棟等,大きな被害が出た。
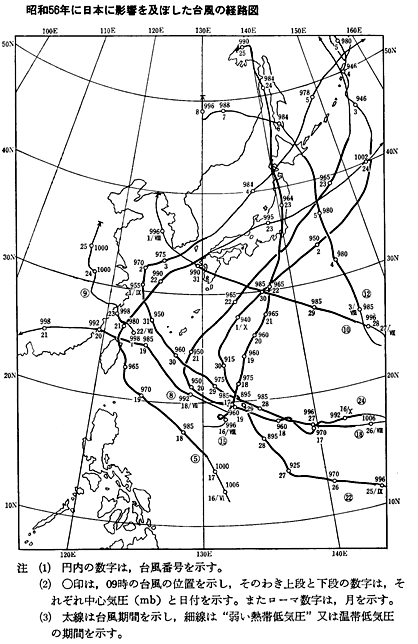
(5) 8月10日から13日にかげて,台風第11号が東シナ海西部を北上した。九州東部では,12日から13日にかけて官崎県を中心に大雨が降り,総雨量は多い所で400ミリメートルを超えた。宮崎県では山崩れ,がけ崩れ等により7人が死亡した。
(6) 8月27日,宮崎県都井岬付近に台風第13号が上陸し,九州東部と山口県を縦断した。
(7) 9月12日,静岡県御前崎付近に台風第18号が上陸し,関東・東北地方を縦断した。東海地方を中心に雨量が多く,所々で600ミリメートルを超えた。被害は,静岡県を中心に27都道府県に及び,死者・行方不明34人等となった。
(8) 9月25日,愛媛県宇和島市付近に台風第19号が上陸し,中国地方西部を縦断した。
|