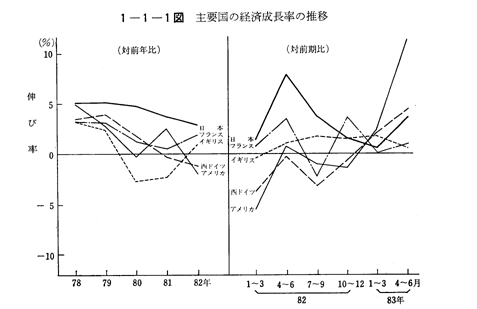|
1 世界経済の概況
(世界経済は3年連続の景気停滞)
1982年の世界経済をみると,主要先進国の多くは第2次石油危機以降3年連続の景気停滞となり,物価上昇率は総じて低下したものの失業問題は極めて深刻化することとなった 〔1−1−1図〕。一方,発展途上国でも世界経済の長期にわたる停滞の影響を受け,石油輸出国の経常収支は70年以来初めて赤字となり,非産油国経済は戦後最低の成長にとどまった。
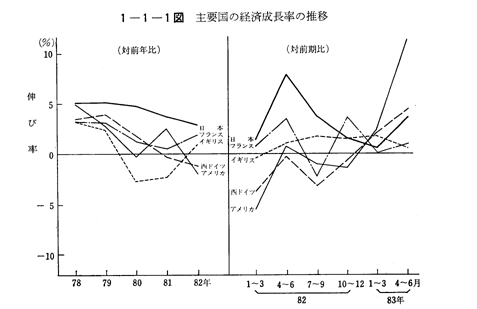
このような世界経済の長期停滞の最大の原因は,世界的高金利の長期にわたる継続であると考えられる。米国におけるインフレ抑制を目的とした厳しい金融引締め政策により出現した高金利は第2次石油危機以降各国がとった引締め政策とあいまって,労働生産性の伸びの鈍化,財政の硬直化,貿易摩擦等の問題を抱えている各国経済に大きなデフレ効果をもたらした。また,西欧諸国が自国通貨価値の下落,物価上昇等への懸念から,金融緩和政策をとることを困難にする一因となった。さらに,先進国向けの輸出の減少,債務利払い額の増大等を通じて発展途上国の債務累積問題にも大きな影響を及ぼした。
主要先進国の経済動向をみると,米国では,高金利の影響を受け,民間住宅投資は激しく落ち込み,設備投資も停滞した。また,輸出もドルの独歩高の影響等を受け減退するなど,ほぼ年間を通じて景気は停滞した。西欧では,英国で年央以降個人消費,住宅投資の持直しを背景に緩やかな景気回復過程にあるものの,西独では個人消費と輸出の減少によりほぼ年間を通じて景気停滞が続いた。フランスでは,82年前半まで積極的景気拡大政策がとられたものの,インフレの高進など経済に悪影響を及ぼしたため,82年央以降緊縮政策への転換を余儀なくされた。
このような状況の中で,財政面では各国とも緊縮政策を持続しつつも,金融面では年後半以降米国で景気,雇用等に配慮した緩和気味の政策へと転換が図られ,この結果,西欧諸国でも年央以降金利引下げの動きが広まった。
(83年に入り景気回復の兆し)
83年に入ると,フランス,イタリア等では依然景気停滞が続いているものの,米国,西独,英国等では住宅投資,個人消費の増加を中心とした景気回復の動きがみられ,また,3月には原油価格が引き下げられるなど世界景気にも明るい動きが少しずつ現われてきた。しかし,米国では金融緩和政策をとったにもかかわらず,財政赤字増大等の影響により,金利の下げ止まり傾向がみられ,米国以外の主要先進国でも巨額の財政赤字等の構造的諸問題を抱えるところが多い。また貿易面でも,近年強まっている保護貿易主義の動き等を考え合わせると,景気回復の持続性については懸念材料が少なくないのが現状である。
|