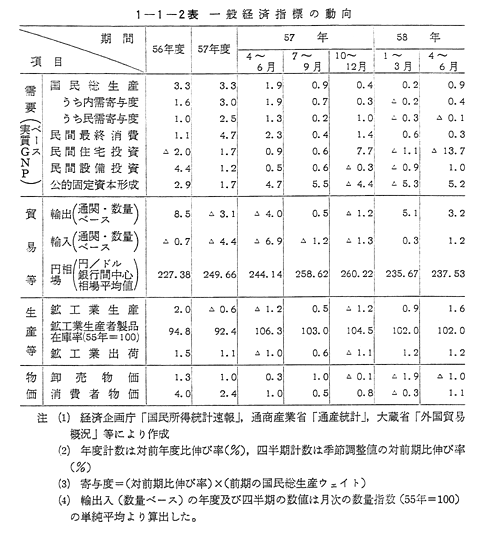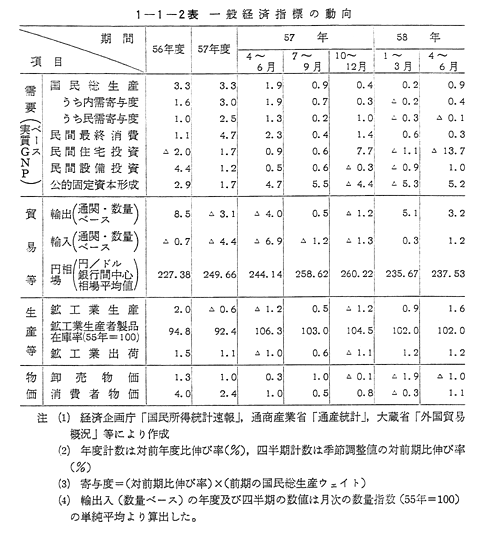|
2 日本経済の概況
(実質経済成長率は3.3%)
昭和57年度の我が国経済は,第2次石油危機後の調整過程から抜け出した後,物価の安定等を背景に,民間消費支出の緩やかな増大を中心として国内需要は回復の方向を示した。しかし56年度後半以降の世界景気の停滞に伴って4年ぶりに輸出が減少し,景気回復は緩慢なものにとどまり,実質経済成長率は56年度に引続き3.3%となった 〔1−1−2表〕。
(消費は物価安定を背景に堅調な伸び)
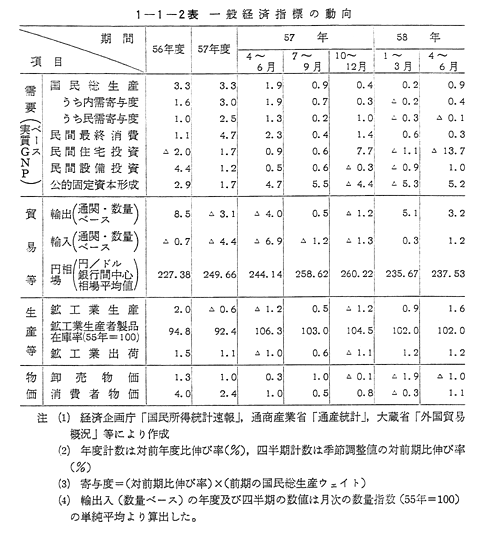
内需をみると,実質GNPの過半を占める民間最終消費(GNPベース,実質)は,年度後半にはやや伸びが弱まったものの,対前年度比4.7%増と堅調な伸びを示した。これは,物価の安定を背景として実質可処分所得が3年ぶりに増加したこと,消費性向が総じて高水準で推移したこと等が主な原因である。
民間住宅投資(GNPベース,実質)は,過去3年間の減少から1.7%の増加に転じたがその伸びは弱いものであった。これを新設住宅着工戸数でみると,対前年度比1.3%増の115万7,000戸と5年ぶりの増加となった。
民間設備投資(GNPベース,実質)は,前年度比で55年度7.7%増,56年度4.4%増のあと,57年度は上期まで増加が続いたものの下期には減少に転じ,年度平均では1・2%増と低い伸びにとどまった。これは,中小企業の設備投資の停滞が続くなかで,堅調に推移してきた大企業の設備投資にも頭打ちの気配が現われたためである。この背景としては,第1に大企業を中心とした技術革新のための大型投資が一巡しつつあること,第2に稼動率低下により設備の過剰感が高まっていること等が考えられる。
公共投資は,上期については前倒し契約が実施されたため,民間需要が回復力を欠く中で景気の下支え効果を発揮した。また,下期に入ると2兆円強の公共投資等の追加が決定された。なお,公的固定資本形成は57年度全体では対前年度比1.7%増であった。
(輸出は減少,輸入も3年連続の減少)
次に輸出入をみると,55年度から56年度上期まで大幅な増加を続けた輸出は,世界景気停滞の影響を受け56年度下期以降減少に転じ,円安傾向が進んだにもかかわらず,対前年度比3.1%減(通関,数量ベース)となった。しかし,58年1〜3月期に入ると,米国を中心とする世界景気の回復の兆し等もあり,輸出は持ち直す気配が出てきた。
一方,55年度以来減少を続けている輸入(通関,数量ベース)は,主に国内生産活動の停滞及び円安の影響により,57年度も4.4%減と3年連続の減少となった。
生産面では,輸出減少の影響を受けた機械等の加工型産業で生産が停滞し,この影響が従来から不振であった鉄鋼等の素材型産業にも次第に波及したため,加工,素材型産業を問わず多くの産業で生産調整が行われた。このため57年夏以降鉱工業生産は前年を下回る水準で推移し,年度全体では対前年度比0.6%減と減少に転じた。
なお,58年度に入ってからの我が国経済をみると,米国を中心とした世界経済の回復に伴って,輸出は増加基調にあり,在庫調整もほぼ一巡し,生産は増加を続けている。しかし,個人消費の伸びは緩やかであり,大企業では設備投資水準は高いものの弱含みとなっており,中小企業では停滞が続いているなど国内需要は盛り上がりを欠くものとなっている。
|