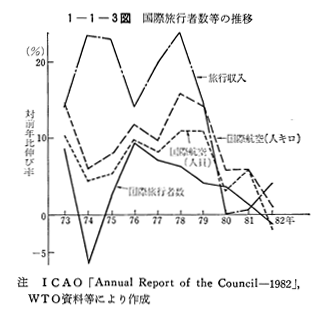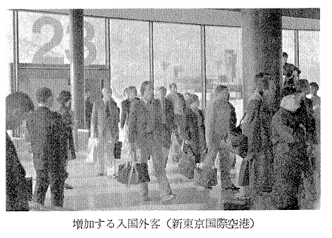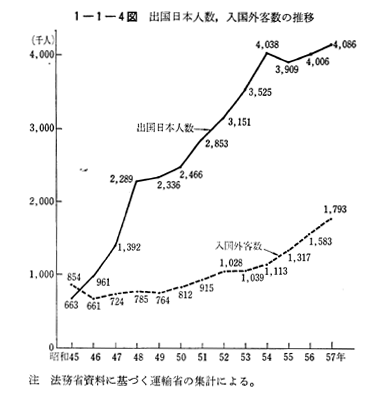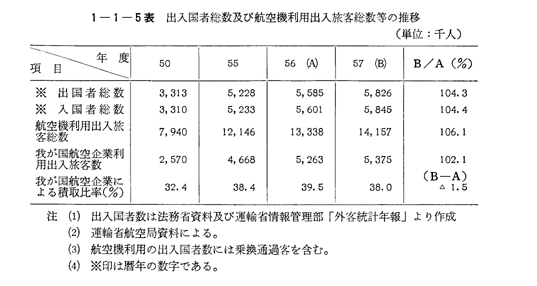|
1 旅客輸送
(国際旅行者は8年ぶりに減少)
1982年の国際旅行者数は,世界観光機関(WTO)の推計によれば,到着数で2億7,990万人,対前年比1.3%減と第1次石油危機の影響を受けた74年以来8年ぶりに前年水準を下回った 〔1-1-3図〕。これは,世界経済が第2次石油危機以降の不況局面から脱することができず3年連続の長期低迷を続けたことによるものと考えられる。しかし,このような厳しい環境にあっても,旅行収入は999億2,500万ドル,対前年比4.1%増となっている。
旅行者の動向を地域別にみると,東アジア・太平洋及び南アジア地域で前年水準を上回ったものの,アフリカ及びアメリカ地域の落ち込みが目立っている。
(世界の国際航空輸送は人員で減少,人キロで増加)
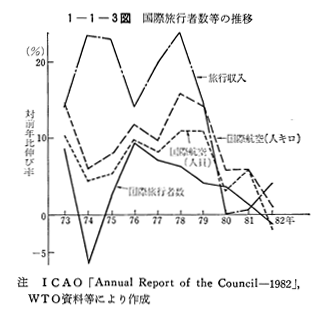
国際航空の動き(輸送人員ベース)をみると,国際民間航空機関(ICAO)の統計によれば,60年代,70年代とも国際旅行者数の伸び率を上回る高い伸びを示していたが,82年は,1億7,000万人,対前年比2.0%減となった。また,輸送人キロは,4,990億人キロ,同1.0%増であった。
(我が国への入国外客数は対前年比13.3%増)
我が国をめぐる国際旅行の動向をみると,近年における入国外客数は,昭和46年と49年を除き順調に増加していたが,53年は円高を反映して1,0%増と伸び悩んだ。しかし,その後円が比較的安値で推移したこと,世界的な物価上昇の中にあって我が国の物価上昇率が諸外国に比べて低かったことにより,訪日旅行費用に割安感があったこと,台湾が54年1月から観光目的の海外渡航を自由化したことなどから,訪日客が増大し,56年は対前年比20.2%増,57年は179万3,000人,同13.3%増となった 〔1-1-4図〕。
州別にみると,アジア州が89万人(対前年比15.0%増)と全体の50%を占め,次いで,北アメリカ州47万人(同12.7%増),ヨーロッパ州33万人(同10.1%増)等となっている。このうち,米国が41万人(対前年比16.3%増)と最も多く,次いで台湾35万人(同4.4%増),韓国19万人(同29.1%増),英国15万人(同25.7%増)等となっている。
(出国日本人数は対前年比2.0%増)
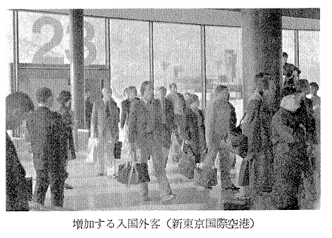
一方,出国日本人数は,55年に景気の低迷,勤労者世帯の実質可処分所得の減少などから39年の海外渡航自由化以来初めて減少したが,57年は過去最高の408万6,000人,対前年比2.0%増となった 〔1-1-4図〕。
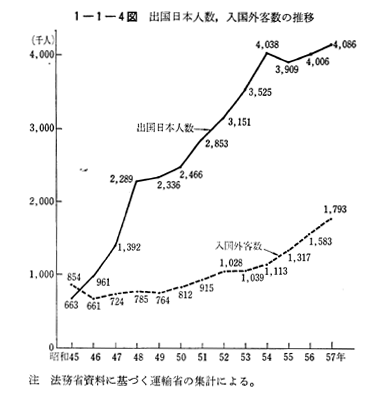
旅行目的別では,観光目的の海外旅行が全体の83.0%を占め,次いで業務等13.8%,その他3.2%となっており,この比率はここ数年あまり変化がみられない。
海外旅行者の旅行先を受入れ地の統計によりみると,海外旅行先は,台湾,ハワイ,香港などアジア・太平洋地域が主流である。同地域の中でも,シンガポール(対前年比6.7%増),タイ(同5.1%増),ハワイ(同4.0%増)などで全体の伸びを上回っている。
これら,海外旅行者の平均旅行日数は,56年8.6日,57年8.7日となっている。
次に,性別構成でみると,男性(277万人)は全体の67.8%,女性(132万人)は32.2%で男性の比率が高い。しかし,過去10年間でみると,男性2.6倍に対して女性は3.9倍の伸びを示し,女性の比率が徐々に高まってきている。
(我が国航空企業による積取比率は38.0%に低下)
このような出入国者数の動きを反映して,57年度の航空機利用出入旅客数は,1,415万7,000人,対前年度比6.1%増(56年度同9.8%増)であった。このうち,我が国航空企業(2社)利用出入旅客数は537万5,000人,対前年度比2.1%増(56年度同12.7%増)と大幅に伸びが鈍化し,我が国航空企業による積取比率は前年度に比べ1.5ポイント減の38.0%となった 〔1-1-5表〕。また,世界の国際航空に占める我が国のシェアは,旅客人キロでICAOの加盟150か国中第4位の5.4%であった。
58年上半期の出入国の動向をみると,入国外客数は91万2,000人,対前年同期比10.8%増であった。一方,出国日本人数は204万4,000人,同1.4%増であった。
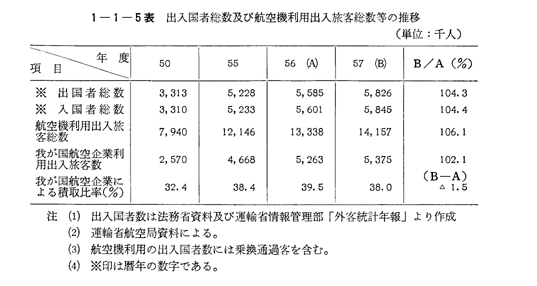
|