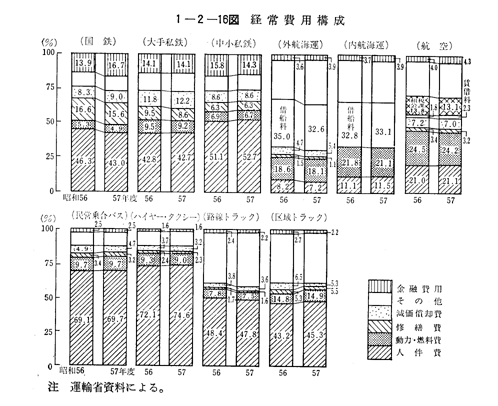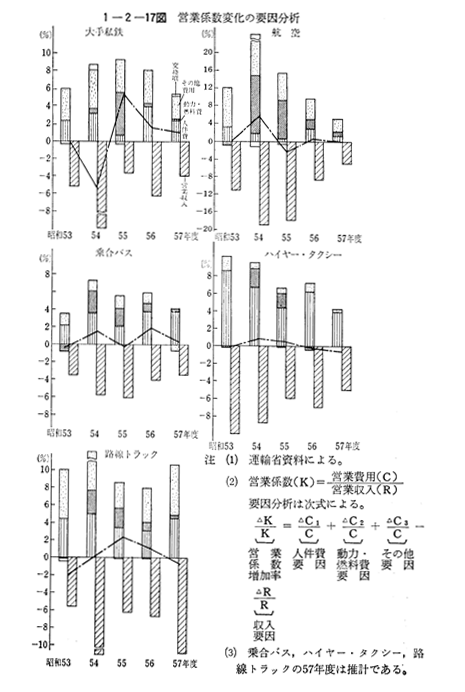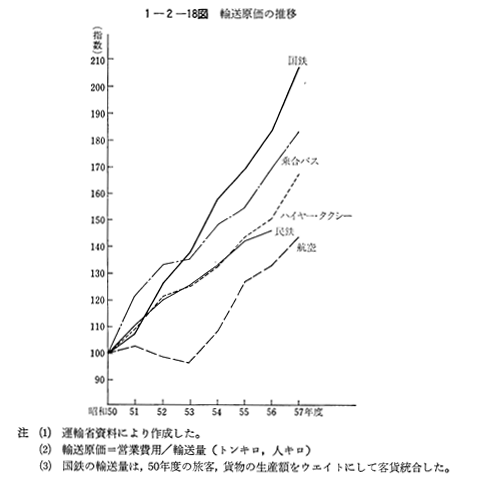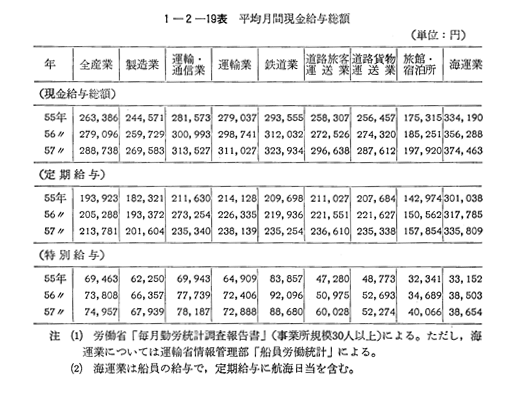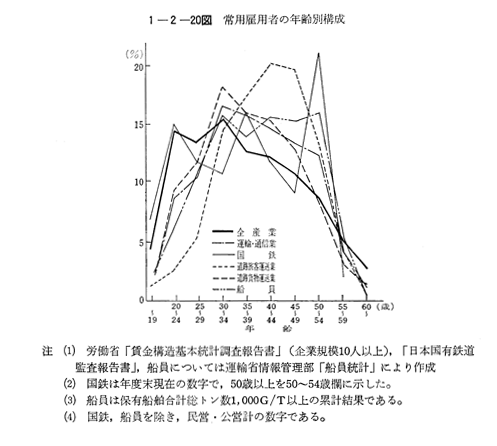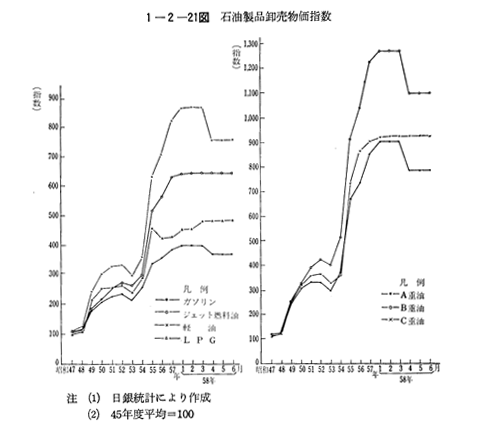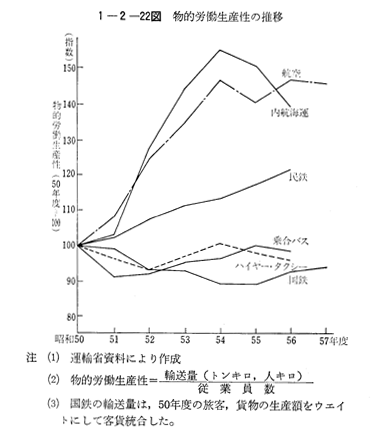|
3 景気停滞期の運輸事業経営
第1次,第2次石油危機を経過して,旅客輸送,貨物輸送のいずれの分野においても総輸送需要の低迷,需要の質的変化という局面を迎えている。
旅客輸送においては,総輸送需要が伸び悩みの傾向を示す中で,自家用乗用車の普及と各種の交通機関の発達により,利用者にとって輸送サービスの選択の幅が広がり,輸送機関間の競争は一段と激しさを増しており,運輸業にとって利用者ニーズに対応したサービスの質的充実がこれまで以上に重要になっている。
また,貨物輸送の分野においても第1章で述べたように産業構造が輸送を生じにくい構造へと変化してきており,総輸送需要が伸び悩む一方で,貨物の小口軽量化が進展しており,これに対応した質の高い輸送サービスが求められるようになっている。
売上げの拡大という観点からいえば,このような利用者ニーズに合致したサービスの提供による需要換起のほかに運賃改定という手段も考えられるが,第1章でもみたように運賃改定には需要の減少を伴うことが多く,運賃改定分の効果が望めないような状況となっており,これまで以上の経営努力が必要となっている。
(1) 運輸事業の費用構成
(ウエイトの高い人件費)
運輸事業の費用構成をみると,一般に人件費の割合が高く(大蔵省)法人企業統計年報」によれば,56年度において全産業11.9%,製造業15.3%に対し,運輸・通信業33.0%(陸運44.7%,水運13.8%)),また,動力・燃料費,減価償却費の割合も高い。
陸上運送業においては,人件費が費用の半ばを占め,特に自動車旅客運送業においては際立ってウエイトが高い。海上運送業や航空運送業では動力・燃料費のウエイトが高くなっている。また,鉄道業については減価償却費や金融費用等のいわゆる資本費の割合が高くなっており,外航海運,内航海運では賃借料(借船料)の割合が高くなっている 〔1−2−16図〕。
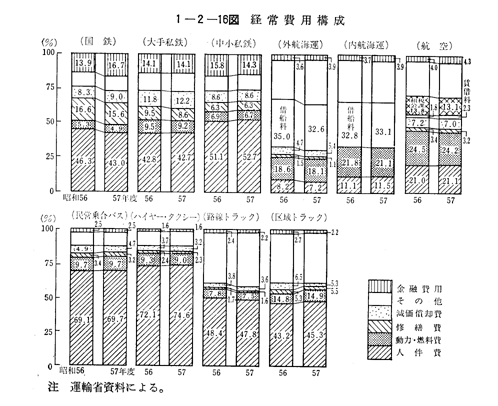
運輸事業における営業係数の変化の要因について分析したものが 〔1−2−17図〕である。これをみると,収入は輸送量の減少等の要因もあり,路線トラックを除き増加幅を縮小させている。また,費用は路線トラックを除き増加幅を減少させている。費用のうち人件費は,55年度において寄与度を低下させたが,概して毎年,営業係数の大きな増加要因となっている。これは,労働市場が下方硬直化しているためであり,今後もこの傾向は続くものと考えられる。また,動力・燃料費は,53年に第1次石油危機後の反動で価格の落ち着きがあったこともあり,一時的に営業係数の低下要因として働いたあと,第2次石油危機に再び大きく営業係数を高める大きな要因となった。しかし,ここ数年は次第に低下してきている。
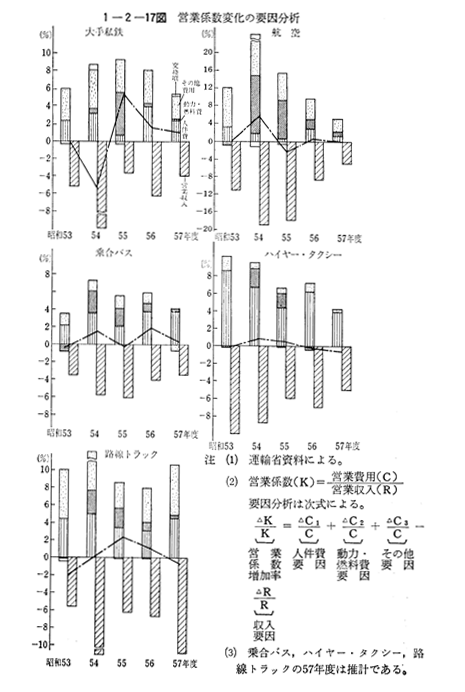
なお,輸送原価の推移をみると, 〔1−2−18図〕のとおり,諸経費の増大により52・53年度の航空を除き全般的に輸送原価は上昇してきた。57年度においては,物価の落ちつきにより諸経費の増大が大きくなかったにもかかわらず輸送量が低迷したため,引き続いて輸送原価は上昇した。
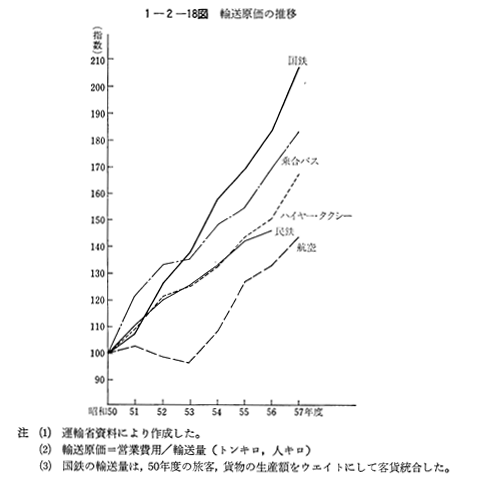
(2) 人件費の動向
(平均を上回った運輸業における賃金上昇)
運輸業の平均月間現金給与総額の伸びは,対前年度比4.1%増と全産業の3.5%増を上回っている。特に,道路旅客運送業は8.8%増と大幅な伸びを示している。額についても運輸業は全産業平均を7.7%上回る31万1,027円となっている。船員の賃金を海運業についてみると57年の平均月間現金給与総額は37万4,463円で,対前年比5・1%増であった 〔1−2−19表〕。これを部門別にみると外航で45万4,958円(対前年比5.0%増),内航で33万1,271円(同5.7%増)となっており,定期給与ではそれぞれ40万5,342円(同7.7%増),29万8,122円(同4.9%増)であった。
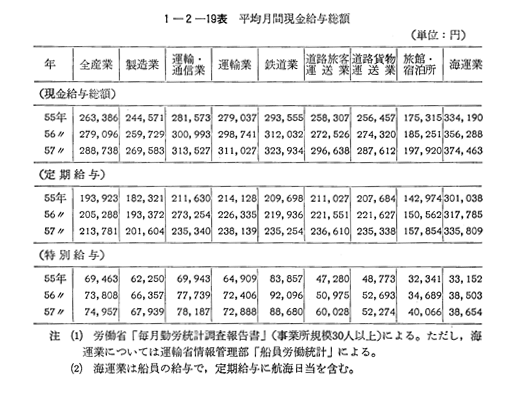
58年春の労働協約改定交渉において妥結をみた賃金の上昇率は,外航,近海,内航,大型カーフェリー及び漁業大型船の各業界とも3.25〜3.90%であった。
(高齢化する運輸業従事者)
また,57年6月現在の運輸・通信業従事者の平均年齢は,全産業平均を2.0歳上回る39.1歳で5年前に比べて1.6歳上昇し,労働者の高齢化が進んでいる。
業種別には,国鉄は,52年の40.8歳に対し,57年には38.7歳となり,平均年齢の低下傾向がみられる。一方,道路旅客運送業,道路貨物運送業では上昇している。船員については,50歳以上層が22.3%(前年度19.1%)に増えたが,40歳未満層では45.2%(同50.9%)となり減少した 〔1−2−20図〕。
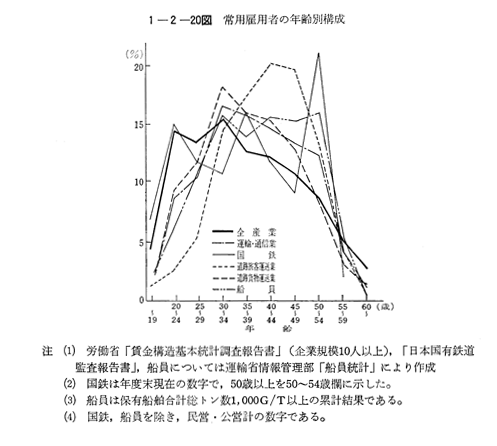
労働者数をみると,国鉄は38万7,000人と対前年比3.7%減,道路貨物運送業は72万9,060人と同14.8%増,道路旅客運送業は58万5,400人と同4.0%増となっている。船員についてみると,57年10月現在の船員数は22万5,000人で,前年に比べて6,000人減少した。これを部門別にみると,外航3万6,700人,内航6万2,400人,漁船10万6,800人,その他1万9,100人で前年に比べて外航700人,内航2,300人,漁船4,700人それぞれ減少し,その他は1,600人増加した。減少の理由は,外航については保有船舶数の減少,1船当たりの乗組員数の減少等,内航については内航海運業界の不況による保有船舶数の減少等,漁船については国際的な漁業規則の強化等による減船等を反映しているものと考えられ,その他の増加の理由は,保有船舶数の増加により,船員数も増加したものと考えられる。
(3) 動力・燃料費の動向
(今後の動向が注目される燃料)
運輸部門で使用している燃料油価格の動向をみると 〔1−2−21図〕のように,第1次,第2次石油危機を通じて価格は大きく上昇し,その後も高水準の価格が維持されており,経営の大きな圧迫要因となってきた。このような中で,各運輸事業においては,省エネ型機材の導入,輸送効率の向上等各種の省エネルギー対策を講じ,その使用量を抑制する等動力・燃料費の縮減に努めてきた。
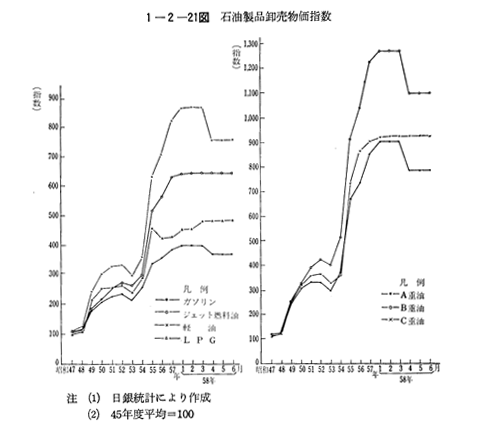
ところが,最近,世界的な不況,省エネルギー対策の進展などにより石油需給が緩和状態となり原油価格が下落した。その結果,石油製品卸売物価はA,B重油等を中心に値下りしている。
このような動きが運輸事業の動力・燃料費に与える影響をみると,まず鉄道部門では,エネルギー源を電力中心としており,電気料金の変動がない限り費用への影響はほとんどないといえる。タクシー等LPGを主に使用する事業では原油の減産等の影響によりLPGは逆に値上りをしており,費用はかえって増加する状況にある。トラック,バス,海運等他の運輸部門では,軽油,重油等は,58年6月の時点以降57年平均に比べ平均6%程度の値下りとなったが,中東情勢が不安定であること等を考慮すれば,その価格の先行きは不透明であり,動力・燃料費をどれだけ節減できるかを見極めるためには燃料価格の今後の動向に着目する必要がある。
(依然として必要な省エネ努力)
発電,製造業における石油需要の減少,非OPEC諸国の原油供給能力の増大等により,近時石油需給は緩和してきているが,流動的な中東情勢等を考慮すれば,石油を中心とするエネルギー需給は依然不安定である。また輸入原油の重質化と石油製品需要の軽質化が進展しており,いわゆる,“C重油ネック”(C重油の需要に応じて原油処理を行えば,軽油,ガソリン等中間留分・揮発油留分の供給に不足をきたす。)が生じつつあり,このまま推移すれば,将来,石油製品に需給ギャップが生じ,中間留分・揮発油留分の供給不足や価格の高騰が起ることが予想される。中間留分・揮発留分の需要の多くは,国民生活に直結したバス,トラック,航空機等の輸送機関で使用されているので,このような需給ギャップが顕在化すれば,輸送の確保に支障を来たす等重大な社会問題となることが懸念される。したがって,運輸部門においては,引き続き省エネルギー対策等を推し進めることが肝要である。
(4) 生産性の向上
(高まる生産性向上努力への要請)
以上のように費用の単価の低下を期待することは困難であり,総経費の縮減をするためには作業の機械化,人員の縮減等の生産性の向上策を実施することが必要となってきている。
最近の運輸事業の労働生産性について従業員1人当たりの輸送量(物的労働生産性)の推移でみてみると, 〔1−2−22図〕のとおり,国鉄は従業員の減少が寄与して向上しているのに対し,乗合バスは輸送量が伸び悩んでいるうえワンマン化等による合理化が一巡したため,また,航空は機材の大型化が一巡したため,いずれも横ばい気味であるなど,運輸事業の物的労働生産性は近年総じて向上がみられない。一方,今日のコンピュータ及び通信技術の著しい発達やいわゆるメカトロニクス技術の進歩により,運輸事業においても,車両の効率的配車や適切な労務管理が可能となる等その経営の近代化を大きく進展させ得る状況となっている。
したがって,運輸事業においても,このような新技術を積極的に導入していくことが肝要である。
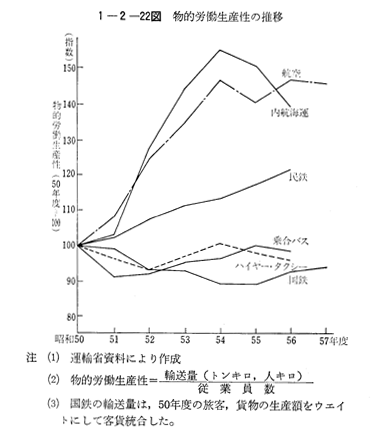
|