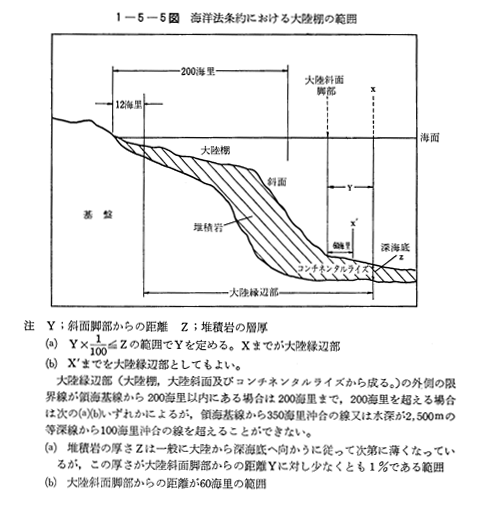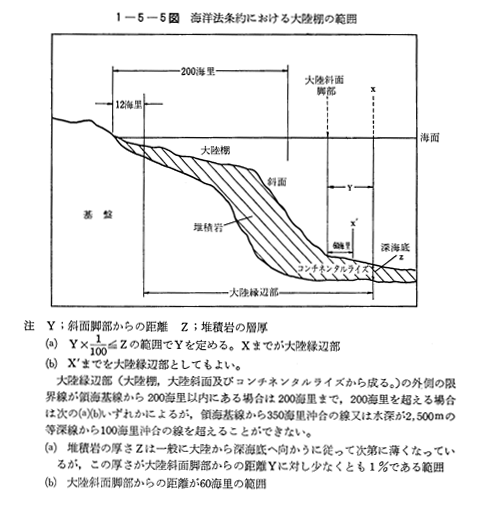|
1 海洋法条約に対応した国内法制の整備及び管轄海域の確定
(1) 国内法制の整備等
(海洋法条約の署名)
第1次国連海洋法会議(昭和33年)において採択された「領海及び接続水域に関する条約」等のいわゆるジュネーブ4条約を基本的枠組みとして形成されてきた海洋秩序を根本的に見直し,新たに海洋秩序の骨格となる海洋に関する包括的な条約を作成するための第3次国連海洋法会議は,57年4月,「海洋法に関する国際連合条約」(以下「海洋法条約」という。)を採択し,同年12月の最終議定書署名会議(モンテゴ・ベイ(ジャマイカ)において開催)をもって約10年にわたる討議の幕を閉じた。
我が国は,同署名会議において同条約最終議定書の署名を行い,また,58年2月,同条約が,海洋国家としての我が国の長期的な国益に合致し,かつ,国際社会全体の利益に沿うものであるとの判断から同条約の署名を行った。
なお,同条約は,60か国が批准又は加入した後12か月を経過した時点で発効することとされており,58年8月31日現在の署名数及び批准数はそれぞれ131及び9である。
(国内法制の整備等)
運輸省は,海運,船舶,船員,港湾,海上保安,海洋汚染防止,海洋調査等海洋に係る多くの行政分野を所管しており,従来から,船舶航行及び人命の安全確保のためのいわゆるSOLAS条約,STCW条約等や海洋の汚染防止のためのいわゆるMARPOL73/78条約等の個別的な条約に対応し,船舶安全法,船員法,船舶職員法,海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等国内法令の整備を図ってきたところである。海洋法条約は,海洋秩序に関する包括的な条約であり,新たに盛り込まれた内容として沿岸国が200海里排他的経済水域(以下「200海里水域」という。)における天然資源の探査,開発,保存,管理その他経済開発に関する主権的権利と,海洋科学調査,海洋環境保護に関する管轄権を有すること及び大陸棚の海底やその下に存在する天然資源を探査・開発する主権的権利を有すること等を規定しており,同条約の批准に備えて上記関係所管法令の見直し,行政運営体制の整備等を積極的に進めていくこととしている。
(2) 管轄海域の確定
(急がれる管轄海域の確定)
海洋法条約を締結した場合に我が国の管轄海域となる200海里水域及び大陸棚において我が国の権益を確保するためには,まず,同海域の範囲を確定しなければならない。このため大陸棚や沿岸海域に関する精密な科学調査を急ぐとともに,本土及び離島の正確な位置を確定し,領海,200海里水域,大陸棚の範囲を海図に表示することが必要である。
特に大陸棚については,現行の大陸棚に関する条約によれば,その範囲は水深200メートルまで又は開発可能水深までの海底及びその下としているのに対し,海洋法条約によれば,原則として200海里まで,また,条約が我が国に対し効力を生じたときから10年以内に,条約に基づき設立される「大陸棚の限界に関する委員会」に科学的技術的データを提出して大陸縁辺部であることを証明すれば,更に200海里を超えて沿岸国の大陸棚とすることができることとされており,そのための精密な海洋調査を行うことが急がれている 〔1−5−5図〕。
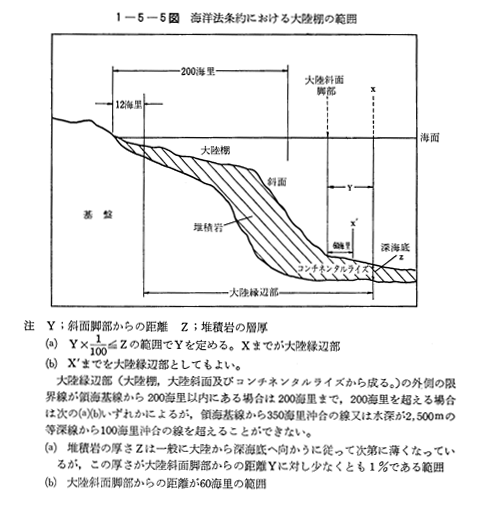
(整備される海洋調査体制)
海上保安庁では,我が国が主権的権利と管轄権を行使することとなる広大な海洋の調査及びその利用を促進するための情報の整備を迅速・的確に実施するため,近代化・効率化を図っており,58年秋に最新鋭測量船「拓洋」を就役させ,大陸縁辺部の精密海洋調査に着手した。また,我が国の管轄海域確定の基準となる本土及び島しょにおける精度の高い測地を行うため,レーザー測距装置による測地衛星ラジオスの観測を行っており,さらに国産測地衛星の観測による測地の精度向上に取り組もうとしている。
また,これらの業務を効率的に行うため,58年4月海上保安庁水路部の組織を企画体制の強化,総合的調査体制の整備・強化,海洋情報の総合的管理・提供体制の強化の観点から,抜本的に再編成した。
|