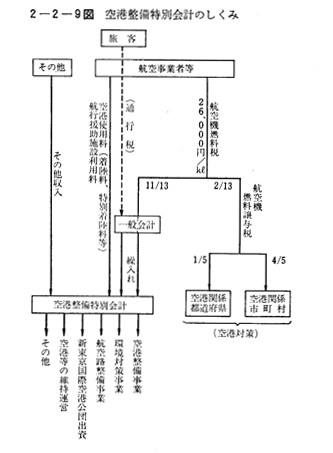|
1 空港整備特別会計の概観
(受益者負担の原則と空整特会)
空港整備事業については,前述のように昭和42年度以降空港整備五箇年計画を策定し,計画的かつ強力に推進してきており,45年度には空港整備特別会計(以下「空整特会」という。)が創設されて一般会計とは別個に経理されることとなった。
空整特会は,空港整備事業,環境対策事業,航空路整備事業等広義の空港整備事業に要する費用のほか,空港等の維持運営に要する費用を主な歳出とし,空港使用料収入(着陸料,特別着陸料,航行援助施設利用料等),一般会計からの繰入れ金等を主な歳入としている 〔2−2−9図〕。
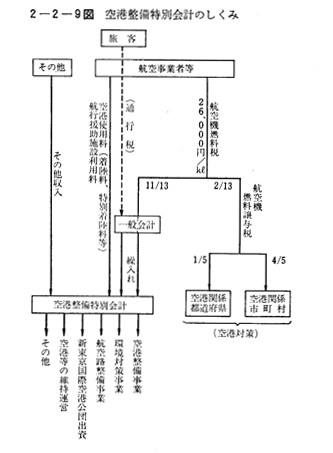
このうち一般会計からの繰入れ金としては,航空会社が負担する航空機燃料税の税収見込み額の13分の11が空港整備特別会計法附則により空整特会の財源として一般会計から繰り入れられていること等空整特会は実質的にはほぼ100%受益者負担によりその財源を賄っているといえる。
このように空整特会が受益者負担の原則に拠っているのは,空港整備事業が他の社会資本整備に比してその利用者の特定が比較的容易であると考えられたためと思われるが,航空需要の急激な増大やこれに伴う就航機材の高速化,大型化による生産性の一層の向上等にも支えられてきたものと考えられる。
空港整備財源の充実強化を図るためにこれまでとられてきた措置の沿革を概観すると,次のとおりである。
空港の諸施設利用の対価として航空機の着陸1回ごとに徴収する着陸料は,古く27年に創設されているが,数度の改定を経て空整特会が創設された45年度には国内線50%,国際線20%の引上げが実施され,その後も52年度及び55年度に国内線について引上げが行われている。
46年度には,第2次空港整備五箇年計画の策定に当たって,従来国が空港及び航空路において無償で提供してきた管制,通信業務等航行援助サービスにも相応の対価を徴収することとして航行援助施設利用料が新設され,52年度には国内線100%,国際線50%の引上げが実施される等数度にわたり財源の強化が図られた。
特別着陸料は,空港周辺環境対策事業費の増大に伴い,これに要する費用に充足するため50年度に創設されたもので,ジェット機の着陸1回ごとに課される空港使用料であるが,53年度には100%の引上げが実施されている。
以上の空港使用料のほか,47年度には航空機燃料の免税措置の期限の到来に伴い,航空機燃料税が創設され,その後3度の改定を経て,当初の1キロリットル当たり5,200円から54年度以降は1キロリットル当たり2万6,000円の税額となっている。同税は,前述のようにその税収見込み額の13分の11が一般会計を経て空整特会へ繰入れられる(残り13分の2は航空機騒音対策等の空港対策費に充当するため,空港関係地方公共団体に航空機燃料譲与税として譲与される。)こととされている。
以上のように,空港整備の財源については,主として空港整備五箇年計画の策定と歩調を合わせながらその充実強化が図られてきた。
|