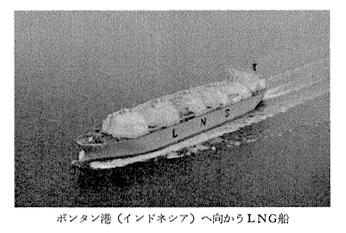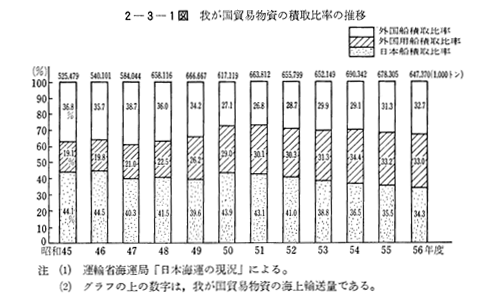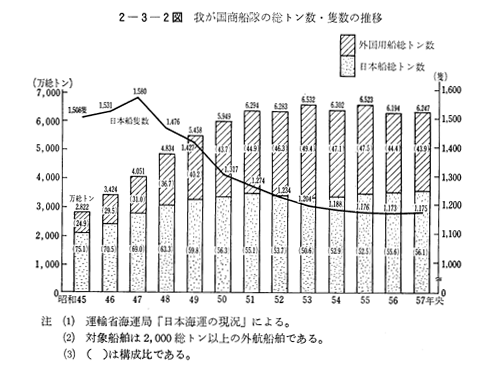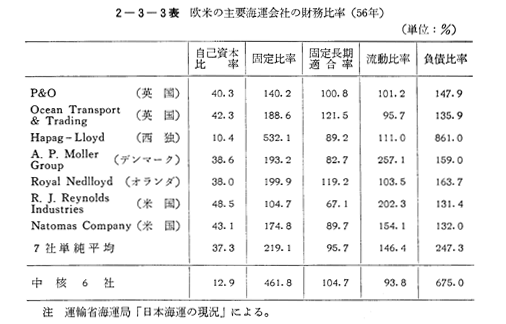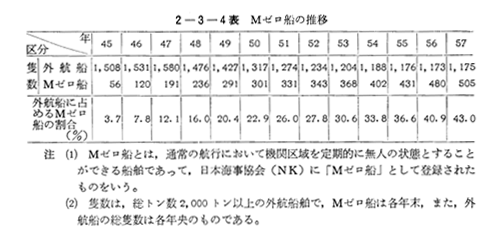|
1 外航海運
(1) 外航海運における南北問題
ア 発展途上国政府の海運への介入
(台頭する発展途上国の国旗差別政策)
国際海運秩序は,従来から,先進海運国の主導の下に,海運活動に対する政府の介入を最小限にとどめるべきであるとする「海運自由の原則」の下に形成されてきた。しかし,近年,大部分の発展途上国は,自国産業の振興や国際収支の改善を図るため,自国商船隊の整備に積極的に努めている。その一環として,これら発展途上国政府は,政府自らが海運活動に介入し,一方的に自国船優遇措置(いわゆる国旗差別政策)をとっている。
しかし,国旗差別政策は,単に先進国海運の活動を制約するばかりでなく,発展途上国にとってもその荷主が最も適切な海運サービスを選択する自由を制限することとなり,その国の貿易の発展が阻害されることとなるので,発展途上国政府に対して,これを撤廃するよう引き続き説得する必要がある。
イ 国連貿易開発会議(UNCTAD)等における発展途上国の動き
(定期船同盟行動憲章条約の発効と我が国の対応)UNCTADにおいて海運問題が最初に顕在化したのは,定期船の分野であった。過去においては,定期船同盟は閉鎖的なものが多く,発展途上国の海運会社が自国関係航路においてさえも加盟できない場合があるなどの不満をもりた発展途上国が少なからず存在していた。このような状況を背景に,発展途上国から,自国船社の定期船同盟への加入による海運の振興,定期船同盟と自国荷主との協議のルール化等の要望が強まり,発展途上国と先進国の妥協の結果,昭和49年に定期船同盟行動憲章条約が採択された。同条約は,貿易当事国船社の同盟への加入,同盟内での輸送配分の決定,同盟と荷主との協議,紛争解決手続等定期船同盟の行動の準則を定めたものである。同条約は,58年4月に西独及びオランダが先進国として初めてそれぞれ批准及び加入したため,58年10月に発効したが,他のEC諸国及び北欧諸国も締結する方向にある。我が国としては,本条約が前述のような発展途上国政府の海運への介入に対する一定の歯止めともなり新しい定期船海運秩序の形成に資するものであるとの観点から,本条約の採択に際し賛成の立場をとって以来,一貫して本条約に速やかに加入することが望ましいと考えてきており,このため,現在政府部内において鋭意検討を行っている。
(検討進むバルク輸送参入問題)
また,発展途上国は,鉄鉱石,石油類等のいわゆるバルク貨物の輸送への自国商船隊の参入が促進されるような措置を講ずるようUNCTADの場で先進国に迫っている。発展途上国は,バルク貨物輸送において,何らかの参入障壁が存在するため,発展途上国船隊の参入が妨げられているので,発展途上国海運の衡平な輸送シェアを確保するための適当な措置がとられるべきであると主張している。これに対し,先進国は,バルク貨物輸送は自由競争原理に基づいて運営されており,参入障壁は存在せず,また,これが最も効率的であると主張している。ドライバルク貨物輸送を検討するための専門家会合は56年に2回にわたり開催されたが,参入障壁の有無については結論が出ず,両論を併記することとし,発展途上国の商船隊の参入が促進されるよう環境を整備するための7項目の勧告を盛り込んだ報告書を全会一致で採択した。57年に開催されたUNCTAD第10回海運委員会では,専門家会合の報告をもとに,議論が行われ,南北の意見は基本的には対立したままであったが,専門家会合での勧告を盛り込んだ決議が採択され,その成果を2年間見守ることが合意された。また,原油及び石油製品の液体バルクに関しても,同様の検討が行われることとなっており,58年4月に第1回の液体バルクに関する専門家会合が開催された。我が国としても,勧告事項の達成には協力するが,輸送シェアの規制等市場介入を導入することは,国際海運の効率性を阻害し,むしろ,発展途上国の利益にならないということを,先進海運国と一体となって,発展途上国に対して説得していく必要がある。
(大詰めの段階に近づきつつある便宜置籍船問題)
また,最近,南北問題として大きく取り上げられているものに便宜置籍船問題がある。
従来,便宜置籍船問題として国際的に討議されてきたことは,いわゆる便宜置籍船と称せられる船舶に,安全,船員の労働条件等の面で問題のあるものが多いという点であったが,この点については,国際海事機関(IMO),国際労働機関(ILO)等において統一的基準を条約等で設け,その実施を図ることによって解決に努めている。
近年,UNCTADにおいて,発展途上国は,便宜置籍船の存在が発展途上国海運の発展にとって大きな障害となっており,船舶登録要件の強化を国際的に行うことにより,便宜置籍船を排除すべきであると主張している。これに対して先進国は,船舶登録要件は各国独自の判断に委ねられるべきであるとして反論を加え,南北間の討議は平行線をたどってきた。57年12月の第37回国連総会決議に基づき,船舶登録要件に関する国際的合意づくりのための全権会議を59年の早い時期に,そのための準備委員会を58年11月にそれぞれ開催することとなっているが,我が国は,便宜置籍船にしばしばみられる責任関係の不明確性については適切な是正策が講じられるべきであると考えているものの,国際条約等によって船舶所有関係における資本,経営,労働の自由な結び付きを制限することは大きな問題があると考えており,この立場から上記会議に積極的に参加していくこととしている。
ウ 今後の南北問題への対応
発展途上国の商船隊は,資本,技術,経営能力等において,先進国の商船隊との間に大きな格差が存在する場合が多く,発展途上国政府の多くは,自国船を保護するため,市場介入的な海運政策をとってきている。我が国としても,海運における南北問題に関しては,UNCTAD等の場を通じて先進諸国と共同歩調をとりつつ合理的な解決に努めるとともに,発展途上国海運が健全な経済的基盤に立って発展することができるよう,発展途上国との協調を図るための多様な対策を講じていく必要がある。
(2) 海上貨物流動の変化と定期航路の不安定化
最近の我が国海上貨物輸送をめぐる環境には,以下のように産業・貿易構造の変化あるいは国際経済環境の変化に対応して,構造的ともいうべき変化が見られるとともに,定期航路の航路秩序に不安定化の動きが見られ,今後の外航海運業のあり方にも大きな影響を及ぼすものと考えられる。
ア 海上貨物流動の変化
(ア) 経済環境の変化
第1に,経済成長率が鈍化していることである。海上荷動き量のベースとなる我が国及び世界経済の成長率が第1次石油危機以降鈍化しており,今後についても高度成長期のような伸びは期待し難い。
第2に,省資源・省エネルギーの進展が挙げられる。エネルギー,原料価格の上昇に対し,世界的に省資源・省エネルギーが進展した結果,石油等の海上荷動き量が低迷する一方,石炭,LNG等の石油代替エネルギーの輸入が著増している。
第3に,産業構造の高度化,高付加価値化が進行していることである。エネルギーコストの高い基礎素材産業が価格競争力の低下と需要減退により停滞する一方,加工組立型産業,特にエレクトロニクス関連業種は着実に生産を伸ばしてきており,基礎素材産業の停滞は原料輸入の減少を招いている。
(イ) 貿易構造の変化
我が国の輸出構造は,機械・機器が全体の約3分の2を占めており,最近では特にエレクトロニクス関連機器等の高付加価値製品の伸びが大きくなっている。高付加価値製品は運賃負担力があるため,航空輸送のウエイトが高く,その増大が必ずしも海上荷動き量の増大に結び付かない面がある。
一方,輸出の代表品目である鉄鋼,自動車は,欧米での貿易摩擦等により伸び悩み傾向にあり,今後他市場での輸出増に努めるにしても,過去のような伸びは期待しにくい。
(ウ) 国際航空貨物輸送の拡大
我が国の国際航空貨物輸送は,海上輸送量が第1次石油危機以降停滞傾向にあるのに対し,順調に拡大しており,57年の航空貨物の割合(金額ベース)は,輸出で8.2%,輸入で9,7%となっている。品目別には,半導体・集積回路等の高付加価値製品の航空化率が高く,今後も,輸出構造の高度化により,航空適合性の強い品目が増える方向にあるので,経済成長率を上回って伸びていくものと考えられる。
(エ) 極東中進国(地域)の貿易の拡大
一方,極東中進国(地域)(韓国,台湾,香港,シンガポール)の経済力伸長により,極東/米国間の貿易の拡大が見られ,これらの地域の対米輸出は,55年で177億ドルに達し,日本の約60%の水準にまで拡大してきている。最近では家電,鉄鋼等の分野でも日本とのシェア格差を縮小させてきており,このような動きに対応して,今後我が国の輸出構造の高度化,高付加価値化が更に進展するものと思われる。
(オ) 企業活動の国際的展開
我が国企業の海外進出は,56年度の海外直接投資で89億ドルと過去最高の水準に達している。従来は,販売拠点の設立や資源確保型の進出が主体であったが,最近は,貿易摩擦の回避等のため輸出市場国での現地生産活動を行う本格的な海外進出が増加する傾向にある。このような我が国企業活動の国際化に伴い,我が国企業の企業活動をめぐる荷動きは,今後国内よりも国外においてより大きく増加すると考えられる。
イ 定期航路の不安定化
(転機を迎えた定期船海運)
最近,北米太平洋航路,欧州航路等の我が国関係の主要な航路において,過度の運賃引下げ競争が展開されるなど輸送秩序が不安定になっており,定期船同盟が,従来,航路秩序の安定に果たしてきた機能が低下しつつあると考えられるが,この原因としては次の点が指摘される。
(ア) コンテナ化の進展
1960年代後半に入ると世界的にコンテナ化が進展していったが,コンテナ化に伴い輸送サービスの均質化が生じたこと,コンテナ関係設備のリース制が普及したこと等により,在来船時代よりも後発社の新規参入が容易になった。また,輸送サービスの均質化に伴い,コンテナ航路は価格競争に陥り易くなり,さらに,海運企業としてもコスト競争力を高めるために船型の大型化を志向することから,結果的に過剰船腹を生じやすくしている。
(イ) 極東中進国(地域)海運の進出
極東中進国(地域)の海運は,自国経済の成長を背景に発展してきており,北米太平洋航路,欧州航路等の競争の激しい航路において低コストを武器に確たる地位を築きつつある。これら急成長をとげてきた中進国海運企業には,定期船同盟を中心とする既存の海運秩序を離れて活動するものがある。
(ウ) 共産圏海運の進出
ソ連を始めとする東欧圏諸国は,自国関係貨物については自国船によりほぼ独占的に輸送するとともに,外貨獲得をめざして三国間航路においても活発に活動しており,ほとんどの就航航路で特定品目に低い運賃を提示して活発に集貨するなどの盟外船活動を行っている。
一方,中国は多年,外国海運に依存するところ大であったが,近年,一般貨物船を中心に着実に自国海運の育成に努め,特に最近では欧州,北米等の遠洋コンテナ航路にも進出しており,一部大型船を投入して本格的参入を図っている。
(エ) 米国海運政策の影響
米国は,独自の独占禁止政策の一環として他の先進国と異なる独自の定期船海運政策をとっており,定期船同盟をはじめスペースチャーター等各種の協定への積極的な政府介入を行っている。定期船同盟への加入脱退を自由とすることを法的に義務付けているほか,同盟の内部規制及び荷主との関係についても大幅な制約を課している。さらに,現在,審議が進められている新海運法案が成立すれば,同盟内での運賃の単独引下げ,特定荷主への特別サービスの提供等を容認する制度の強制的導入により,定期船同盟の運賃協定としての機能が低下することは免れない。
以上の諸要因からみて,定期船同盟の自律的調整機能のもとに運営されてきた定期船海運は,一つの転機を迎えているといえる。
ウ 海上貨物流動の変化と定期航路の不安定化への対応
(要請される企業行動の多様化)
以上みてきたように,今後,我が国の輸出入貨物の内容が変化するとともに,その量的拡大が鈍化する一方,極東中進国(地域)の経済成長及び我が国企業の海外進出に伴ってこれらに関連する荷動きが増加すると考えられるので,我が国海運企業もこれらの変化に対応し,LNG等石油代替エネルギー輸送分野への積極的進出を図るとともに,合弁による現地法人の設立,三国間輸送への進出等企業行動の多様化を検討する時期に来ているといえよう。
我が国へのLNG輸送については,従来外国船に依存してきたが,日本の船社においても計画造船制度による長期低利の財政資金を活用して,LNG専用船の建造を行い,58年8月より第1船が就航し,日本船もLNG輸送に参入することになった。また,我が国外航海運企業の場合,従来便宜置籍船を利用するため船舶保有会社を海外に設立することはあったが,輸送活動は我が国貿易物資の輸出入にほとんど限定され,海外に本拠を置き,三国間輸送に従事するという意味での海外進出はほとんど行っていないが,このような中で,邦船2社が,56年8月から57年5月にかけて極東/北米という三国間航路の運航を開始したことは,企業行動多様化の一つの現われと見ることができよう。
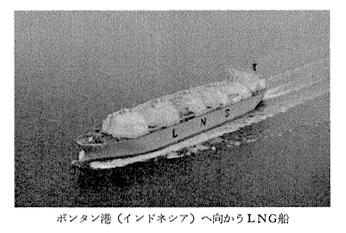
(期待される国際複合輸送)
次に,定期航路の不安定化の動きに対しては,我が国定期船海運が厳しい競争に耐えるようあらゆる面でのコストダウンを図って体質を強化するとともに,荷主のニーズに適時,適切に応えられるよう輸送サービスの向上に努め,国際複合輸送等に積極的に取り組んでいく必要がある。
なお,国営企業としてさまざまな恩典を受けている共産圏海運の活動に対しては,先進海運国の海運企業が商業的基盤に立って競争することは極めて困難であるので,今後著しく航路秩序が乱される場合には,その対策を検討する必要がある。
(3) 海上輸送力の確保
(一定量の日本船確保は不可欠)
四面を海に囲まれ,資源の多くを外国に依存するとともに,工業製品を輸出するという経済構造を有する我が国にとって,安定した海上輸送力を常時確保しておくことは我が国経済の維持,発展のために必要不可欠である。また,58年2月の運輸政策審議会総合安全保障部会の報告にも述べられているとおり,我が国の総合安全保障の観点からも,第三国間において紛争が発生した場合等の事態を考えると,例えば,紛争当事国が自国の輸送の必要性等から我が国貿易に従事する自国船員,船舶を引き上げるおそれがあり,このような不安定な要素を有する外国船に過度に依存することは,我が国の海上輸送における脆弱性を増すこととなるので,日本人船員の乗り組む一定量の日本船を確保しておくことが必要である。
また,日本船は,長期契約による安定した運賃,外国船に対するバーゲニングパワー,日本人船員の雇用の確保などの点からも重要な意義を有している。
ところで,日本船の現状をみてみると,日本船と外国用船から構成される我が国商船隊の我が国貿易物資の積取比率は,ここ10年来7割前後で推移しているが,日本船と外国用船との船腹量の割合は,45年には総トンで75:25であったものが,日本船の競争力低下により53年には50:50にまでなった。54年度から56年度まで外航船舶緊急整備対策を講じたことにより,日本船の減少傾向に歯止めはかかったものの,57年央の日本船の割合はなお56%にとどまっている 〔2-3-1図〕 〔2-3-2図〕。
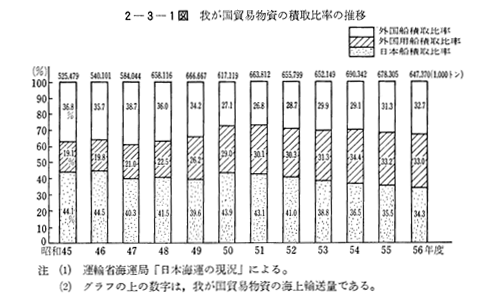
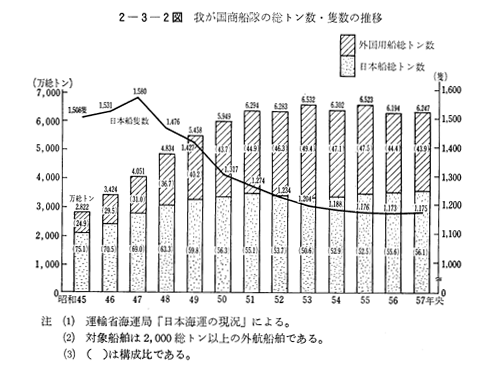
このような現状から,今後とも日本船を維持・整備していくためには,日本船1船ごとの国際競争力をつけることと,安定的に船舶を建造できるように企業体力を強化することの2つの方策が必要である。
(日本船の国際競争力回復)
第1に,日本船の国際競争力を回復するためには,国際競争力喪失の主たる原因が船員費を中心とする船舶コストにあるので,まず海運労使の一致した企業努力が必要である。
乗組定員の少数精鋭化については,57年の船員法及び船舶職員法の改正により制度的な整備が行われたところであり,今後は18人程度の少数精鋭の乗組定員の外航船舶が普及することが期待される。また,日本船の減少により外国船等への労務提供,陸上他社への出向派遣等の形で勤務している,いわば企業内の潜在的な船員供給源としての予備船員が増加しており,これらに係るコスト負担が日本船のコストとして各船に割りがかり,日本船の国際競争力の低下を招いている。日本船の国際競争力を回復するためには,乗組定員,予備員率の合理化により外国船との船員費格差の縮小を図ることが必要であり,そのために海運労使のより一層の努力が望まれる。
このような企業努力とともに,船舶建造資金コストの低減を図るための施策が必要であるが,現在,計画造船制度により日本船を建造する海運企業に対して長期かつ低利の財政資金を日本開発銀行を通じて貸し付けており,58年度にはこのために1,180億円の資金を確保している。
(企業基盤の強化)
第2に,日本船整備のためには,整備の当事者である海運企業が安定的に船舶の建造を行っていけるように企業基盤を強化することが必要である。
外航海運の活動は,全世界的な競争市場で行われるものであり,市況は各国の政治,経済,社会情勢等に応じて大きく変動し,また,収入の多くが外貨建てであるため,為替変動の影響を受けやすく,海運企業の経営構造は,厳しい条件下に業績の乱高下要因を内包したものとなっている。
財務内容としては,我が国外航海運企業の場合,借入金に依存する度合いが強く,企業体力は脆弱である 〔2-3-3表〕。
また,市況変動の激しい外航海運の場合,好況時に上げた利益を極力社内に留保し,不況時に耐え得る企業体力を養うことが必要であるが,従来内部留保の蓄積に寄与してきた特別償却制度は漸次縮小されてきており,準備金残高は49年度をピークに大幅な減少を続けている。先進海運諸国においては,英国の自由償却制度を始めとして早期償却による内部留保の充実が可能な税制が確立されていることをみれば,我が国においても,海運企業が安定的に船舶を建造していけるようにするための方策を検討する必要があるといえよう。
我が国の安定した海上輸送力の確保のためには,今後,以上のような多角的な施策を総合的に講じて,日本船を常時一定量確保していくことが重要である。
(4) 船員制度の近代化
ア 概説
(変化著しい日本船員を取り巻く環境)
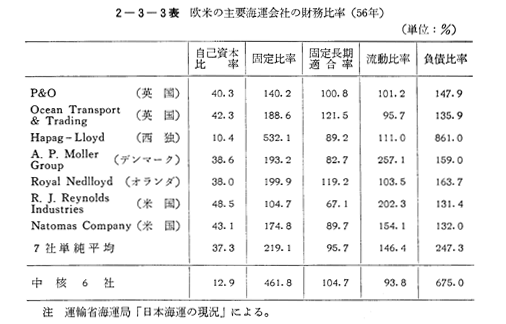
近年,我が国の外航海運の担い手である日本船員を取り巻く国際的な環境の変化には著しいものがある。
すなわち,40年代の後半から日本船の国際競争力の低下が顕著となった。これに対応して,我が国の海運企業は,競争力を回復するため,機関の無人運転が可能なMゼロ船の導入を始めとして,船舶の設備面における自動化等の技術革新を積極的に推進する一方 〔2-3-4表〕,便宜置籍船を中心とする外国用船への依存傾向を強め,それに伴って我が国の外航船員数は,減少の一途をたどってきた。このような傾向が進むと日本船員の職域がますます縮小するばかりでなく,日本船員が乗り組む日本船の一定船腹量を確保しなければならないという経済的安全保障上の要請にも対応できなくなるおそれがあり,日本船の国際競争力の回復が急務となってきた。
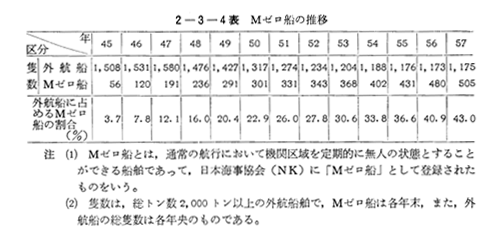
また,42年に英仏海峡において発生したリベリア籍タンカー「トリー・キャニオン号」の座礁事故を契機として,船員の資格,技能について国際的な最低基準を定めるべきであるとの要請が高まり,53年7月に政府間海事協議機関(IMCO-57年5月にIMOに改称)において「1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約」(STCW条約)が採択された。
(推進される船員制度近代化)
このような内外の環境の変化に対応して,日本船員がその優れた技能を十分に活用し,意欲的に職務を遂行することができるような新しい職務体制を確立するとともに,これにより日本船員が運航する日本船が国際海運界において比重を増し,日本船員の職域が確保される条件を整備することを目的として,技術革新の進んだ船舶における新しい職務体制と船内就労体制に対応した船員制度の近代化の検討が進められ,また,STCW条約についても,その国内実施を図るための検討が行われてきた。
上記の検討を経て,船員制度の近代化の円滑な推進及びSTCW条約の国内実施のための「船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律」が第96回国会において57年4月23日に可決成立し,5月1日に公布された。
その後,関係政省令が58年2月から4月にかけて制定され,一部改正法に基づく新しい船員制度が,58年4月30日から施行されたところである。また,STCW条約の締結についても,同じく57年4月23日の国会において承認され,5月27日1MOに加入書を寄託し,我が国は同条約の18番目の締約国となった。この条約は,25か国以上の国が締結し,その保有商船船腹量が世界の商船船腹量の50%以上となった日から1年後に発効することとなっているが,58年4月に発効要件を満たし,59年4月28日から発効することとなっている。
イ 船員制度の近代化
(船員制度近代化は第2段階へ)
船員制度の近代化については52年4月船員制度近代化調査委員会が設置され,54年4月には船員制度近代化委員会に発展的に改組され,同委員会の下で新しい船内職務体制及び船内就労体制の試案についてその実行の可能性と妥当性を検討するための実験船による実験を進めてきた。
同委員会は,55年5月には実験を効率的に推進するための目標として「仮設的船員像」を策定した。これは「将来の目標としての仮設的船員像」とそれに至る過渡的段階の「移行過程としての仮設的船員像」とからなっているが,後者においては,甲・機両部にわたる職務を行う新しいタイプの船員として,部員レベルでのデュアル・パーパス・クルー(D.P.C.),職員レベルでのウォッチ・オフィサー(W/0)を導入することとしている。これを受けて56年2月から「移行過程としての仮設的船員像」の第1段階に沿って,三等航海士と三等機関士が相互に連携して甲・機両部の航海当直を中心とする業務を行うこと等を主な項目とする実験に着手し,56年10月には,その実験結果を踏まえて,今後の船員制度の近代化の推進に関する第1次提言を行った。
第1次提言は,これまでの実験によりD.P.C.,W/Oについて有効性が検証されたこと,今後さらに,第2段階へ実験を進めるべきこと,近代化を推進する上での制度的な制約要因を除去する必要があること等を内容としている。
この提言をもとに,船員法及び船舶職員法の改正を行い,技術革新の進んだ近代化船に乗り組む船舶技士及び運航士等の新しい制度を創設するとともに,関係政省令の制定により,船員制度の近代化の第1段階についてその制度化を図り,58年4月から施行している。
また,この提言を受けて57年度以降引き続き,第2段階,すなわち,二等航海士・機関士レベルにおいてもこれらの職員が相互に連携して航海当直を中心とする業務を行う段階へ実験を進めている。
ウ STCW条約への対応
STCW条約は,船員の知識・技能,当直基準等人的側面における国際基準を定めることにより,船舶の航行の安全を確保しようとするものであり,その主な内容としては,①船長,一等航海士,機関長,一等機関士,当直担当職員等の資格を与えるために必要な知識及び海上航行履歴の要件,②知識,技能のレベル維持のための要件,③甲板部,機関部における当直を維持するための基本原則,④甲板部,機関部における当直担当部員の要件,⑤タンカー乗組員のための特別の要件,⑥救命艇手の要件,⑦締約国政府による海技免状の裏書制度,⑧入港国における監督手続等が定められている。
我が国においては早期にこの条約を締結し,国際的な船員の資質の向上とそれによる航行の安全の確保に資する必要があるとの考えに立って,船員法及び船舶職員法の改正を行い,同条約の締約国となったが,今後は,同条約の趣旨に沿って海上における人命の安全と海洋環境の保護に資するため,国内実施について適正な運用を図っていく必要がある。
エ 船員教育体制の今後の方向
(充実される船員教育体制)
船員制度の近代化を円滑に推進していくためには,近代化船に乗り組む優秀な船員を確保する必要がある。
このため,船員教育機関における教育のあり方について,海上安全船員教育審議会において審議を行った結果,57年12月,甲板部及び機関部の両部にわたる知識・技能を有する船舶職員及び部員の養成等,船員制度の近代化に対応した教育の整備充実に関する答申が得られたことから,同答申の趣旨に沿って,海技大学校においては,近代化課程の教育を運航士制度に対応したものとするため,また,海員学校の高等科の教育については,近代化船における甲板部及び機関部の航海当直をすべき職務を有する部員に対応したものとするため,教育カリキュラムの変更等,教育内容の整備充実を図り,58年度から実施している。
また,商船大学及び商船高等専門学校については,運航士制度に対応して教育内容の整備を実施する方向で検討が進められているところである。
一方,STCW条約において船舶職員となるための要件とされている消火,レーダー,救命等に関する知識・技能については,講習の形でその知識・技能を確保すること等の船舶職員法の改正が行われており,これに対応して,海技大学校及び海員学校においては,教育カリキュラムの見直し等,教育訓練体制を充実し,58年度から実施している。
オ ILO第147号条約の締結と国際情勢への対応
商船における最低基準に関する条約(ILO第147号条約)は,商船の乗組員に関し,船内の安全基準,労働条件,居住施設等について国際的な最低基準を定めるとともに,その実行を確保するため自国の港に入港する外国船を,一定の手続により監督すること等を規定したものである。
この条約は,56年11月に発効しており,既に欧州諸国は,57年7月1日より本条約等を基準とする統一的な入港船舶の検査制度を実施している。
我が国としては,先進海運国として,船内の安全や船員の労働基準に関する国際的な最低基準の確保のための国際協力に寄与するとともに,我が国の外航商船が同条約の基準を充足していることを国際的に明確に示すことは極めて有意義であると認められるので,第98回国会において58年4月27日に同条約の締結につき承認を得,5月31日に我が国の批准をILO事務局長に登録した。その結果,1年後の59年5月31日に,我が国について本条約の効力が生ずることとなった。
なお,同条約の規定する最低基準については,既に国内法令により実現されており,また,その実行を確保するための諸措置についても,現行の国内法令をもって対処することとしている。
|