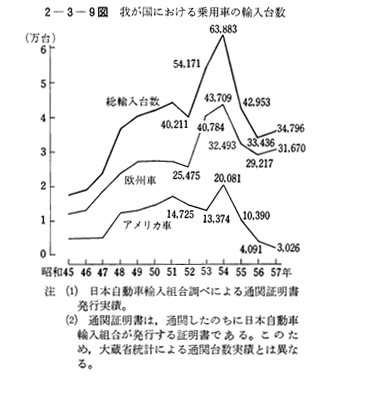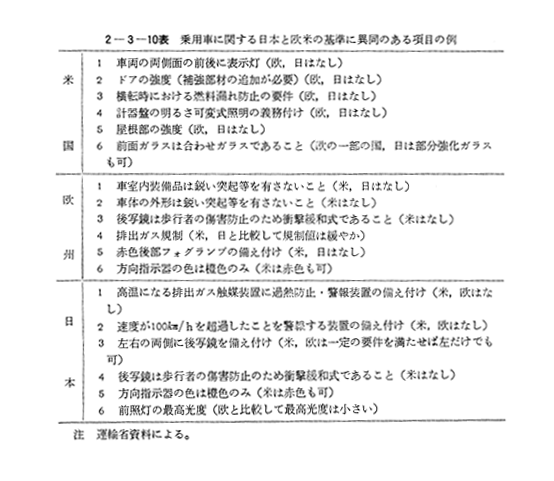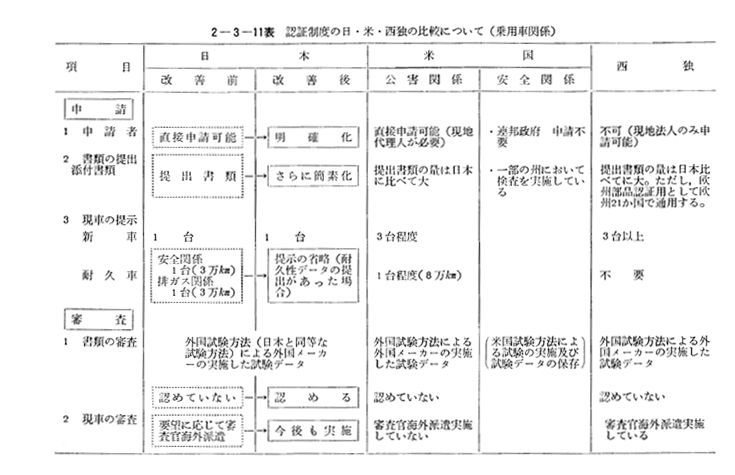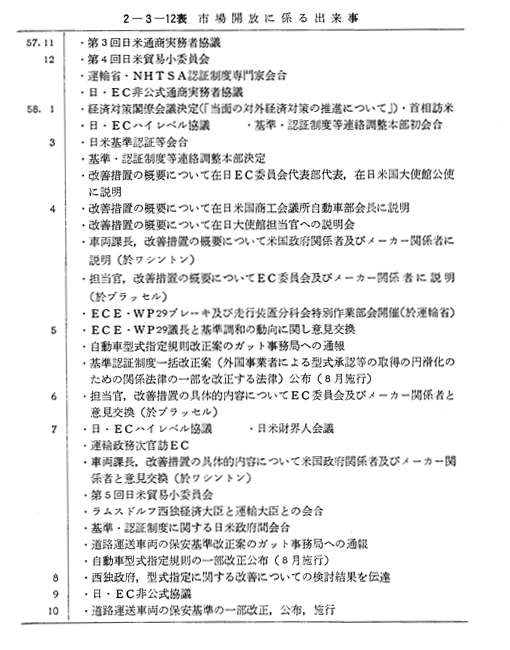|
2�@�����Ԃ��߂���s��J�����ւ̑Ή�
(1)�@�����Ԃ��߂���R���E�������̔w�i
�@�A�@�䂪���ɂ������p�ԗA�o���̕s�ύt
�@�@(�A��1��ɑ��ėA�o��108��)
�@�@�䂪���̊�E�F�ؐ��x�ɌW��ŋ߂̉��ĂƂ̊Ԃ̖��C����,�䂪���Ɖ��ĂƂ̂������N�ɂ킽��f�Վ��x�̕s�ύt�����̍���ɂ���ƍl������B�Ȃ��ł�,�����Ԃ�,��i�����̊�Y�Ƃł��邾���ɊS�͍���,���̂��ߖf�Ֆ��C�̏ے��I�ȑ��݂̈�ƂȂ��Ă���B57�N�̉䂪���ɂ������p�Ԃ̗A�o����,�A��3.5����ɑ��ėA�o��377����ƗA��1��ɑ��ėA�o����108��̔䗦�ƂȂ��Ă���,���̗A�o���̔䗦�͍ŋ�10�N�Ԃ�ʂ��Ă̈�т�����ł���B�䂪���ȊO�̎�v�����Ԑ��Y���ɂ������p�Ԃ̗A�o���̏��݂��,�A��1��ɑ���A�o�䐔�̔䗦��,����2.62(�A�o219.4����/�A��83.7����:57�N),�č�0.12(��35.3/306.8),�p��0.34(��31.3/93.4),�t�����X1.48(��146.4/99.2)�ƂȂ��Ă���B
�@�@���̂��߉��Ċe����,�䂪���ɑ��ėA�o���l�����߂���,���ʓI�A�����������s���Ȃlj䂪������̏�p�Ԃ̗A�o��}�����悤�Ƃ�����,�䂪���Ɏ����Ԃ̗A���g��̂��߂̎s��J���w�͂����߂Ă���B
�@�@�䂪����,�A�o�̎��l���s���ƂƂ���,�����Ԃ̗A���ɂ���,�����ԋy�ю�v�����ԕ��i�̊ł̓P�p���l�X�Ȏs��J���w�͂��d�˂�ƂƂ���,�����Ԃ̐R���E�����Ɋւ��Ă�,��q�̗l�X�ȉ��P�[�u��}���Ă�����,���Ċe���ɂ������p�Ԃ̗A���䐔�Ƃ̊u���肪�ˑR�Ƃ��đ傫������,�܂�,�O������p�Ԃ̗A���䐔��54�N�ȍ~������Ă��邱�� �k�Q�|�R�|�X�}�l�Ȃǂ�,���Ď����Ԑ��Y���Ƃ̊ԂŎ����Ԃ̐R���E�������̂����Ԃ葱����w�i�ƂȂ��Ă���B
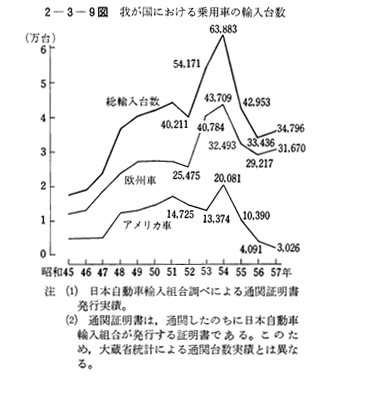
�@�C�@�e���ɂ����鎩���Ԋ�E�F�ؐ��x�̑���
�@�@(�e���̎���ɉ�������E�F�ؐ��x)
�@�@����,�����Ԃ̊�y�єF�ؐ��x�ɂ��Ă�,��v�����Ԑ��Y���ɂ�����,���ꂼ��̍��̗��j�I,�Љ�I,�n���I,�o�ϓI�Ȕw�i�⍑���̎����Ԃ̈��S,���Q�h�~���ɂ��Ă̈ӎ��f����,�قȂ���̂��̗p����Ă���B
�@�@���Ȃ킿,��ɂ��Ă�,���{,�č�,���B(�p��,����,�t�����X,�C�^���A,�X�E�F�[�f��)���̊e��v���Y���ɂ����Ă�, �k�Q�|�R�|�P�O�\�l��1��������悤�ɈقȂ������̂��߂Ă���,�܂�,�F�؎葱�ɂ��Ă��e�����Ɏ����̖@�߂Ɋ�Â��葱���߂Ă���,�č��̂悤�ɓ��ꍑ���ɂ����Ă��A�M�@�ƏB�@�ł��ꂼ���߂Ă���������B�����,���ݔF�ؐ��x���̗p���Ă���EC����ɂ����Ă�,���̑Ώۂ͑��u�ʂ̔F�ɂƂǂ܂��Ă���,�ԗ��S�̂Ƃ��Ă̔F�ɂ��Ă͎��{����Ă��Ȃ��ł���B
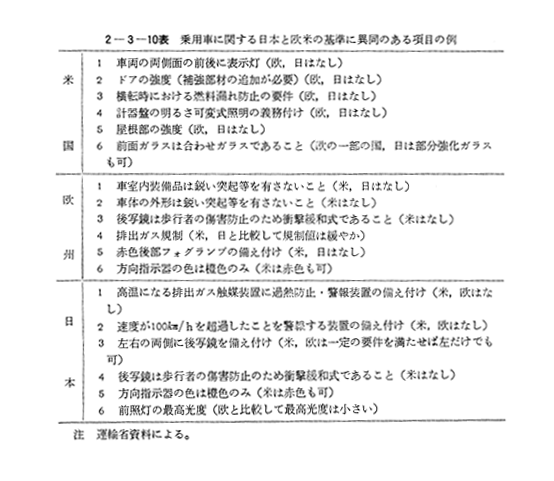
�@�@����������,�����Ԃ𑼍��֗A�o���邽�߂ɂ�,�e�A�o���荑�ɂ����邻�ꂼ��̊�ɓK������悤�Ɏd�l�ύX���̑���s��������,�e���̎葱���ɏ]���F���邱�Ƃ��K�v�ƂȂ��Ă���B
(2)�@���ĂƂ̎����Ԗ�苦�c�̂���܂ł̌o��
�@�A�@��W
�@�@�č��ɂ��Ă�,�����ԐR���E�������Ɋւ�,50�N�ȗ����Ď����Ԗ�苦�c�̏�Ō������������,�R�����̊C�O�h��,�O���쐬�����f�[�^�̎���ꓙ�̉��P�[�u���Ƃ��Ă����B
�@�@���̌�č������56�N10�����S�E�����Ɋւ��鎩�ȔF�ؐ��x(Selfcertification)�̗̍p�̐\�����ꂪ�Ȃ���,���̂���57�N12���ɂ�,���ĉ^�A�Ȃ̐��Ƃ������̎����Ԍ^���F�ؐ��x�ɂ��ċZ�p�I�Ȉӌ��������s�����B���ȔF�ؐ��x��,��v�����Ԑ��Y���ł͕č��݂̂����S�K���y�ё����K���Ɋւ��̗p���Ă���(�r�K�X�K���ɂ��Ă͍������O�R�������{���Ă���B)���̂�,�����ԃ��[�J�[�����̐R���E�������邱�ƂȂ����R�ɔ̔��ł�,���͈��S��������I�Ɋm�F���鐧�x�ł��邽��,���̖̂��R�h�~����{�Ƃ��Ă���䂪���̍l�����Ƃ͑��e��Ȃ����̂ł���B����������,�䂪����,���ĊԂ̋��c�̏�ŌJ��Ԃ����ȔF�ؐ��x�̗̍p��������Ȃ��|���Ă���B���̂悤�ȓ��ė����̐��x�̈Ⴂ��,���S�m�ۓ��Ɋւ��鐭�{�̖����ɂ��Ă̓��ė������̍l�����̑��Ⴊ���̍��{�ɂ���ƍl������B
�@�C�@EC�W
�@�@EC�̎�v�����Ԑ��Y����,�䂪���Ɠ��l�Ɏ��O�R�����x���̗p���Ă��邽��,�䂪���ɑ���v�]��,�ʂ���̓I�ł���,���EEC�n�C���x�����c�̏�Ō�������Ă�����,����܂�,�R�����̊C�O�h��,���I�����@�ւɂ�鎎�����ʂ̎����,�O���쐬�����f�[�^�̎���ꓙ�̉��P�[�u���u����ƂƂ���,57�N6���ɂ�EC����v�]�̋����������I�����@�ւ̒lj����F�����{���Ă����B�܂�,�䂪���ɂ�����A�������Ԃ̃V�F�A�̑唼���߂鐼�Ƃ����,�ʂɈӌ���������o����,�����̂����ō����I�Ŏ��{�\�ȋ��x�v�Z���̍폜���ɂ��ĉ��P�[�u���u���Ă����B
(3)�@��E�F�ؐ��x���A�������{������Ɋ�Â��s��J����
�@�@(�啝�Ɋȑf�����ꂽ�^���w��̎葱,�v����)
�@�@56�N������,�Γ��f�Վ��x�̈�����w�i��,�䂪���̋K�i,�A��,����,�T�[�r�X,�Y�Ɛ������L�͈̖͂��ɂ��Ďs��J�������߂铮�����č�,������EC����N����,���N10���ȍ~�o�ϑ�t����c�𒆐S�ɐ��{�������Ď�g�݂��s���,���N12���ɂ͎s��J�������̑ΊO�o�ϑ�,57�N1���ɂ͂������1�e�̎s��J����,���N5���ɂ͂������2�e�̎s��J����,58�N1���ɂ́u���ʂ̑ΊO�o�ϑ�̐��i�ɂ��āv�����肳�ꂽ�B�����,58�N1���̌���Ɋ�Â�,���t�ɐݒu���ꂽ��E�F�ؐ��x���A�������{�����s��J���̊ϓ_�����E�F�ؐ��x�ɂ��đS�ʓI�Ȍ��������s��,���N3���ɖ{��������s�����B
�@�@�����ԊW�ł�,��1�e�̎s��J�����58�N1���̑ΊO�o�ϑ����Ɋ�Â�,�A�������葱���̉��P�ɂ��đ����̍��ڂ����{���Ă�����,���N3���ɂ�,57�N5���ɓ������ꂽ�����䐔�戵���x�̓K�p�Ώۂ̊g�哙���}��ꂽ�B
�@�@�܂�,58�N3���̖{������ɂ����Ă�,�@�O�������ԃ��[�J�[���^���w�萧�x�ڗ��p�ł��邱�Ƃm�����邽�߂̓��H�^���ԗ��@�̉���,�A�^���w��̎葱�y�їv���̑啝�Ȋȑf��,�B��̍��ۓI���a��Ƃւ̐ϋɓI�ȎQ��ƂƂ���,���ʂ̑[�u�Ƃ��Ẳ��ĂƂ̊�̐������̕��j�����肵���B������Ɋ�Â�,���H�^���ԗ��@�̈ꕔ�������܂O�����Ǝ҂ɂ��^�����F���̎擾�̉~�����̂��߂̊W�@���̈ꕔ����������@���Ă�58�N4���ɍ���ɒ�o����,5���ɐ�����,���z����,8������{�s���ꂽ�B�܂�,�@���̎{�s�Ǝ��������킹�Č^���w��̎葱����啝�Ɋȑf��������P���s�����B����ɂ��,�䂪���̔F�ؐ��x��,���E�̎�v�����Ԑ��Y���ł͍ł��ȑf�����ꂽ���̂̈�ƂȂ����ƍl������ �k�Q�|�R�|�P�P�\�l�B�����,���N10���ɂ͕ۈ���ɂ��ď��v�̉������s�����B
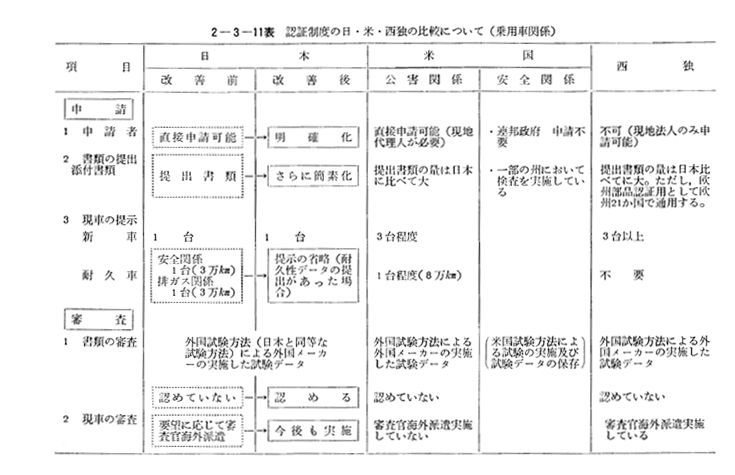
�@�@���̌���,�č�������v�]����Ă����o�^�O�̎�����1�䖈�ɂ��čs���錟���̏ȗ��ɂ��Ă�,���ɂ�鎩����1�䖈�̌ʌ�����K�v�Ƃ��Ȃ��^���w�萧�x�̎葱�y�їv���̊ȑf�����s���,�č��̗v�]�Ɏ��̓I�ɉ����邱�ƂƂȂ����B���P�[�u�̎��{�זړ��̌����ɓ������Ă�,�������ƃ��x���ɂ��ӌ�������p�ɂɏd�˂�����,�č����{����͉��P�[�u�ɂ��Ĉꉞ�̕]���������Ă���B
�@�@�܂�,���B�̂������Ƃ���^���w�萧�x�̉��P�[�u�̈ꕔ�Ɋւ���Ɣ閧�ɐG��邱�ƂƂȂ邨���ꂪ����Ȃǂ̖�肪��N���ꂽ��,���ƌo�ϑ�b�Ɖ^�A��b�Ƃ̉�k����ʂ��ĊW�҂̗��������߂�w�͂��s��������,���P�[�u�����}����|�̕\�������ꂽ �k�Q�|�R�|�P�Q�\�l�B
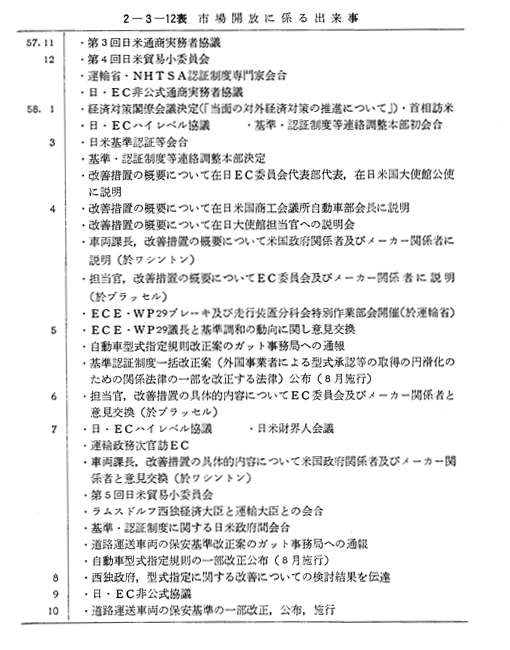
(4)�@�s��J�����̍���̌��ʂ�
�@�@(�]�܂��V���x�̊��p)
�@�@�䂪���̎����ԂɌW��A�o���̋ɒ[�ȕs�ύt�͓����̊ԑ������Ƃ��\�z����,���̂���,�䂪���̐R���E�����葱���f�Ֆ��C���̈�Ƃ��ĂƂ肠������\���������邱�Ƃ͂Ȃ��ƍl������B�Ȃ��Ȃ�,�A���̕s�U�̌����͉䂪���̐R���E�����葱�ɂ���Ƃ���F�������O�Ƃ��ɕ��@�����ɂ͑����̊��Ԃ�v����ƍl�����邩��ł���B
�@�@�䂪���ɂ�����A�������Ԃ̔̔����i�ɂ��Ă͈�ʓI�ɗA�������Ԃ����Y�Ԃɔ�r���Ă��Ȃ芄���ƂȂ��Ă��邪,58�N6���̑����{�̕����@�ւł���f�Չ�c�E���i�A�����c�̕ɂ����ď�p�Ԃ̔̔����i�����O���Ɣ�r�������ʂɂ���,�O������p�Ԃ̉䂪���ɂ�����̔����i��,���Y��p�Ԃ̐��Y���ȊO�̏����ɂ����邻��Ɣ�r���Ăقړ����ł��邩,���邢�͉�����Ă���,�䂪���̎s�ꂪ���I�ł���Ƃ̎w�E�����Ă��Ȃ����Ƃ������Ă���B�A���Ԃ̕s�U�̎�v�Ȍ����Ƃ��Ă�,���i�̂ق�,�ԗ��̃n���h���ʒu,�T�C�Y,�d���,������A�t�^�[�T�[�r�X�̑̐��̖�肪�e�����Ă�����̂ƍl������B�O�q�̂悤��58�N3���̖{������Ɋ�Â�,�����Ԃ̔F�ؐ��x�ɂ��čő���̊ȑf���[�u�����{���ꂽ�Ƃ���ł���,����͗A���ԊW�҂��ԗ��̃T�C�Y,�d���,������R��Ȃǂ̓_�ʼn䂪���̎s��ɍ����������Ԃ𓊓�����ƂƂ���,�V�������x�̊��p�ɂ���w�̔̔��w�͂��X����,�A���̊g�傪�}���邱�Ƃ��]�܂��B���,���{�������,�䂪���̎����Ԋ�E�F�ؐ��x�ɂ���,����Ƃ����O���̎����ԊW�҂ɑ������,�ӌ��������ɂ��ӎu�a�ʂɓw��,�C�O�����ԃ��[�J�[���̗����ƔF����[�߂�w�͂𑱂���ƂƂ���,�����I�Ȋϓ_�����q�����E�F�ؐ��x�̍��ۓI���a�����ɐϋɓI�ɎQ�悵�Ă������Ƃ��d�v�ł���B
�@�@�Ȃ�,��{�I�ɂ�,�A���g��ɂ��A�o���̕s�ύt�����邱�Ƃ��d�v�ł���,58�N10���Ɍo�ϑ�t����c�ɂ����Č��肳�ꂽ�����o�ϑ�Ɋ܂܂��e��̗A�����i��̐��ʂ����҂����Ƃ���ł���B
(5)�@��E�F�ؐ��x�̍��ۓI���a�����ւ̎Q��
�@�@(ECE���Ɖ�c�ł̉䂪���̐ϋɓI�Ȏ�g��)
�@�@�����Ԃ͓��ĉ��̂�����̍��ɂƂ��Ă��d�v�Ȗf�ՎY�i�ł���,���ۓI���i�Ƃ��Ď��R�ɗ��ʂ��邱�Ƃ��]�܂�Ă���,���̂��߂ɂ�,�e��������ɉ����Ē�߂Ă��鎩���Ԃ̊�̓��ꉻ���K�v�ƂȂ��Ă��Ă���B
�@�@55�N5���ɂ�,�䂪���ɂ����Ă��u�f�Ղ̋Z�p�I��Q�Ɋւ��鋦��v(�K�b�g�E�X�^���_�[�h�E�R�[�h)��������,���̖ړI��1�ł��鍑�ۋK�i�y�э��۔F�ؐ��x�̔��W�������Ԃ̐R���E�����ɌW��s���̂����Œ����I�Ȋϓ_����d�v�ȉۑ�ƂȂ��Ă���B
�@�@���ۓI�ɓ��ꂳ�ꂽ�����Ԋ���Ȃ������_�ɂ�����,����̍��ۓI���ꉻ�ɒ��S�I�������ʂ�����@�ւ�,���S,���Q���ɌW���E�F�ؐ��x�ɂ��ĉ��B������K���̍쐬���s���Ă��鍑�A���B�o�ψψ�����Ԉ��S���Q���Ɖ�c(ECE�EWP29)�ł���BWP29��,���B�e�����������Ă���u�ԗ��̑��u���тɕ��i�̔F�����̓���y�єF�̑��ݏ��F�Ɋւ��鋦��v(1958�N�W���l�[�u����)�Ɋ�Â��������s���Ă���@�ւł���,���B�����݂̂Ȃ炸�č�,�I�[�X�g�����A,���{����v�����Ԑ��Y�����Q�����Ă���B�䂪����,52�N����WP29�ɖ���o�Ȃ�,�K���쐬�̓�����c������ƂƂ���,�e���Ə��������s���Ă����B����,���ʍ�ƕ���ɂ����ĉ��ĊԂ̓����̍쐬��Ƃ��i�߂�����,���Ƀu���[�L,���Ί�,�Փˎ�����ی쓙�̕���̍�Ƃ͑傫�Ȑi�W���݂��Ă���,�č�,�I�[�X�g�����A�����B��O���̐ϋɓI�Q���Ƒ��܂���ECE�K����,����Ɏ�����̍��ۊ�Ƃ��Ă̈ʒu���ł߂���B
�@�@�䂪����,�O�q��58�N1���̎s��J����y�ѓ��N3���̖{������ɂ����Ċ�̍��ۓI���a�̂��߂̊����ɐϋɓI�ɎQ�悷�邱�Ƃ����肵�Ă���,���̕��j�̂��Ƃ�,�u���[�L����a���ʍ�ƕ����58�N4���ɓ��{�ɂ����ĊJ�Â����Ƃ���ł��邪,�����,���̕���ւ���w�ϋɓI�ȎQ����s���ƂƂ���,��Ăւ̈ӌ���o,�Z�p�f�[�^�����s��,�䂪���̈ӌ����\���ɔ��f�����Ȃ���,����̍��ۓI���ꉻ�𐄐i���Ă������ƂƂ��Ă���B
�@�@���,�F�ؐ��x�̍��ۊԂ̓���ɂ��Ă�,1958�N�W���l�[�u����ɉ��������������݊Ԃł�,�����Ԃ̓��葕�u�ɌW�鑊�ݔF�ؐ��x���̗p����Ă���,���ꂪ���B��O�܂Ŕ��W����\��������B���̂���,�䂪���Ƃ��Ă�,���̓����ɒ��ӂ���,�����̉\���ɂ��Č������邱�ƂƂ��Ă���B
|