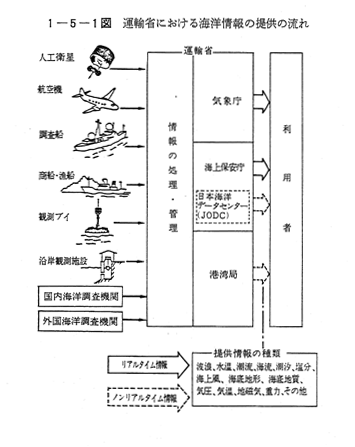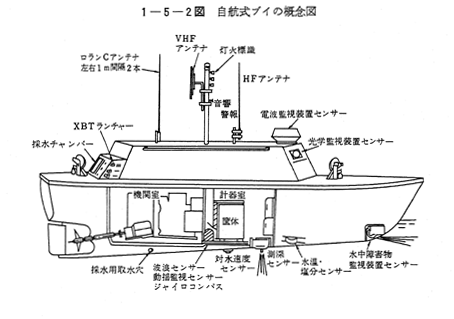|
2 海洋調査及び海洋情報の収集・提供の充実・強化
海洋の開発・利用を進めるうえで,海洋に関する情報は必要不可欠であり,海洋の開発・利用の進展に伴い,海洋情報に対する需要は多様化,高度化し,量的にも急速に増大している。
運輸省では,海上保安庁,気象庁,港湾局において広範にわたる海洋調査を実施し,海洋の開発・利用に関する諸活動に必要な波浪,海流,水温,海底地形等各種の海洋情報をリアルタイム(即時)情報あるいはノンリアルタイム(非即時)情報として提供しており,広域かつ総合的な海洋調査及び海洋情報の収集・提供を恒常的に行う我が国唯一の機関として,海洋の開発・利用の推進に大きな役割を果たしているが,上述のニーズに対応し,情報提供の迅速化,広域化,局地情報の質の充実,情報精度の向上等海洋情報の高度化を図るためこれらの業務のより一層の充実・強化を進めている。さらに,国際的には,ユネスコ・政府間海洋学委員会(IOC)が設けている国際海洋データ交換システム(IODE)において,海上保安庁の日本海洋データセンター(JODC)がノンリアルタイム情報の交換を行っているほかIOCと世界気象機関(WMO)が共同で推進している全世界海洋情報サービスシステム(IGOSS)計画において,気象庁が太平洋域の特別海洋中枢(SOC)としてリアルタイム情報の交換を行っており,国際間の海洋情報の交換を通じて,国際的な海洋情報の収集・提供を行っている 〔1−5−1図〕。
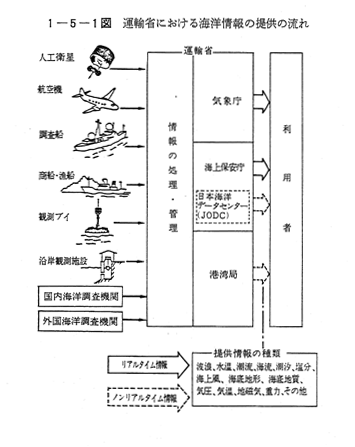
先に述べた情報提供の迅速化,広域化に関しては,「ひまわり」等の人工衛星を利用したリモートセンシングの推進,船舶や航空機による広域調査の充実,人工衛星を介した観測データの伝送,有線回線を用いた隔地観測網の整備等による観測データ伝送システムの高度化,多大な情報の処理管理のための計算機システムの充実,ファクシミリ等による情報提供システムの高度化を図っている。局地情報に関しては,沿岸海洋観測網の拡充,国内海洋調査機関の観測データの収集等により,沿岸海域の波浪データの提供,「沿岸の海の基本図」の刊行等を行い質の高い情報の提供に努めている。情報精度の向上に関しては,調査機器,調査手法及び情報処理手法の開発等により精度の一層の向上を図っている。
また,今後の海洋調査の一層の充実を図るため,海底火山周辺海域等の危険海域を調査する遠隔操作の自航式ブイ 〔1−5−2図〕の開発,長期間海洋においてデータ収集が可能な太陽エネルギーを利用した漂流観測ブイの研究,砕波帯域での波の変形,海浜流,漂砂等の観測を行う観測桟橋(茨城県鹿島灘)の建設,広域にわたる水温等の海面下構造の即時的把握が可能となる海洋音波断層システムの開発等を進めている。
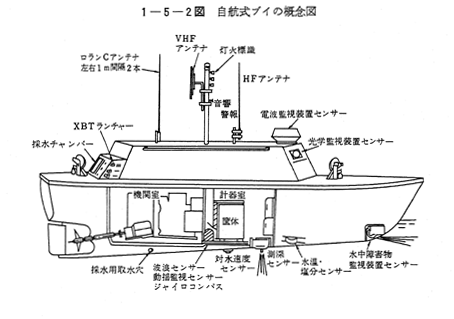
|