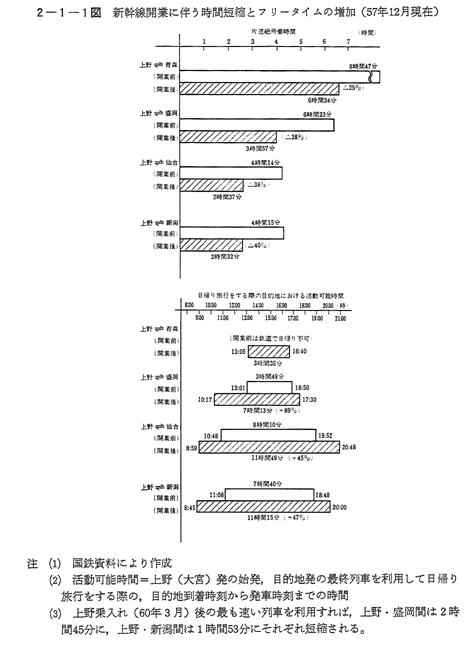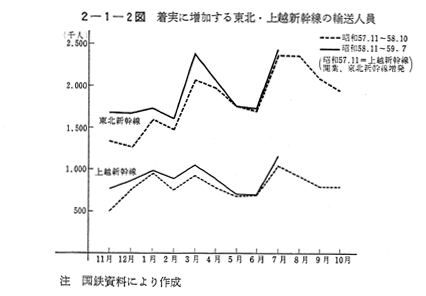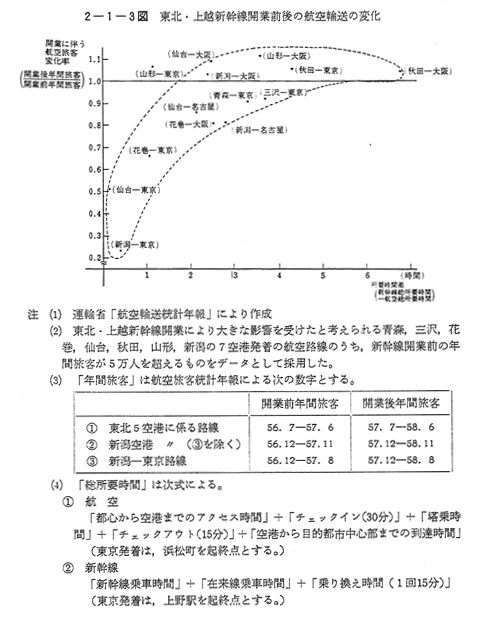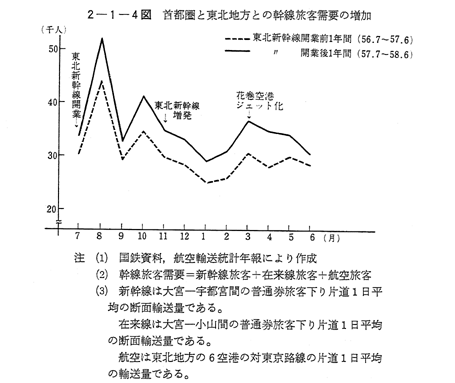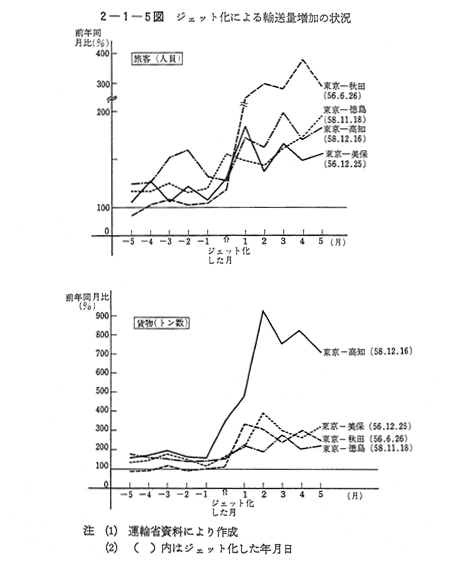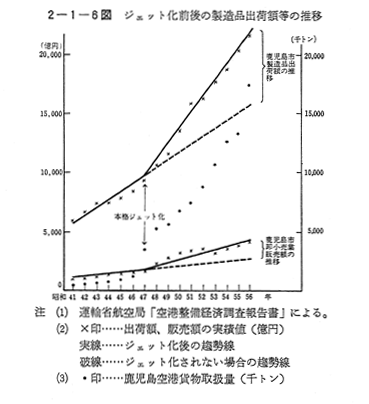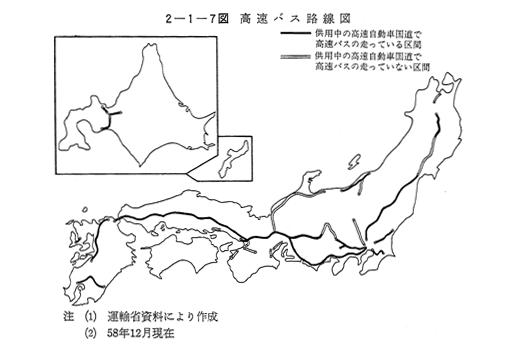|
1 高速化の進展
(進展する高速交通網の整備)
大都市集中型社会から地方分散型へと定住構想を進め,国土の均衡ある発展を図るとともに活力ある社会を築くためには高度なモビリティの確保が必要であり,大都市圏と地方圏及び地方圏相互を結ぶ高速交通網の充実が重要な政策課題となっている。こうした中で高速交通網の整備が順次進められている。
(1) 東北・上越新幹線の開業
(輸送人員も着実に増加)
昭和57年6月及び11月にそれぞれ開業した東北新幹線(大宮〜盛岡間),上越新幹線(大宮〜新潟間)は,首都圏と東北地方,新潟地区との時間距離を大きく短縮し,日帰り滞在時間の拡大など利便の向上が著しく,輸送人員も着実に増加している 〔2−1−1図〕, 〔2−1−2図〕。
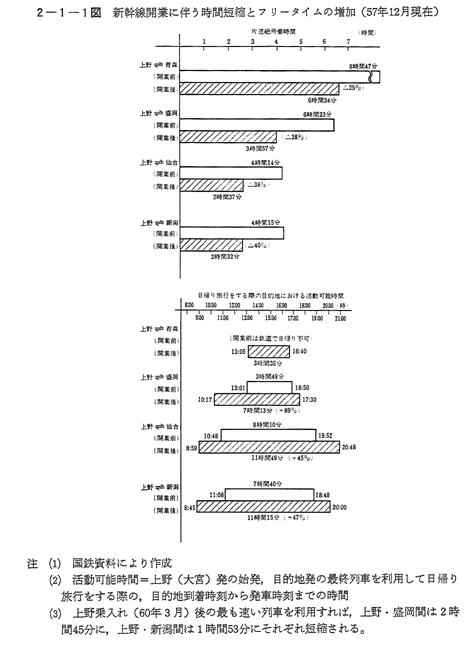
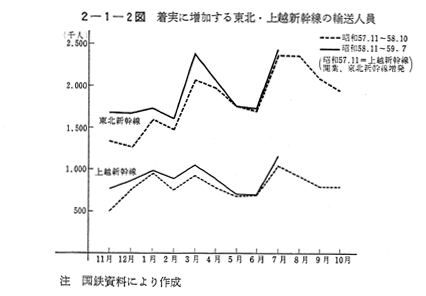
(時間差の小さい航空路線ほど減少)
東北・上越新幹線の開業により並行する航空路線の航空旅客の減少が著しいが,東北及び新潟の各空港を発着する航空旅客数の新幹線開業後1年間の増減(前年同期比)と新幹線利用の場合と航空利用の場合の所要時間差との関係をみると 〔2−1−3図〕のとおりである。新幹線との時間差の小さい航空路線ほど旅客の落ち込みが著しく時間差1時間未満の仙台-東京線では48%減となっており,新潟-東京線では航空旅客は2割程度に落ち込み,58年9月航空路線の休止に至っている。また,2時間未満の花巻-東京線では34%減となっているが,4時間程度以上の路線や鉄道を利用した場合新幹線から乗継ぎが必要な路線では航空旅客への影響は余りみられない。
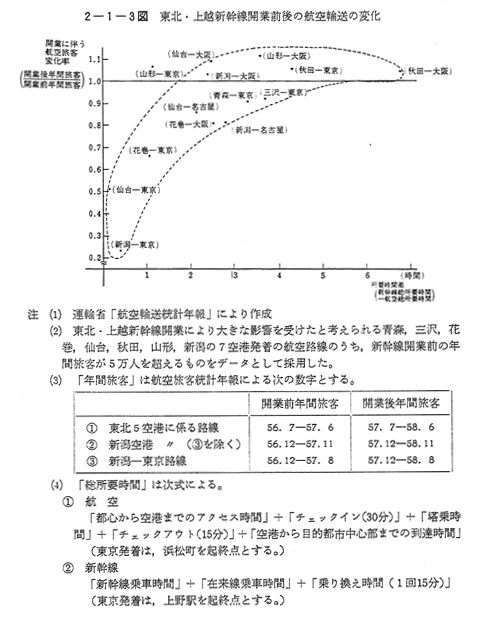
(幹線交通需要全体が増える)
このように新幹線の開業は,航空輸送の利用動向に大きな影響を与えているが,首都圏と東北地方との幹線旅客需要全体がどう変化したかを,東北新幹線の大宮-宇都宮間,在来線の大宮-小山間及び東北地方の各空港の対東京路線の56年7月〜58年6月の旅客需要の統計の推移でみると 〔2−1−4図〕のとおりである。東北新幹線,在来線,航空路線を合わせた全体の需要は,新幹線開業前に比べて6〜23%増加しており,特に開業年の8月,10月の夏休み,帰省,観光シーズンの増加が目立つが,58年度に入ってからも着実な増加を示しており,一時的な新幹線ブームが多少はあったものの東北新幹線の開業が首都圏-東北地方間の幹線交通需要の誘発的増加をもたらしたものと考えられる。
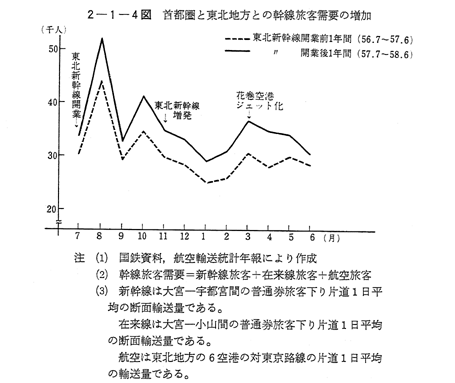
さらに東北新幹線開業後,東北各県で観光客の増加,百貨店売上高の伸び,企業活動における情報収集の円滑化,技術者の交流の活発化等各方面でプラスの影響が表われており,新幹線開業は交通市場の構造を大きく変えるだけでなく地域の経済社会に大きなインパクトを与えている。
また,60年3月には,東北・上越新幹線の上野乗入れが予定されており,これに伴い所要時間の大幅な短縮,乗換えの不便の解消等一層の利便の向上が期待される。
(2) 地方空港のジェット化
(飛躍的に増加するジェット機就航空港)
基幹空港(羽田,成田,大阪),離島空港(那覇を除く。)及び小型機用の空港(調布,八尾,弟子屈)を除くその他の地方空港のジェット化率は,50年度末に44%であったものが58年度末には71%(41空港中29)と飛躍的に増加している。
58年度1年間をとっても対馬,徳島,高知,富山の4空港がジェット化しており,さらに60年代前半のジェット化を目指して稚内,女満別,青森,鳥取,岡山,高松,福江,奄美の各空港において整備工事が進められている。
(ジェット化は地域経済にも大きな影響)
空港のジェット化は,時間距離短縮の他,ジェット機就航による輸送力増強と相まって旅客,貨物輸送量の飛躍的増加をもたらしている 〔2−1−5図〕。
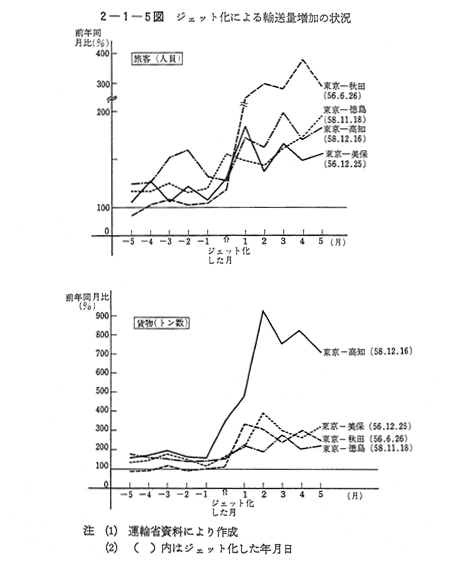
さらに,空港のジェット化は,九州の各空港の周辺に立地しているICなどの先端産業の例からわかるように工場進出の契機となっており,地域経済にとっても大きな影響を与えている。空港のジェット化が地域経済に与える影響を,44年に旧空港でジェット化,47年に滑走路2,500mを有する本格的な大型ジェット機の就航する新空港として供用開始した鹿児島空港についてみると 〔2−1−6図〕のとおり鹿児島市の製造品出荷額,卸小売業販売額は同空港発着の航空旅客数及び航空貨物輸送量の飛躍的増加と並行して増加しており,地域経済の成長にジェット化が相当の寄与をしているものと考えられる。
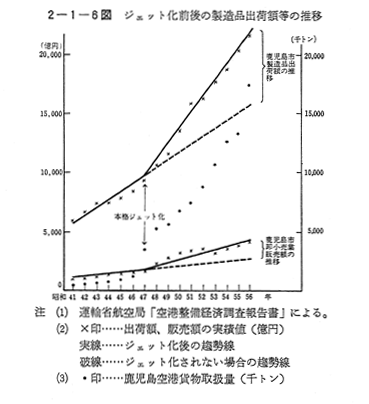
(3) 高速道路網の充実
(国土の背骨となる縦貫道が概成)
高速自動車国道の供用延長は,58年度末には3,435キロメートルにしており,特に58年3月には中国縦貫自動車道千代田-鹿野間の開通により同自動車道が全通したこと等から国土の背骨となる縦貫道が概成している。
(高速バスが伸びる)
高速道路網の充実に伴い,高速道路を利用した高速バス(運行系統キロの概ね半分以上が高速道路利用のもの)の進展も著しく,所要時間,運行頻度,運賃,市街地へのアクセス等の面で利用者ニーズに適合した高速バスは多くの利用者を集めつつあり,その輸送人員は,一般の路線バスが年々輸送人員を減少させているのに対して57年度は対50年度比2.25倍と大幅に増加している。また路線網は,59年5月に中国縦貫自動車道において新大阪・千代田,新大阪・三次,新大阪・加計の3系統が開業し,59年10月現在48社179系統となっている 〔2−1−7図〕。
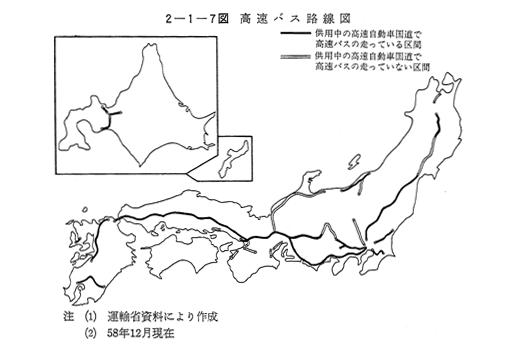
|