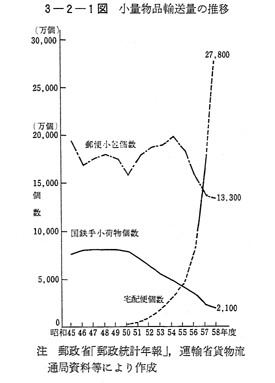|
1 貨物流通サービスの新しい展開
(1) 産業物流の展開
(高度化する物流ニーズ)
第1節でも記述したように,近年,国民生活の面において,価値観の多様化が進展するとともに,消費生活の質的充実への要請が高まりつつある。
一方,産業界においては,マーケット戦略に焦点をあてて物流の効率化を求める動きがあり,その表われとして,一つには在庫コストの削減を図ること,もう一つには上記の消費者ニーズの高度化,多様化に対応することを目的として,少量,多頻度かつ迅速な輸送を求める傾向が強くなっている。
また,輸送の分野に止まらず輸送以外の分野,すなわち保管,流通加工等の分野まで含んだ質の高い総合的なサービスを求める傾向も強まっている。
この結果,近年においては,保管,流通加工等の機能を持った交通拠点の整備,コンピューターを駆使した各種の荷役,仕分機械の開発,問屋街や流通業務団地等を基盤とした出荷配送の共同化等少量多品種の物流動向への対策が進んでいる。
さらに,国際的には,近年海陸空にわたる輸送手段を組み合わせて戸口から戸口まで一貫した責任と運賃で輸送を行う複合輸送に対するニーズも高まりつつある。
複数の異なる輸送手段を有機的に結合して行う国際複合輸送は,在来船時代からも商社等により行われていたといわれているが,コンテナリゼーションの進展が契機となって大きく展開した。さらに近年に至り,国際海上輸送における競争の激化を背景に,より付加価値の高い輸送を求める荷主ニーズに対応するものとして,急速に進展しつつある。具体的には,船社,フォワーダー(港湾運送,倉庫会社等),商社等がそれぞれの立場でこの新しい分野の国際物流サービスに取り組みつつあり,従来のシベリアランドブリッジ(日本-ソ連-ヨーロッパ),ミニランドブリッジ(日本-米西岸-米東岸等)等に加えて,最近においても,インテリアポイント・インターモーダル・サービス(日本-米西岸-米内陸地点),カナダランドブリッジ(日本-カナダ-ヨー口ッパ)等様々なルートが整備されつつある。
これらの国内及び国際的な動きに対応し,我が国物流企業においては輸送の一層の効率化を進めること,輸送以外の面での物流サービスの付加価値を高めること,複合一貫輸送体制の整備を図ること等が必要になってきている。
(多面的な貨物流通政策の展開)
このような課題に対応するため,行政においても,従来の交通機関別アプローチから発想を転換し,貨物の流れそのものに着目しつつ,今後の経済社会の進展に即した貨物流通政策を策定していくことが必要である。このため,まず,荷主たる産業界を中心に,きめ細かな物流ニーズの把握に努め,輸送量全体の伸びが停滞する中で,物流企業が自らの活力と創意工夫によって新しい事業展開を行っていけるよう多面的な政策展開を図ることが必要である。
特に物流企業はその多くが中小企業によって占められていることにかんがみ,柔軟で活力のある中小企業の育成,強化を図り,これによって物流事業全体の活性化を図っていくことが重要である。
(2) 消費者物流の進展
ア 宅配便,引越し輸送
(急増する宅配便,引越輸送)
トラックによる宅配便は,最近4,5年輸送量が著しく伸びており,昭和58年度の宅配便取扱個数は全体で2億7,800万個に達し,郵便小包の取扱個数の2倍にまで達するに至っている 〔3-2-1図〕。
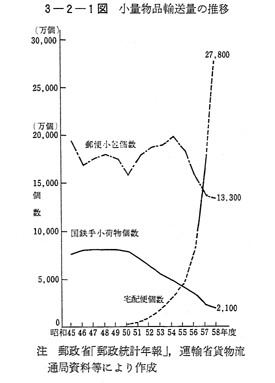
このような宅配便の急成長は,一般消費者の身近な所での受付け体制の整備,迅速な輸送体制の整備,所要日数の明確化等質の高い輸送サービスを利用者に利用しやすい形で提供したことによるものと考えられる。
また,各事業者はサービスの充実による競争力の強化を図っており,宅配便のシステムを利用してゴルフ,スキー用具の輸送,産地直送便等を行い,サービスの多様化を図っている事業者も見られる。
宅配便と同様に,一般消費者が利用する輸送サービスとして,近年トラックによる引越し輸送の成長が著しい。このような急成長は,生活水準の高度化に伴い,家具,家財の大型化,高級化により引越しにおける運搬にもかなりの労力と技術が必要となる一方,運送事業者の側においても梱包,荷役等の基本的な付帯サービスのみならず,不用品の廃棄処分,冷暖房機器の取付け・取外し,家具の防虫消毒等多様化する消費者ニーズに対応してサービスの充実を図ってきたことによるものと考えられる。
(宅配便,引越輸送に係る消費者対策)
このような宅配,引越し輸送の進展に伴い,消費者とのトラブルの問題を生じており,このため,次のような施策を講じている。
①トラブルの防止を図るため,各事業者に対して運賃等についての取次店での掲示状況,苦情窓口の整備状況についての監査を実施するとともに,利用者保護についての指導を強化する。
②また,トラブルのなかには,輸送サービス内容のPR不足や契約内容の確認の不徹底などによる利用者と事業者の間のサービス内容についての認識の食い違いなどを原因とするものもあることから,社団法人全日本トラック協会を通じ,宅配便については宅配便の上手な利用のためのパンフレット,引越し輸送については見積内容をわかり易くした標準見積書を作成し,そのサービス内容の周知を図る。
③さらに,社団法人全日本トラック協会を始め,各都道府県トラック協会における宅配便,引越し輸送等に関する苦情の相談コーナーを拡充し,利用者からの相談に応じる場を設ける。
④また,現行の標準貨物運送約款は48年に告示されたものであり,一般消費者を対象とする宅配便や引越し輸送の実態に対比すると,現実的でない面が見られる。
例えば,宅配便における引渡し期日,遅延損害,引越し輸送におけるキャンセル制度などの点において,消費者の一般的通念と異なることがあり,消費者保護の観点から必ずしも適切なものになっていない面が生じてきており,58年11月には国民生活審議会の消費者政策部会からも,その点の指摘がなされている。
このため,消費者保護の観点から,標準約款の適正化に関し検討を進めており,59年度中を目途に概案をとりまとめる予定である。
イ トランクルーム
(急増するトランクルーム)
近年,大都市圏における住宅事情,海外赴任の増加等生活環境の変化に伴い,あるいは盗難予防,防災等保管上の理由から家財,美術品,毛皮,衣類等の物品を定温,定湿,防塵機能等を備えた倉庫において,適正に保管してもらいたいという一般消費者のニーズが高まっている。
一方,これまで倉庫業者は,主としてメーカー,商社等を対象として比較的ロットの大きな物品の保管を行ってきたが,多品種少量化等の動きの中で保管需要の伸び悩みもあって,一般消費者等を対象とした小口物品の保管業務に進出するものが増加しつつある。
このような新しい形態の保管サービスは,一般にトランクルームサービスと呼ばれ,従来のサービスに比べ高度に保管されたサービスを提供するものである。営業所の数は,50年末に19だったものが58年度末には88へと急増しており,今後とも一層普及していくことが予想される。
(トランクルームに係る消費者対策)
トランクルームサービスには,現在事業者間取引を念頭において定められている標準倉庫寄託約款が適用されているが,同約款は,消費者取引には通常用いられていない条項があるほか,損害賠償責任に関する規定等が消費者の一般通念と著しくかけ離れていたり,不明確な表現を用いているため解釈によっては利用者に不利益が生じるおそれがある条項や規定内容が専門的にすぎ一般消費者には理解が困難であるといった条項が含まれていることなどから必ずしも適切でないものとなっており,宅配便,引越し輸送と同様,58年11月には国民生活審議会の消費者政策部会からもそれと同様の問題点が指摘されている。
したがって,トラブルの未然防止を図る観点から,運輸省では,上記約款の適正化に関し検討を進めており,59年度中を目途に概案をとりまとめる予定である。
(3) 貨物流通情報システムの整備
(貨物流通の分野における情報化の進展)
高度情報化時代を迎えVAN,INS,CATVなどについて期待をこめた議論がなされている。貨物流通の分野においても,大企業を中心に情報化への積極的な対応が進められている。
事務処理効率や作業効率を高めるためコンピュータを利用したシステムの構築が各社で個別に行われているが,航空貨物の追跡管理や関連情報の伝達及び処理を行う日本航空の新貨物情報システム(JALMAX CARGO)などはこの代表例である。また,車両運行の効率化を図るため,無線の周波数の有効利用を可能とするMCA(MultiChannel Access),トラック等の運行状況を自動的に把握するAVM(Automatic Vehicle Monitoring,車両位置等自動表示)といったシステムが宅配便の集配車等に適用されている。
これらのほか,複数の企業を結んだ情報ネットワークの整備も進められている。
トラック事業者のVAN事業への進出意欲は強く,59年9月現在全届出事業者49社のうち14社がトラック事業者またはその子会社である。宅配便をはじめとする多数の小口貨物の1個1個について,荷主に対するサービスの一環として追跡管理を行うためには,連絡運輸会社をも含めた情報ネットワークの整備が不可欠となっている。また,このようにして整備された機械設備やシステムの有効利用を図る方法として,例えば荷主とその取引先との間での受発注のデータ伝送を引き受けるシステムを構築すれば,自ら直ちに配送も行い得るというメリットも期待できる。
このようにトラック事業者は荷主に対するサービスの高度化等の観点から今後更にVAN事業への進出を図っていくこととなろうが,第101回特別国会で継続審議となった電気通信事業法が成立し,施行されれば,その動きに一層のはずみをつけることとなろう。
海貨業者,検量・検数業者,船会社等の複数の港湾関係業者をオンラインで結び,港湾貨物に係る情報の伝達・交換を行うことによって業務の効率化等を図る港湾貨物情報ネットワークシステム(SHIPNETS)については,60年4月を目途に京浜港において輸出貨物を対象に第2次実験が行われる予定であり,その成果が大いに期待されている。
また,税関,航空会社等をオンラインで結び,航空貨物の通関関係業務等の電算処理を行う航空貨物通関情報処理システム(NACCS)についても,従来の輸入業務に加えて60年初頭より輸出業務も行えるようになるなど機能の拡張が図られつつある。
(望まれる総合的な情報システム)
このように,それぞれのシステムが分野に整備される一方,貨物流通業界全体および銀行,荷主等をネットワークして,各種手続をコンピュータで処理するとか,各輸送機関を通じて一貫して貨物の追跡管理を行うといった総合的な情報システムの構築が望まれており,関係者の調整,システムの設計等について検討が進められている。
(4) 貨物流通技術の開発
(技術開発の必要性)
ア 高度化・多様化する物流ニーズに対応した新しい技術の開発
貨物流通産業は,作業そのものが労働集約型であることから生産性の向上を図るうえでの障害も少なくない。しかし,各産業の在庫コスト等を含めたトータル物流コスト低減化の要請に応えていくため,輸送技術・保管技術の改善はもとより,最も労働集約的な部門である荷役,仕分といった作業を中心として貨物自動仕分機,立体自動化倉庫,無人搬送車の導入などメカトロニクスの技術を駆使した各種の新システムの開発導入を進めつつあり,また,いわゆるユニット・ロード化(コンテナ化,一貫パレチゼーション)のための各種機器の開発,規格の統一化等も着実に進展している。
一方,物流に対するニーズも,輸送の正確性,小口化,多頻度化,取扱いサービスの高度化など,物流サービスの高品質化,多様化への要請を強めている。これらの要素は一面的には効率性を阻害する要因も含まれており,物流産業として,これらの要請に即応してゆくためには,ニーズの変化に対応して物流機器等ハード面の技術開発に積極的に取り組んでゆく必要がある。
また,現在,エレクトロニクス技術,光通信など新たな技術革新による知識集約型産業の成長にはめざましいものがあり,特に通信技術と情報処理技術の飛躍的な進歩とこれらの融合による情報革新が急速に進展しつつある。貨物流通の分野においても,こうした先端技術を活用するソフト技術の開発を促進し,今後積極的に導入していくことにより,省力化,生産性の向上を図っていくことが望まれる。
(今後の貨物流通技術開発上の課題)
さらに,今後の貨物流通技術の開発への取り組みにあたっては,特に国際・国内経済の動向,産業構造の変化・消費者価値観の多様化の動向等将来の物流をとりまく環境を予見した上で物流システムを確立することが重要であり,行政としても,技術開発における官・民の役割分担を十分見極めつつ,システム・エンジニアリングを導入した技術開発体制の充実化,物流技術に係るデータ・ベースの作成等,技術開発問題に積極的に取り組んでいくこととしている。
イ 危険品等特殊貨物に係る輸送技術の開発
(特殊貨物輸送の対策)
貨物の輸送対象物は,一般的にはいわゆる軽薄短小化の傾向にあるといわれるが,一方においては,工業技術の高度化等に伴い,特に化学製品等の中の危険品や輸出プラント機器等の長大・重量物などのいわゆる特殊貨物の輸送需要が近年急速に増加してきている。これら危険品等の特殊貨物は,海・陸・空において円滑,迅速な一貫輸送を行うことが安全性の確保,物流コストの低減を図るうえで極めて重要である。したがって,今後これら特殊貨物輸送の分野において,輸送技術面,荷姿,規格,技術的制度等の各面のネックを明確にし,物流ニーズと行政その他のニーズ(安全対策,公害対策,空間制約条件への対応等)との調和に十分配慮しつつ,所要の技術開発,技術規格の整合化等を図っていく必要がある。
(放射性物質輸送対策)
なお,これら危険品等貨物のうち,特に放射性物質(原子燃料・アイソトープ)の陸上輸送の分野においては,原子力開発の進展,医療・工業・学術等の伸展に伴い,今後輸送量も増大していくものと考えられるので,この分野での必要に応じた安全性向上技術の開発体制の充実強化を図っていくことがますます重要な課題となっている。これらの貨物輸送は陸上輸送とりわけトラック輸送のウエイトが年々増大してきているため,運輸省としても,関係省庁と緊密な連携を図りつつそのための安全輸送対策に重点的に取り組んでいくこととしている。
|