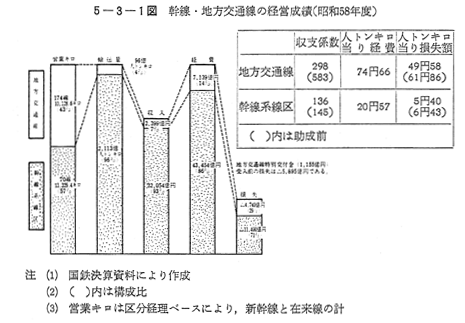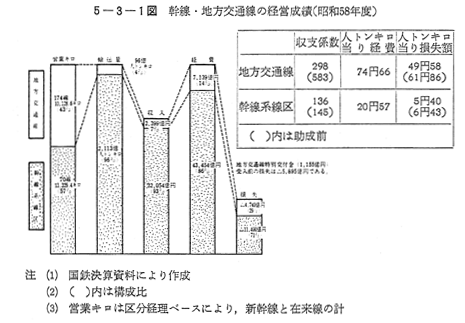|
2 事業分野の整理
(1) 貨物輸送
(拠点間直行輸送システムへの転換)
貨物輸送については,主としてヤード系輸送のサービス水準が低く,自動車等への転移が進んだため,輸送量は55年度以降4年連続して対前年度約10%程度の減少を続ける等大幅な減少の一途をたどり,過去最高の輸送量であった45年度と比較すると約60%減となっている。
これに伴い,貨物部門の収支は,57年度についてみると収入2,855億円に対し支出が1兆371億円に達し,7,516億円の赤字を生じており,また,旅客,貨物両部門に共通する経費を除いた貨物固有経費5,739億円すら償えない状況にある。このように貨物営業は,国鉄全体の経営悪化の大きな要因となっており,貨物輸送の合理化は,国鉄経営改善のための重要な課題である。このため,大量,定型という鉄道特性を発揮し,かつ,市場のニーズに適合した輸送を提供できるよう,57年11月のダイヤ改正時における合理化(100ヤード,800駅体制)に加え,さらに59年2月のダイヤ改正において非効率なヤード系集結輸送を全廃し拠点間直行輸送システムへ転換するとともに,貨物取扱駅の再編成(460駅体制)を行ったところである。これにより輸送コストの低減の他,到達所要時分の短縮等サービスの向上による競争力の強化を図り,貨物収支の改善を目指すこととしている。
この結果,59年2月〜8月のコンテナ輸送実績は月平均90万トン(対前年度比18%増),車扱輸送実績は月平均530万トン(対前年度比20%減)となっている。
今後は60年3月のダイヤ改正において,輸送の一層の効率化を図り,コンテナを中心とした増送・増収,きめ細かな収支分析をはじめとする厳しい収支管理等を行うことにより,60年度において貨物固有経費での収支均衡を達成し,引き続き,収支の改善を徹底し,旅客部門に負担をかけることなく事業を行える体制の確立を図ることとしている。
(2) 地方交通線対策
(本格化する地方交通線対策)
国鉄がその運営の改善のために適切な対策を講じたとしてもなお収支の均衡を確保することが困難な路線である地方交通線については,58年度においても,駅の停留所化・業務委託,貨物取扱駅の再編成等,各種の合理化施策が講じられたが,特別交付金1,155億円の助成後においてもなお4,740億円の損失を計上した。地方交通線は,輸送量で全体の4%,助成後収入で全体の7%を占めるに過ぎないにもかかわらず,経費では14%,損失では29%を占めており,まさに国鉄経営の大きな負担となっている。このため,さらに徹底した合理化努力を行うとともに,地方交通線の中でも輸送需要が極めて少なく,国民経済的にみても鉄道による輸送に代えてバス輸送を行うことが適切な路線であるいわゆる特定地方交通線については,バスによる輸送等への転換を図る必要がある 〔5−3−1図〕。
56年9月に選定承認がなされた第1次線40線約730キロについては,すべて特定地方交通線対策協議会が開催されており,既に過半数の27線(59年10月末現在)について転換またはその方向付けがなされているところである。このうち,10線が転換済みであり,白糠,日中,赤谷,魚沼,清水港の5線はバス輸送へ,また久慈,盛,宮古,神岡,樽見の5線は第3セクターによる地方鉄道へと,それぞれ円滑な転換が行われている。
また,57年11月国鉄から申請のあった第2次線については,59年6月,代替道路の実情等について更に調査が必要なため取扱いを保留した岩泉線など6線を除き,27線1,540キロの選定承認がなされたところである。これらについても,遅滞なく特定地方交通線対策協議会を開催するなど,円滑な協議の推進を図っていく必要がある。
本年8月,国鉄再建監理委員会の第2次緊急提言を受けて,運輸省は国鉄再建緊急対策推進本部を開催し,これら第1次線及び第2次線の一層円滑な転換を図ることとし,60年度以降に転換が予定されている輸送密度(1日1キロ当たりの輸送人員)4,000人未満のいわゆる第3次線については,当面,国鉄において,これらの線区のうち代替輸送道路の未整備など政令除外要件に該当するものを選ぶ前提となる輸送実態の分析,代替道路の調査,開発計画の確認等のための準備を行わせることとした。
さらに,これら特定地方交通線以外の地方交通線についても,国鉄からの分離を積極的に進めていくとともに,引き続き国鉄が運営する地方交通線については,駅の停留所化,輸送力の適正化等の徹底した合理化を行うことにより業務運営の効率化を推進し,収支の改善に努めることが必要である。
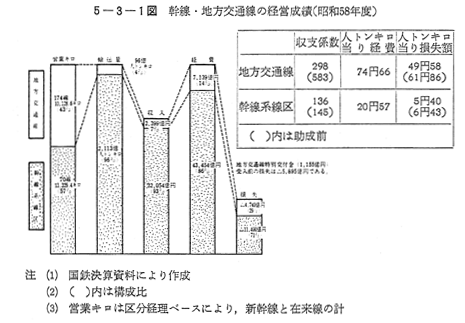
|