|
2 基幹空港の整備
ア 関西国際空港計画の経緯等
我が国経済の発展と豊かな国民生活の実現を図り,また,国際社会における責務を果たしていくうえで,航空輸送の果たす役割はますます重要なものとなっている。 しかし,現在の大阪国際空港は,首都圏と並ぶ我が国の2大都市圏のひとつである近畿圏にあって世界の多数の都市と国際航空路線で結ばれる一方,我が国国内航空ネットワークの2大拠点のひとつを形成しているにもかかわらず,環境対策上の配慮から離着陸回数の制限等多くの制約を受けているため,同空港の国内航空旅客輸送に占めるシェアーは,45年度の55%と比べて,58年度には30%となるまでに低下してきており,特に西日本を中心とした国内航空輸送の面で同空港は大きなボトルネックとなっている。また,我が国には,いまだ本格的な24時間運用可能な国際空港が整備されていないため,我が国の国際航空の発展にも大きな支障が生じている。 このような状況に適切に対応し,大阪国際空港の環境問題の抜本的な解決にも資するため,関西国際空港の早期実現が望まれるところである。 (航空審議会答申と地元との協議・調整) 関西国際空港の計画については,航空輸送需要の増大等に対処するため,40年代の初め頃から運輸省において各種調査を実施してきたが,46年10月,運輸大臣は,航空審議会に対し「関西国際空港の規模及び位置」について諮問し,同審議会は49年8月,関西国際空港の位置について泉州沖,神戸沖,播磨難の3候補地を総合的かつ客観的に評価した結果,泉州沖の海上が最も望ましいとする旨の答申(第1次答申)を行った。 これを受けて運輸省は,関係府県(大阪府,兵庫県,和歌山県)と十分な協議・調整を行う等地域社会の理解と協力を得る努力を重ねるとともに,本格的な海上空港を建設するための広範囲にわたる調査を実施してきた。 その後,同審議会は,第1次答申を基礎にその後の調査研究の成果を積極的に取り入れて鋭意検討を重ね,55年9月に「関西国際空港設置の計画について」を答申した(第2次答申)。 56年には,2度にわたる航空審議会答申とこれまでの調査検討の結果を踏まえて取りまとめた「関西国際空港の計画案」,「関西国際空港の環境影響評価案」及び「関西国際空港の立地に伴う地域整備の考え方」(いわゆる3点セット)をもとに関係府県との間の意見交換を鋭意進めた結果,地元自治体議会の新空港反対決議が撤回される等地元における情勢も変化し,57年7月には大阪府から,8月には和歌山県から,59年2月には兵庫県から,それぞれ計画の具体化を進めるべき旨の回答がなされた。 (関西国際空港株式会社の設立) このような地元との協議・調整等の進展を背景として,58年度予算において,関西国際空港の着工のための準備を行う経費として関西国際空港着工準備調査費(32億円)が新たに認められ,また,58年5月には,関西国際空港関係閣僚会議が開催され,政府としての取組み体制が整備された。 さらに,関係省庁,関係府県等と所要の協議・調整が進み,59年度予算において,民間活力の導入を提言した臨時行政調査会答申の趣旨を踏まえて,国,地方公共団体及び民間が一体となった協力・責任体制のもとに,弾力的,効率的な企業的経営が可能な事業主体を導入することとして,国,地方公共団体及び民間が出資する特殊法人たる関西国際空港株式会社の設立を中心とする所要の予算が計上された。また,本年3月に国会に提出された関西国際空港株式会社法案が本年6月に成立し,関係政省令とともに公布,施行された。 さらに,本年7月には,関西国際空港の設置及び管理の基本となる関西国際空港株式会社法第3条第1項の関西国際空港の基本計画を定めるとともに,関西国際空港株式会社設立委員会により同会社の設立手続が進められ,10月1日に同会社が設立された。
イ 関西国際空港計画の概要
(ア) 位置
(イ) 第1期計画
なお,関西国際空港の全体構想においては,4,000メートルの主滑走路2本,3,400メートルの補助滑走路1本,面積約1,200ヘクタール,年間離着陸回数約26万回となっている。
ウ 関西国際空港株式会社の概要
このような会社の行う事業の公共性を確保するとともに民間活力の円滑な導入を図るため,会社に対して関西国際空港株式会社法等において,運輸大臣が定める基本計画に適合した空港の設置及び管理,事業計画の認可等の監督措置を講ずるとともに,政府による株式の二分の一以上の保有,債務保証,無利子貸付け等の財政措置,固定資産税,不動産取得税等について特例措置を講ずるほか,関西国際空港の整備に要する費用の支出に備えるため準備金制度を設けたところである。 民間資本を導入した株式会社方式により国際空港を整備する本方式は,世界的にみても初めてのケースである。 会社は,空港敷地として約500ヘクタールの用地造成を行い,滑走路1本とこれに対応する諸施設を整備し,24時間運用可能な本格的な国際空港を運営するが,設立時の資本金は51億円(設立時授権資本金204億円)であり,政府が34億円,地方公共団体が8億5,000万円,民間が8億5,000万円を出資し,設立時の役職員は約150人である。 空港の建設に要する事業費(第1期工事分に係るもの約1兆円)の資金計画については,出資金は事業費の12%(約1,200億円)であり,その内訳は,国からの出資金8%(約800億円),地方公共団体からの出資金2%(約200億円),民間からの出資金2%(約200億円)であり,借入金等(財政投融資,民間等からの借入等)は事業費の88%(約8,800億円)である。なお,事業費の30%相当の無利子資金を確保するため,会社に対し国,地方公共団体及び民間からは,資金調達への協力等が行われることとなっている。
エ 今後の進め方
関西国際空港の建設運営に際しては,空港と地域社会との調和を図るため地元の意向を反映するよう努力するとともに,環境保全,アクセス等の関連施設整備,民間の創意工夫の活用等に十分留意していく必要がある。 また,空港の立地に伴い必要となるアクセス等の関連施設整備については,本年10月5日に開催された関西国際空港関係閣僚会議において,関西国際空港関連施設整備連絡調整会議の設置が了承され,今後,関係省庁間で連絡・調整を行うこととしている。
ア 現況
新東京国際空港は,53年5月,4,000メートル滑走路及びこれに附帯する諸施設で開港し,すでに6年余の運用実績を有している。この間,厳重な警備体制の中とはいえ,大きなトラブルもなくおおむね順調に運営されてきたといえる。 現在,同空港に乗り入れている国際線は,33か国(日本を含む。),38社(日本企業2社を含む。)の定期航空会社であり,58年度における1日平均の発着回数は188便,利用旅客は27,000人,航空貨物は1,800トンとなっている。 開港以来,利用旅客数は堅調に推移し,一方,発着回数は機材の大型化により旅客増が吸収された結果,57年度までは横ばいであったが,58年度において,利用旅客数(対前年度比9%増),貨物量(同26%増)及び発着回数(同6%増)はいずれも顕著な伸びを示した 〔6-1-7図〕。 これは,58年8月の航空燃料パイプラインの供用開始による燃料の制約の解消,ユナイテッド航空及びフィンランド航空の新規乗入れ等によるものである。なお,同パイプラインは供用開始以来事故もなく順調に運用されており,本年8月には2本の導管のうち残る1本も供用を開始するに至っている。
イ 空港早期完成の必要性
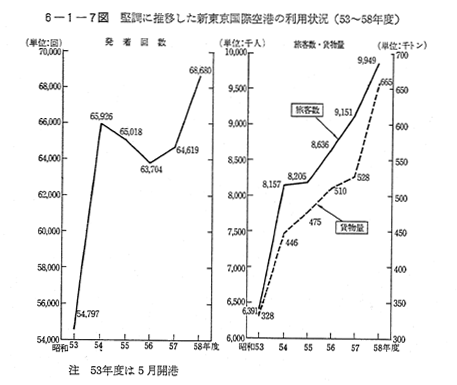
このように,新東京国際空港は,我が国の表玄関としての役割を果たしており,国際空港としての評価も着実に定着してきているが,主要な国際空港としては他に例を見ない滑走路一本による運営を余儀なくされており,また,今後とも航空需要は確実な増加が見込まれるところであり,現有施設の能力との関係及び第二旅客ターミナル等の残された工事に要する期間を考慮すると,できるだけ早くこれらの工事に着手し,空港の早期完成を図る必要がある。
ウ 地元の動き
空港の早期完成を図っていくに当たっては,空港と周辺地域社会とが一体となって調和のある発展を遂げていくようになることが必要であるので,従来から環境対策,農業振興策等の地元対策,地元要望事項の処理を積極的に推進してきたところである。 その結果,58年11月には,運輸大臣と千葉県知事との会談において地元要望事項(航空博物館の建設,B・C滑走路の騒音対策等)の処理について合意し,空港早期完成の必要性について意見の一致をみるに至った。また,昨年から今年にかけて千葉県議会,空港周辺の19市町村の議会,千葉県市長会,町村会等において相次いで空港の早期完成を求める決議がなされ,空港早期完成に対する地元の積極的な協力が得られる状況となった。
エ 今後の課題
(ア) 未買収地の取得
(イ) 空港の保安の確保
(ウ) 地元要望事項の処理
ア 沖合展開事業の経緯
運輸省は,東京国際空港の航空機騒音問題の抜本的解消と今後の需要増大に対処するため,46年頃から長期的視野にたって整備計画の検討を進めてきたが,52年3月,東京都知事から,現空港の羽田沖への移転を前提に地元を含めた話合いの場を設けて欲しいとの要望があり,52年8月,運輸省,東京都及び地元区で構成する「羽田空港移転問題協議会」(以下「三者協議会」という。)が発足した。 運輸省は,三者協議会における意見交換を進めるとともに,これと並行して沖合展開計画試案を作成し,53年12月,これを三者協議会に提示した。この試案については,地元区からいくつかの要望が提出されたため,運輸省はさらにこれに関する検討及び調整を重ね,要望をできる限り取り入れた修正案を提示し,56年6月,滑走路配置等基本的事項について合意に達した。 ついで運輸省は,この基本的合意を踏まえて具体的計画を策定するため,56年10月に建設省,東京都及び運輸省からなる「東京国際空港沖合展開計画連絡調整会議」を設置し,この場で廃棄物埋立計画,道路計画,鉄道計画等の関連事業との調整を図った上で,58年2月,東京国際空港整備基本計画を決定した 〔6-1-8図〕。
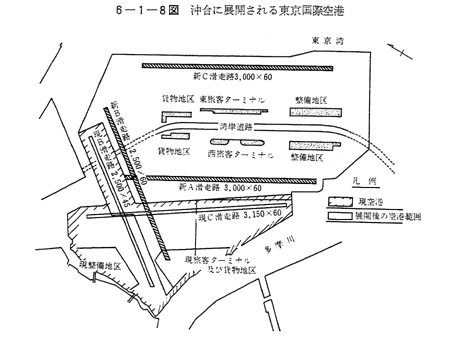
その後,航空法に基づく飛行場の施設変更の手続,東京都条例に準じた環境影響評価の手続を経て59年1月に工事に着手することとなった。
イ 計画の概要
東京国際空港は,国内航空交通の拠点として全国36空港との間に1日約400便のネットワークが形成され,年間約2,200万人の人々に利用されている。 本空港の離着陸処理能力は,46年頃よりその限界に達し,53年5月に成田空港が開港したことにより,しばらくの間若干の余裕が生じたが,その後に増便が行われたこと等により今や再びその限界にきている。 本計画は,首都圏における国内航空交通の拠点としての機能を将来にわたって確保するとともに,懸案であった航空機騒音問題の抜本的解消を図るため,羽田沖の東京都廃棄物埋立地を活用し,現空港を沖合に展開するものであり,次のような目的及び特徴がある。
(ア) 航空輸送力の確保
(イ) 騒音問題の解消
(ウ) 廃棄物処理場の有効利用
(エ) 空港跡地の利用
また,本計画においては,新A滑走路(3,000メートル),新B滑走路(2,500メートル)及び新C滑走路(3,000メートル)の3本の滑走路を整備することにより,滑走路の離着陸処理能力は年間で現在の17万回から24万回に,一日当たりでは同じく460回から660回となり,航空機の大型化と相まって輸送力は飛躍的に強化され,現在の約4倍にあたる年間8,500万人程度の乗降客を取り扱うことが可能となる 〔6-1-9表〕。 3本の滑走路に囲まれたターミナル地域には,ほぼ中央部に旅客ターミナル地区,その北側に貨物地区,南側に整備地区を各々配置することとしている。 空港へのアクセス交通施設としては,道路及び鉄道の導入を計画している。道路については,既存の環状8号線と首都高速道路1号線に加えて,建設中の湾岸道路との取付けを計画している。 一方,鉄道については,西旅客ターミナル供用開始時にモノレールを同ターミナルまで延伸し,京浜急行空港線をモノレールに接続する地点まで延伸するとともに,東旅客ターミナル使用開始時には,モノレールを同ターミナルまでさらに延伸することを計画している。また,将来の東京国際空港への旅客輸送需要の動向等を勘案し,適当と認められる時点において京浜急行をターミナル地区まで延伸する計画である。
ウ 事業の進め方
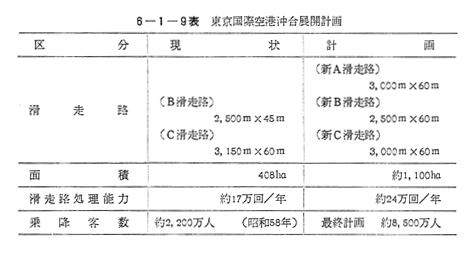
本事業は,現空港がもつ施設を最大限に活用しつつ,今後の航空輸送需要に対応できるよう段階的に順次沖合に展開しようとするものである。したがって,新施設の整備のテンポ,現有施設の飽和年次及び工事中における機能の確保を考慮し,関係者と十分調整のうえ,段階的に移行させる必要がある。
|