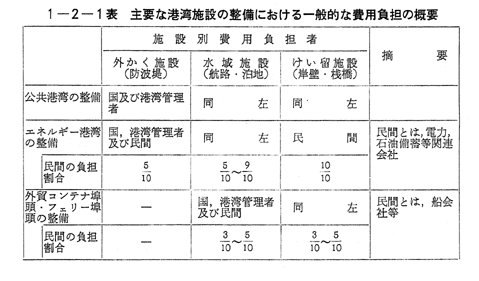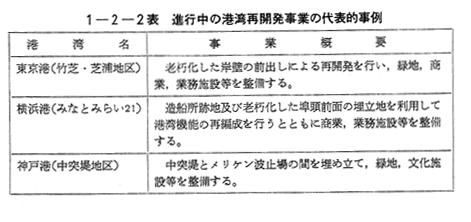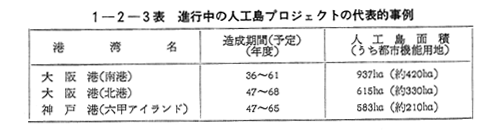|
1 民間活力の活用による事業の推進
運輸の各分野においては,陸,海,空にわたり,従来より民間主体で事業を推進している分野が多いが,さらに内需拡大の観点も踏まえ,各々の事業ごとにその性格等に応じ民間活力の活用を図ることとしている。
運輸において民間活力の活用により事業を推進する基本的な考え方は,次の三つに分類される。
第1に,民間の経営能力,効率性等を事業運営に導入する観点からの公的事業部門の民営化である。
輸送構造の変化等事業を取り巻く環境の変化により,従来のように公的主体による事業の運営では利用者ニーズに応じたサービスの提供が困難となったり,より効率的な経営が必要となっているもので,国鉄事業や日本自動車ターミナル(株)がその例である。なお,国鉄については次章で述べる。
第2に,国鉄用地の有効活用である。
特に,都市内の国鉄用地について,国鉄事業再建の観点と併せ,民間活力活用の場を提供し民間投資の拡大を図ろうとするものである。
第3に,効率的な施設整備を進める観点から事業の推進に当たり民間の資金,経営ノウハウ等を導入するものである。
従来公共事業として行われていた空港整備に民間資金等を導入し,株式会社方式で整備することとした関西国際空港の整備や官民が協力して事業を行う港湾再開発,人工島の建設等がその例である。
運輸省においては,このように各分野を通じて,事業の性格,事業を取り巻く環境,事業の緊急性等を勘案して積極的に民間活力の活用を図っていくこととしている。
(1) 日本自動車ターミナル(株)の民営移行
日本自動車ターミナル(株)は,昭和40年7月に特殊法人として設立されて以来,民間資金のみによる建設が困難な東京都の市街地周辺部における一般トラックターミナルの整備運営により,トラック輸送の合理化,道路交通の円滑化に大きく貢献してきたが,その後の事業の進捗等により特殊法人としての同社の設立目的はおおむね達成されたとみられるに至った。
一方,我が国の物流についても,近年その小口化,高頻度化,さらには,宅配に代表される消費者物流の進展など,大きく変化してきていることから,同社としても,公共性の極めて高いトラックターミナル事業の安定的継続を図りつつ,このような変化に対応すべく,民間の活力を活かした経済性のより高い施設経営へと進むべき時期にきているものと判断される状況となってきた。
このため,特殊法人の整理合理化の一環として,同社を民営移行することとし,60年4月に所要の法律が公布,施行された。これを受けて民営化のための諸手続きが進められ,6月18日,同社は完全に民営移行された。これにより,同社は,民間企業としての特性を発揮し,物流の変化に一層的確に対応した弾力的な経営を行い得ることとなった。
今後同社は,このような経営により民間企業としての地歩を着実に固めていくこととなるが,当分の間,政府としてもそのために必要な支援を行っていく必要がある。
(2) 国鉄用地の有効活用
国鉄用地の有効活用については,58年6月,モデルプロジェクトとして錦糸町,梅田南,新宿,汐留の4地区を対象として,国鉄に計画検討委員会及び基本構想研究委員会が設置され,開発準備構想の検討が行われている。このうち梅田南については,土地区画整理事業方式で基盤整備を行うこととなり,土地区画整理組合が60年6月に設立された。
また,58年10月に内閣に設置された「国有地等有効活用推進本部」において,都市内の国鉄用地に民間活力を導入して有効活用を図ることは,内需拡大による景気振興に資するだけでなく,国鉄の財政にも寄与するものであるとの観点から,59年2月,民間活力導入検討対象財産が選定され,有効活用の促進について順次検討が進められている。このうち,名古屋市の東芳野町及び中村町の対象財産については,一般公開競争入札により売却された。
(3) 関西国際空港の整備
関西国際空港の整備については,民間活力の導入を提言した臨時行政調査会答申の趣旨を踏まえて,国,地方公共団体及び民間が一体となった協力・責任体制のもとに,弾力的,効率的な企業的経営が可能な事業主体を導入することとして,国,地方公共団体のほか民間も出資する株式会社方式により行うこととし,59年10月,関西国際空港(株)が設立された。
民間資本を導入した株式会社方式により国際空港を整備する本方式は,今後の大規模プロジェクトのモデルとして注目されており,民間の創意工夫の発揮,機動的弾力的な経営による効率的な空港整備が期待されている。
(4) 港湾整備における民間活力の活用
港湾整備においては,受益者が特定できるエネルギー港湾や外賓コンテナ埠頭,フェリー埠頭の整備について受益者負担という形で民間資金を導入しながらその整備を進めてきているほか,港湾再開発や人工島の整備に当たり,官民が分担,協力して整備を進めるなど民間活力の活用を図っている。
ア エネルギー港湾及び外貿コンテナ埠頭,フェリー埠頭の整備
エネルギー源の多様化・安定供給という国家的要請に基づく石油備蓄や電力立地等に対応した岸壁等の港湾施設の整備及び埠頭公社等の第三セクターにより行われている外賓コンテナ船,カーフェリーのための港湾施設の整備については,一般的に 〔1−2−1表〕のような費用負担に基づき民間資金の導入を図りつつ主要な港湾施設の整備が行われており,59年度には,エネルギー港湾の整備を能代港,苫小牧港等9港において,また外貿コンテナ埠頭,フェリー埠頭の整備を横浜港,神戸港等6港において実施した。
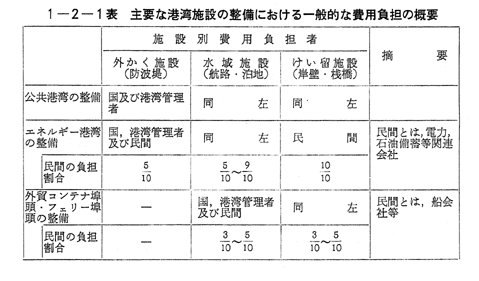
イ 港湾再開発及び人工島の整備
都心部に近く利用価値の高い地区を対象として港湾再開発を実施し,公共埠頭,緑地,臨港道路等の港湾施設を整備するとともに,これと一体的に業務ビル,見本市会場等の各種施設の整備を民間活力を活用して,造成用地の一部において行うことにより,総合的な機能を有する港湾地区の整備を進めている 〔1−2−2表〕。
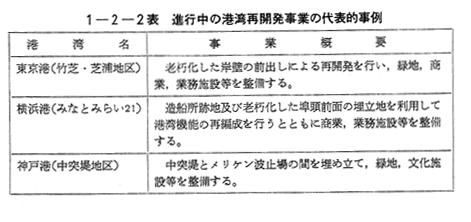
また,公共事業によるコンテナ埠頭や緑地等の整備により人工島外周部を形成するとともに,これらと体的に各種施設の整備を民間活力を活用して中央部用地において行うことにより,総合的な機能を有する港湾空間としての人工島の整備を推進している 〔1−2−3表〕。
59年度には,港湾再開発事業を東京港,横浜港,神戸港等15港において,また人工島の整備を大阪港,神戸港等において実施した。
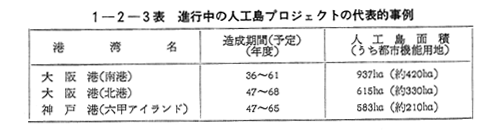
|