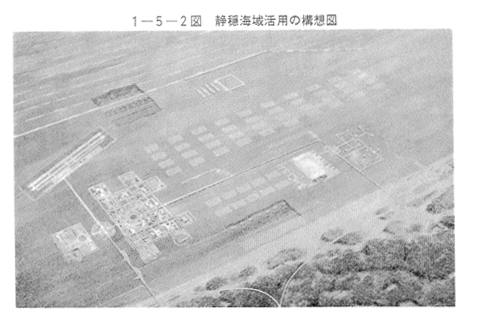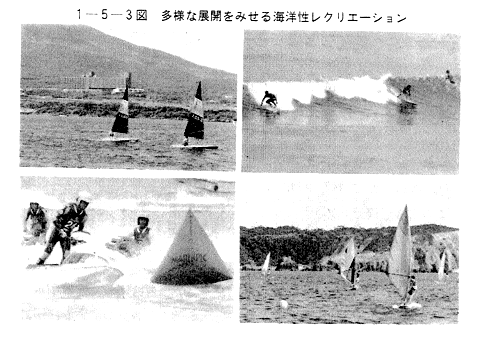|
3 海洋の開発・利用の推進
(1) 海洋調査及び海洋情報の収集・提供の充実・強化
海洋の開発・利用を進める上で,海洋に関する情報は必要不可欠であり,海洋の開発・利用の進展に伴い,海洋吉報に対する需要は多様化,高度化し,量的に急速に増大してきている。
運輸省は,「ひまわり3号」等の人工衛星,航空機,調査船,観測ブイ,沿岸観測施設等による広範にわたる海洋調査の実施等により,海洋の開発・利用に関する諸活動に必要な波浪,海流,水温,海底地形等各種の海洋情報を収集し,ニーズに応じて適切な処理を行ったうえ,リアルタイム(即時)あるいはノンリアルタイム(非即時)の情報として利用者へ提供しており,広域かつ総合的な海洋調査及び海洋情報の収集・提供を恒常的に行う我が国唯一の機関として,海洋の開発・利用の推進に大きな役割を果たしてきている。なお,運輸省では,これらの海洋情報を,ファクシミリ等により船舶等へ提供するほか,総合的海洋データバンクである日本海洋データセンターを通じて提供している。今後,増大するニーズに対応し,海洋情報の高度化を図るため,これらの業務のより一層の充実・強化を進めていくこととしている。
このほか海洋情報の収集・提供の充実・強化のため,国際的な活動にも積極的に参加しており,全世界海洋情報サービスシステム(IGOSS)計画及び西太平洋海域共同調査(WESTPAC)等に参加し,積極的にその推進を図っている。
また,今後の海洋調査の一層の充実を図るため,海底火山周辺海域等の危険海域を調査する遠隔操作の自航式ブイの開発,人工衛星を利用して海流等の変動を面的に把握するための調査システムの研究,音波により広域の水温等の変動を常時モニターする音波断層システムの開発,一般商船や漁船による表層水温,塩分の自動観測伝送システムの開発等を行っている。
(2) 海洋の開発・利用の推進
先に述べたとおり,今後の我が国の発展のために,海洋の開発・利用のより一層の推進が強く望まれており,運輸省では,より広域にわたる海洋の開発・利用を推進するため,総合的な観点に立った施策を進めてきている。
海洋空間のなかで,沿岸海域は国民生活と密接に結びついた空間として盛んにその開発・利用が進められている。沿岸海域のなかでも多目的かつ高度に利用されているのは,一般的には,港湾やこれ以外の自然条件に恵まれた内湾・内海の一部であり,これらの海域を除いた沿岸海域は,総じて海域利用の程度は低く,単機能的な利用にとどまっている。
海洋空間の有効利用を進めるに当たっては,このような海域の特性に応じた施策の推進が必要である。
(三大湾等の計画的利用の推進)
三大湾等の利用が稠密な海域においては,旺盛かつ高質な海域利用へのニーズに対応し,適正な利用を図っていく必要があり,運輸省ではこれらの海域の利用と保全のあり方を検討し,総合的な観点に立った各種の方策を定め,計画的利用を推進してきているが,今後は,沖合人工島等による新たな発展の場の整備,廃棄物の広域的処理(フェニックス計画),広域的な海洋環境改善のための施策(シーブルー計画)等を含め,一層の計画的利用を推進していくこととしている。
(外海に面する海域の有効利用の推進)
一方,外海に面する沿岸海域は,波浪等の厳しい自然条件等が原因となって,そのポテンシャルが十分に発揮されていない。このため,これらの海域においては,海域のポテンシャルに適合し,その開発・利用を先導するプロジェクトの策定と推進によりその有効利用を図る必要があり,運輸省では地域振興の核となる沖合人工島構想や波浪の制御により波の荒い海域を内湾・内海並みの波静かな海域(静穏海域)とし,海域の利用ポテンシャルを高め,多目的な利用を図る静穏海域整備構想 〔1−5−2図〕を推進していくこととしている。
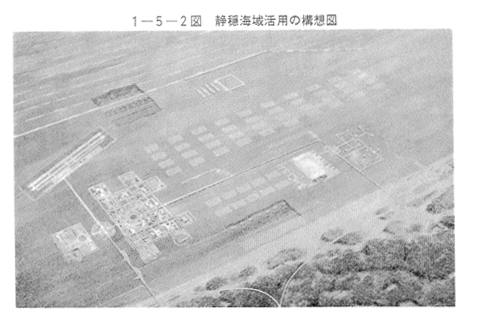
(沖合人工島構想の事業化)
また,運輸省で従来から検討を進めてきている沖合人工島構想については,これまでの成果等をもとに,地方公共団体等による沖合人工島計画策定のガイドラインとなる計画指針の作成を進めている。今後は,この計画指針をもとに,地方公共団体における沖合人工島計画を聴取して,その中から海域を選びフィージビリティスタディを行い,事業の推進を図っていくこととしている。
(海洋の開発・利用を支援する技術の開発)
今後の海洋の開発・利用の推進のためには,波浪等の厳しい自然条件を克服するための技術開発が必要であり,運輸省では,港湾整備等で培われた海洋土木技術及び世界をリードしてきた造船技術を結集することにより,これらの技術開発に取り組んでいる。
海洋空間の一層の有効利用を図るため,前節において述べたマルチセルラー式防波堤,軟弱地盤着底式防波堤等の開発を進めるとともに,耐久性,耐低温性に優れ,鋼とコンクリート両者の利点を併せ持つハイブリッド海洋構造物の開発を進めている。
このほかに,北極圏の豊富なエネルギー資源の大量輸送手段として氷海域でも航行可能な氷海可航型船舶の研究を行っている。
(3) 海洋性レクリエーションの振興
(海洋性レクリエーションの普及・発展)
海域利用への要請が多様化・高度化するとともに,生活水準の飛躍的向上,余暇時間の増加等を背景として国民の余暇活動は活発化・多様化してきており,このようななかで海洋性レクリエーションは急速に普及・発展してきている 〔1−5−3図〕。海洋性レクリエーションに対する国民のニーズは高く,海を活用した地域振興方策の一つとしての期待も大きいため,今後,その普及・発展は更に進むものと考えられる。
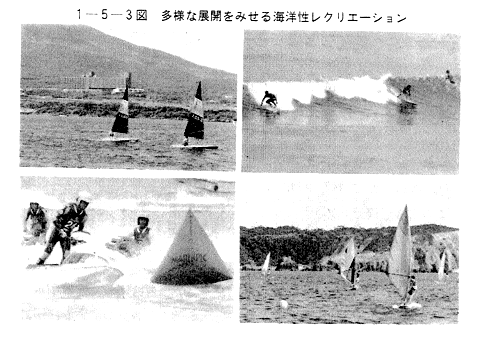
(海洋性レクリエーション振興のための施策の推進)
運輸省では従来から,公共マリーナ,港湾緑地,人工海浜,観光レクリエーション地区等の整備による海洋性レクリエーションの環境作り,船舶検査,海技資格免許,安全指導等による安全の確保,海難救助,気象・海象等の情報提供など海洋性レクリエーションに関する多面的な業務を推進してきているが,今後の海洋性レクリエーションの普及・発展に対応し,その健全な発展,振興を図るため,ハード・ソフト両面からのバランスのとれた総合的な施策の推進が必要である。このため,海洋性レクリエーションに関する普及・啓発活動の推進,関連産業の育成とともに,海洋性レクリエーションの環境作り,関連情報の収集・提供,安全の確保等を今後,更に進めていくこととしている。
|