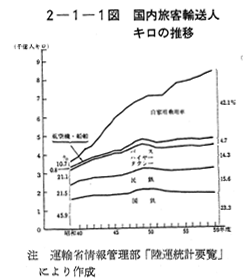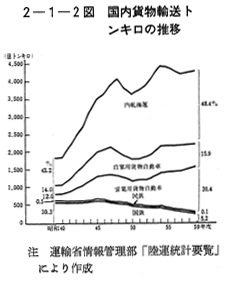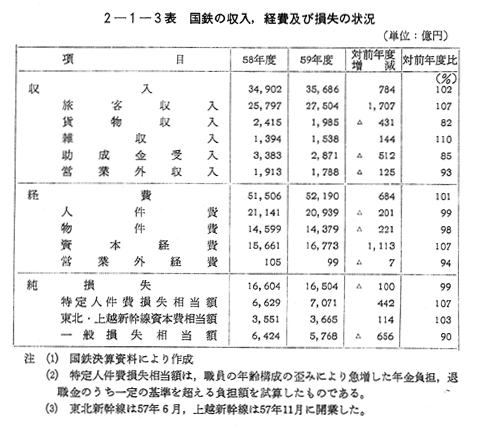|
1 経営の現状
(1) 輸送の動向
(国鉄のシェアの低下-旅客23%,貨物5%)
国鉄は,昭和24年に公共企業体として発足して以来,基幹的輸送機関として我が国経済の復興と高度成長に大きな役割を果たしてきた。
産業構造の変革,各種交通機関の発達等国鉄をめぐる状況が変化する中で,旅客輸送については,49年度の2,156億人キロをピークに,50年度以降57年度までは減少傾向に転じた。58年度の輸送量は東北・上越新幹線の通年営業の効果等により微増し,59年度においても,運賃改定が行われたにもかかわらず,定期旅客の増加等により1,942億人キロと2年連続して増加(0.7%)したが,国鉄の旅客輸送量のシェアは40年度に46%であったものが,59年度は23%へと低下している 〔2−1−1図〕。
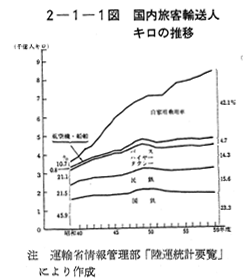
また,貨物輸送量については,45年度の624億トンキロをピークとして逐年減少を続けている。59年度の輸送量も,59年2月のダイヤ改正においてヤード系輸送システムから拠点間直行輸送システムヘの転換を実施したことにより,車扱貨物が大幅に減少(対前年度比32.3%減)したほか,コンテナ貨物が増加(同19.7%増)したものの車扱貨物からの転移が十分に図られなかった結果,全体では227億トンキロ(同16.1%減)となり,そのシェアは40年度に30%であったものが,59年度は5%となるに至っている 〔2−1−2図〕。
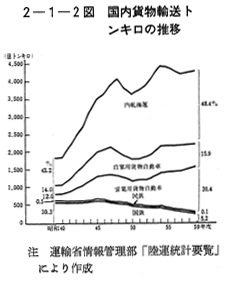
(2) 収支状況
(増え続ける累積欠損額と長期債務)
以上のような輸送需要の動向の中で,国鉄の経営は39年度に単年度赤字を生じて以来,輸送量の伸悩みと運賃値上げの遅れ等から収入の増加が得られず,一方でこれに対応する経費の縮減が図られなかったことから,各年度の欠損額は次第に増加し,41年度に利益積立金取崩し後繰越欠損を生じ,46年度には償却前赤字を生ずるに至った。51年度及び55年度に債務の一部棚上げ等の措置が講じられたにもかかわらず,長期債務の利子の負担増のほか,国鉄職員の年齢構成の歪みから生じる退職金,年金負担の増大が近年に至って顕在化したこと等もあって,経費節減のための各種施策が講じられているものの,毎年度の欠損額はこの数年1兆円を超えている。
59年度においては,収入は,58年度に比べ,貨物収入が431億円減少したが,旅客収入及び関連事業収入等で1,851億円増加し,784億円増の3兆5,686億円となった。一方,経費は,要員合理化,節減努力等によって人件費,物件費合わせて422億円減少したものの,利子及び債務取扱諸費が1,140億円増加したことにより,684億円増の5兆2,190億円となった。その結果,純損失は,5年ぶりに前年度より減少(100億円)したが,依然として1兆6,504億円という巨額に達している 〔2−1−3表〕。
この結果,59年度末の累積欠損(特別勘定を含む。)は12兆2,754億円に,また,長期債務残高(特別勘定を含む。)は21兆8,269億円に上っている。
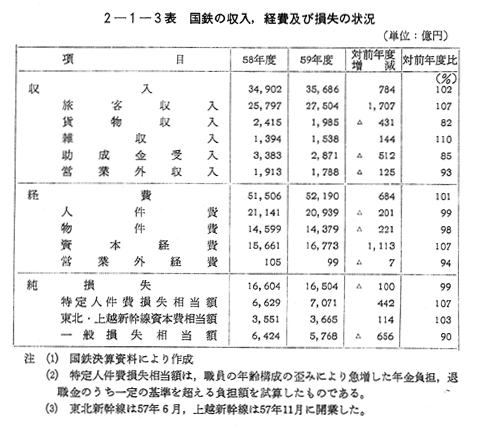
|