|
2 現在の経営形態における再建対策
(日本国有鉄道経営再建促進特別措置法に基づく再建対策)
運輸省及び国鉄は,当面する国鉄の経営悪化を極力防止するとともに,効率的な経営形態の確立の円滑化に資する観点から,再建監理委員会の各種提言を踏まえつつ,経営改善計画等に基づき緊急対策をはじめ所要の施策を積極的かつ強力に推進してきたところである。今後,新経営形態への移行までの間,「意見」の趣旨に沿って引き続きその推進を図っていくこととしているが,その概要は次のとおりである。
ア 職場規律の確立
臨時行政調査会をはじめとする国鉄再建に関する論議の高まりを契機として,職場規律の乱れが国鉄の正常な業務運営を著しく阻害しているとの指摘が相次ぎ,世論の厳しい批判を招いた。 このような状況にかんがみ,国鉄は,運輸大臣の指示の下に,57年3月以降60年3月の総点検まで半年ごとに7回にわたる総点検を実施し,職場規律の是正と定着化に努力した結果,ヤミ休暇,ヤミ手当の完全解消,現場協議制度の改定等全体としては職場規律の是正が進んでいることが報告されている。しかしながら,60年3月の総点検結果をみると,点呼,ワッペン,氏名札等特定の項目の改善がはかばかしくなく,また,飲酒も59年10月の飲酒による西明石駅の脱線事故を契機に指導を行ったにもかかわらず,根絶されていないなど,いまだに職場規律が定着しているとはいい難い状況にある。このため,運輸省としては,未是正項目について管理者・職員の意識を更に喚起する等により,職場規律の確立に万全を期することとしている。
イ 余剰人員問題
国鉄における余剰人員問題は,輸送量の減少下における一層の要員合理化の必要性と退職者の減少傾向を背景として生じてきたものであるが,国鉄事業再建の成否にかかわる重要な課題であり,是非とも解決しなければならないものである。 国鉄は,59年8月に余剰人員対策委員会(60年6月には余剰人員対策推進本部に改組)を設置し,余剰人員対策として特別改札等の増収活動,外注作業の一部直営化等による経費節減,教育の充実,直営店舗の開設等の活用策を立てて取り組んでいるが,余剰人員の規模及び見通しを勘案し,これらの活用策に加えて有効な雇用調整策を講じていくことが必要であるとの判断に立って,休職及び派遣制度の拡充を59年10月から実施し,さらに勧奨退職を促進するための退職制度の見直しを行った。 この結果,退職者数約30,000人,休職者数約1,000人,派遣者数約2,500人の実績(60年4月1日現在)をあげたが,60年度首の余剰人員は,合理化の進捗に伴い前年度より1,000人増加し,25,500人となっている。 運輸省においては,第2次緊急提言の趣旨に沿い,当事者である国鉄に対し,雇用調整策を確実に実施するとともに,これに引き続く対策を検討するよう指示し,さらにその進捗状況を踏まえつつ,60年7月には,臨時行政調査会第3次答申後の57年9月に事務次官を本部長として設置された国鉄再建緊急対策推進本部(60年7月,国鉄改革推進本部に改組)の決定により国鉄の余剰人員対策を支援しその促進を図るため,運輸省職員の採用に当たって国鉄職員からの採用について十分配慮するとともに,所管の関係法人,事業者等に対し国鉄職員からの採用及び出向の受入れを要請することとし,現在,国鉄職員の受入対策を推進している。 この問題は,「意見」の中で国鉄事業再建に際して解決すべき諸問題の重要な柱として位置づけられているものであり,国鉄改革実現のためにも,新経営形態移行前において再就職先の確保,退職時の給付の特例措置等所要の施策を講じた上,希望退職募集を行うことにより極力余剰人員の削減を図っていく必要がある。
ウ 事業分野の整理
(ア) 貨物輸送
国鉄の貨物輸送については,ヤード系輸送のサービス水準が低いこと等により,他の輸送機関への転移が進み,近年,大幅に減少しており,59年度の輸送量はピーク時(45年度)に比べ63.6%減の227億トンキロとなっている。また,収支も59年度収入2,096億円に対し,支出8,114億円となり,6,018億円に上る赤字を生じている。 このように,貨物営業は国鉄全体の経営悪化の大きな要因となっており,これに対処するため,大量・定型という鉄道特性を発揮し,かつ,市場のニーズに適合した輸送を提供できるよう,59年2月のダイヤ改正においては,非効率なヤード系集結輸送から,拠点間直行輸送システムへ転換するとともに,貨物取扱駅の再編成を行った。さらに,60年3月のダイヤ改正においても,その深度化を図り,車扱直行列車の大幅削減,営業線区,貨物取扱駅の一部廃止等を行い,これにより,60年度における固有経費での収支均衡の実現をめざすこととしている。しかしながら,59年度の貨物輸送量をみると,一般車扱貨物からの転移を見込んだコンテナ及び専貨物資が計画どおりに確保できなかったこと等貨物輸送をめぐる状況には極めて厳しいものがある。 このような状況を踏まえ,「意見」においても,鉄道貨物輸送がその特性を発揮し得るためには,旅客部門から分離し,基本的には全国一元の経営体制とすることが適当である旨の提言がなされており,今後,この提言の趣旨に沿って,国鉄貨物輸送に関する抜本的対策を早急に樹立することが必要である。
(イ) 地方交通線対策
地方交通線については,59年度においても,駅の停留所化,貨物取扱駅の再編成等,積極的に各種の合理化施策が講じられたが,特別交付金857億円の助成後においてもなお5,264億円の損失を計上した。地方交通線は,輸送量(人トンキロ)で全体の4%,助成後収入で全体の6%を占めるに過ぎないにもかかわらず,経費では14%,損失では33%を占めており,国鉄経営の大きな負担となっている。このため,収支の改善を図るためには更に徹底した合理化努力を行うとともに,地方交通線の中でも輸送需要が極めて少なく,国民経済的にみても鉄道による輸送に代えてバス輸送を行うことが適切な路線であるいわゆる特定地方交通線については,地域における効率的な交通体系を形成し,地域交通を確保する観点からも,「意見」に沿って,バス輸送等への転換を図っていく必要がある 〔2-1-4図〕。
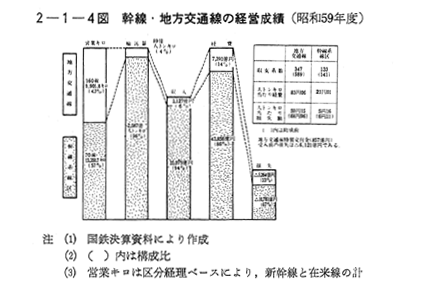
56年9月に選定承認された第1次線40線730キロについては,協議中断中の3線を除き,既に32線が転換を完了し,5線がその方向付けがなされている(60年10月末現在)。転換済みの32線のうち,白糠,日中,赤谷等の22線が民営あるいは公営のバス輸送へ,また久慈,盛宮古等の10線が第3セクターあるいは民間事業者による地方鉄道へそれぞれ円滑な転換が行われている。
エ 業務の効率化
国鉄における要員合理化は,経営改善計画に基づき,実施されているが,59年度の収入に対する人件費の比率は,前年度の大幅な要員縮減の効果により,対前年度4%減となり年度予定の59%を達成したものの,依然として高いものとなっている。 59年5月,前述のとおり経営改善計画を変更し,60年度の要員規模を35万人から32万人に改めたが,59年度においては,現下の厳しい状況にかんがみ,引き続き新規採用を原則停止したほか,60年3月のダイヤ改正において動力車乗務員の運用効率化及び旅客駅体制の見直し,保守部門の各種合理化,直営医療機関の近代化等業務全般にわたり徹底した合理化施策を推進し,計画を6,000人上回る31,000人の要員合理化を実施した。 また,60年度首の予算人員も計画目標32万人に対し5,000人減の31万5,000人となった。60年度においても,新規採用の原則停止を継続するとともに,各部門における近代化,合理化を推進し,30,500人の要員合理化を計画している。 しかしながら,国鉄事業の再建のためには,私鉄並みの生産性を前提とした効率的な要員配置とすることが不可欠であり,新経営形態への円滑な移行を図るためにも,今後,業務運営方式そのものの見直しをはじめとして,職員の多能的運用,業務量に見合った要員配置及び作業体制の見直し,実作業時間の改善等徹底した効率化を進めていく必要がある。
オ 運輸収入の確保
国鉄の運賃については,再建監理委員会の提言をも踏まえ,59年4月の改定時に,旅客運賃につき明治以来とってきた全国一律運賃制度を改め,大都市圏は幹線に比べ上げ幅を抑制し,地方交通線は6.5%増の割増運賃とする地域別運賃制度を導入する等の措置を講じたが,60年度においても,債務増大を抑制し,収支悪化を防止する観点から,平均4.3%(旅客関係4.4%,貨物関係3.1%)の運賃改定を行った。この改定において,旅客運賃については,引き続き大都市圏運賃や特急料金の近距離,遠距離の上げ幅を抑制するなどの措置を講じたほか,通学定期割引については,その割引率が71.3%と大きな割引となっていたことから,9月から1%引き下げることとした。一方,貨物運賃については,60年3月のダイヤ改正に対応して,車扱貨物のコンテナ輸送への転移を促進する等の見地からコンテナ貨物運賃は据え置くこととし,また,荷物運賃については,民間宅配便が採用している地域区分等を勘案しつつ,従来の6地帯制を12地帯制に改めることとした。このように今回の運賃改定は,他の輸送機関との競争関係等に配慮した内容となっている。 他方,営業面においても,新規需要の開拓,潜在的な輸送需要の喚起を図るなど,積極的な営業努力により全体として輸送量の維持増大に努めることが重要であり,現在,旅客輸送ではフルムーンパス,Qきっぷなどの企画商品の開発販売,「エキゾチック・ジャパン」キャンペーン,また貨物輸送では車扱貨物のコンテナ化,コンテナ適合貨物の新規開発などの増収施策を展開しているところである。このような各種施策の展開とも相まって,59年度の旅客収入は,旅客輸送量の伸びを反映し,対前年度7%増の2兆7,504億円となっている。今後とも,輸送市場の動向,利用状況等に十分配慮したきめ細かな運賃設定,積極的な増収努力により,運賃収入の確保,増収に努める必要がある。
カ 関連事業・資産処分
国鉄は,経営改善計画の55年度から60年度までの収入目標5,000億円の確保をめざして,積極的に関連事業を展開してきたが,59年度は前年度に引き続き,駅ビル・ホテル事業,地上権付分譲住宅等の開発を行うとともに,新たに電気通信事業へも投資を行った。また,駅構内等において,直営店舗204店の開設を行い,余剰人員の活用と関連事業収入の拡大を図った。以上の結果,関連事業収入は対前年度比11%増の921億円となり,55年度からの累計で3,685億円となった。今後も,増収施策の重要な柱として創意工夫を行いつつ関連事業収入の増大を図っていく必要がある。 資産処分については,59年度において1,531億円の用地の売却を行った結果,55年度からの累計で4,721億円となり,経営改善計画の60年度までの資産売却6,000億円の目標は達成できる見込みとなった。 また,国鉄用地の有効活用については,前述(P.31)のとおりその促進について検討が進められている。 今後も,「意見」に沿って,長期債務等の適正な処理の観点から事業用用地と非事業用用地との仕分けにより売却可能用地の生み出しを積極的に行うとともに,当面必要な収入の確保,国有地への民間活力の導入等の観点も踏まえつつ適正な処分,活用を図ることとしている。
キ 設備投資の抑制
設備投資については,国鉄の経営悪化に伴い,その効率化,重点化が図られてきたが,国鉄の経営が赤字基調に転じて以後,政府からの助成のほか財源を外部資金に依存して行われてきたことから,借入金の累増に伴う利子負担が経営の大きな圧迫要因となっている。 このため,安全確保,老朽施設取替等緊急度の高い投資を除き,原則として設備投資を抑制してきており,その結果,56年度まで毎年1兆円を超えていた投資規模は逐年圧縮され,59年度の実績は6,493億円(対前年度1,020億円減)となっているが,この中には60年3月の上野開業に向けた東北新幹線上野・大宮間の建設(1,078億円)及びこれと一体施工の通勤別線の建設に対する設備投資(667億円)が含まれている。60年度予算では4,329億円(対前年度予算1,335億円減)となっており,今後とも,国鉄の厳しい経営状況にかんがみ,設備投資を極力抑制する方針であるが,その際,限られた設備投資資金の有効活用を図るため規格・標準等の見直し,工事施工方法の改善等により工事費の圧縮を図るとともに,新経営形態への円滑な移行に必要な工事の実施にも留意していくこととしている 〔2-1-5図〕。
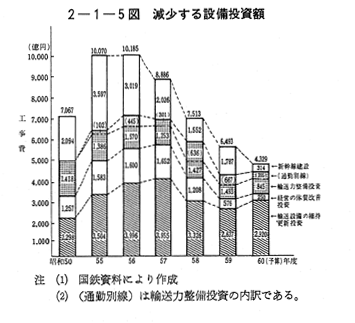
|