|
(1) 米国
日米間の国際運輸市場は,航空分野においては年々輸送需要が拡大しており,59年度における日米間の定期航空旅客数は500万人に近づき,その日本発着旅客数に占めるシェアも約30%となっている。海上輸送量についても,カナダを含む北米への輸出が増加しており,我が国の全輸出海上輸送量に占めるシェアは58年の約14%から59年には20%弱へと増加している。日米間の国際運輸関係の現状を示したのが 〔3−1−1図〕である。これでみると,日米間の海上輸送量は我が国の全海上輸送量の10%を超えるシェアを占め,定期航空旅客数のシェアが高いことと併せ我が国との結付きの強さがうかがえる。
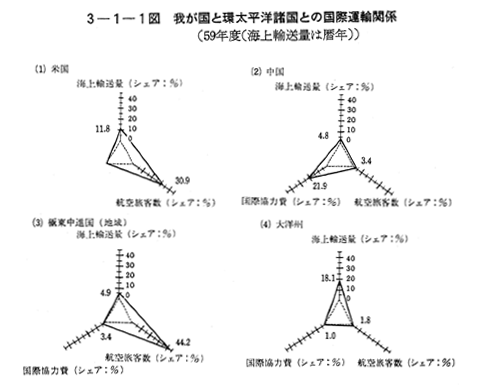
米国は,53年以降,航空の自由化政策を推進してきたが,この政策は,米国の航空業界を刺激しただけでなく,欧州にもその影響が波及し,59年に英-蘭,英-西独間で二国間航空関係を極力自由化することが合意されるなど欧州内においても国際航空の自由化が進められてきている。外航海運の分野においても,定期船海運に関する競争促進政策が59年の米国新海運法の成立という形で実施された。同法は59年6月から施行されたが,これにより北米関係航路における定期船同盟の運賃調整機能は一層低下することとなり,その結果北米航路の競争は激化し,日本のみならずヨーロッパ諸国の海運活動に多大の影響を及ぼしている。
|