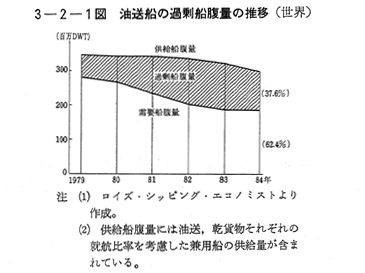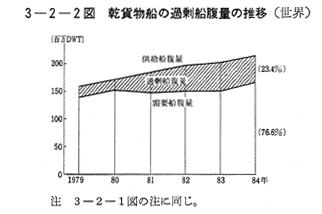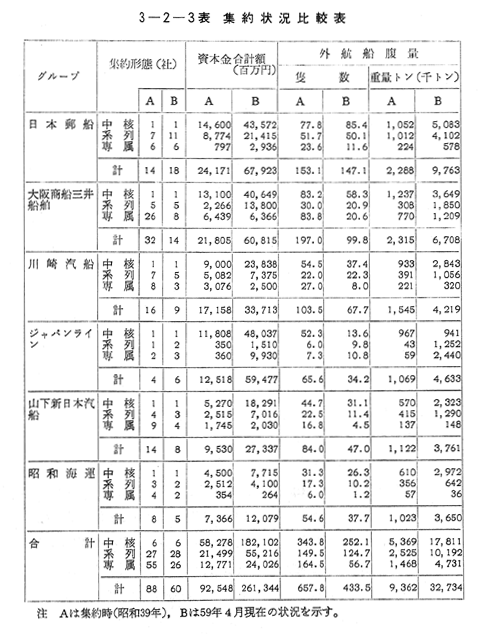|
1 外航海運
(1) 厳しさを増す国際環境
(我が国海運の活動の場の制約)
海運不況とともに,我が国の海運業界を困難な状況においているのが国際環境である。我が国は,外航海運市場を完全に外国船に開放しているが,多量の国際海上貨物を有しながら,同様の政策をとっている国は,英国を初め一握りの国に過ぎず,海運取引の制限を維持している国が大部分である。
特に我が国を取り巻く発展途上国のなかには,自国船に貨物を留保したり,政府貨物を自国船に積む政策をとったりする国がある。また,定期船同盟行動規範条約に定期船同盟内の輸送配分についての規定があることを根拠に,自国関係貨物全般について,このような輸送配分をすることに応じない国の海運企業に対しては,自由に横取活動をさせないという政策をとる国もある。また,保有船腹量で世界第5位と第9位を占めるソ連や中国のような国営貿易国は,荷主国としての立場が強く,かつ,海運企業も国営の強みがあるため,商業ベースでこれらの国の海運と競争することは,制度的に困難な面がある。
この1年の間に,我が国は,他の先進国とも協調して,各国政府が上記のような形で海運取引に干渉することを改めるよう努力してきた。その結果,インドネシアにおける貨物積取許可制度の廃止や,フィリピンからの木材輸送における邦船の参加を制限する政策に若干の方針変更がみられたことなどの進展があったことは喜ばしいことであった。しかし,全般的にみると,我が国海運企業が自由に海運取引を行うことができる海上貨物の範囲は減少の傾向にあり,我が国の外航海運の活動の場が減少していくという意味で,深刻な事態に直面している。今後とも,我が国海運企業が不当に不利益な取扱いを受け,その利益が著しく害される場合は,所要の対抗措置の発動を真剣に検討する必要がある。
(他の先進国の制限措置に対する対応)
先進国の中でも,例えば,自国の政府貨物は自国の船社に優先的に船積みするとか,発展途上国の一部とシェア協定を結ぶというような海運取引の制限をしている国がある。今後このような取引の制限が拡大しないように,過去に取られた制限はそのままにして,新たな制限はしないようにする約束をしょうとする動きがあるが,定期船海運の競争条件をそろえるという観点からも,また,発展途上国の制限措置に抗議していく上でも,首尾一貫しない考え方であろう。
(米国船の活動保証を求める米国)
また,米国は,日本が加入を準備中の定期船同盟行動規範条約に加入すると,事実上日本と近隣諸国との間の市場が閉鎖的になるとして,日本が同条約に加入する際には,日本関係の航路において米国船の活動を保証することを強く求める一方,これを日米経済摩擦の一つとして提起するなどの動きがある。我が国としても,同条約についての加入の時期及び方法を決定するに当たってはこのような主張に十分注意を払いつつ,同条約についての我が国の立場を米国に十分に説明しながら,我が国の海運市場開放の政策を維持していく必要がある。
(運航を脅かすイ・イ紛争)
また,イラン・イラク紛争は,日本関係船舶の安全運航を脅かしている。昭和60年2月,クウェイト籍コンテナ船「アル・マナク」が被弾し日本人船員1名が死亡したことは,いたましい出来事である。日本政府は,関係国に日本関係船舶の安全確保について申入れを行うとともに,民間に対しては,船舶運航の安全対策を強化するよう指導している。
(2) 国際競争の激化と日本船の国際競争力の低下
(北米関係航路の競争激化)
日米間の定期船同盟は,米国の独占禁止政策に立脚した新海運法により,その運賃調整機能を一方的に低下されたうえ,定期船同盟に参加しないで,低コストを武器に大いに発展してきた韓国,台湾,香港,シンガポールの海運の追上げもあって,我が国定期船海運は,日米間定期航路の運営に苦闘している。また,定期船運賃の不安定さの度が過ぎると荷主に対する安定したサービスが維持されないという問題が生じ得る。
我が国としては,日米両国の法制の調和を図り,航路の健全な発展を図るため,日米間で頻繁に協議の機会を持っている。現在,比較的に多量の貨物を提供する荷主のために貨物の数量に応じて運賃を割り引く制度の導入を認めるとともに,小口荷主の利益保護のために,全ての貨物を海運同盟に積む荷主に対しては,貨物の量に関係なく,一定の運賃を割り引くフィデリティ・コミッション・システムという運賃制度を創設すべく,米国当局と協議を進めているが,いまだ解決に至っていない。
日米の定期航路の今後の先行きは,新しい米国海運法の運用が行き過ぎると健全な航路の経営が行えない事態になるのではないかと憂慮されている。
(国際競争力の低下と便宜置籍船問題)
他方,我が国海運が擁する日本船の国際競争力の低下の傾向は,ますます強まってきており,特に中小型船においては,その傾向が顕著である。雑貨,南洋材や鋼材を近隣諸国との間に輸送している近海船については,これを維持していくことができるかどうかという深刻な事態に至っている。
日本の海運が日本船とともに支配している便宜置籍船は,このような事態に対し日本海運のコストを全体として引き下げる役割があると位置付けられているが,国際的には,便宜置籍船を段階的に排除していくべきであるという意見も根強い。59年7月から3度にわたってジュネーブで開催されている船舶の登録要件に関する国連主催の全権会議は,この問題について,船舶の登録要件の面から船員配乗,船舶所有,船舶経営について国際ルールの統一を図りつつある。すなわち,船員の配乗については,旗国の船員供給の状況,船舶の国際競争力に留意しながら,原則としては,船舶に配乗する船員の一部は旗国民とすること,船舶の所有については,旗国の個人または法人が所有すること,船舶の経営については,船舶所壱会社が旗国の法令に基づいて設立されておらず,旗国に本店もない場合には,船舶に係る責任について財務的にも船主を代表し得るような代表者を置くことについてはほぼ基本的な意見の一致をみた。このように長年協議を続けてきたこの問題について,全参加国が支持できそうな内容で国際合意が成立する可能性が出てきたことは,明るいニュースである。
(3) 外航海運不況の状況
ア 総説
59年の世界経済は,OECD諸国の実質経済成長率が,58年の2.7%に対して,59年は4.9%となるなど,米国の景気拡大をけん引車にして,前年に引き続き景気の回復が進んだ。このような状況の下に,世界の海上荷動き量も54年以来5年ぶりに前年比で増加した(トン数で5.7%増,トンマイルで3.8%増)。しかしながら,世界の外航海運業は,特に油送船部門・不定期船部門における相当量の船腹過剰状況,発展途上国の外航海運企業の参入による競争激化,定期船部門では米国新海運法(1984年6月発効)の影響等により,全体として苦しい経営を強いられている。
イ 油送船部門
世界の石油荷動き量は,二度にわたる石油危機の影響による石油需要の減少,北海,ラテンアメリカ等石油供給源の多様化により,トンベースでは54年を,トンマイルベースでは52年をピークに減少しており,59年の荷動き量はトンマイルベースでピーク時の48%,トンベースでもピーク時の69%にとどまっている。
このような石油の荷動き量の減少により,60年6月現在,係船船腹量は5,314万重量トン(全油送船船腹量の21%)となっており,大幅な需給のアンバランスの状況が続いている 〔3-2-1図〕。
こうした状況の下で,油送船の市況は近年低迷を続けており,特に15万重量トン以上の大型油送船の運賃指数(ワールドスケール)は,船費・運航費をカバーする採算点がおおむね40であるといわれているのに対し,60年5月現在,25.5と採算点を大幅に下回っており,厳しい運賃市況が続いている。
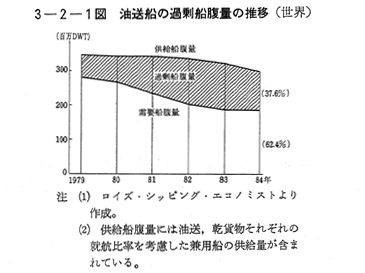
ウ 不定期船部門
世界の乾貨物の荷動き量は,トンベース,トンマイルベースとも57年以降減少に転じていたが,59年はトンベースで対前年比8.5%増,トンマイルベースで対前年比7.7%増となり3年ぶりに増加したものの,10年前の49年に比してトンベース,トンマイルベースとも約1.3倍の伸びにとどまっている。
しかしながら,ばら積貨物船の船腹量(1万重量トン以上の船舶)は50年代を通じて一貫して増加しており,.49年の8,900万重量トン(2,781隻)から60年初には1億8,800万重量トン(4,856隻)と約2倍に達している 〔3-2-2図〕。このような荷動き量の増加を上回る船腹量の増加により,不定期船運賃指数(航海用船)は,一時的な好況を示した55年及び56年を除き低迷を続けており,55年末のピーク時を100として60年7月で67と,かろうじて船費・運航費をカバーするといわれるほどの低い水準にとどまっている。
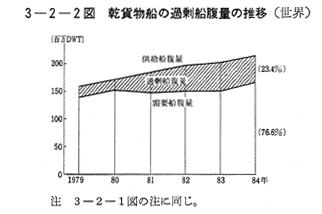
エ 定期船部門
我が国の定期船貿易量は,コンテナ船の輸送量の伸びに支えられ年々拡大してきているが,我が国商船隊は,積取り比率の低下に悩む状況となっている。59年度における我が国定期船貿易量をみると,全体量が7.7%の伸びを示したのに対し,我が国商船隊の輸送量は横ばい,運賃収入は2%増にとどまった。これは,近年における台湾,香港,シンガポール等の極東中進国(地域)の海運企業の日本・極東~北米航路への参入による競争激化のほか,運賃・サービス面での船社間の自由な競争を促進する米国新海運法の影響により,例えば繊維製品の日本/北米太平洋岸向け同盟運賃が新法施行前の59年4月と比較して60年9月現在で12.5%低下するなど,運賃が下落傾向にあること等に起因するものと考えられる。
オ 我が国外航海運企業の経営状況
(依然厳しい損益状況)
近年の海運市況の低迷は,上述したように世界的な海上荷動き量の低迷,船腹量の過剰状況のために,長期化して極めて深刻な様相を呈しており,このような中で我が国海運企業の経営内容も極めて厳しいものとなっている。
近年の外航海運企業の損益状況を大手海運企業10社(資本金規模での上位10社)についてみると,56年度に10社合計で693億円の経常利益を計上したが,その後,世界的な荷動き量の減少等により三部門(油送船,不定期船,定期船)同時不況の状態となったため,57年度からは経常損失を計上する状況となり,59年度は279億円の経常損失となった。
その内容をみると,油送船主力の2社の赤字幅が大きく,また,10社中配当実施会社が5社しかないなど厳しい経営状況になっている。上記10社以外の運航主力企業や貸船主力企業にあっても,経常損失を計上する企業が多くなっている。
このような厳しい経営状況を打開していくためには,市況低迷の原因となっている世界的な船腹過剰状況を解消することが急務となっており,我が国海運産業においても,近代化船の整備等商船隊の国際競争力の回復を図るための対応等と併せ,老朽・不経済船の解撤促進による減量化を強力に進めていく必要がある。
(三光汽船(株)が会社更生法に基づく更生手続開始の申立て)
近年の厳しい海運市況のもとで,油送船主力大手企業である三光汽船(株)は,60年8月に会社更生法に基づく更生手続開始の申立てを行うに至った。
同社は,世界的な石油荷動き量の減少,運賃市況の低迷等により,58年3月期から60年3月期の各期決算において500億円を超える経常損失を計上し,油送船偏重型船隊構成からの転換を図るためのハンディサイズのばら積貨物船の整備等についても厳しい市況の中で経営改善のための効果を上げ得ない状況となっていた。
運輸省としては,同社の更生手続開始の申立ての事態に対し,我が国外航海運の国際的信用を傷つけることのないよう関係者が適切に対処することを強く要請した。
三光汽船(株)の会社更生法による再建は裁判所の判断に待たなければならないが,再建のためには同社挙げての努力はもとより,関係者の協力支援が不可欠となっている。
(4) 海運造船合理化審議会答申
(今後の外航海運政策のあり方を答申)
我が国外航海運は,現在,前述のように海運秩序をめぐる国際的な動きが複雑に変化しつつあるなかで,日本船の国際競争力の低下,船員問題,海運企業経営の悪化等の構造的問題に直面している。このような状況にかんがみ,今後の我が国外航海運のあり方について,中長期的視点に立って抜本的な検討を加えるため,59年4月,運輸大臣より海運造船合理化審議会に対し,「今後の外航海運政策はいかにあるべきか」について諮問した。同審議会では,59年8月に,近代化船を増強して商船隊の中核とし,外国用船等各種船舶を組み合わせて,国際競争力ある商船隊を構成すること,海運企業経営の活性化,合理化を促進するため,国の諸規制の見直し,緩和を図ること等を内容とする中間答申を行い,さらに,60年6月に海運集約体制・定期航路運営体制に関する規制緩和等に関して最終の答申を行った。以下は,最終の答申の概要である。
ア 今後の海運企業体制
(問題が生じてきた海運集約体制)
(ア) 39年に確立された海運業の集約体制は,外航海運企業の企業規模の拡大と投資力の充実等に役立ち,海上輸送の安定的確保に大きく貢献してきたが,爾来20年を経過し,集約参加企業の実質的な企業関係の変化等が生ずる 〔3-2-3表〕とともに,海運施策上も集約参加企業と不参加企業に対する取扱い上の差異が徐々になくなってきた。また,企業間の関係を長期にわたり行政の基準によって維持することが行われてきたため,経営の自主性や活力ある企業経営が抑制される面があること等の問題点が生じている。
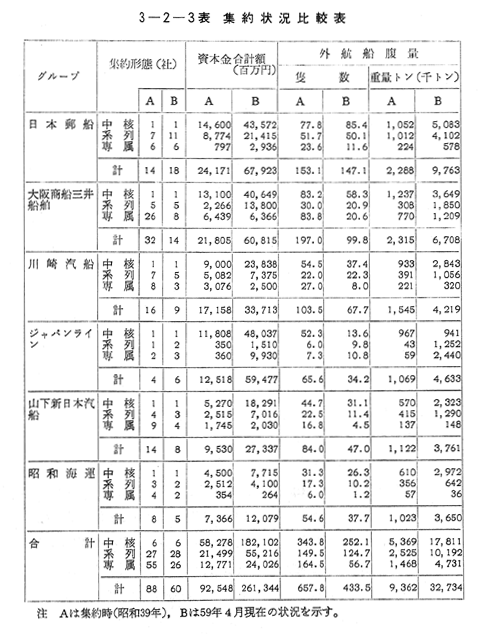
(それぞれの事情に応じた企業関係の形成)
(イ) 今後,厳しい国際場裡で将来にわたって国際競争力のある日本海運を維持していくためには,個々の企業の経営の自主性の発揮と経営の活性化を図ることがより重要な課題である。このためには,従前のような行政規制は極力少なくしていくべきであり,民間において,自律的に合理的な活力ある海運企業体制が形成されていくことが望ましい方向である。これに伴い,外航海運業における競争秩序の形成のため,企業経営者自らの良識と責任ある行動がより強く期待されることとなる。
このような観点から,集約体制に関する規制を緩和し,今後は,当該企業の自主性と責任に基づき関係企業間の十分な話し合いによってそれぞれの事情に応じた企業関係が形成されていくことが認められることとすべきである。
行政においては,企業間の関係に問題が生じた場合に,必要に応じて,その円滑な解決が得られるよう関係当事者に助言と指導を与える等の適切な対応が行える態勢を整えておく必要がある。
イ 今後の定期航路運営体制
(ア) 郵船社間のスペース・チャーター制は,邦船社間の提携,協調の強化による過当競争の排除をうたった41年及び44年の本審議会の答申を受けてとられてきた。しかしながら,このスペース・チャーター制については,邦船各社の創意工夫をしにくくする面が見受けられるようになり,米国新海運法の改正による状況の変化もあって日本/極東~北米定期船市場において,航路運営上適切でない面が多くなった。
(イ) そこで,41年及び44年の本審議会の定期航路運営体制に関する答申は一たん白紙に戻し,基本的には,邦船社の自己の経営責任による多様な企業努力を最大限に尊重する方向をとることとし,迅速な意思決定,荷主ニーズヘのきめ細かい対応等の利点を有する単独運航も新たな選択肢として考慮する。また,船社の状況,航路の状況によって,単独運航が事実上不可能で何らかの形の共同運航方式を採用する場合にも,パートナーの選択,実施方法等について,自由な商業ベースの企業判断によることを可能にするよう弾力化を図る。
ただし,航路秩序が不安定で競争の激化が見込まれることから,今後とも邦船社相互間の基本的な理解と信頼を基礎とし,自律的に過当競争を排除することも極めて重要である。
ウ 国際的課題への対応
海運秩序をめぐる国際的な動きが複雑に変化しつつあるなかで,我が国外航海運が今後とも我が国経済社会において十分な役割を果たし得るよう海運自由の原則を基礎としつつも,環境の変化に対応し,安定的な国際海運秩序の形成に努めて行く必要がある。
また,世界の船腹過剰問題への取組みのなかで,我が国における船舶の解撤の促進を図るとともに,関係者が協力して発展途上国等における解撤事業に対する技術協力等を進めるなど船腹過剰問題への対応策を推進する必要がある。
(5) 答申後の動き
ア 中間答申を踏まえた海運施策
59年8月の海運造船合理化審議会の中間答申を踏まえ,以下のような海運施策が実施された。
(ア) 船舶の近代化の促進
近代化船への代替建造を中心とする外航船舶の整備を促進するためのインセンティブとして,60年度予算において,超省力化船の融資比率について,従来より10%引き上げて60%とすることとし,融資規模は,計画造船建造見通し約135万総トンとして開銀融資枠1,000億円が確保された。他方,船舶の改造の融資比率は,60%または50%から40%に引き下げられた。
また,60年度の税制については,特別措置が厳しく見直される状況の中で,近代化船以外の船舶については特別償却率が,15%から14%に引き下げられたが,船舶の近代化の推進の必要性にかんがみ,近代化船の特別償却率については15%から18%に引き上げた。
(イ) 規制緩和
① 配当規制の緩和
外航船舶建造融資利子補給臨時措置法は,利子補給対象海運企業が相当の利益を計上した場合,その一部を国庫に納付する制度を設けている。近年,他産業の企業は,時価発行増資等により,低コストの資金調達を行い,自己資本比率を高めているのに対し,利子補給対象海運企業の場合,同法施行令により対資本金利益率が10%を超えると国庫納付義務が生じたため,1割配当をする場合の負担が欠き過ぎ,証券市場を通じた株式の時価発行増資等による資金調達が事実上困難なものとなっていた。
そこで,外航海運企業経営の活性化を図るため,最近における企業一般の対資本金利益率・配当率の動向等を勘案しつつ,関係政令を60年3月に改正し,国庫納付義務が生じる対資本金利益率を10%超から13%超へ改めることにより,1割配当を容易にし,60年3月期の決算から適用した。
② 報告義務制度の緩和
(事前報告件数は半分以下に減少)
利子補給対象海運企業が一定金額以上の固定資産の取得や投資等を行う場合の報告義務を緩和するため,60年4月に外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則を改正し,事前報告件数を大幅に減少させた。
イ 最終の答申を踏まえた海運施策
60年6月の海運造船合理化審議会の最終の答申を踏まえ,以下のような海運施策が実施された。
(ア) 海運隻約体制に参加した企業間の関係
今後の企業体制について,60年6月に新通達を発出し,海運造船合理化審議会の答申の趣旨に沿って対処することとした。
(イ) 定期航路運営体制の見直し
(企業の経営責任において選択)
また,北米関係定期航路の運営体制については,従来郵船社間のみでスペース・チャーターが行われてきたが,一部邦船社がぬけ出て極東船社との提携によるスペース・チャーターも出現することとなるなど,海運造船合理化審議会の答申の方向に沿って,従来のスペース・チャーター体制の枠にとらわれず,外国の船社との連携,運航グループの再編成,運航方式の合理化等の検討が具体的に進められている。
|