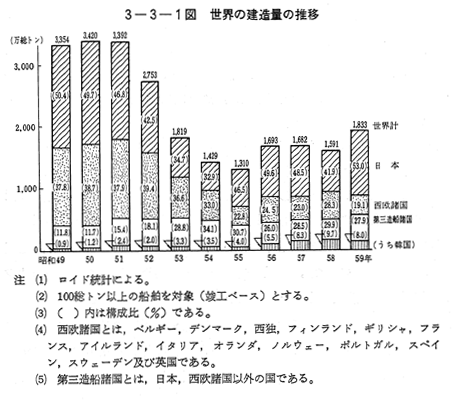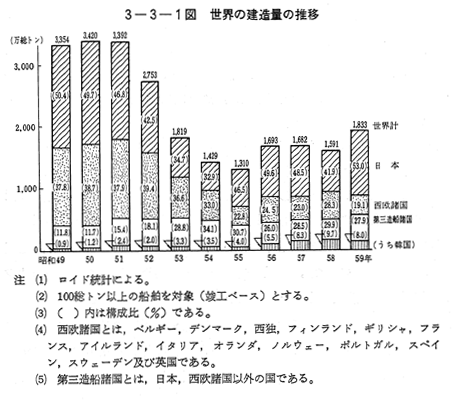|
1 我が国造船業をとりまく国際情勢
(1) 世界の建造量の推移
(西欧造船諸国の衰退と第三造船諸国の台頭)
米国の景気拡大に伴う世界経済の回復基調を背景に,昭和59年の世界の海上荷動き量は減少傾向に歯止めがかかったものの,英国海運総評議会資料によると,59年末現在において3千万総トン程度の船舶が係船されており,依然として船腹過剰状態が続いているため,造船業にとっては厳しい状況が続いている。ロイド統計によれば59年の世界の新造船建造量は,前年のばら積貨物船の発注増により,1,833万総トンと前年に比べ15.2%増加したものの,これはピーク時の50年と比べると1/2程度の水準に過ぎない 〔3−3−1図〕。
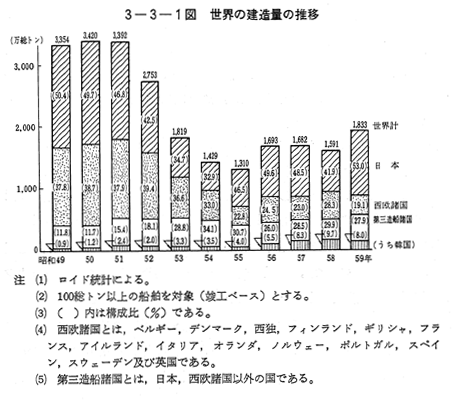
59年の建造量の国別構成比率をピーク時と比べると,我が国はおおむね50%程度のシェアを維持しているが,西欧造船諸国は38.7%から19.1%ヘシェアを半減している。代わって第三造船諸国が11.7%から27.9%ヘシェアを伸ばしており,なかでも韓国は1.2%から8.0%へと著しくシェアを伸ばしている。
このシェアの推移から明らかなように,50年代において西欧造船諸国はその相対的地位を低下させ,代わって韓国を中心とする第質造船諸国が台頭してきており,引き続き造船市況の低迷が予想されるなかで,我が国造船業をめぐる国際情勢はますます複雑かつ厳しくなっていくものと見込まれる。
(2) OECD造船部会の動向
(進められる日欧の対話)
59年度以降のOECD造船部会は第62回(59年4月)から第66回(60年7月)まで計5回開催され,新造船建造需要見通し,各国の造船業の状況及び造船政策等について意見や情報の交換が行われ,相互理解が深められたが,最近は受注シェア,船価,EC諸国の造船助成等の問題が議論の中心となっている。
受注シェアの問題については,西欧造船諸国は我が国の受注シェアが増大しているとして非難しており,これに対し,我が方は,操業調整等を行うことにより対処していると反論している。
船価問題については,西欧造船諸国より,船価引上げの方策をとるよう提案が出されており,これに対し,我が国は既に船価引上げのための努力を行っているものの,船価は基本的には市場メカニズムにより決定されるべきものであり,政府の介入は極力減らすべきであると主張している。
また,EC諸国の造船助成については,今後とも継続されることとなっているが,我が国は,このような助成政策は,企業活力を損なうとともに,OECDの諸取極に反するものであり,早急に廃止するよう求めている。
このほか,OECD造船部会とこれに非加盟の韓国との国際協調を進展させるための方策についても検討が行われている。
(3) 造船における日韓の政府レベル会議
(成長著しい韓国との対話の始まり)
59年は造船について我が国と韓国が政府ベースで対話を始めたという点で画期的な年であった。59年10月,60年3月及び6月と3回の会合(開催場所はそれぞれソウル,東京,ソウル)を重ね,我が国から設備削減,操業調整等の政策を説明し,世界の造船能力が過剰となっているなか,船価水準の低落を防止するために,韓国側も所要の対策を講ずるよう要望した。これにより,韓国との対話の糸口が開かれた訳であるが,今後とも我が国と韓国との一層密接な情報交換や政策調整が必要である。
|