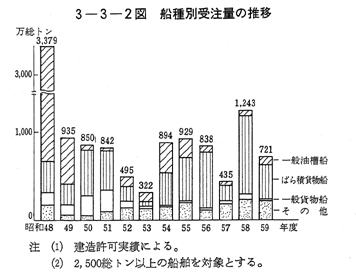|
2 我が国造船業の現状と経営安定化対策
(1) 我が国造船業の現状
(厳しい状況が続く我が国造船業)
59年度の新造船受注量(建造許可ベース)は,前年度比42.0%減の721万総トンと大幅に減少した。これは3隻のVLCC(超大型一般油槽船)の代替需要があった一般油槽船や,大型化傾向に伴い好調であったコンテナ船等の受注量が前年度に比べ若干増加したものの,前年度好調であったハンディーサイズ(1万〜3万総トン)のばら積貨物船の受注量が同77.5%減の163万総トンと大幅に減少したことによるものである 〔3−3−2図〕。これに伴って60年3月末現在の新造船手持工事量は対前年同月末比16.1%減の1,143万総トンとなっており,当面7割程度の低操業が続くものと思われる。また,船価水準も依然として回復せず,今後企業経営の悪化が懸念される。
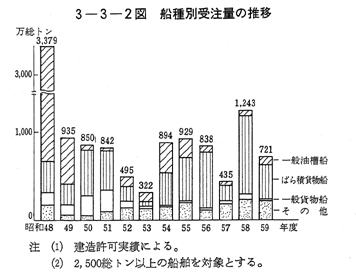
今後の見通しについては,石油危機を契機とするエネルギー需給構造の変化,世界経済の低成長化等により,海上荷動き量の大幅な増加は期待できないこと,依然として大量の過剰船腹が存在することから,老齢船や不経済船の代替需要が中心となると見込まれるため,新造船需要の急速な回復は望めない状況にある。
(2) 造船業の経営安定化対策
(新造船需要の低迷に対処するために)
50年代初頭以降我が国造船業は非常に困難な状況におかれているが,このような状況にかんがみ,運輸省においては設備の新設,拡張を極力抑制するとともに以下のような施策を講じている。
ア 操業調整
低操業に対応した建造体制への円滑な移行を図るため,52年度から59年度までの間,57年度を除いて大臣勧告,不況カルテルにより操業調整を実施してきた。
60年度及び61年度については,需要見通しに基づく生産ガイドライン(各年度の操業量は,それぞれ410万及び400万CGT(標準貨物船換算トン数)であり,建造能力比70%弱の水準)を示し,企業の適切な対応を求めることとしている。
イ 雇用・中小企業対策
工事量の減少に伴い,雇用及び関連中小企業への影響が懸念されるため,「特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法」における特定不況業種としての船舶製造・修理業の指定期間を60年7月からさらに2年間延長し,労働者の雇用の安定化を図っている。
また,「中小企業事業転換対策臨時措置法」,「特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法」の業種指定により,中小企業者の経営の安定化を図っている。
ウ 解撤事業の促進
造船事業者の仕事量の確保と外航海運における船腹過剰解消を図るため,53年度に船舶解撤促進助成金制度を設け,船舶の解撤促進を図ってきた。今後とも国内における解撤促進を図るとともに,工業化の進展に伴い国内の鋼材消費需要の増大が期待され,かつ,人件費等のコストが安い開発途上国における解撤事業を促進するために必要な調査研究等を行うこととしている。
|