|
(2)�@�����I���v��I�Ȓn���ʍs���̓W�J
�@�@���̂悤�ȏɑΉ����Ēn���ʃl�b�g���[�N�̉��P��}�邽�߂ɂ�,�n��̎�������Ă��Ē����I�Ȏ���ɗ������n���ʂɊւ��鑍���I�ȑ�����ƂƂ���,�s��,��ʎ��Ǝ�,���p�҂̍s���w�W�ƂȂ��ʌv���n�悲�Ƃɍ��肷��K�v������B
�@(1)�@�s�s�S���̐���
�@�@���S�̐ݔ������ɂ��Ă�,���S�m�ۂ̂��߂̓����ɏd�_��u���ɗ͗}�����Ă��Ă��邪,��s�s���̗A���͑��������ً}��v������̂ɂ��Ă�,�d�_�I�ɓ������s���Ă���B �@�@�V���̌��݂Ƃ��Ă�,�ʋΕʐ�(�鋞��)�ԉH�E��{��(18km)��60�N9���ɊJ�Ƃ�����,����ɋ��t�������E�h���(46km)���̍H�����i�߂��Ă���B �@(�n���S�̐���) �@�@�n���S��,���̑�ʂ̗A���\�͋y�э���������,�s�s���ɂ����Ăӂ���������H�ʌ�ʂɑ���D�ꂽ��ʎ�i�Ƃ���,���y�ђn�������c�̂̕⏕�̂���,���̐������i�߂��Ă��Ă���,���p�Ґ������̌�����ʋ@�ւɔ��,�傫�ȐL�ї��������Ă��� �k�S�|�Q�|�S�}�l�B
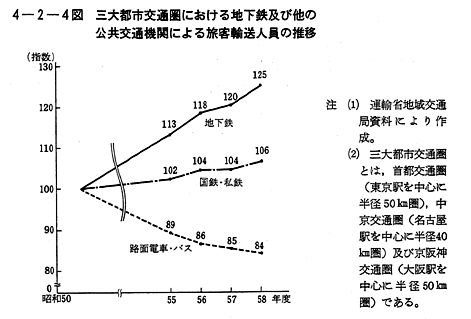
�@�@50�N�x���ɂ�,��s�����x��ʉc�c�y��5�s�s(�D�y�s,�����s,���l�s,���É��s,���s)�ɂ����ĉ^�c����Ă�����,���݂ł�,���s�s,�_�ˎs,�����s�ɂ����Ă��^�c����,�����9���Ǝ҂̑��c�ƃL����,60�N8�����݂�436.9km��50�N�x���̖�1.5�{�ƂȂ��Ă���,�����,�����̎��Ǝҋy�ѐ��s�ɂ����ĐV�����݂��i�߂��Ă���B
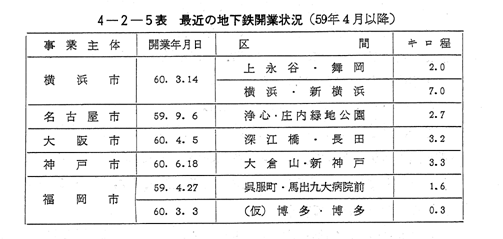
�@(�j���[�^�E���S���̐���)
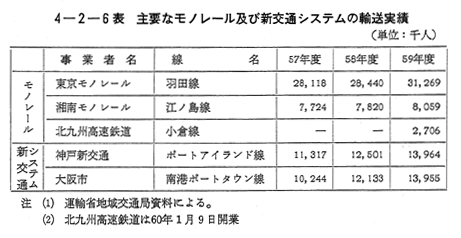
�@�@���̂���,�ԗ��̗�[���ɂ��Ă݂Ă݂��, �k�S�|�Q�|�V�}�l�̂Ƃ���,59�N�x��,�����E���n��̍��S�̗�[����77.7%,��薯�S14�Ѝ��v�̗�[������78.5%�ƂȂ��Ă���,50�N�x�ɔ�ׂĂ��ꂼ��3.7�{,2.3�{���x�̑啝�Ȍ���������Ă���B
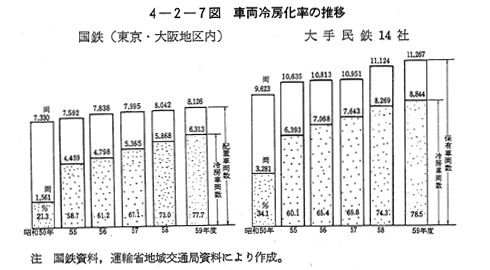
�@�@�܂�,�w�ɓ��̎{�݂̉��P�ɂ��Ă�,���S�y�і��c�S���e�Ђɂ�����,���̌o�c�������Ă���,�v��I�Ƀz�[������,�G�X�J���[�^�[���̐�����}��,���p�҂̗��ւ̌���ɓw�߂Ă���B����,�����,�g�̏�Q�҂̈ړ��̗������m�ۂ�,������ʎ�҂̎Љ�Q���̐��i��}��ϓ_����,�Ԉ֎q�ʘH,�U���u���b�N,�g��җp�g�C�����̎{�݂̐����������i�߂Ă���B
�@(2)�@�������ɂ������ʖԂ̐���
�@(�������̏����W�]) �@�@�������̐l����,��t��,��ʌ�,��錧�암���̌���̖k���Ȃ��������n��𒆐S��75�N�܂łɖ�400���l������,���,�Ɩ��n�ɂ��Ă�,�s�S3��y�ѕ��s�S�̂ق�,���l,���,����,�����q,��{,�Y�a���ւ̕��U�����i�W������̂ƌ����܂��B �@�@�����̓_����,�����s�敔�ւ̗����l����75�N�܂łɖ�80���l������,���Ɍ���̖k���Ȃ��������n�悩��̗����l���̐L�т������ƂȂ���̂ƌ����܂��B �@(�v�����ɓ������Ă̊�{�I�l����) �@�@�����s�S���𒆐S�Ƃ��邨���ނ˔��a50km�͈̔͂�ΏۂƂ�,75�N��ڕW�Ƃ��鍂���S���Ԃ̐����v����������B �@�@�H���̑I��ɓ������Ă�,���ݐ��̍��G�ɘa�ɏd�_��u��,�ō��G��Ԃɂ�����ō��G1���Ԃ̍��G���������ނ�200%����H���ɂ��ĐV�����ݓ����s�����ƂƂ����B �@�@�܂�,�l���̊O����,�j���[�^�E���v��ւ̑Ή����`�A�N�Z�X�̉��P��}��ƂƂ���,���s�S�@�\�̋����y�ыƖ��j�s�s�ւ̈琬�ɂ�������悤�z�������B�Ȃ�,�o�X���ɂ��Ή��ɂ��Ă���������ƂƂ���,�ɗ͊������{�݂̗L�����p��}�邱�ƂƂ����B �@(��v�ȐV�K���\�H���̊T�v) �@�@�H���v��̍���ɓ������Ă�,����̗A�����v�̓������܂���,�V�K�ɘH���̐ݒ蓙���s���ƂƂ���,����܂ł̓��\�H����,�K�v���̔��ꂽ���̂ɂ��Č��������s�����B����̓��\�ɂ�����,�V���ɘH���̐ݒ�܂��͉��L���s�������͈̂ȉ��̂Ƃ���ł��� �k�S�|�Q�|�W�\�l,�����̘H���̐����ɂ��e�H���̍ō��G��Ԃɂ�����ō��G1���Ԃ̕��ύ��G����55�N�x�̖�220%����75�N�ɂ͖�180%�ȓ��ƂȂ�,�܂�,�x�O�̋��Z�n�̑啔�����瓌��,���l���̋Ɩ��W�ϒn�֖�90���ȓ��œ��B�\�ƂȂ���̂ƌ����܂��B
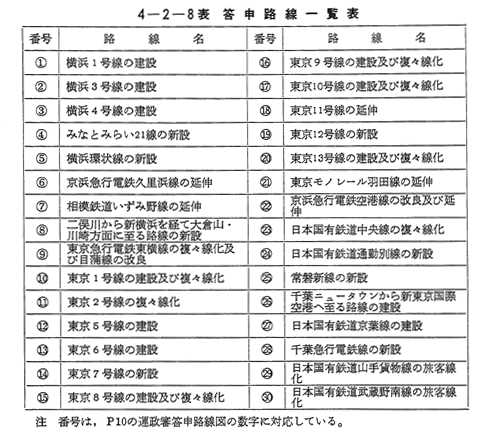
�@(�v��������̂��߂̕���)
�@�A�@�����J���v��Ƃ̏\���Ȓ���
�@�C�@�����ᗘ�̎����̊m��
�@�E�@�J�����v�̊Ҍ�
�@�G�@�Ɩ��n�J���ɂ�����J�����S��
�@�I�@�~���ȉ^�c�̊m�ۂ̂��߂̉^���̂����
�@�J�@��V���̐�������
�@(3)�@�s�s�V�o�X�V�X�e�����̐���
�@�@�s�s�ɂ�����o�X�A����,���[�^���[�[�V�����̐i�W���ɔ������s���̈����ɂ��,�o�X�̗��������ΓI�ɒቺ�������Ƃ�����v����������ƂƂ��ɃR�X�g��������,���̂��ߍ̎Z����������,���ꂪ�T�[�r�X���P��x�点�邱�ƂƂȂ�,����Ƀo�X���v������������Ƃ������z�Ɋׂ��Ă���B���,�s�s��ʂɂ����Ă�,�~���ȃ��r���e�B���m�ۂ���ƂƂ��ɏȋ��,�ȃG�l���M�[���̗v���ɑΉ����Ă������߂ɂ�,�o�X�𖣗͂����ʋ@�ւƂ��čĐ����Ă������Ƃ��K�v�ł���B���������ϓ_����,�o�X��p���[���̐ݒu���o�X�̑��s���̉��P�𐄐i����ƂƂ���,�^�A�Ȃ�,�o�X�ԗ�,�◯���{�ݓ��̉��P���w�����Ă��Ă���,�����,�s�s��o�X,�s�s�V�o�X�V�X�e�����ɑ��ď������s�����Ƃɂ��,�s�s�ɂ�����o�X�T�[�r�X�̉��P��������͂ɐ��i���Ă��Ă���B �@(�i�ޓs�s�V�o�X�V�X�e���̐���) �@�@�s�s�V�o�X�V�X�e����,�o�X�T�[�r�X�̉��P����̏W�听�Ƃ���,�o�X��p���[���̐ݒu�ƕ����ė��p���₷���ߑ�I�Ȏԗ��y�ђ◯���{�݂����邱�Ƃ���e�Ƃ���s�s��o�X�V�X�e�������P��,����ɃR���s���[�^�𗘗p�����o�X�H�������Ǘ��V�X�e�������邱�ƂŃV�X�e���S�̂̃O���[�h�A�b�v��}�������̂ł���,�s�s��ʑ̌n��̍����ƂȂ�ׂ���v�ȃo�X�H���ɂ�����,�o�X��p���[���̐ݒu�ƕ�����,��̓I�ɂ�,���̂悤�Ȏ{�݂̐������s�����̂ł���B �@�@�@�o�X�H�������Ǘ��V�X�e������,�R���s���[�^����ɂ��ԗ��^�s�̒����Ǘ��ɂ�����^�]�̊m�ۓ���}��ƂƂ���,�o�X���P�[�V�����V�X�e���̐����ɂ��◯���ɂ�����o�X�ڋߕ\�����s��,�o�X�҂��̃C���C��������������B �@�A�@�Ᏸ,�L�h�A,��g�[,��^������������s�s�^�ԗ��̓����ɂ��,�o�X�A���̉��K�������コ����B �@�B�@�V�F���^�[,�d�Ǝ��|�[����������◯���{�݂̐ݒu�ɂ��o�X�A���̗��������コ����B �@�@�����̐����ɂ��Ă�58�N�x���珕���[�u���u���Ă���,���N�x�͓����s�y�ѐV���s�ɂ����ē�������,���p�҂̗��������߂�Ȃǂ̌��ʂ������Ă��� �k�S�|�Q�|�X�}�l�B
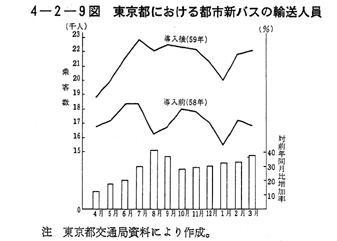
�@(���É��s�y�ы���s�̓s�s�V�o�X�V�X�e��)
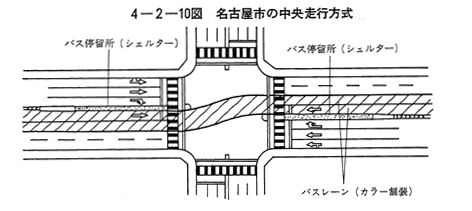
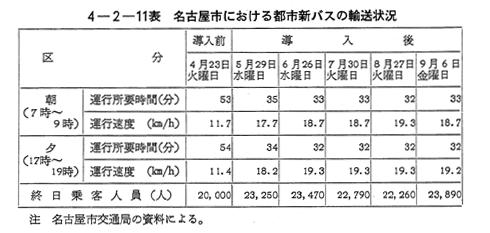
�@�@����s�ɂ����Ă�,�s�s�V�o�X�V�X�e��������w,���іV,�L���H�𒆐S�Ƃ���3�H���ɓ�����,60�N3������^�s���J�n���Ă��邪,����3�H���ȊO�ɂ��o�X�H�������Ǘ��V�X�e����17�H���ɓ�����,�R���s���[�^�ɂ��^�s�Ǘ����s�����Ƃɂ��,�o�X�A���̗����y�щ��K�������コ���Ă���B
�@(1)�@�������S�y�ђn���o�X�̈ێ��E����
�@�@�������Ȃ���,�A���l����58�N�x�ɂ�����,�������S��3.3���l(�ΑO�N�x��3%��),�捇�o�X74���l(��3%��)�ƗA�����v��������^�������͐L�єY��ł���,�܂�,�l����̏��o��������铙�ɂ��ɂ߂ċꂵ���o�c��]�V�Ȃ�����Ă���B �@(�������S�̈ێ��E�ߑ㉻�̑��i) �@�@�������S��,�n����ʂɏd�v�Ȗ������ʂ����Ă���,�唼�̎��Ǝ҂��Ԏ��o�c�ƂȂ��Ă�����̂�,�o�c���P��}�肻�̈ێ��ɓw�߂Ă���Ƃ���ł���,�c�Ǝ��x��(�c�Ɣ�p/�c�Ǝ����~100)�ɂ��Ă݂��,50�N�x��105.9����58�N�x�ɂ�103.5�Ɖ��P�������Ă��邪,�������w�̌o�c���P�ɓw�߂Ă����K�v������B �@�@������,�ݔ��̈ێ�������Ȃ��ߘV�������Ă�����̂�,���̗A�����p������Ȃ��ƒn��Z���̑��̊m�ۂɎx�Ⴊ��������̂ɂ���,���͒n�������c�̂Ƌ��͂��Ă��̌o�푹���z�ɑ���⏕���s���Ă���B�܂�,�ݔ��̋ߑ㉻�𐄐i���邱�Ƃɂ��,�o�c���P,�ۈ��x�̌���܂��̓T�[�r�X�̉��P���ʂ��������Ƃ݂�����̂ɑ��Ă�,���͒n�������c�̂Ƌ��͂��Đݔ�������̈ꕔ��⏕���Ă���B59�N�x�ɂ����Ă�,�����̕⏕�Ƃ���35�Ђɑ�,��8���~�̍��ɕ⏕������t���� �k�S�|�Q�|�P�Q�\�l�B
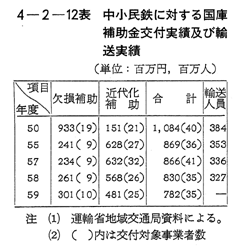
�@(�o�c���P�ւ̓w�͂��]�܂��n���o�X)
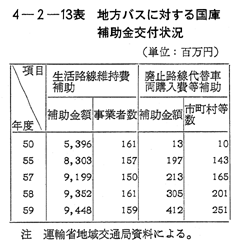
�@�@�����n���o�X�H���^�s�ێ����,55�N�x�ȍ~59�N�x�܂ł�5���N�Ԃ̑�Ƃ���Ă�����,60�N�x�ȍ~5���N�ԉ������邱�ƂƂ�,�⏕���x�ɂ��Ă͌��s���x�̊�{�I�g�g�݂��ێ�����,�⏕�v���̓K�����y�ё�փo�X�^�s��⏕�P���̉�����s�����B
�@(2)�@���q�D��
�@�@�䂪���ɂ�,�L�l����420�]����,�Z���̕K�v�s���Ȑ����̑��Ƃ��ďd�v�Ȗ������ʂ����Ă��闣���q�H��,���̌Ǔ��ƌĂ��ƒn�ɒʂ��������q�H���܂߂�,60�N4������,390�q�H���邪,����痣���q�H�̑�����,�A�����v�̒��,�R������͂��߂Ƃ��鏔�o��̏㏸���ɂ��,�Ԏ��o�c��]�V�Ȃ�����Ă���B �@�@���̂���,����,�����q�H�̈ێ��E������}�邽��,�]������,�n�������c�̂Ƌ��͂���,�����q�H�̂������̗v��������������q�H�ɂ���,���̌����ɑ��⏕���s���Ă��Ă��邪,�����z�̑����ɔ������ɕ⏕���̊z�������X���ɂ���,59�N�x�Ɍ�t���ꂽ���ɕ⏕����50�N�x��2.6�{�̖�36���~�ƂȂ��Ă��� �k�S�|�Q�|�P�S�\�l�B
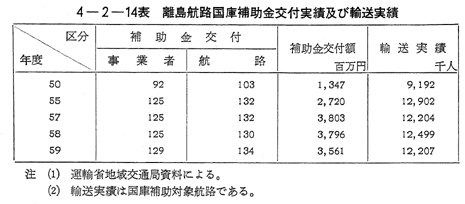
�@�@�����q�H�̌o�c��,59�N�x�͔R����̈��蓙�ɂ��,�����z�͌������Ă��邪,�����I�ɂ�,�A�����v�̌���,���o��̏㏸���ɂ��o�c�͈������邱�Ƃ��\�z����,�܂�,���̍����������i�ƌ������ɂ��邽��,����Ƃ������q�H�Ƃ��Ă̗����q�H���ێ����Ă������߂ɂ�,��w�̌o�c������,����������}��K�v������B���̂���,59�N�x���痣���q�H���P�̂��߂̒������s���Ă���,���̌��ʂ܂��ė����̎���ɑ������q�H�̉��P��������肷�邱�ƂƂ��Ă���B
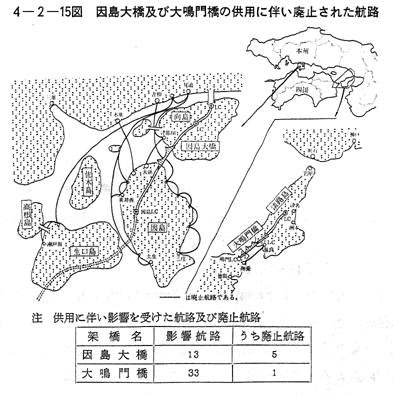
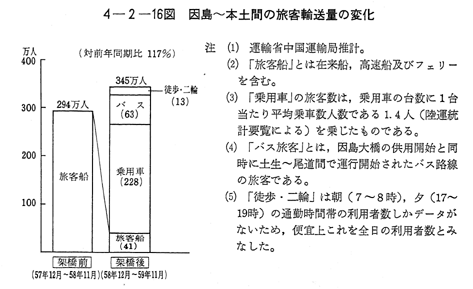
�@�@�_�ˁE�僋�[�g�̑�勴�̊֘A�ł�,60�N6���̓������p�J�n�ɔ���,�q�H��p�~�������̂�1�q�H(1���Ǝ�),�q�H�̋K�͏k�����s�������̂�3�q�H(3���Ǝ�)����,���ꂼ�ꎖ�Ǝҋy�ї��E�҂ɑ��Ĉ����勴�̏ꍇ�Ɠ��l�̑[�u���u�����Ă��� �k�S�|�Q�|�P�T�}�l�B
�@(3)�@���S����n����ʐ��̓]��
�@�@���S����n����ʐ����,�S���ɂ��A���ɑウ�ăo�X�A�����s�����Ƃ��K���ȘH����p�~��,�����ɑ���n��Z���̐����̑����m�ۂ��邽�߂ɗA�����v�Ɍ������������I�ȗA����i���m�ہE����������̂ł���,��{�I�ɂ̓o�X�A���ւ̓]�����]�܂������̂ƍl������B��1���I�����ł�,60�N10������,�k�C���̔��f����22�����o�X�A���ɓ]������Ă���B �@(�o�X�]����̏�) �@�@�o�X�A����,�◯���̐����������邱��,���v���Ԃɍ��킹���^�s�̐ݒ肪�\�ɂȂ邱��,��[�����̎ԗ����g�p����ꍇ���������Ɠ�,���S�������ɔ䂵�ė����͑������Ă���B �@�@�܂�,�]����̃o�X�A���ɂ��Čo����x�ɂ����đ������������ꍇ�ɂ�,�J�ƌ�5�N�Ԃ͗v�j�Ɋ�Â����̑S�z�������⏕���邱�ƂƂ��Ă���B59�N�x�ɂ����Ă͑Ώ�5�H���̂���,�������⏕���邱�ƂƂȂ����̂�2�H���ł���B �@(�n���S���]�����̏�) �@�@59�N4���ɓ]�������v���{�Ëy�ѐ���3���ɑ���,60�N10�����݂܂ł�10��172.8km���n���S���ɓ]�������B �@�@�����̓S����,�������,�S���o�c������ƂȂ��Ă����H���ɂ����Ă����Ė��c�ɂ��S�����o�c����Ƃ������Ƃ�,�W�n�������c�̂��͂��߂Ƃ���n���W�҂��F����,���Ƃ̍̎Z�����ɂ��ď\���������s���������œS���𑶑������邱�Ƃ�I���������̂ł���,�����̘H���������p�������Ǝ҂�,�v���̍팸���o�c�̍�������i�߂���,�����̎���ɔz�������_�C���ݒ���s�����ɂ����v�̊��N�ɓw�߂�Ȃǂ̌o�c�w�͂��s���Ă���B �@�@�܂�,�e���Ǝ҂̗A����,���̂悤�Ȍo�c�w�͓��ɂ��,���݂̂Ƃ��덑�S����������r�I�����Ȃ��̂����� �k�S�|�Q�|�P�V�\�l�B
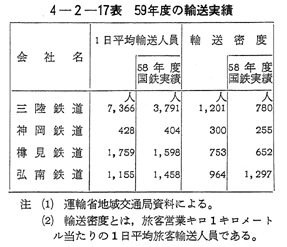
�@�@�e���Ǝ҂̎��x�ɂ��Ă�,�]�����ɍ��S�����t�����]����t���y�э��S�����L���Ă����w��,�H��,�M���{�ݓ��S���^�c�ɕK�v�Ȏ{�݂̖������n���͑ݕt���̉���������,���S�������Ƃ̔�r�ɂ��Ɖ��P����錩�ʂ��ł͂��邪,�ˑR,�o����x�ɂ����đ����̐����鎖�Ǝ҂̏o�邱�Ƃ������܂�,���̏ꍇ,�J�ƌ�5�N�Ԃ͑�����2����1��������Ă邱�ƂƂ��Ă���B
|