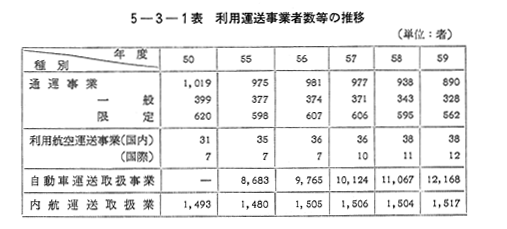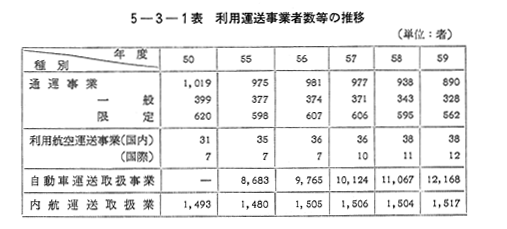|
5 利用運送業
(1) 利用運送事業等の現状
(重要性を増す利用運送事業等)
利用運送事業等には,内航運送取扱業,通運事業,自動車運送取扱事業,利用航空運送事業等があり,利用又は取扱の相手方となる運送事業の動向を反映して,自動車運送取扱事業及び利用航空運送事業が伸びている反面,内航運送取扱業及び通運事業は横ばい又は減少傾向にある 〔5−3−1表〕。
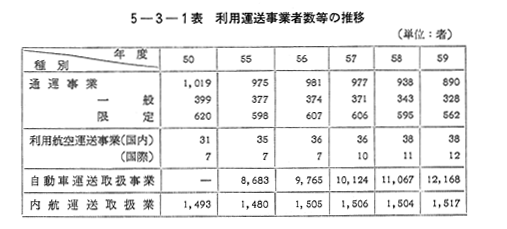
これらの事業は,運送事業者の販売窓口として,また高度化,多様化する荷主のニーズに応えて適切な輸送手段を選択するフォワーダーとして,物流関係企業の発展に重要な役割を果たしており,今後とも健全な育成を図る必要がある。
(2) 通運事業
(国鉄貨物再編への対応)
国鉄の貨物輸送量は39年度の2億700万トンをピークに年々減少し,59年度においては7,500万トンにまで落ち込んでいる。この国鉄貨物輸送の低落と相次ぐ国鉄貨物の合理化等により,通運事業経営は全体としては縮小傾向をたどるとともに,約6割が赤字経営を余儀なくされ,各事業者は経営の一層の多角化,総合化を図ってきている。また,国鉄再建監理委員会の「意見」に基づく新貨物輸送体制のあり方いかんによっては通運事業のあり方にも変化が生ずるものと考えられ,通運行政もこれらの事態を踏まえた新しい展開を求められることとなる。当面,59年2月及び60年3月と相次いで実施された国鉄貨物のシステムチェンジに関連した通運対策として,運輸事業振興助成交付金の活用による事業の近代化のための設備資金,運転資金等の融資施策の推進,雇用保険法に基づく雇用調整助成金の対象業種へ指定等の措置を講じた。
今後は,引き続き前記施策を推進するとともに,国鉄再建監理委員会の「意見」を踏まえた国鉄貨物輸送の今後のあり方に対応し,必要な施策を講じていくこととしている。
(3) 利用航空運送事業
(利用航空運送事業の活性化)
利周航空運送事業は近年の航空貨物輸送の進展に伴い着実な伸びを示し,各事業者とも健全な経営が行われている。航空貨物輸送量に占める利用航空運送事業者の混載貨物輸送量をみると,国内線においては50年度以降一貫して70%以上のシェアを占めており,また,国際線においても50年度には20%と僅少であったものが59年度には54%(出国ベース)とシェアを年々拡大してきており,国内,国際ともに航空貨物輸送にとって多大な貢献をしてきている。59年度においては最近の消費者物流充実の要請に対応して,一般消費者を対象とした小口混載貨物の需要拡大を図るための努力が続けられ,60年2月より一般消費者に利用の多い45kg未満の国内小口航空混載貨物運賃について,航空貨物運賃の変更に対応して分かり易い定額運賃制が採用され,事業の活性化が図られた。今後とも小口航空混載貨物の需要動向等の変化,消費者ニーズに対応し適切な対策を講じていくこととしている。
|