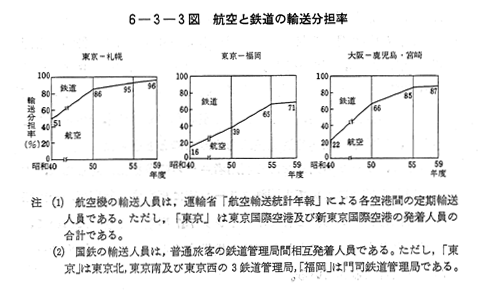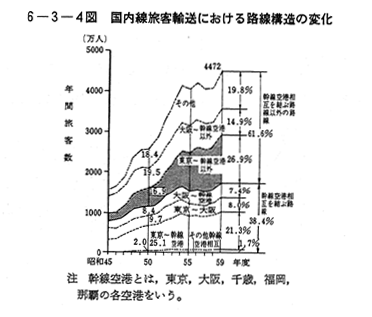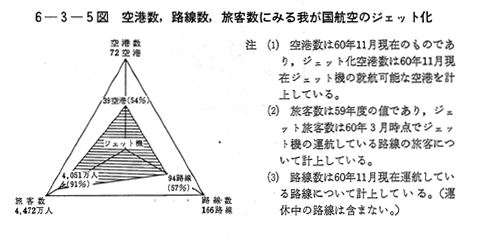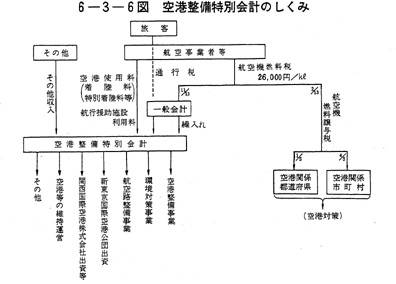|
1 航空輸送と空港整備
(1) 航空をめくる情勢の変化
(増大する航空輸送)
昭和26年に再開された我が国の航空輸送は,旅客・貨物ともに急激な発展を遂げ 〔6−3−1図〕, 〔6−3−2図〕,現在,旅客については,国際旅客と国内長距離旅客の大半が航空を利用しており 〔6−3−3図〕,貨物についても,付加価値の高い製品を中心に幅広く利用されている。


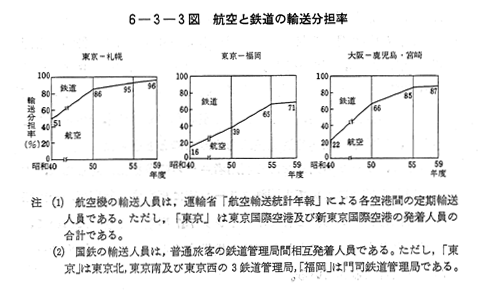
その理由としては,①所得水準の向上と産業活動の活発化により時間価値が高まり,このことが時間短縮効果が大きく快適性にも優れる航空輸送の特性に合致したこと,②ジェット機の就航,ジャンボジェット機の就航等の一層の高速化・大型化の進展及び燃費向上等の技術革新による生産性の向上により,輸送コストが相対的に低下し,実質的な航空運賃が低下してきたことがあげられる。
55年度以降低迷していた国内線旅客は,59年度に入って増大傾向に転じ,4,472万人(前年度比9.5%増)となり,国際線旅客は,1,669万人(同9.0%増)となっている。
また,航空貨物は,国内線・国際線とも順調に伸び続け,59年度において国内線は435千トン(同9.5%増),国際線は794千トン(同8.0%増)となっている。
(航空に対する新たなニーズ)
このような航空輸送の量的な拡大が進行する一方で,近年,ヘリコプターを含めた小型航空機による地域航空輸送,地方空港の国際化,IC関連産業など臨空港型産業の立地による地域開発の推進など航空輸送の新たな可能性への期待が高まるとともに,サービス面においても利用者ニーズは多様化してきている。
このうち小型航空機による旅客輸送については,58年に運航を開始した日本エアコミューター(株)をはじめとする4社が主に離島路線で行っており,59年度の輸送実績は17万人となっている。
また,60年3月から筑波研究学園都市で開催された国際科学技術博覧会の期間中に,筑波〜羽田,筑波〜成田等の路線でヘリコプターによる旅客輸送が行われたが,運賃が割高であったこと,利用客が午前中は往路に夕方は復路に集中したため座席利用率が低率であったこと等から,期間中の旅客輸送実績は約2万人にとどまった。
さらに,サービス面における利用者ニーズの多様化に対しては,本年11月から航空においても国鉄グリーン車に相当する特別席が一部路線で導入されている。これはボーイング747型機の2階席において,一般席よりもゆったりとした座席を提供するものであり,機内サービスの充実も図られている。
(2) 我が国航空ネットワークの特徴
(国内線は2眼レフ構造)
我が国の国内線航空ネットワークの最大の特徴は,需要の大多数が東京国際空港と大阪国際空港の2つの空港に集中するいわゆる「2眼レフ構造」となっている点である。
59年度の実績では,国内線旅客のうち東京国際空港を利用した旅客は56.2%(50年度51.7%),大阪国際空港を利用した旅客は30.3%(同37.6%)である。このうち,東京〜大阪線の利用客が8.0%(同9.7%)であることから,東京又は大阪の少なくとも一方の空港を利用した旅客は78.5%(同79.6%)に上っており,環境対策上の運用制限等により,大阪国際空港のシェアは減少しつつあるものの,旅客はこの2つの空港に集中している 〔6−3−4図〕。
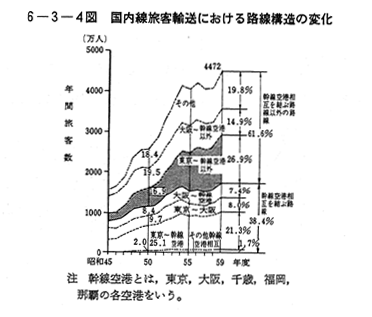
とくに,東京と大阪,千歳,福岡,那覇の4空港以外の空港とを結ぶ路線は,近年,国内線旅客におけるシェアを拡大しつつあり,59年度において26.9%(同16.9%)となっている。
また,航空ネットワークについては,59年度に札幌〜那覇,小松〜仙台等5路線が開設され,60年度に入り,名古屋〜花巻,函館〜秋田の2路線が開設されている。
(国際線も東京・大阪に集中)
さらに,国際航空路線も多くが東京及び大阪の国際空港に集中しており,59年度実績では,国際線旅客のうち,新東京国際空港及び東京国際空港の利用旅客は70.8%,大阪国際空港の利用旅客は20.6%であり,これらの国際空港を利用する旅客は全旅客の91.4%にも上っている。
(3) 空港整備の進捗状況
(進展するジェット化)
前述のような航空需要の増大に対処するほか,航空交通の安全確保を図り,環境保全の要請に応えるため,空港整備の推進,航空保安施設等の整備,空港周辺環境対策の推進を図る観点から,42年度以来,「空港整備五箇年計画」を策定し,計画的に空港整備事業が進められてきた。現行の第4次空港整備五箇年計画(計画期間56〜60年度,投資計画額1兆7,100億円)は60年度をもって終了するが,60年11月現在で定期輸送の行われている空港は72(うちジェット化空港39)となっており,空港数の5割,路線数の6割,旅客数の9割がジェット化のメリットを享受している 〔6−3−5図〕。
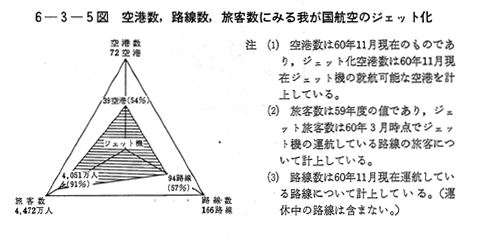
(4) 今後の空港整備の方向
(今後の課題)
航空輸送は,今後とも我が国経済社会の国際化の進展,国民の所得水準の向上,高速性志向の高まり等を背景として着実にその役割が拡大していくものと考えられる。現行の第4次空港整備五箇年計画が昭和60年度をもって終了することから,今後の空港整備の課題について,現在,航空審議会等の場で検討しているところであるが,基本的には,今後,次のような方針で空港整備に取り組むこととしている。
ア 3大プロジェクトの推進
国際及び国内航空路線の東京及び大阪への集中,環境対策上の運用制限等のため,新東京国際空港,東京国際空港及び大阪国際空港の3空港は既に利用の限界に達しつつあり,このまま推移すれば,今後,日本の国際及び国内航空ネットワークの健全な発展を阻害するあい路となることが予想される。このため,当面は,事業が本格化することとなる関西国際空港の整備,新東京国際空港の整備及び東京国際空港の沖合展開のいわゆる「3大プロジェクト」を最重点課題として推進することとする。
イ 一般空港の整備
一般空港については,現在実施中の事業が完了すれば,ジェット化,大型化が相当のレベルに達することとなるので,今後とも,継続事業を鋭意推進することに重点を置くとともに,将来の航空需要の増大に対処してジェット化・大型化を図る必要がある既存空港や,航空輸送サービスを享受し得ない地域における新設空港について,需要の動向,地域開発効果等を勘案しつつ,投資効率の高いものから順次整備を進めることとする。
ウ 環境対策の推進
環境対策については,60年度中に希望者に対する住宅防音工事がおおむね完了する見込みであることから,今後は,空港と周辺地域との調和ある発展を図るため,移転の促進による空港と住宅地域との分離,緑地整備による航空機騒音の緩衝,公園等の整備による周辺環境の改善等地域の環境整備を中心とした抜本的な対策に取り組むこととする。
エ 航空保安施設の整備
今後とも増大する航空輸送需要に対処して,航空輸送の安全性の向上と効率性の確保を図るため,従来から進められてきた航空保安システムの近代化を達成させるとともに,新しいシステムの開発・整備を進めることとする。
(収支が厳しい空港整備特別会計)
空港整備事業等については,45年度に「空港整備特別会計」が創設され,一般会計とは別個に経理されている 〔6−3−6図〕。
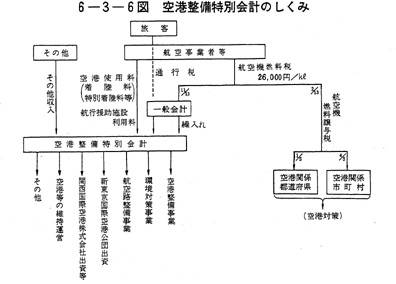
空港整備特別会計は,空港整備事業,航空路整備事業,空港周辺環境対策事業等広義の空港整備事業に要する費用のほか,空港等の維持運営に要する費用を主な歳出とし,空港使用料等収入(着陸料,特別着陸料,航行援助施設利用料等),一般会計からの繰入れ金(航空機燃料税財源及び一般財源)等を主な歳入としているが,近年,その収支は極めて厳しくなっている。その原因として考えられることは,歳入面では,第1に需要の伸悩み等のために,使用料収入の伸びが小さいことであり,第2には通行税(航空分)の取扱いである。通行税自体は一般税であり,一般会計の歳入とされているものであるが,一般会計から空港整備特別会計に繰り入れられている一般財源は,従来は航空旅客の支払う通行税収に見合う額となっていた。しかしながら,55年度以降厳しい国家財政事情を反映して一般会計受入れ枠に極めて厳しいシーリングが設定されるに至ったため,一般財源として繰り入れられる額は,通行税(航空分)の税収を下回る事態となっている。
他方,歳出面については,関西国際空港の整備,新東京国際空港の整備及び東京国際空港の沖合展開の「3大プロジェクト」の推進,一般空港の整備等の空港整備事業が今後数年間にピークを迎える予定であり,多額の資金が必要となる見込みである。したがって,所要の空港整備事業を円滑に実施していくためには,その財源対策についても検討する必要があるが,特に,現在の空港整備特別会計の歳入のしくみや運用について,幅広い検討を加えていく必要がある。
|